
外国人として中国を善意に批判する
政治・外交- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
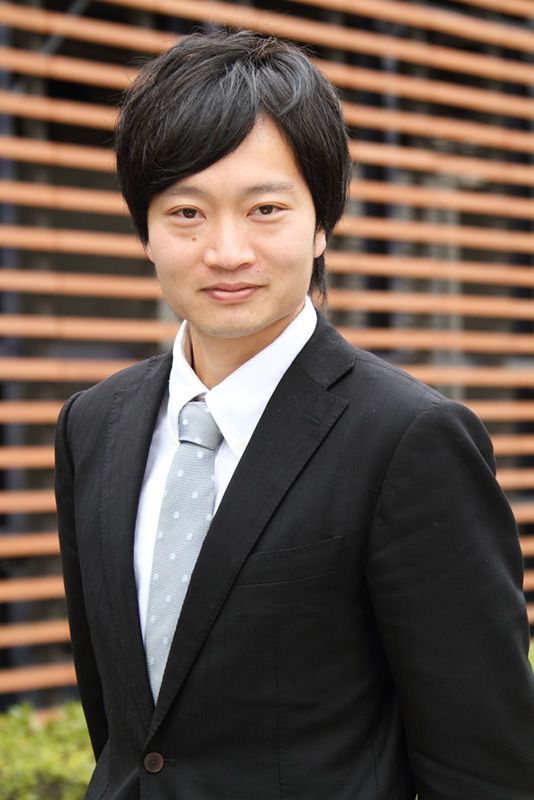
加藤 嘉一
KATŌ Yoshikazu
1984年静岡県生まれ。2003年高校卒業後、北京大学に留学、同大国際関係学院卒業。英フィナンシャルタイムズ中国語版、香港≪亜洲週刊≫、The Nikkei Asian Reviewコラムニスト。2012年3月現在、香港系フェニックスニューメディア(鳳凰網)における加藤氏のブログは 6000万アクセス、中国版ツイッター(新浪微博)のフォロワーは130万人を超えている。
100大学訪問で中国の若者とガンガンやる
竹中「中国100大学訪問」は、ご自身で発案されたプロジェクトですか?
加藤2003年から2010年までは北京で忙しくしていたので、2011年は中国全土を回ってみたいという思いを持っていました。ちょうど本の出版時期とも重なって、出版社から大学で本のプロモーションをしたいという提案があったんです。そこで、ロジスティックスを出版社と大学にやってもらい、各大学にある共産主義青年団(共青団)のサポートを得て実現しました。本のプロモーションが終わった後も、自分で続けています。僕のチャイナウォッチにとって一番大切な対象は大学生とポリシーメーカーです。一番発信したい相手は、大学生と胡錦濤主席周辺ですね。
竹中胡錦濤周辺ですか(笑)
加藤実際、この二つのグループが僕の読者になっている。中国の未来に直接影響を与えるのはこの2大グループだと思います。
竹中100大学訪問は、いつから始めましたか。
加藤去年(2011年)です。大体回り終わりましたが、現在もまだ続いています。
竹中1年半で100大学だと、1日に1校くらいですか。
加藤多いときは南京市で1日3校ということもありました。僕は、中途半端に交流して帰るのが嫌いなので、制限がなければ深夜まで講演してましたよ。ガンガンやるわけです。(笑)「仮に日中が戦争したらどうしますか」という質問には、「くだらん質問をするな、俺は日本人だぞ」みたいに返しますよ。(笑)とにかく場を盛り上げるべく心掛けています。
「人民日報」を読んだり、中国上層部の政策研究をするのは大事ですけれど、中国の今後の発展を考えたら、大学生が何を考え、何に悩み、何に困っているかを実際のコミュニケーションを通じて知ることが最大の中国理解なわけです。「80後(パーリンホウ)(※1)」と呼ばれていますが、80年から89年生まれの人だけで2億人いる。90年から99年に生まれた人たちも2億いるわけですよ。大きな存在です。
竹中2億人ですね。
中国の発展の方向性は民主化しかない
加藤これだけで4億人以上です。たとえば、「中国はインフレが深刻だ」だと言われるけれど、実際彼らがどう感じているかを交流を通じて知る必要がある。僕にとって、2011年は大衆理解、中国研究がアップグレードされた大きな1年でした。
中国にはいまだ言論統制が横行していて、なかでも大学は特別にセンシティブな場所、非常に重要な場所なんだけれども、大学が自由・民主主義を重んじなければ中国の将来は暗くなってしまうと思う。僕や中国のリベラリストたちは自由や民主主義に改革の方向性を見出す。「民主化すべき」「グローバルスタンダードを重んじるべし」「統制止めるべし」という立場。いろんな国に行けば行くほど、民主主義、自由民主主義制度の優位性を感じる。まさにチャーチル(元英首相)が言ったように「民主主義は最低の制度。民主主義を除いては」だと思う。中国にいればいるほど感じるんです。やっぱり中国の発展の方向性は民主化しかないと僕は信じて疑わない。
竹中大学は自由だけど、制度が……。
加藤僕が大学に講義に行くと、ときには3千人が現場にいて、同時にネットにアクセスしながら積極的に発信している。中国版ツイッターもやっているから、制御できない。結果的にリアルタイムで何万人、何十万人もが見ていることになる。
竹中怖いですね。
ガンガンやるのは外国人としての善意の批判
加藤だから、当局としては警戒しますよね。改革を訴えるリベラリストたちはみな大学生に影響を与えたいと思っている。キャンパス内で講演したいんですよ。でも、多くの場合当局に妨害されてしまう。当局は大学生が暴れだすんじゃないかと警戒してしまう。だから守りに入る。でも、僕はやります。外国人だから僕に対する管理が緩いということはある。共青団との関係を強化してきたから、どの大学にも共青団の支部があって、基本的にはそこが主催者になってくれた。主張と妥協の繰り返しですけれどね。
竹中ホストしてくれたわけですか。
加藤僕が行くと、トップの書記が食事の席を設けて歓迎してくれる。当局との関係はしっかり築きますが、中国問題に対する批判では遠慮しませんよ。僕が中国の政治体制の批判を始めると、現場で監視している大学の先生たちは冷汗をかき始める。学生には「恐らく今、君らの先生はすごく怖がっている」と言う。「でも、君たち勘違いするなよ。僕の批判は善意の批判であって、決して土台を壊すものじゃない」「共産党批判するんだったら、おまえらがやれ」「だったら、胡錦濤さんの代わりにやってこい」「現状で共産党政権がやれなかったら誰がやるんだ。オルタナティブ(代案)を提案しろ」「先生方も君たちをまとめるのが大変だということを理解しろ」と。
今年の4月から日本のダイヤモンド・オンラインというメディアで「だったらおまえがやれ!」という連載コラムを始めましたが、僕はいつもこの精神を持って、中国の学生たちに当事者意識を持つことの重要性を呼びかけている。「無責任な批評はするな」と。
一方で先生方には「自分たちの学生を信じてあげなさい」と言ってきた。「先生が学生を信じなかったら、誰が彼ら彼女らを信じてあげられるんですか」と言うと、学生と先生方が和解してスタンディング・オベーション(総立ちの拍手)してくれる。だから、大学側は僕を歓迎するんだと思う。基本的には問題を直視して、未来に向かって突っ走ろうというスタンスですから。中国の上層部は、決して僕が中国の国家転覆とか分裂を狙っているのではなくて、中国がより開放的、民主的になることが世界共通の利益だという視点から善意の批判をしていると分かっている。
竹中それは分かりますよ。
ネットワーキングの拠点としての大学
加藤さまざまなしがらみがあるなかで、僕は自覚しながらバランスを取ってきた。今回これだけの数の大学に行けたのは、ある意味で僕の青年期における中国問題研究にとっての集大成ですね。中国の大学は単なる大学ではないんです。大学が企業経営やベンチャービジネスをやったり、敷地内にテクノロジーパークを造ったりして資金をやりくりしている。人材を社会に放出している。政府の会議の会場になるとか、シンクタンクみたいな役割も果たすんです。まさに産学官の拠点になっている。
竹中みんなが交流する場ということですね。
 加藤
加藤大学にはオケイジョン(機会)があり、ポリシー(政策)、ポリシーリサーチ(政策研究)があって、なおかつソーシャル(社会)サービスの役割を果たしている。非常に立体的なんですよ。だからこそ、僕は中国理解のなかで、全国各地の大学を攻めるんです。大学を落とすことが大事なんです、ネットワーキングの拠点になるから。
僕にとっても、東西南北に位置する大学を回った2011年は集大成の意味合いが強い。ひとつ言えることは、北京大学に在籍していたことが大きかった。「北大(ベイター)ブランド」はどこに行っても役に立った。僕自身も「北大人(ベイターレン)」としての誇りを持って取り組んできた。これまでに築き上げてきた結果が、ようやく一本のプロセスにつながったという感覚を持っている。大学めぐりはその象徴ですね。2012年の1月1日はすがすがしい心境で迎えました。これからは違う言語でも発信していきたい。英語による発信も本格的に始まっている。
竹中すごいですね。
加藤毎日、日中英三つの言語で執筆しています。この上ない頭の体操ですね。「フィナンシャル・タイムズ(FT)」「The Nikkei Asian Review」「ダイヤモンド・オンライン」「週刊プレイボーイ」「広州日報」「亜洲週刊」と意識的に地域やメディアの種類も分散させている。多角的に発信していきたいから。外から見れば、現場主義で常に瞬時に判断しているだけかもしれないけれど、国境を越えた価値観や性別、年齢を超えて、時代の趨勢、物事の本質に迫るべく、自分なりに走りながら総括していくところに僕のスタイルがある。これまでバラバラにやってきた自分の軸足が安定してきているのを実感している。
大学の出席率は15%?
竹中ところで、大学の成績はよかったそうですが、出席率は15%だったのですか。
加藤出席率15%だけど、成績評価に出席が占める割合も15%くらいだから問題ありませんでした。ギリギリ卒業できたという感じです(笑)。担当の先生たちにも「先生の授業はつまらない」と率直に申し上げました。ただ続けて、「先生が作るシラバス(資料)や参考文献は非常に勉強になる。僕は全部読んで、学期の終わりでも、1ヵ月に一度でもいいから、先生と徹底議論します」と、面と向かって言ったんです。
竹中そういうこと言ってしまっていいのですか。
 加藤
加藤僕は、そういうことを公の場で思いきって言うタイプ。言葉にしないと思いは伝わらないから。先生にも面子があるので、その場で怒ったりしないですよ。別に僕は違法行為をしているわけじゃないですから。
竹中だけど、先生が怒って単位をやらないとかにはならないのですか。
加藤そしたら大学やめますよ。「じゃ退学します」と言って去るだけです。「スケジュール調整も含めて自己管理を見直します、反省します、出直します」と言いながら、「自分はあくまでも善意でやっている」と言う。「同級生はおしゃべり、放課後に恋愛している。僕は身を粉にしているじゃないですか。自分の過失は認めるし、改善するように心掛けます。駄目なら、僕は喜んでやめます。男ですから」と言う。
竹中それは確かにそうですね。
時には中国のトップとも接触
加藤攻撃が最大の防御なんですよ。守っちゃいけない、攻めながら守るのが僕のスタイル。不言実行は誰にでもできる。大事なことは、でっかい口を叩いた後に結果を残すことです。
竹中有言実行という感じですね。
加藤有言実行。僕は、海外で頑張っている同世代のサッカー選手を結構意識している。一番意識しているのは年齢も出身も一緒の長谷部誠選手ですが、本田圭祐はスケールが大きいと思う。本田はでかい口を叩いて結果を出そうとしている。批判を恐れずに、自らが信じた道をまっすぐ進んでいる。これ、一番難しいことですよ。
竹中有言実行のほうが実はプロダクティビティ(生産性)が上がるという説もあるそうです。
加藤失敗したら、僕は必要なかったということですよ。これまでもそうしてきたし、これからも実行していこうと思います。
竹中胡錦濤さんをはじめ、中国執行部とはコンタクトを保っているのですか?
加藤不定期ですが、政策決定者との関係は大切にしています。でも適度な距離感を保つことが大切です。最近は慎重ですよ。政治の季節になっているので。基本的には政策論議をします。日中関係をどうするかとか対外関係が中心ですね。内政に関する議論もします。僕の意見が政策に反映されることもある。意識して人脈も作ってきたし、バランスも取ってきた。次は習近平さんですからね。どのように当局と付き合っていくか、今新たな戦略を練っているところです。
近過ぎるとのみ込まれ、遠くだと見えない中国
加藤最近、「中国からいなくなるんですか」とか、「加藤さん、中国離れるの」「もう帰って来ないの」とか盛り上がっているみたいです。でも、僕はやはり中国をきちんと見ていきたい。改革のプロセスに身を投じていきたい。ただ外から批判しているだけでは全くもって生産性に欠ける。今後どういう立場、アクター、場所で働こうと、インディペンデントに、ニュートラルに、チャイナをウォッチする。「生涯を通じて、中国語で、中国のことを、中国人に発信していく」と、すでに公の場で宣言しました。チャイナ・ウォッチとライティング・チャイニーズ、スピーク・トゥ・ザ・チャイニーズということを続けていきます。
竹中一生続けるのですか。
 加藤氏の著作『從伊豆到北京有多遠』(伊豆から北京まで、いかに遠いか)の表紙
加藤氏の著作『從伊豆到北京有多遠』(伊豆から北京まで、いかに遠いか)の表紙
死ぬまでやると宣言しています。そうするのに日本人的な距離感が生きる。距離感が1から10までだとしたら、中国人は1から3または7から10。日本人は3から7。
竹中そうそう。
加藤日本は「親しき仲にも礼儀あり」だから、3から7の距離感。中国は大国で、近づき過ぎたらのみ込まれる。でも、遠過ぎたら見えない。だから、中国に対する発信を続けながら、いったん中国を離れようと思います。そのためのベース(土台)は意識的に作ってきました。
竹中アメリカから見る中国は違うでしょうね。
加藤みなさん、それを知りたいだろうから、アメリカからチャイナレポートを送りますよ。
竹中アメリカから中国がどう見えるかというのは、日本からとも中国からとも全然違いますよね。
米国に行く三つの理由
加藤アメリカに行く理由は三つある。僕は「3」という数字が好きなんです。まずはウォッチャーとして、アメリカという大国を知らないことには何も始まらない。
竹中加藤さん、米国に住んだことはないですね。
加藤そう、住んだことがないから、行きたいし、行かなくてはいけない。二つ目は、アメリカから見た中国やアメリカ人の対中理解を知りたい。ただ知るだけではなくて、中国人に伝えたい。
三つ目は、日本人としての第三者的な視点を探りたい。第三者的な日本人として、アメリカから中国にブリッジを架けるとか。日本の国際的なプレゼンスを高め、発言力を高めていくために、米中間で何かできないかを真剣に考えたい。以上、三つ。それが中国のためにもなる、と僕は信じている。中国の人にもそう伝えてある。これから1年、2年、もっと長くなるかもしれないけれど。どこかのタイミングでドクターは取りたいと思っている。でも焦る必要はないと思う。別にドクターを取ること自体が目的ではないし、ドクターを取って認められるのは当たり前。ドクターがなくても認められるのが男としての魅力だと思う。僕は制度とかルールとは別の次元で勝負をしてきた。これからもそうありたい。旧態依然とした、生産性に欠けるルールはすべて自分がぶっ壊すつもりでやって来たし、これからも当然そうあり続けたい。
ネットにこそある中国の世論
竹中修士論文のテーマは何でしたか。
加藤テーマは「ネットナショナリズムが中国の対日外交政策決定過程に及ぼす影響」。日本語に翻訳すれば12万字ぐらいの分量を中国語で書きました。そもそも、ネットナショナリズムは新しい分野です。ナショナリズム研究はベネディクト・アンダーソン(※2)などたくさんあるけれども、ネットナショナリズムは新しい分野です。しかも、それが中国の意思決定プロセス、対日外交に与える影響については初めての研究なので、資料も何もなかった。
竹中そうですね。
加藤指導教官たちからは「学術研究として成立しません」と言われた。僕が実際にやったことは、中国の公安部、外交部など、政策決定に携わる人たちとの直接インタビュー。「政策決定する際にネット世論を脅威だと思ったことはありますか」という質問に、回答者全員が「ある」と答えてきました。
竹中なるほど。
加藤それらを一応根拠にして論証し、結果的にそれなりに評価されたのです。学術的な評価は難しいけれども、政策研究として意義があると言ってもらえた。今後ともこのテーマに関しては研究を続けていきます。
竹中「ネットの5億人」をすごく強調されていますね。中国は言論統制しているし、共産党への批判は許さない。でも、ネット世論を常に意識せざるを得ない状況になっていると。
加藤なぜそこまでネットを強調するかと言うと、そこにこそ中国の世論があるからです。日本やアメリカは選挙が一番の世論、民意なわけですけど、中国ではいわゆる民衆社会の装置がきっちりしていない。じゃあ、民意はないのかと言えば、それはまさにネットにある。中国には中国の有権者がいて、中国には中国の民意がある。そこを軽視したら、今の中国、これから中国が向かっていく方向性は決して見えてこないということを言いたいのです。
聞き手=竹中 治堅(政策研究大学院大学教授、nippon.com編集委員)
撮影=高島 宏幸

