
「フランスから響け!復興への音色」バイオリニスト竹澤健
文化- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
クラシック、ポップス問わず、世界各地で活躍する日本人音楽家は多い。フランス北東部の街、メスに本拠地を置くフランス国立ロレーヌ管弦楽団のコンサートマスター、竹澤健さんもその一人だ。1991年、弱冠27歳で同オーケストラのコンサートマスターとなってから21年、日仏両国で精力的な音楽活動を続けている。2011年12月、2年ぶりに日本でのソロ・リサイタルを行った竹澤さんに日仏の音楽事情の違い、海外からみた日本の音楽風景などについて聞いた。

竹澤さんの演奏はコチラ→【動画】バイオリニスト竹澤健リサイタル
「タイスの瞑想曲」に込めた思い
——リサイタルの最後に「タイスの瞑想曲」を弾かれましたね?
「フランスの音楽に引かれて留学し、フランスで仕事をしていますから、フランスの作曲家の作品に自分に近いものを感じています。リサイタルでは必ずフランスの作曲家のものを演奏します。タイスの瞑想曲もフランスの作曲家マスネ(1842~1912)の作品です。東日本大震災後、フランス各地で開催された日本のためのチャリティ・コンサートに出演したときにも演奏しました。一人の力は小さいけれどみんなで力を合わせればもっと大きな力を発揮できる、たくさんの人が後ろにいるんだという気持ちは、お金なんか問題にならないほど力になる、と演奏しながら実感できました。自分にとって非常に大きな経験になりました。」
——竹澤さんは、いつフランスに渡られたのですか?
「大学(東京藝術大学)4年の途中でパリに留学しました。パリの国立高等音楽院、コンセルバトワールの年齢制限に間に合うよう行きました」
——留学生活での不安は?
「知り合いもほとんどいないし、一人暮らしも初めてで大変緊張しました。いつかはフランスへ行きたいという夢はあったので大学でもフランス語を専攻していたのですが、最初に行った1985年当時は気の利いた小さな辞書も電子辞書もなくて言葉がうまく通じず、本当に苦労しました」
——学校を卒業してすぐフランス国立ロレーヌ管弦楽団に入団されたのですか?
「パリのオーケストラは卒業したての若者より経験者が採用されると聞いていました。オーケストラはパリに限らないし地方のオーケストラにどんなものがあるのかと、資料を取り寄せました。そのうち一番試験の日にちが近かったのが、ロレーヌのオーケストラでした。僕は楽団にとって初めての外国人で珍しかったので、新聞にかなり大きく取り上げられました」
——最初からコンサートマスターだったのですか?
「そうです。募集するときに最初からコンサートマスターという席の募集があり、応募する側もそれを狙って受けます」
理論立てて話すフランス人、背中で見せる日本人
 ——大所帯のオーケストラの人間関係は大変だろうなと想像します。
——大所帯のオーケストラの人間関係は大変だろうなと想像します。
「偉大な指揮者が必要ですね。指揮台に立つ人が、みんなの注意力をパッと集められる人かどうかで違います。しかしオーケストラと指揮者の関係は難しいところがあり、いいなぁと思っていた指揮者でも馴れ合いが生まれることもあります。カラヤンとベルリンフィルでさえ、最後の方はかなりギクシャクしたそうです。やはり一人の指揮者があまり長くオーケストラに居るのはよくないですね。客演の指揮者が頻繁に来るような場合は、バランスがとれるのでうまく行くと思います」
——竹澤さんの就任は「日本」という新鮮な風が入って大きな刺激になったのでしょうね。
「そうですね。楽員に対する接し方ひとつとってもフランス人は何でも口にして、理論立てて話すのが好きですね。日本人の私は、弾き方は身体で示して後ろの楽員たちが感じる部分で処理できれば一番いいんじゃないかと思っています。言葉にしなきゃいけないことは確かにありますが、それ以外はよほどのことがないと口を出しません。それに指揮者から何か提案があっても、指揮者の前にしゃしゃり出て何かを話すということはしません。そういうスタンスで接しているので、オーケストラ内もキリキリとしたテンションになることはほとんどないですね。かといって、ゆるくなり過ぎてもいけないので、バランスには気を付けています」
——日本のオーケストラで仕事をされたことはありますか?
「学生時代にエキストラで少しやった程度で、プロとしてやっていたことはありません。日本もフランスもオーケストラのあり方は同じでしょうが、目指しているものが少し違うように思います。今そんなこというと、日本側から“もうそんなことないよ”といわれるかもしれないし、そうであってほしいのですが、日本のオーケストラはかつて、キチッとそろえること、はみ出さないこと、みんなが同じように合うことを目標にしていました。その目標を達成してから“音楽”をしよう、という雰囲気でした。しかし、それだと音楽の勢いやフレーズの流れが生まれにくい。流れがあるから全員が合わせられるという側面もあるのに、最初から合わせることだけを目指すと流れが途切れてしまいます。とはいえ、日本のオーケストラも日々変わってきていますし、成長してきていると思います」
ストラディバリウスの特別な音
——日本音楽財団からストラディバリウスを貸与されて弾かれていたことがありましたが、特別なものでしたか?
 「1999年に日本とフランスでリサイタル・シリーズをやったときに貸与していただきました。借りたのは“ムンツ”です。彼の最晩年の作品で、楽器の内側に手書きで“我が92歳のときの作”と書いてあります。それでもキレイというと変ですが、素晴らしい。ストラディバリウスは高音のハーモニクス、日本語で『倍音』といいますが、それがものすごく豊富ですね。1つの音を弾いても、それが鳴るだけじゃなく、まわりにも広がります。この楽器に慣れるまでは少し時間はかかりました。普段120~130キロそこそこしかでない車に乗っていたのが、いきなりフェラーリに乗ったみたいな感じです。最初は少し怖く感じても、スピードを上げてみたらもう止められない、というような感触でした(笑)」
「1999年に日本とフランスでリサイタル・シリーズをやったときに貸与していただきました。借りたのは“ムンツ”です。彼の最晩年の作品で、楽器の内側に手書きで“我が92歳のときの作”と書いてあります。それでもキレイというと変ですが、素晴らしい。ストラディバリウスは高音のハーモニクス、日本語で『倍音』といいますが、それがものすごく豊富ですね。1つの音を弾いても、それが鳴るだけじゃなく、まわりにも広がります。この楽器に慣れるまでは少し時間はかかりました。普段120~130キロそこそこしかでない車に乗っていたのが、いきなりフェラーリに乗ったみたいな感じです。最初は少し怖く感じても、スピードを上げてみたらもう止められない、というような感触でした(笑)」
文化は伝える努力をしないと衰退する
——日本とフランスではお客さんは違いますか?
 「フランスに限らず欧米全体でそうかもしれませんが、お客さんが感じたものをすぐに表現します。ダメだったら平気でブーイングをしますし、演奏している側にも直接的に感覚として伝わってくるものがあります。一方で、日本のお客さんは集中して聞いているという感覚があります。ホールの空気が違います」
「フランスに限らず欧米全体でそうかもしれませんが、お客さんが感じたものをすぐに表現します。ダメだったら平気でブーイングをしますし、演奏している側にも直接的に感覚として伝わってくるものがあります。一方で、日本のお客さんは集中して聞いているという感覚があります。ホールの空気が違います」
——日本ではクラシック音楽は常に根強い人気がありますが、フランスではいかがですか?
「若い人がクラシックから離れていく傾向にあります。フランスに限らず、ドイツでもそうですね。フランス人にいうと驚くし、僕も驚くに値することだと思うんですが、実は、戦後日本は学校教育の中で西洋音楽を自分たちにないものだからと、きちんと時間をとって教えようとしてきましたよね。たいていの小学校では各教室にピアノがありますが、フランスでは考えられません。音楽の授業時間も日本のようにはありません。フランスではかつて、教会に行けば日常的に音楽を聴くことができた。それが教育にもなっていた。それが今では崩壊してしまっています。今こそフランスでは時間をとって教育することが必要だと思うんです。僕も自分の子供が小学生のときに担任の先生に提案して、コンサートのリハーサルを子供たちに見学してもらったことがあります。日本の伝統文化も同じです。途切れないように伝えていかないといけない。外国に紹介するのはもちろんですが、日本の中で伝える努力をしなくてはいけません」
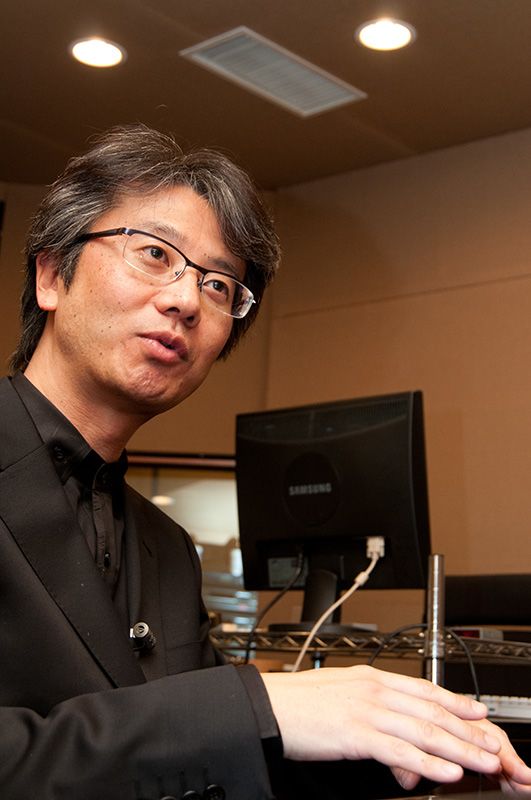 芸術の力を世界から日本へ
芸術の力を世界から日本へ
——最後に日本へのメッセージをお願いします。
「2011年に大変なことがおこって、日本は再建のために頑張らなければなりません。音楽などの芸術、その他いろんな分野で活動されている方が日本国内だけに止まらず、世界各国いろんなところから、力を寄せてくださることが大事だと思います。かつては外国にいる感覚だと“日本は経済的に豊かな国だから、そのうち自力でなんとかなるよ”という見方をする人もいましたが、今は世界中どこかで皆つながっているわけです。どこからのエッセンスでも日本はいただいていい方向に向かってほしいですし、それに力を貸せることがあれば何でもやりたいと思います」
撮影=染瀬 直人
取材・文=和田 靜香
