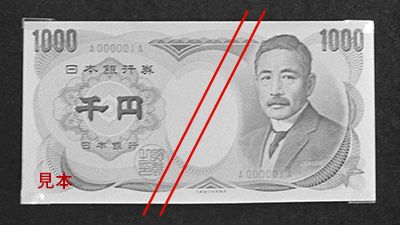夏目漱石:世界中で読み継がれる永遠の現代作家
文化- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
近代日本を代表する小説家、夏目漱石(本名・夏目金之助)は、今からちょうど150年前の江戸時代の末年、1867年に生まれ、100年前の1916年に49歳で死んだ。1世紀も前の小説家なのに、今の日本人にとって古さを感じさせない永遠の現代作家だ。中国人、韓国人にも普遍的な小説家として受け入れられ、欧米では20世紀文学の開拓者との評価もある。漱石の小説は、近代日本で初めての世界文学と言えるかも知れない。
孤独な幼少期を経て英文学者へ
漱石は1867年2月9日、江戸・牛込馬場下横町(現東京都新宿区喜久井町)で、名主の夏目直克の5男として生まれた。その後、友人夫妻の養子として育った後、夏目家に戻るなど複雑な幼少期を過ごした。その結果、孤独感から自立心を強めたとされる。
親の都合で小学校をたびたび転校した後、東京府第一中学校、漢学塾の二松学舎、英語塾の成立学舎を経て、17歳で、大学予備門(後の第一高等中学校)に入学。1890年、帝国大学(後の東京帝国大学)文科大学英文学科に入学し、93年に大学院に進んだ。大学予備門では、俳人で、俳句の近代化を大成した正岡子規と出会った。
後に英文学者として教職に就く漱石だが、二松学舎に学んだのは、当初は英語が嫌いだったためだ。漱石の漢詩文の愛好は生涯続く。「漱石」という雅号も、負け惜しみの強さを示す中国の成語「漱石枕流(そうせきちんりゅう)」(※1)が出典だ。中国古典を基礎教養とした、江戸知識人の姿を受け継いでいるようにみえる。
漱石は大学時代から、教職に就いている。92年、東京専門学校(現、早稲田大学)の英語の講師となった。93年には、東京高等師範学校の英語教師に就いた。当時の校長で、講道館創始者である柔道の大家、嘉納治五郎に気に入られ、同校の教師への就任を懇請されたのだという。このころ鎌倉の円覚寺の塔頭、帰源院で参禅したことも、後に大きな影響を及ぼす。
95年、愛媛県松山市の愛媛県尋常中学に教師として赴任した。松山は子規の故郷であり、当時、結核の静養のため帰郷していた。松山では、子規とともに句会を開くなどして、俳句に精進した。この時の経験が、名作『坊っちゃん』の下敷きとなる。96年には熊本県の第五高等学校講師、その後、教授に就任した。五高勤務の時代に、中根鏡子と結婚した。
英国留学で勉学に没頭、神経を病む
1900年、漱石は文部省から「英語研究のため」に英国留学を命じられ、10月末に現地に着いた。渡英後、化学者の池田菊苗(いけだ・きくなえ)と約2カ月間同居した。池田はグルタミン酸を発見し、うま味調味料「味の素」の発明者となる。専門分野にとどまらない教養人で、哲学にも造詣が深く、漱石は知的刺激を受けた。
留学の残り1年間は、勉強に明け暮れた。「文学とは何か」ということが主題で、この時の猛勉強は、後に『文学論』として結晶する。この間、神経衰弱が悪化し、文部省が一時、精神の異常を疑ったとされる。
帝大講師を辞め小説家に専念
1903年1月、英国から帰国すると第一高等学校嘱託と東京帝国大学の講師に就任した。05年1月、俳人、高浜虚子が主催する雑誌『ホトトギス』に『吾輩は猫である』の最初の1篇が掲載され、読者から大好評を得た。その後、同誌などに 『倫敦塔』『坊っちゃん』と相次ぎ作品を発表、小説家としての名を急速に高めた。
06年、毎週木曜日に漱石を慕う教え子や若手文学者が集まる「木曜会」の第1回が開かれた。内田百間、野上弥生子らの小説家や、安倍能成、和辻哲郎ら学者の他、まだ学生で後に著名小説家となる芥川龍之介や久米正雄らも参加していた。
07年、一切の教職を辞め東京朝日新聞社へ入社し、本格的に小説家としての道を歩み始めた。日本の最高学府である一高と東京帝大の教師から小説家への転身は、当時の立身出世観からは考えられない逸脱として、世間の話題を呼んだ。同年、生家に近い牛込区早稲田南町(現・東京都新宿区)に転居した。後に「漱石山房」と呼ばれたこの家で、「木曜会」が続けられた。
漱石は朝日新聞紙上で、『虞美人草』『坑夫』『夢十夜』を書き、前期三部作として知られる『三四郎』『それから』『門』を連載した。
10年、43歳のとき胃潰瘍となり東京の病院に入院する。退院後、療養先の修善寺温泉(静岡県伊豆市)で一時、危篤状態に陥り、仲間や弟子が駆けつける騒ぎとなった。これを「修善寺の大患」と言う。
11年、文部省から博士号授与の通達があったが、漱石は辞退した。学位のために学問する当時の気風を嫌ったためだ。
12年から『彼岸過迄』『行人』『こころ』後期三部作を朝日新聞に連載し完成させた。この間、胃潰瘍が再発し、神経衰弱も悪化した。16年に『明暗』の連載を始めたが、胃潰瘍が悪化し、12月9日に49歳で死去。『明暗』の連載は第188回で中断した。
エゴイズムと孤独を見つめ則天去私へ
漱石の小説をたどると、エゴイズムとそれがもたらす孤独の苦しみを描き続けた後、私心にとらわれず、身を天地自然に委ねて生きる「則天去私(そくてんきょし)」の境地に至る軌跡がみてとれる。
『吾輩は猫である』は、猫「吾輩」が、飼い主の家に集まる奇妙な知識人の生態を観察し、笑い飛ばすユーモア小説だ。猫を語り部にした独特の作風と、落語を参考にした生き生きとした語り口が読者を集め、漱石の小説家としての地位は不動のものとなった。
『草枕』は、文明に満ちた東京での生活に耐えられなくなった画家が、温泉場に向かい、世間的な欲望や理非を超越した「非人情」の心持ちで遊ぶ様を描く。
前期三部作は『三四郎』『それから』『門』。『三四郎』は純朴な青年の愛の形とともに、「迷える羊」に似た青春の危うさが描かれている。『それから』以降の小説は、男性2人と女性1人の三角関係が好んで取り上げられている。
『それから』は、資産家子息の有閑な知識人が、友人の妻を深く愛し、一緒に自立して生きて行くことを決意する物語。『門』では、親友の妻を奪ってひっそり暮らす役所勤めの男が、罪悪感に苦しみ救いを求める様が描かれる。
後期三部作の『彼岸過迄』『行人』『こころ』では、エゴイズムと孤独というテーマをさらに掘り下げた内容となっている。
中でも『こころ』は、現代の高校の教科書に掲載され、漱石の小説の中で、今でも最も広く読まれている。物語の核心部分は「私」が、自殺した「先生」から送られた遺書の中で語られる。「先生」は、学生時代の友人Kを裏切り、「奥さん」と結婚。Kは失意のため自殺してしまう。「先生」は苦悩しながら生きてきたが、エゴイズムと、それがもたらす孤独に苦しみ、明治天皇の崩御をきっかけに自殺してしまう。
遺作の『明暗』は、円満ではない夫婦関係を軸に、エゴイズムと孤独を追った小説で、最後は「則天去私」を描こうとしたとされる。晩年に理想と考えた境地だ。漱石の参禅の経験が下敷きにあったとされ、漱石の葬儀で導師を務めた円覚寺の釈宗演管長は「大乗仏教の真精神」と評している。
 1912年、明治天皇の崩御に際し、喪章をする45歳の漱石(国立国会図書館所蔵)
1912年、明治天皇の崩御に際し、喪章をする45歳の漱石(国立国会図書館所蔵)
近年高まる海外での評価
漱石の作品は、欧米では川端康成や三島由紀夫に比べて著名ではないが、いくつかの作品が英訳されている。また、近年になり研究も多様化し、評価が高まってきた。
1965年に英国の日本文学研究家によって『坊っちゃん』『草枕』などが英訳された。英国の日本文学研究者、ダミアン・フラナガン氏は、2005年に『倫敦塔』の英訳を出版し、漱石をシェークスピアにも比肩しうる世界的な文豪と評している。
米国の日本文学研究家、マイケル・K・ボーダッシュ氏は、漱石を魯迅、カフカ、ジョイスと並ぶ20世紀文学の開拓者の仲間と位置づけた。また、心理学や社会学も用いて、文学とは何かという問題を考えた『文学論』について、世界的にも先駆者だと評価している。
中国では、最も有名な日本人小説家で、早くも中華民国期に、魯迅が漱石の小品2本を翻訳しているほか、魯迅の弟、周作人も作品を紹介した。現在は、ほぼ全ての作品が翻訳され、『吾輩は猫である』は少なくとも20種類近くの翻訳版があるとされる。
漢詩文への造詣が深く、約200本に上る漢詩や漢文の作品があることや、中国の作家と同様、国家や社会への目配りがあることも、漱石が中国人に親近感を持たれる理由のようだ。何より、近代中国と同じく、激動の近代化、西洋化の中でもがく日本の知識人の姿が、共感を呼ぶ。中国人にとって漱石は、国の違いを超えた普遍性を持つ作家と言えるだろう。
韓国では歴史的な背景から、日本文学の受容までに複雑な経過をたどり、漱石は1990年代になってようやく読まれ始めた。これまでに、漱石全集14巻が刊行。日本の小説というより、世界文学として受け入れられている。
夏目漱石の生誕から150年。これを機に漱石文学に挑戦してみてはいかがだろうか。きっと何か新しい発見があるはずだ。
 漱石公園隣接地(左側)では「新宿区立漱石山房記念館」が建設中(2017年9月オープン予定)
漱石公園隣接地(左側)では「新宿区立漱石山房記念館」が建設中(2017年9月オープン予定)
取材・文=井上 雄介
写真=ニッポンドットコム編集部
(※1) ^ 中国の孫楚は「石に枕し流れに漱(そそ)ぐ」と言うべきなのに、「石に漱ぎ流れに枕す」と言ってしまった。その誤りを指摘されると「石に漱ぐのは歯を磨くため、流れに枕するのは耳を洗うためだ」と屁理屈を並べて言い逃れをした。そこから負け惜しみの強いことを意味するようになった。