
いくつもの『方丈記』:「3.11」がドイツに与えた文化的、哲学的衝撃
社会 文化- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
東日本大震災を最も深刻に受け止めたドイツ
2011年3月11日の東日本大震災と、その後に起こった福島第一原子力発電所の事故は、全世界に大きな衝撃を与えたが、中でもそれを最も深刻に受け止めたのはドイツ国民だったようだ。ドイツ政府はこの大惨事から数日足らずで、原子力発電を段階的に廃止すると発表し、同年6月には、このエネルギー政策の大転換を議会も追認した。しかし、「3.11」の波紋は政治のレベルを超えたところまで及んでいる。それがなかなか表に出てこないのは、ドイツ人の日常的な文化の奥深くで進行しているからであろう。
しかし、ここでは「3.11」に対する直接の反応について言及するつもりはない。もちろん、震災以降、団結と寄付を呼びかけるイベントや募金活動、一時的に国外避難を希望する日本人を受け入れようとする試み、東北の被災地復興援助のため日本に行くボランティアの若者たち(私の大学の学生も含まれる)など、多くの取り組みが今でも続いている。ドイツのあらゆるメディアも当然、震災と原発事故を大きく取り上げたが、その後も、そうした出来事に対する適切な対応とはどういったものかなどの議論が続いている。あるテレビ局の記者は被災地からの報道が評価され、メディア関係者憧れの報道賞を受賞した。もちろん多くの記者が現地を訪れ、津波で家を流され仮設住宅で厳しい生活を強いられている被災住民、あるいは荒廃した故郷の村に戻った人々などに直接インタビューするなど、山積する問題に深く踏み込んだ印象深い報道もあった。
震災後1年で報道は再びピークに
震災から1年たった頃、関連報道は再びピークに達した。あるテレビ局は、菅直人前首相への取材を中心に、日本の当局の不十分と思われる情報開示や意思決定に対する失望感などの背景を鋭くえぐり出し、大きな注目を浴びた。この番組は日本語の翻訳付きでYouTubeにアップされ、今年5月の時点ではすでに100万回以上も視聴されていた。私が今年4月末に日本を訪れた時、いつものヘア・スタイリストの女性から、YouTubeでこの番組を見たと聞いて驚いたものだった。
しかし、もっと広く文化的な側面での影響はどうなのか。政治家や学者は、原発の段階的廃止による経済、環境、社会、倫理への影響について、あるいは災害報道に際してのセンセーショナルで質の悪いジャーナリズムなどについて議論しているが、そうしたものを超えた影響を確認することはできるのだろうか?
東北地方の地震、津波、原発事故による三重苦は、世界の日本へ対する関心を改めて呼び覚ます効果があった、そう言うと、いささか皮肉に聞こえるかもしれない。しかし、震災発生当時日本に滞在していた人々の報告も含め、「3.11」を分析する書物が驚くほど多く出版されたことにもその影響は現れている。
メディアの文化欄は、日本人の精神性、日本における地震の歴史、ゴジラや鉄腕アトムなどの漫画のキャラクターと災害の関係といったテーマを特集した。『シュテルン(Stern)』や『デア・シュピーゲル(Der Spiegel)』など、週刊誌の特別版も多くの写真を掲載し、著名日本人へのインタビューや、ジャーナリスト、日本専門家による多くの記事を織り交ぜ、日本の歴史と文化を分析した。
特別な意味を持つ独訳『方丈記』の再出版
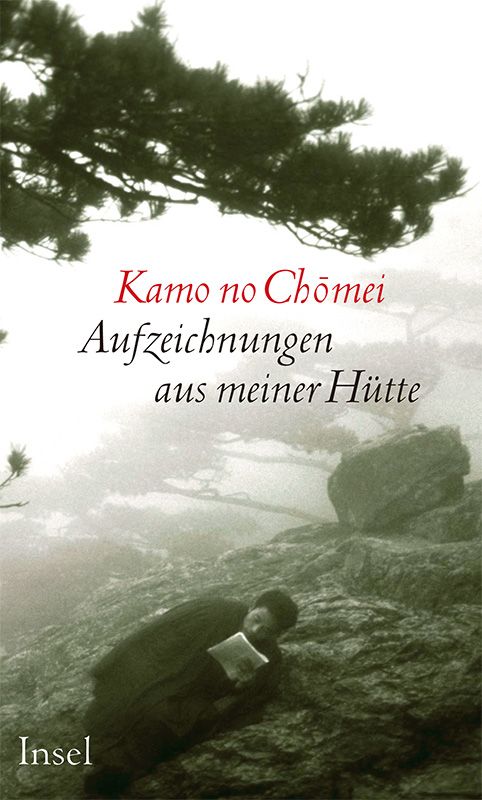 鴨長明『方丈記』ドイツ語訳(訳者:ニコラ・リスクティン、Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG、ベルリン、2011年)。
鴨長明『方丈記』ドイツ語訳(訳者:ニコラ・リスクティン、Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG、ベルリン、2011年)。
こうした中で、13世紀初めの優れた日本文学の古典、鴨長明の『方丈記』のドイツ語訳が再出版されたことには特別な意味がある。『方丈記』は、長明が生きた時代の天変地異や飢饉の記述、回想をつづった印象的な随筆である。あるドイツの専門家はこの作品を、過去への愛着と無常観の間で揺れる心情を描いたものと評した。小さな庵(いおり)を意味する「方丈」は、心を解き放つ場所であると同時に隠れ家でもある。『方丈記』は読むものの心に、不安と激動の時代をどう生きるかについて、時代を超えた視点を与えてきた。
季刊誌『Neue Rundschau』の2012年春号は、「3.11」を考える現代の日本人作家10人の作品のドイツ語訳を特集した。その中には、メディアの役割を問い直す人文科学系の作家や学者と並んで、川上弘美、平野啓一郎、桐野夏生、岡田利規、大江健三郎といった著名人の名前もあった。編集サイドの説明によると、このプロジェクトは東日本大震災の前に日本の雑誌『群像』と共同企画していたが、「3.11」を受けて急遽刊行されたという。
影響の大きさを示す映画監督クルーゲの最新本
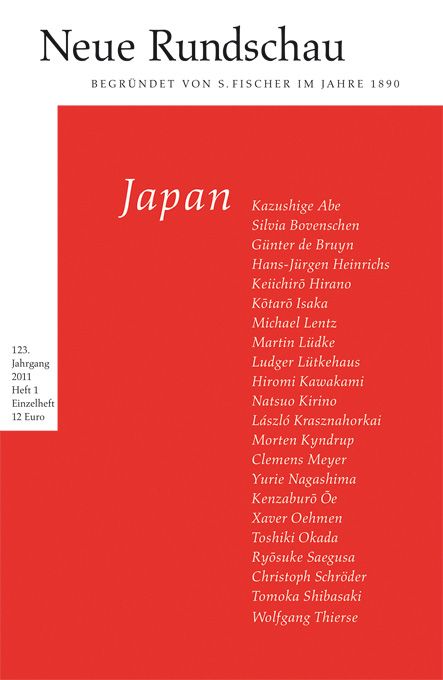 季刊誌『Neue Rundschau』の2012年春号は、東日本大震災を考える特集号となった(S.Fischer Verlag GmbH、フランクフルト、2011年)。
季刊誌『Neue Rundschau』の2012年春号は、東日本大震災を考える特集号となった(S.Fischer Verlag GmbH、フランクフルト、2011年)。
震災が今後のドイツ文学にどのような影響を与えるのかを評価するのは早計すぎるが、すでにきわめて独創的なとらえ方が散見されることは指摘しておいてもいいだろう。その中で、おそらく最も異彩を放っているのは、2012年春に80歳の誕生日を迎えた作家で映画監督のアレクサンダー・クルーゲの最新作、『Das fünfte Buch: Neue Lebensläufe. 402 Geschichten(第五の書:新しい履歴書。402の物語)』である。クルーゲは、50年前から始めた周期的な「実話」収集という大いなる物語プロジェクトを、この作品で終わらせるつもりのようだ。クルーゲは言う。「我々が積み重ねてきたこれまでの経験(履歴書)というのは、家のようなもので、その家の窓から私たちは世界を解釈しようとするのである。つまり、経験の器を文学風に語ることも可能なのである」
564ページに及ぶこの作品の表紙には、「3.11」の津波で流され、がれきの中に立つ家の屋根に取り残された、象徴的な船の写真が掲載されている。第一章は、18世紀のフランスの小説や有名な歴史上の人物との出会いなど、さまざまなテーマについての創作や実話、回想録、エッセイなどが織り交ぜられている。また、第一章には「原子力の長年の友だち」と銘打った箇所があり、クルーゲはそこで、未来人のための地球外災害シェルターや古代の地震や津波についての研究報告を交えながら、福島の原発事故に関する専門家の話を紹介している。
震災の衝撃が、日独をこれまで以上に結び付けた
 アレクサンダー・クルーゲの最新作は、大惨事をテーマにし、より独創的なアプローチをとっている(Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG、ベルリン、2012年)。
アレクサンダー・クルーゲの最新作は、大惨事をテーマにし、より独創的なアプローチをとっている(Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG、ベルリン、2012年)。
クルーゲは、第二次世界大戦の空襲の中をかろうじて生き延びた。生き延びたのはほんの偶然にすぎないという思いが、彼の主題である。ある批評家が指摘したように、クルーゲの主人公たちを突き動かしているのは真実の探求でも情熱でもない。それは自尊心であり、防衛本能であり、プロ意識である。他にもクルーゲは、大作『Das fünfte Buch』にも通じる極限の体験をテーマに、今年4月に放送されたラジオ・ドラマの脚本を書いた。高い評価を受けたこの作品は、日本の危機がドイツ文学にどのように影響しているかを示す、ほんの一例にすぎない。いうなれば、これもひとつの『方丈記』なのである。そしておそらく、これからもっと多くの『方丈記』が登場してくると思われる。
東日本大震災は、より多くの犠牲者を出した2004年のインド洋大津波よりもはるかに強くドイツ人の心を揺さぶったといえる。日本のような高度に発展した国で起こった今回の大災害は、ドイツの人々に、自然を支配しようとすることの傲慢(ごうまん)、さらには技術と進歩の限界を強く感じさせ、心の深みに横たわる哲学的レベルにおいて、自らの存在の基盤を問い直すきっかけを与えたようだ。今回の災害を通じてドイツ人は、人間存在の危うさに改めて気づかされたのである。そしてその衝撃が、日本の人々と私たちドイツ人をさらに強く結び付けたのだと思えてならない。
(2012年8月2日、原文英語掲載)