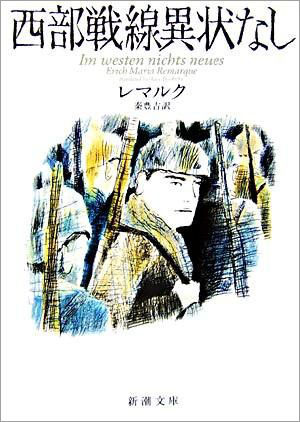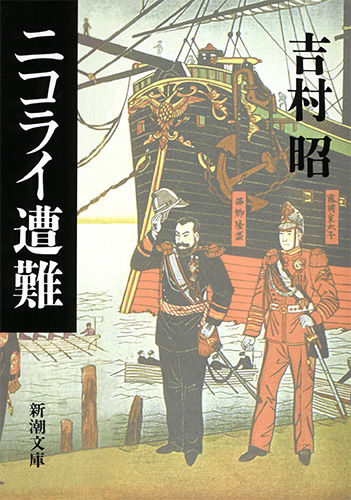【書評】「古き良き時代」のスパイの世界へ:ロバート・ゴダード1919年三部作
Books- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
レトロでノスタルジックなスパイ小説だが、けして色あせてはいない。
文庫にして6冊にわたる大長編だが、ひるむことはない。いったん、ページをめくるや、本作の著者ロバート・ゴダードは、「古き良き時代」のスパイの世界へと、一気に読者をひきずりこんでいくことだろう。そこには豊かな物語に出会えた至福の時がある、と断言してもよい。
ここで取り上げる”1919年三部作”は、2017年1月から5月にかけて3巻にわけて順次刊行された。
初めの巻を刊行まもなく手にした私は、次巻以降のいちはやい出版を待ちわびたものだが、いまの読者は全巻を一気に読むことができる。これは僥倖である。
舞台は講和会議最中のパリ
巻を開く前に、本作が描く時代の簡単な予備知識を――。
1919年4月、第一次世界大戦の終結により、フランスのパリで対独講和に関する会議が開催された。史上、パリ講和会議と呼ばれるものだが、米英仏伊日を中心とする戦勝国側の利害が衝突し、講和条約(ヴェルサイユ条約)締結に至るまで5カ月を要することになる。
この会議には、世界から33カ国の代表団が参加したものの、実質的には米英仏の3国が議事進行を牛耳っており、ウィルソン米大統領、ロイド・ジョージ英首相、クレマンソー仏大統領ら三巨頭にオルランド伊首相を加えた非公開の4人会議がしばしばもたれ、互いが権利を主張する中での腹の探りあいが続いた。各国代表団もまた、蚊帳の外におかれまいと秘密会議の討議内容を探るべく、情報収集活動にいそしむことになり、ここに各国情報部員やロビイストらが暗躍することになる。
本作には、日本首席全権・西園寺公望侯の率いる日本代表団も重要な役回りで登場する。
こうした歴史背景が本作の重要な舞台装置になっているので、歴史好きにとってはおおいに興味をそそられることになるだろう。
そしてなにより、映画や小説でよくお目にかかる現代スパイが駆使する無粋なハイテク道具なんてものとはいっさい無縁である。スマホやインカムといった通信機器や、パソコンを使った検索やGPSを駆使しての追跡なんてものもない(クラシカルな自動車による追跡劇は描かれているが)。
頼りになるのはおのれの知恵と足を使った行動力。手掛かりを得るためには人脈を駆使した情報収集と、根気のいる張り込みや尾行、聞き込みが重要になる。
往年のスパイの世界では、いやおうなしに敵味方の入り組んだ人間関係が濃密になってくるわけで、本作に登場する主人公や数多くの脇役たちは、いずれもが個性と魅力に溢れている。
多彩な人物描写と巧みな群像劇、このあたりが本作品の最大の読みどころといえるだろう。
主人公は複葉機のパイロット
さて、前置きが長くなった。本作は、まさにパリ会議が行われている最中に起こった小さな事件を契機として、物語が展開していく。
主人公は元英国陸軍航空隊(RFC)の中尉ジェイムズ・マクステッド(通称マックス)である。
彼は、パリ会議のこの年、27歳になる長身痩躯の魅力的な若者で、
「中年を迎えても苦み走った魅力を放つであろう端整な顔立ちをしていて、少年のように無造作な金色の瞳を持ち、わずかにゆがめた口元が皮肉屋の雰囲気を感じさせる」(『謀略の都』上巻9頁)
という人物像。おまけに「行動と本能の人」であり、困難をものともせず突き進む。そもそもが、外交官である第二代準男爵サー・ヘンリー・マクステッドの次男として生まれ、後継ぎではない気楽さから空に冒険を求めていくのだ。
その経歴は、ケンブリッジ大学卒業後、ファーンバラ航空学校を経て陸軍航空隊の複葉機のパイロットとなり、第一次大戦を迎えて西部戦線へ。そこで偵察任務につくが、前線で敵陣の背後に墜落、幸い命を落とさずにすんだものの、ドイツの捕虜収容所で1年半、囚われの身となる。
収容所で終戦を迎えたマックスは、戦後は相棒の航空機整備士サム・トゥエンティマン(通称サム)と組んで、航空学校を経営しようと考えていた。
だが、パリ会議に英外交団の一員として参加していた父サー・ヘンリーが、猥雑なモンパルナスのアパートメントの屋根から謎の転落死。英仏政府は会議最中のスキャンダル化を恐れ、事故死で片づけてしまう。訃報に接しパリへ赴いたマックスは、死亡状況に不審を抱き、ついには何者かによって殺害されたという確信に至る。
手掛かりは、父親が遺した1枚のメモ書き。そこに記された文字と数字の謎を解き明かさなければならない。かくしてマックスは、殺害犯を突き止めるべく、孤軍奮闘するのだが。
事件はパリ会議にまつわる利権争いと密接にかかわっている。そこに英米仏の情報機関の思惑が交錯し、マックスは、事件を解明していくにしたがってその謀略の渦中に投げ込まれていく――。
「大胆さと度胸にはAランク」
先に、多彩な人物描写と巧みな群像劇と述べたが、主要な登場人物の中でも、ここでは、まずこの3人の紹介は外せない。
まず第一に、マックスと行動をともにし、ときに彼の窮地を救う航空機整備士のサム。ふたりは戦時下に強い絆で結ばれた間柄だが、
「戦争中に(略)サム・トゥエンティマンがその勤勉さと工夫によって、十通りの方法で十回はマックスの命を救ったであろうことは明白な事実だった。サムは一度たりともマックスを失望させなかった。そんな忠実な人間はほかにだれもいない」(同246頁)
というほどの頼もしい相棒である。
最終巻の最後の最後まで、ふたりの活躍から目が離せない。
そして、パリに在駐している英国の情報機関、内務省秘密検察局のホレス・アップルビー。彼は百戦錬磨、凄腕の情報部員として描かれる。
パリでは表立って動きにくい英情報部は、アップルビーの発案で、マックスの真相究明を黙認し、ときに手掛かりを与え、彼の行動を見張ることでその成果の果実を横取りしようと考える。
アップルビーは、ロンドンの秘密検察局本部で疑り深い上司を前に、マックスを評してこう太鼓判を押す。
「私は本人に会っていますが、大胆さと度胸にはAランクをつけますね」(同204頁)
つまりスパイとしての適性を見出すわけだが、そもそもふたりは敵なのか味方なのか。
当初、アップルビーは、マックスを利用しようとだけ考えていたが、巻を追うにしたがってふたりの関係が微妙に変化していく。試練に直面し、それを乗り越えていくにつれふたりの信頼感が醸成されていく様は、読者の胸を熱くすること必定。
最後に、パリで出会い、やがて心強い味方となっていく米国人でロビイストの片割れだったスクールズ・モラハン。マックスから見て、彼はこんな男だ。
「体が大きく、自信にあふれ、船のエンジンのように低く重々しい声をもつモラハンは、そこにいるだけで安心感があった」(同311頁)
幾多の修羅場を潜り抜けたモラハンは、しばしばハードボイルドな名セリフを口にする。私がしびれたのは次の場面。
マックスが、父ヘンリーを知るモラハンに、亡くなる直前の父の印象を尋ねたときのこと。
「目が生きてると思った」(同313頁)
と、モラハン。それに続く言葉がうならせる。少々長くなるが引用させてほしい。
「あの歳の男の多くは、持ち札を伏せてテーブルを離れる。まだ勝っているのにゲームを放棄する場合、そんなふうにするんだ。そのとき彼らの中で何かが死ぬ。(略)目に光がなくなったのがわかる。それは二度と戻ってこない」
だが、ヘンリーはまだ光を持っていたという。
「テーブルを離れていなかった。まだゲームに挑んでいた」
「それはいいことなんだね?」
とマックス。
「それでこそ生きていると言える」
この後、マックスは何度も絶望的な窮地に立たされるのだが、都度、モラハンから最後まで諦めてはいけないことを学び、困難を乗り越えていく。
最終巻冒頭シーンは横浜の埠頭
とはいうものの、けしてタフガイだけが活躍する冒険活劇ではない。物語に彩をそえる魅力溢れる美貌の未亡人や女スパイも登場するので、どうぞお楽しみに。
そして、謎解きの一部だけ披露すれば、マックスとともに彼らが追いかけるのが、帝政ドイツの大物スパイだったフリッツ・レンマーである。
彼はヨーロッパ中にはりめぐらされたスパイ網を束ねていた。帝政ドイツ崩壊後、カイザーとともにオランダに亡命したまでは知られているが、その後の消息は不明。たが、レンマーと彼のスパイ網は生き残って復権を目論んでおり、各国の情報機関は神経をとがらせている。用心深いレンマーの容貌はほとんど知られていないし、現在の居所は誰にも知られていないはずだった。
作者のゴダードは、主人公のマックスとともに、読者を長い旅路へ導いていく。第二巻にあたる『灰色の密命』からレンマーが姿を現し、舞台はパリから英国スコットランド、ロンドン、再びパリを経てマルセイユから最終巻では日本へ向かう。
日本の読者にとって、最終巻はなおさら興味深いものになるだろう。マックス活躍の場はまるまる日本となり、冒頭シーンは横浜の埠頭で始まる。そこから新橋、銀座、深川、そして真相を求めて京都へ向かうのだ。
とかく外国人が描く日本は違和感満載になりがちだが、作者は見事に当時の時代の空気をつかみ、行き交う人々、貧しい町屋の佇まい、そして風習まで見事に描き切っている。
などと感心して読み進むと、物語はいよいよ佳境へ。マックスは、父ヘンリーが日本駐在の二等書記官だった頃に、日本で生まれている。最初の巻でさらりと触れられているのだが、まさか最後の最後にかような展開になろうとは!
そもそもの謎の原点には、1891年5月、おりしも来日中だったロシアのニコライ皇太子の暗殺未遂、いわゆる大津事件がかかわっていた――。
最後に、本作ではエンターテインメントを堪能すると同時に、ここで描かれた歴史への興味も湧くはずだ。西部戦線の様相ならレマルクの『西部戦線異状なし』を。大津事件については吉村昭の『ニコライ遭難』をお薦めする。
謀略の都(上) 1919年三部作 1
ロバート・ゴダード(著)、北田 絵里子(翻訳)
発行 講談社(講談社文庫)
文庫判 384ページ
定価 1060円+税
ISBN 9784062935739
発売日 2017年1月13日
謀略の都(下) 1919年三部作 1
ロバート・ゴダード(著)、北田 絵里子(翻訳)
発行 講談社(講談社文庫)
文庫判 384ページ
定価 1060円+税
ISBN 9784062935746
発売日 2017年1月13日
灰色の密命(上) 1919年三部作 2
ロバート・ゴダード(著)、北田 絵里子(翻訳)
発行 講談社(講談社文庫)
文庫判 384ページ
定価 1000円+税
ISBN 9784062936217
発売日 2017年3月15日
灰色の密命(下) 1919年三部作 2
ロバート・ゴダード(著)、北田 絵里子(翻訳)
発行 講談社(講談社文庫)
文庫判 368ページ
定価 1000円+税
ISBN 9784062936224
発売日 2017年3月15日
宿命の地(上) 1919年三部作 3
ロバート・ゴダード(著)、北田 絵里子(翻訳)
発行 講談社(講談社文庫)
文庫判 336ページ
定価 980円+税
ISBN 9784062936620
発売日 2017年5月16日
宿命の地(下) 1919年三部作 3
ロバート・ゴダード(著)、北田 絵里子(翻訳)
発行 講談社(講談社文庫)
文庫判 336ページ
定価 980円+税
ISBN 9784062936637
発売日 2017年5月16日