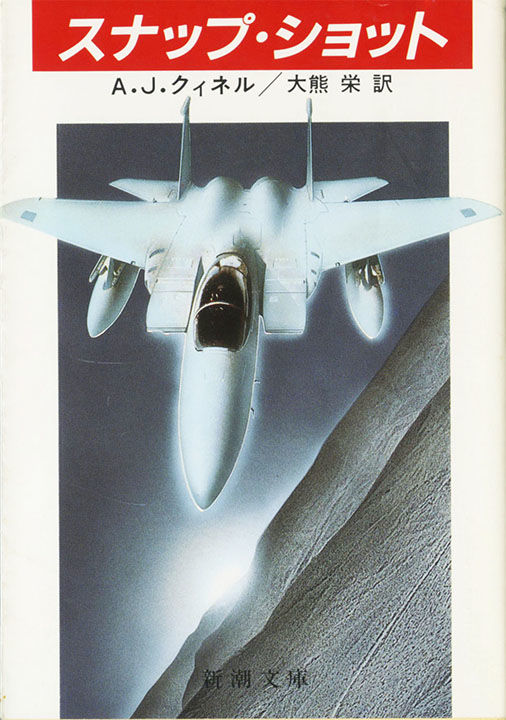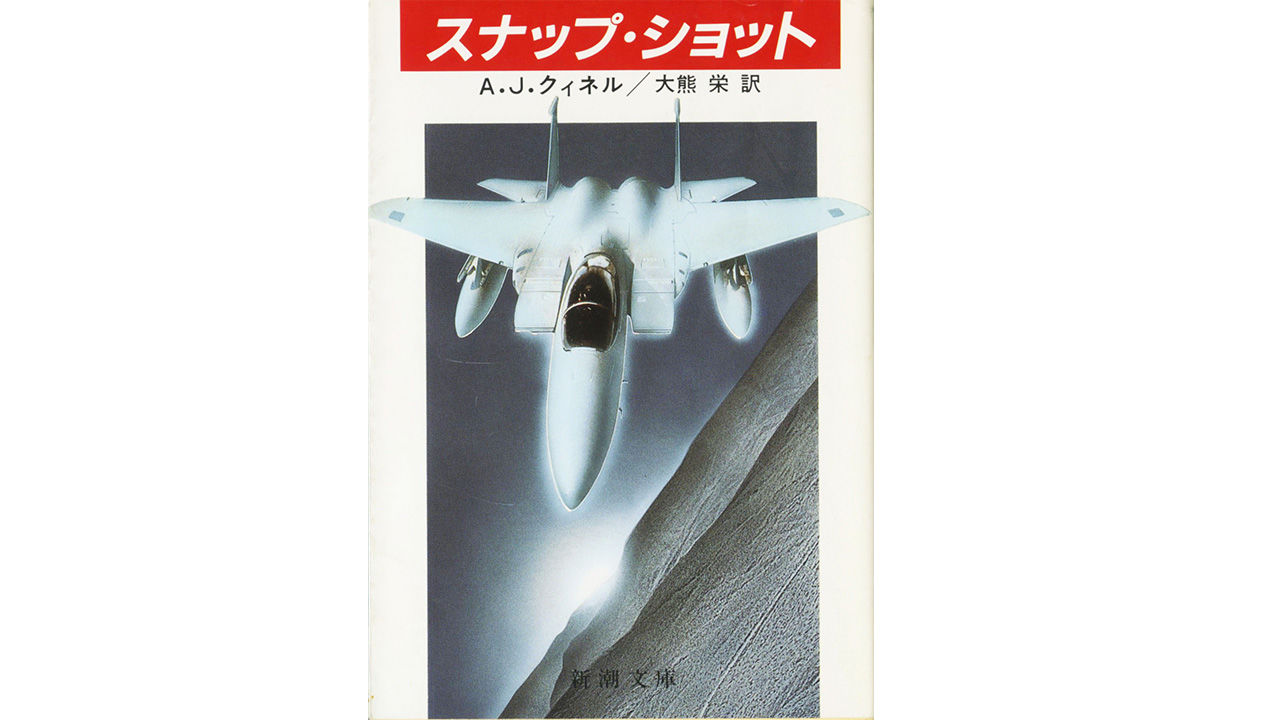
【書評】首相に爆撃を決断させた「1枚の写真」:A・J・クィネル著『スナップ・ショット』
Books- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
トランプ大統領と金正恩委員長との米朝首脳会談は、世紀の茶番だったのか。その評価は後年定まるとして、ひとまず対話の継続が合意され、米国が軍事オプションを選択する危機は当面、回避された。思い返せば、昨年から年初にかけては、いよいよ米軍が核ミサイル施設に先制攻撃を仕掛けるのではないか、との観測も流れていた。
そういえば、かつて似たように緊迫した状況があったなあ、と。ふと、昔に読んだスパイ小説の傑作を思い出したので披瀝させていただきたい。
敵国の、核兵器開発につながる原子炉への先制破壊攻撃と、それを可能にした情報機関の暗闘がスリリングに描かれている。
それがここに紹介する『スナップショット』である。
この作品は、私の好きなスパイ小説のベスト3に入る。
標的はフランス製原子炉
本作は、実際に起こった爆撃を題材にしている。
まず、わかっている事実を列挙しよう。
1981年6月7日、イスラエル空軍のF15、F16最新鋭戦闘機、計14機がイラクに向けて飛び立った。標的は、イラクの首都バグダッドから南西の、とある場所に建設されたフランス製原子炉であり、この爆撃により完全に破壊された。
2日後、イスラエル政府は声明を出した。
内容は、イラクのフセイン大統領はイスラエル攻撃を念頭に原爆製造を目的とした原子炉を建設した。同原子炉は広島型原爆と同規模の原爆を製造する能力をもっている。これはイスラエルの国家そのものの存在に対する脅威であり、同原子炉が稼働する前に作戦行動に移った、というもの。
むろんイラクは、原子力計画は平和目的だったと猛反発した。原子炉製造元のフランスはいうにおよばず、世界中の国々がイスラエルを「暴挙」と非難。同盟国である米国ですら、レーガン大統領が厳しい声明を発表し、国務省はイスラエルへの軍事、経済援助の削減をほのめかした。
国連では、イスラエルに対する制裁決議が検討される。
ところが、土壇場で米国政府は制裁決議に拒否権を発動し、不成立。なぜか強硬姿勢をあらためるのだが、この直前に、レーガン大統領はイスラエルのベギン首相から書簡を受け取っていた――。
孤高の天才カメラマン
なぜ、米国政府は態度を変えたのか。
ここから小説世界に入っていく。
時代はさらにさかのぼり、1960年代後半。ベトナム戦争は泥沼化し、出口が見えぬまま無益な戦闘が繰り返されていた。
南ベトナムの首都、サイゴンには世界中から戦争カメラマンが集まり、悲惨な戦場の写真を通信社や本国の新聞社、雑誌社に送っていた。
その中に、孤高の天才カメラマンがいた。
まだ30歳にすぎないのに、この仕事のキャリアは10年になり、これまでキプロス、ビアフラ、北ボルネオ、アンゴラなどの紛争地を転戦、同業者からも、
「デイヴ・マンガーはほんもののプロだった」
と、一目置かれていた。
「立派な戦争写真を撮る秘訣は適切な時間に適切な場所にいて、しかも頭を冷静に保つことだ」
マンガーにはその資質がありあまるほどあり、彼の行くところ、必ず風雲急を告げる戦闘があった。しかし、もっぱら白黒で仕事をする彼の写真は、ありきたりの戦闘シーンなどではなく、たとえば、
「疲れ果てて恐怖に戦く若い兵士のこわばった表情を写真に撮り、戦争の顔を百万の心に刻印することができるのだった」
このあたり、かつて同時代を生き、東南アジアの戦場に散った著名なカメラマン、ロバート・キャパや沢田教一を彷彿とさせるだろうか。キャパ自身による著作『ちょっとピンぼけ』は是非読んでほしい1冊である。
とはいえ、マンガーに権力や金といった野心はない。彼は淡々とひと仕事終えると、たいていバーカウンターの片隅にひっそりと坐り、ウォッカ・ソーダを飲んでいる。その姿は、
「全体として小柄で、ほっそりとして、目立たず、金髪の髪はもじゃもじゃ、細面の顔には苦悩の表情があった」
しかし、それで彼の魅力が失われているわけではない。
「目は彼のいちばん印象的な造作だった。大きくて、深く、色は驚くほどくっきりとしたブルー」
むろん、女性にもてた。さる貞淑な夫人をして、こういうありさま。
「からだごと吸い込まれそうな目だった。彼女はどきどきし、肉体的に魅了される衝撃を覚えた」
愛用のカメラは「ニコンFTN」
そんなマンガーが、米特殊部隊の偵察に単独同行した後、サイゴンに帰還すると別人のように憔悴している。
そして、長い髪のブロンドのガールフレンド、ジャニーヌ・ルサージュにこう告げる。
「明日、香港へ行く。チャンに頼んでカメラを競売にかけてもらう。それがすんだら東洋におさらばしてどこかよそへ行き、なにかほかのことをやってみるつもりだ」
突然の引退。何があったのか。
マンガーは、ベトナム戦争で本当の地獄を目撃した。
彼の精神は荒廃し、肉体的にもダメージが深く、性的不能者になる。
この体験は物語のなかで重要な意味をもつ。
さて、香港の外国人特派員クラブで、列席者が注目するなか、マンガーの愛用していたカメラ「ニコンFTN」がオークションにかけられた。
新品の同機種の値段の800香港ドルからはじまり、たちまち値が吊り上っていく。
7000香港ドルで競り落としたのが、米国人でマンガーとは同業のカメラマン、ダフ・ペイジェット。
ダフは妻ルースのために、結婚記念日のプレゼントとして高価なブレスレットを買うつもりでいたが、その全額をつぎこんだ。
彼はマンガーに大きな借りがあった。
「カメラを使うつもりかね?」
と尋ねられ、ダフは即答して、
「とんでもない!だれにも使わせません。マンガーがまた必要とする時まで、だいじに保管しておきます」
これが1969年10月のこと。この競売にまつわるエピソードは、後に感動的なシーンにつながっていく。
暗号名は「オレンジ・ワン」
ベトナム戦争では、香港に各国の情報部員が集っていた。表向きの職業は、貿易商、旅行業者、建設業の技術者などなど。誰にも怪しまれず外国へ出入りできる職種ならなんでもよかったが、なかでも外国特派員や写真家はお誂えむきだった。
そして、くだんのオークションの場には、こうした情報部員が興味津々、顔を出していた。
ダフ・ペイジェットは、マンガーのおかげで戦場カメラマンとしても名声を博していたが、実はCIAの要員だった。ジャニーヌ・ルサージュは仏紙の極東特派員という肩書だが、フランスの国外情報防諜部SDECE所属のスパイ。イラクの情報機関ムクハバラートのサミー・アサフも、中東ニュース社の記者としてその場にいた。
もうひとり、本作で重要な登場人物となるウォールター・プラムも競売を見守っていた。彼は、ユダヤ人の血をひく白系ロシア人で、ロシア革命後に上海に亡命、中国市場での貿易を足掛かりに巨万の富を築き、香港を拠点としている。
見てくれは小太りで成金趣味。老獪で世故に長け、機を見るに敏だが、内実はなかなかの正義感でもある。
いまや多国籍企業となったウォルターの会社は、世界中にネットワークを広げていた。彼のもうひとつの顔が、モサドの有力な協力者。1956年の中東戦争をきっかけに、ダヤン将軍の知己を得て、イスラエルのために役立つことを決意する。1960年代末までには世界中に「オレンジ」という暗号名でスパイ網を構築し、彼自身が「オレンジ・ワン」として知られるスパイの親玉になっていた。ここまでが、主要な登場人物のおぜん立ての部分。
舞台はベイルートへ
マンガーが姿を消してから9年が経った。舞台は東南アジアから中東へと移る。
すでにお馴染みとなった情報機関の面々は、ベイルートに集まっていた。
CIAのダフはカメラマンの肩書を隠れ蓑にPLO本部の監視任務についているが、CIAはイラクの原子炉計画に懸念をもっていた。
SDECEのジャニーヌは、フランス本国がイラクとの原子炉取引の直後、イラクのムクハバラートとの連絡係の任務についていた。カウンター・パートは、東南アジアで知り合いになっていたサミー・アサフ。彼は今やムクハバラートの副長官になっている。
彼らはCIAとモサドの動きを警戒していた。
イスラエルにとっては、イラクの原子炉稼働は死活問題だった。
これを阻止することが最優先の課題となり、モサドはそのための作戦基地をここベイルートに置いていた。「オレンジ」を操るウォルターも、ベイルートとは目と鼻の先、キプロスに拠点を移していた。
そして、この紛争地に、ふたたびマンガーが姿を現し、戦争カメラマンとして復活する。
ここからの展開が、本作の核心部分となる。
原子炉は、フランスからイラクへ引き渡された。いよいよ手詰まりとなったイスラエルは、地上から工作員を入れて原子炉を爆破させるか、あるいは戦闘機によって空爆するしか手はない。実行するにためらいはない。しかし、国際社会の中で孤立するリスクだけはどうしても避けたい。
イラクは間違いなく原爆を製造しようとしている。その証拠がほしい。少なくともレーガン大統領には、イスラエルの先制攻撃はやむなしだった、と納得してもらえる証拠が――。
決定打はヒューマン・インテリジェンス
各国情報機関は激しくしのぎを削り、暗殺、テロ、拉致拷問など、あらゆる手を尽くし、敵の企てを阻止しようとする。わずかな油断や手抜かりが、情報員を次々と死に追いやっていく。この物語の作者であるクィネルは、イスラエルの作戦成功までの舞台裏を、これはノンフィクションかと思わせるほど克明に描き出し、最後の最後まで読者を飽きさせない。
が、それ以上に読者を感動に導くのは、ひとりの男の再生をめぐる物語でもあるからだ。
とことん挫折を味わい、カメラを捨てて隠遁生活を送っていたマンガーが、トラウマを克服し、あらたな人生の目的や生きる意味を見出すまでの苦悩が読者の共感を呼ぶ。
マンガーの再生には、彼を支える友人たちの存在が欠かせなかった。そしてまた、それぞれ魅力的な登場人物たちが、母国のために、愛する人のために、無償の献身とわが身の犠牲とをいとわなかったからこそ、ことは成就するのである。
この作品は30年以上前に書かれたスパイ小説だが、けして古臭くなってはいないし、いまだから読む意味がある。
情報機関のインテリジェンス能力とは、軍事衛星による監視や電波通信情報の傍受など、ハイテク機器を駆使しての情報収集だけでは十分ではない。
現代においても、最後に決定打となるのが「ヒューマン・インテリジェンス」(人による情報収集)。つまり、作戦成功の鍵は、いかに敵の懐深く情報部員が潜入し、エビデンス(証拠)を入手し得るか。そのためには多くの情報員の「勇気と犠牲」が必要であることを本作は物語っている。
クィネルは、マルタ島に住んで執筆活動をしていたが2005年に亡くなっている。処女作『燃える男』から元傭兵を主人公にしたシリーズ冒険小説など、是非お薦めの良作が多い。
本作を含め絶版になっているのは残念だが、今の世の中、ネットで検索すれば古本だが簡単に入手できるのがありがたい。