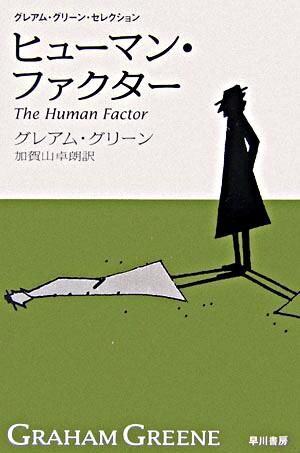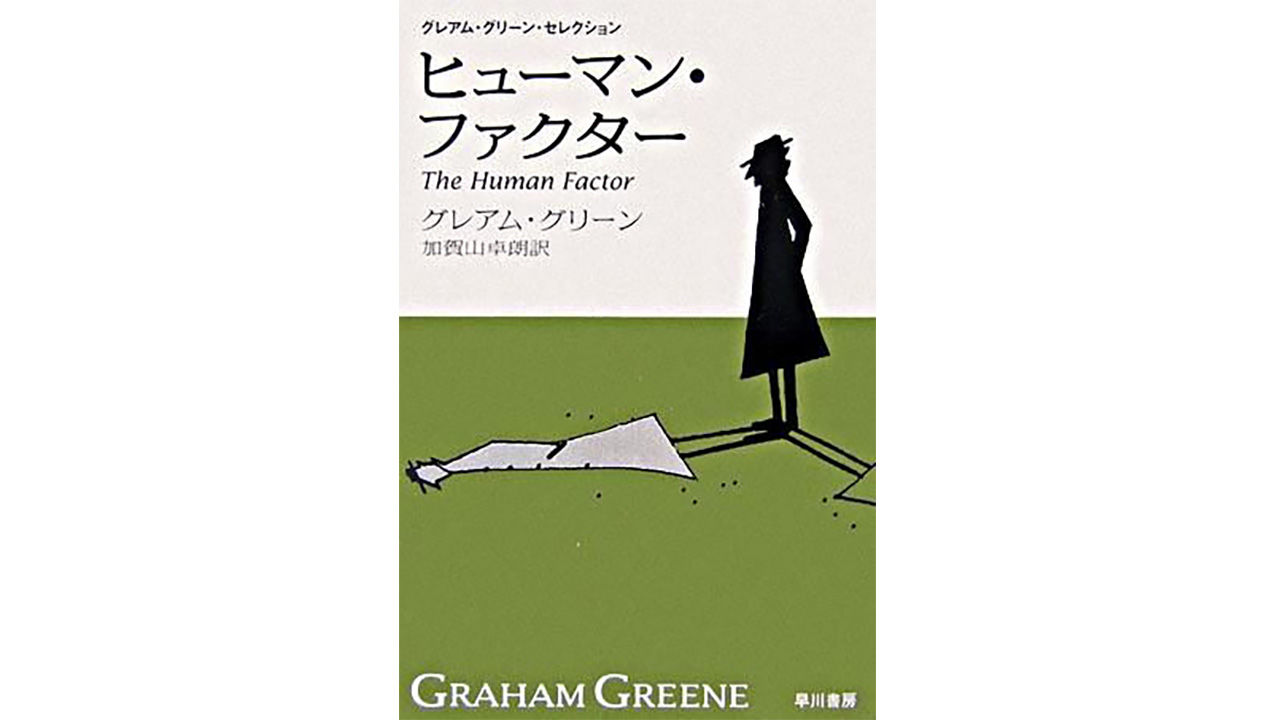
【書評】人はなぜ、祖国を裏切るのか:グレアム・グリーン著『ヒューマン・ファクター』
Books- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
今回は、スパイ小説を語るうえで避けては通れない必読の作品を紹介する。いつの世になっても、スパイが祖国を裏切って敵国に寝返るには、それなりの「動機」が存在する。二重スパイの本質まで掘り下げた作家のひとりがグレアム・グリーンであり、表題作がこれにあたる。いまや古典的名作ではあるが、現代スパイにおいても、「何に忠誠を誓うのか」、その心情においては同じであろう。
そして、本作は、血気盛んな若い頃よりも、ひととおりの人生経験を経て、中高年の域にさしかかった人が読んでこそ、真の味わい深さがわかるのではないかと思う。それこそ、一語一語噛みしめるようにして。
さっそく物語世界に入ってみる。
凡庸なスパイ
主人公のモーリス・カッスルは、英国情報部に入って30年以上になり、定年も近い。このまま無事勤め上げれば、静かな年金生活が待っている。
彼の人生は、華々しい戦歴に彩られたものではなかった。むしろ凡庸なスパイ。
かつては南アフリカの大使館に出向し、アパルトヘイト(人種隔離制度)の研究という名目で情報収集の任務についていた時期もあるが、今では本部でアフリカの東南部を担当する6Aと名付けられた部署にいる。
ここで極秘情報に接する資格があるのは、カッスルと同僚のデイヴィスのふたりだけで、彼らのいずれかが暗号電文を解読する規則になっているが、
「彼らの小さな部門に緊急を要する案件など入ってこないことは、ふたりともよくわかっていた」
し、ソ連や中国のアフリカでの活動に目を光らせてはいるものの、
「われわれの担当する大陸が世界の運命を決することはありませんから」
と、デイヴィスはいみじくも言っている。
つまり閑職的な位置づけの部署ということになる。
そんな有様だから、独身貴族のデイヴィスはポートワインを愛し、賭け屋に出入りするなど気ままな暮らしを謳歌している。
一方のカッスルは、判で押したように単調な生活を送っていた。
妻セイラと小さな息子サムの親子3人で、ロンドン郊外に住宅組合の資金を借りて購入した一軒家に住んでいる。職場へは最寄駅まで長い道のりを自転車で行き、そこから電車で一時間。よほどのことがない限り、
「彼は必ず七時半までに帰宅する。息子を寝かしつけ、八時の夕食前にウィスキーを一、二杯飲むのにちょうどいい時間だ。」
スパイとはいえ、まるで定時出退社の地方公務員みたいな生活なのだ。
「狩りの獲物は二級品だ」
「一風変わった職業についていると、毎日くり返すありきたりのことが大きな意味を持つようになる。」
カッスルにとっては変化のない日常が、なによりの幸せだった。
彼は几帳面な性格で、時間に正確。慎重で注意深く、極力、人目に立たないように行動する。昼食はいつもオフィス近くのパブでとり、ウイスキーはJ & Bを愛飲しているが、これだとソーダで割ったときに、はたから見ると色が薄く強いアルコールを飲んでいるようには見えないから、という理由。なにかにつけ用心深いのだ。
あるいは、なにかに怯えているかのように。
物語は、ディントリー大佐が新たな保安担当者として赴任し、職場の規則が守られているかどうか、カッスルやディヴィスに事情聴取するところから動き出す。
実は、彼らが所属する部署に、敵国への情報漏洩の疑いがもたれていた。
情報組織の長官であるハーグリーヴズ卿と側近のパーシヴァル医師は、保安担当のディントリー大佐を交えて謀議する。
二重スパイは誰で、敵の狙いは何なのか。
なにしろ、当時のアフリカに核兵器の秘密はなく、小物の独裁者や部族間の争いはあったにしても、どれも機密情報とはほど遠い。
ハーグリーヴズ卿は言う。
「敵はこちらを攪乱し、士気を低下させ、アメリカとの関係を悪化させようとしている。漏洩があったと公表されれば、漏洩自体より大きな打撃になる」
「だから敵の狙いはスキャンダルじゃないかと思う。またしてもイギリス情報部にもぐりこんだことを証明するわけだ」
これまでにもガイ・バージェスやドナルド・マクレーン(ともに1951年にソ連に亡命)から後にキム・フィルビー(63年に同亡命)ら、二重スパイの存在がたびたび発覚し、その都度、英国情報部はスキャンダルにまみれ、ダメージを受けてきた。
それだけは避けたい。長官からディントリー大佐に下された密命は、調査の続行と犯人の特定。
「ただしこの狩りの獲物は二級品だ。撃ち落としたキジにはがっかりさせられると思う」(ハーグリーヴズ卿)
漏洩のあった部署の関係者の顔ぶれは小物ばかりだ。
下された結論は、犯人を特定しても逮捕したり裁判にかけたりしない。大騒ぎになれば、それこそ敵の思うつぼ。自然死にみせかけて、闇から闇へと葬ってしまえ、となる。
ここまでが前半部分のあらすじ。
本作には、活劇的なスパイ小説にありがちな派手な場面展開はないが、ここから先も、登場人物それぞれの思惑や心理描写が丹念に描かれ、その積み重ねで、じわじわとクライマックスへと読者を導いていくのである。
いわば「静的なサスペンス」といった趣だろうか。
同僚の突然死
もう少し、物語に踏み込んでみよう。
ここから先の展開が、本作の読みどころであり、なぜ、人は祖国を裏切ってまで二重スパイになるのか、というテーマにつながっていく。
まっさきに疑われたのはディヴィスだった。普段の素行からして疑わしい。まもなく、彼は肝硬変で突然の死を迎える。
これで情報漏洩がなくなれば、まさしく犯人はデイヴィスだった、となる。
真相は、カッスルこそ二重スパイだったし、むろん家族にも秘密にしている。
上層部に露見しなかったことで、彼はこのままディヴィスに濡れ衣を着せ、黙っていれば安泰でいられるはずだった。
ところが、カッスルは、ある任務を引き受けたことから、どうしても東側に通報しなければならない重要な情報を耳にしてしまう。
はたして、平穏な生活を棒に振ってまで、彼は行動するのだろうか。葛藤の末、どう決断したか――。
英国情報部の歴史には、第二次大戦期から冷戦期にかけて二重スパイが続々と登場する。彼らが寝返る「動機」はいったい何なのだろう。
現体制への不満、思想信条、金への欲望、あるいは弱みを握られて、といったところだろうか。
われわれは英国と同じ西側の体制に属している。その立場からみれば、カッスルの行為は「祖国への裏切り行為」であり、許されざることであるはずだ。
ところが、奇妙なことに、われわれ読者は、物語を読み進むにつれて、彼の行為が上層部にバレないことを期待するようになっていく。
いよいよ切羽詰まった状況になり、カッスルはソ連へ救助の緊急シグナルを送る。この逃亡劇にいたり、物語はようやく「動的なサスペンス」となるのだが、われわれは彼が無事、モスクワへ亡命できることを願ってしまうのだ。
なぜ共感が生まれるのか。それはカッスルの「動機」にかかわっている。
「あなたは裏切ってないわ」
カッスルは最初の妻を病気で亡くし、いまの夫人は南アフリカで知り合った黒人女性である。しかし、かの国では黒人女性と結婚できないし、国外へ連れ出すこともできない。
彼らを救ったのは、南アの弁護士で共産主義者のカースンだった。
この作品の白眉のひとつは、最後の最後、窮地に立たされたカッスルが、妻のセーラに自らの罪を告白する場面である。要約すれば、
「カースンはきみとサムを救ってくれた男だ。その彼が見返りに要求したのは、ほんのわずかな手助けだった。」
「それのどこが悪いの」
「だから私は――人の言う二重スパイになった。セイラ。終身刑に値する行為だ」
カッスルの場合の「動機」は、家族への「愛情」とカースンに対する「恩情」。極めて個人的な「感情」だった。
彼は、亡命を促すソ連側スパイに、
「共産主義のために闘っているのではない。」
と言い放っている。だが、カッスルは二重スパイになったことで開き直っているわけではなく、重い罪の意識を抱えていた。
再び妻に告白する場面。
「つまるところ、私は人の言う裏切り者だ」
「それがなんなの」
と、続けたセーラの言葉に、読者は胸を打たれることだろう。こうだ。
「わたしたちにはわたしたちだけの国がある。あなたとわたしとサムの国。あなたはその国は裏切ってないわ」
熟成された文学作品
スパイは祖国に忠誠を誓っている。そしてもうひとつの「小さな祖国」すなわち家族に対しての忠誠もある。
ときとして、二者択一を迫られたらどうするか。任務の遂行のために、家族を犠牲にするスパイもいることだろう。
祖国か家族か。カッスルは後者を選んだのである。
ここまで、物語の展開に踏み込み過ぎただろうか。
いや、こんな程度で、この作品の面白さや感動が損なわれることはない。ここで紹介した以上に、物語は豊かなふくらみをもっており、クライマックスに近づくにつれ、ひとつのセリフやひとつの描写に込められた意味を深く味わい、静かな、しかしとてつもなく大きな感動に浸ることになるだろう。
カッスルが二重スパイであるのかどうか、上層部との駆け引きや彼の亡命劇にはどんでん返しの仕掛けがほどこされており、緊張感に満ち溢れている。
そうして、ラストシーンには、思わず涙ぐまずにはいられないはずである。
グレアム・グリーンは1904年生まれ。オックスフォード大学を卒業後、26年から「ザ・タイムズ」に勤務。作家デビューは29年とされる。
本作が出版されたのは78年のことであり、作家が70歳を超えてからの作品ということになる。
二重スパイの事件としてあまりにも有名なキム・フィルビーがソ連に亡命したのは63年のこと。フィルビーは、第二次大戦中に情報部で働いていたグリーンの上司でもあった。
グリーンは、本作を60年代に途中まで書いていたが、この事件をきっかけに執筆を中断したといわれている。
彼にとっては、それほどまでに衝撃的だったのであろう。
英紙タイムズのコラムニストで作家のベン・マッキンタイアーは、自著『キム・フィルビー かくも親密な裏切り』の中で、フィルビーの副官だったグリーンは、
「キム・フィルビーほどのいい上司は、おそらくいなかっただろう」
「ほかの誰よりも熱心に働きながら、苦労している素振りは一向に見せなかった。常にリラックスしていて、何事にも動じなかった」
と語っていた、と記している。
上流階級出身のフィルビーは、名門パブリックスクールからケンブリッジ大卒後、ほどなく英国情報部に入り、第二次大戦中は対独の情報戦に従事し、戦後の冷戦期には情報部のワシントン支局長を務めるなど、表の顔は第一線で活躍する情報部の輝かしいエリートだった。
しかし、実際にはすでにケンブリッジ在学中にリクルートされており、共産主義の実現を理想として、ソ連側のスパイとなっていたのである。
社交家のフィルビーは、誰からも好かれ、グリーンですら欺かれていた。
しかし、本作の主人公カッスルは、フィルビーとは人物造形がまったくちがう。根本的には、二重スパイになった動機におおきな乖離がある。
グリーンは、フィルビー事件で受けた衝撃から、あえて異なった二重スパイ像を創造したかと思えるのだが、これはうがった見方というものだろうか。
ともあれ、執筆中断から発表までに10年以上の歳月が流れたが、グリーンがいったん筆をおいたことで、この物語はさらなる熟成を重ね、豊かな文学作品へと昇華したのであろう。