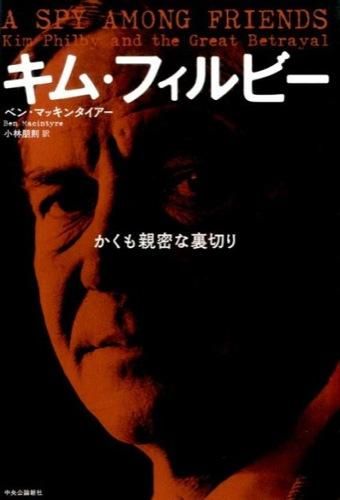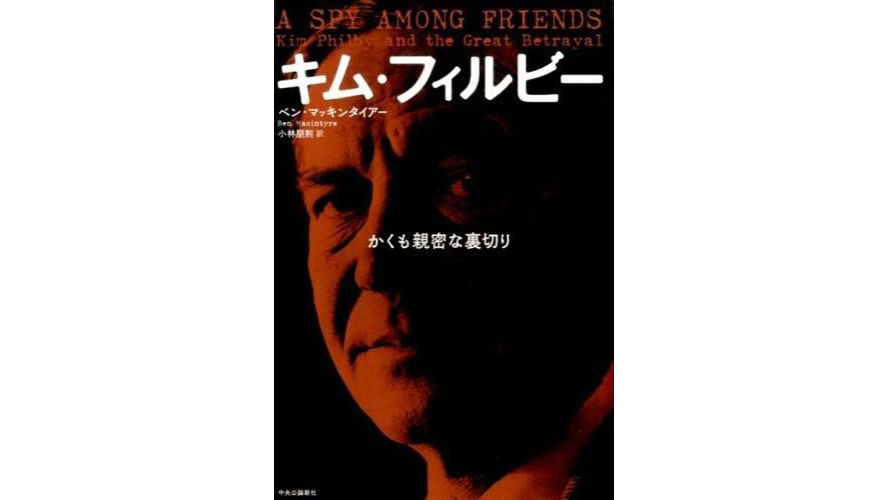
【書評】歴史に刻まれたスパイの墓碑銘(前編):ベン・マッキンタイアー著『キム・フィルビー かくも親密な裏切り』
Books- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
今回はノンフィクション作品ではあるけれど、並みのスパイ小説をはるかに凌ぐ面白さがあるので、是非、紹介したい。
キム・フィルビー事件に触発されたスパイ小説では、ジョン・ル・カレの『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』やグレアム・グリーンの『ヒューマン・ファクター』が著名だが、そのほかにも数多くの作品が影響を受けている。
であるなら、この事件の在り様を知っておけば、よりスパイ小説を楽しむことができるだろう。
しかも本書は小説のような物語仕立てになっており、ストーリーを追って読み進むにつれ、読者は自然と魑魅魍魎としたスパイの世界へと引きこまれていく。
著者は冒頭の「はしがき」で、
「これまで詳しく論じられることのなかった、いかにもイギリス人らしい人間関係がテーマなのだ」
と書いている。これが類書にない新たな視点である。
だから本書では、フィルビーとともに、彼の盟友だったMI6(対外情報機関)の幹部ニコラス・エリオットが、重要な役回りを演じる登場人物として描かれている。
ともに上流階級に生まれ、名門パブリックスクールからケンブリッジ大学というエリートコースを歩み、すすんで情報部に入る。
後年、フィルビーに関して、いくたびか二重スパイの疑惑が取沙汰されても、エリオットは終始、彼を擁護した。それはなぜなのか。
エリオットら情報部の同僚たちが終始フィルビーを庇い続けたため、はっきりと正体が暴かれるまでに、相当の年月を要したのである。
志願をほのめかす
それでは本書の世界へ踏みこんでみよう。まずは、キム・フィルビーの表の顔から。彼は、誰からも好感をもたれる社交性が武器だった。著者はこう記す。
「キム・フィルビーを語るのに最も頻繁に使われた言葉は、「魅力」であった」
「笑うのが大好きな上に、酒を飲むのも人の話を聞くのも大好きで、しかも聞くときは心の底から真剣に、興味津々になって聞いた」
彼は、1912年1月、父親が植民地行政官を務めていたインドのパンジャーブで生まれている。大学卒業後、タイムズ紙の特派員となってスペイン内戦を取材。第2次世界大戦が勃発すると、欧州大陸に渡り、ドイツ軍の侵攻で撤退を余儀なくされるギリギリまで記事を送り続けた。
しかし、フィルビーの本当の志望はジャーナリストになることではなく、MI6のスパイになることだった。
むろん、この組織は、正式に求人を出しているわけではない。
彼は、情報機関の関係者にそれとなく志願をほのめかす。むこうから声が掛かるのをじっと待ち続けるのだ。
フィルビーの身元を保証したのは、MI6の副長官。彼は、フィルビーの父とは昔から親しい仲だったので、問題なく採用された。
ときあたかもヒトラーのナチズムが欧州を席巻していた時代。めでたく情報部入りしたフィルビーは、ほどなくしてニコラス・エリオットと出会う。フィルビーはエリオットより4歳年上だったが、2人は、
「経歴も気性も驚くほどよく似ていた」
エリオットの父親クロードは、名門パブリックスクールであるイートン校の校長で、フィルビーの父親シンジャンは著名なアラブ学者にしてサウジ王族の顧問だったが、父親同士もケンブリッジで学んだ友人だった。
「二人とも、主に乳母に育てられた後、学校教育で人格を形成された。それは一目瞭然で、実際エリオットはイートン校OB用のネクタイを誇らしげに着用していたし、フィルビーはウェストミンスター校のスカーフを大切にしていた」
秘密の共有で結束した
「二人はすぐに友情を結んだ」
勤務外の時間には、気の合った仲間たちで夜な夜な集まっては大酒を飲み、バカ騒ぎした。ここに機密漏えいの温床があった。
「諜報機関のメンバーは、自分たちの仕事を友人や妻、両親、子供らに話すことを禁じられており、だからこそ多くの者が、他人に絶対知られてはならない秘密を共有することで結束している閉鎖的な集団に引き寄せられていた」
この閉鎖的なクラブのような集まりでは、エリオットも同様で、
「完全に信頼できる人々に囲まれ、外部では考えられないほど何でもオープンに話すことができた」
ここで聞き耳を立てていたのが、フィルビーだったというわけである。
フィルビーとエリオットは順調に出世街道を歩んでいく。
1939年、フィルビーはアイリーン・ファーズと結婚。彼女は旧家に属する階級の出身で、ケンブリッジ時代の女友達が仲をとりもった。
夫妻は女子と2人の男子をもうけ、周囲からフィルビーは子煩悩だったと見られていた。
フィルビーの家は、情報機関の若手メンバーの溜まり場になる。
当時、フィルビーの副官の1人だった、後に作家となるグレアム・グリーンのフィルビー評が紹介されている。
「彼には、何か特別な感じがあった。言ってみれば冒険小説に出てくる小隊長のような、誰からも好かれる権威のオーラがあり、そのため誰もが彼の前ではいいところを見せようとした。上官さえ彼の能力を認め、その意見に従った」
彼は組織のなかで絶大な信頼を得て、秘密を打ち明けられていたわけである。
「決定的に重要な人物」
では、キム・フィルビーは、いつどこで、どうして二重スパイになったのか。
彼は、学生時代、すでに18歳のときに共産主義に感化されていた。
1930年代、イギリスでは、「欧州で拡大するファシズムに対抗できるのは共産主義しかない」という思想的潮流が大きなうねりとなっていた。
ケンブリッジ大学内でも、その熱狂に巻き込まれた学生たちが左傾化していった。フィルビーも同世代の左翼の友人と深く交わるようになり、なかにはやはり二重スパイとなるガイ・バージェスやドナルド・マクレインがいた。
ソ連のスパイになっていくプロセスはこうだ。
フィルビーはすすんでマルクス経済学者の指導教官を訪ね、国際的な共産主義組織コミンテルンのパリ駐在工作員を紹介される。その工作員から、さらにオーストリアの共産主義組織につながっていく。
1933年の秋、さっそくフィルビーはウィーンへ向かい、そこで知り合ったのが22歳の黒髪のユダヤ女性リッツィだった。彼女は共産主義地下組織で活動し、ソ連の情報機関とも接触していた。
フィルビーは彼女とたちまち恋仲になり、1934年2月にウィーンで結婚。数か月後に2人してロンドンに戻る。その数週間後、
「フィルビーはリージェンツ・パークのベンチに座り、リッツィから人生を変えることになると確約された『決定的に重要な人物』が来るのを待っていた」
それが「オットー」と名乗るソ連の工作員で、本名アルノルト・ドイッチュ。彼はケンブリッジ・スパイ網を作り上げた中心人物で、将来、社会的に高い地位につくことが約束されたエリート学生に狙いをつける。
「ソ連の情報機関は長期戦を想定しており、今まいた種は何年も後に収穫できればいいし、場合によっては休眠状態でもかまわないと考えていた」
ドイッチュの誘いに、フィルビーはためらうことなく乗った。
著者であるマッキンタイアーは、こう分析している。
「『エリート部隊への入隊を提示されて、ためらう者などいない』とフィルビーは書いている。この一文がすべてを物語っている。この新たな役割に魅かれたのは、それが誰でもなれるわけではない排他的なものだったからだ。ある意味、フィルビーの物語は、どこまでも排他的なクラブを求め続けた男の物語と言える」
フィルビーは、ケンブリッジ卒業後、ドイッチュの勧めで報道機関に職を得て、やがて、はかったように念願だったイギリスの情報機関入りをはたした。
すでに、おわかりだろう。フィルビーは、MI6のスパイになってからソ連に寝返ったのではない。敵国のスパイとなり、その後、本人の弁によれば「ソヴィエトの利益のために働く潜入スパイ」として、祖国イギリスの情報機関にもぐりこんだのである。
CIAも騙された
フィルビーは、ほどなくしてリッツィと離婚。その後、前出のアイリーンと子供たちとの円満な家庭生活を演じて周囲の信用を得ていたが、一番の親友とみられていたエリオットも、そして家族も欺かれていたわけである。
そして、CIAも騙された。
アメリカは第2次大戦を契機に新たな情報機関として1942年に戦略事務局(OSS)を設立。これが後にCIAとなるが、当時はスパイ組織としての経験が不足していた。
そこで、イギリスにOSSの将校を派遣し、訓練させることにしたのだが、皮肉なことに、MI6ではその教官役にフィルビーをあてることにした。
これによりフィルビーは、彼らとも昵懇になっていく。なかでも重要人物が、後のCIAで大物幹部となるジェームズ・アングルトンだった。
1949年10月、いまや組織の中枢にいるフィルビーは、MI6のニューヨーク支局長に着任する。
フィルビーとアングルトンはニューヨークにある高級レストラン「ハーヴィーズ」で定期的にランチをともにし、そこで頻繁に情報交換が行われた。
フィルビーは、イギリス贔屓のアングルトンとも親密な関係を築き、そのおかげで、米英両国の隠密作戦がすべてソ連に筒抜けになっていくのである。
それでは、それで西側陣営はどれほどの損害を被ったのか。それが本書の読みどころのひとつでもある。
フィルビーがソ連に漏らした情報により、イギリスやアメリカが画策した作戦の数々が失敗に終わる。戦後、特に悲劇的だったのは、共産化された欧州アルバニアでの反政府活動を支援する作戦だった。西側から送り込まれた工作員は、ことごとく迎え撃たれ惨殺されてしまうのだ。
フィルビーの密告によって、東側に潜入した工作員や現地の協力者が次々と囚われの身となり、処刑されていく。
そうしたいくつもの事例を、著者は豊富なエピソードを交えて克明に記す。これにより、われわれはフィルビーのもたらした災厄について知ることになる。
(後編へ続く)