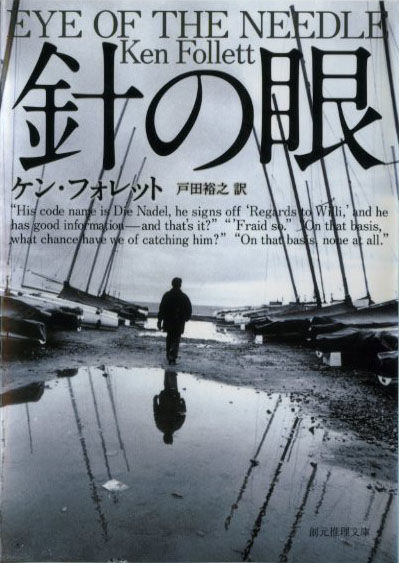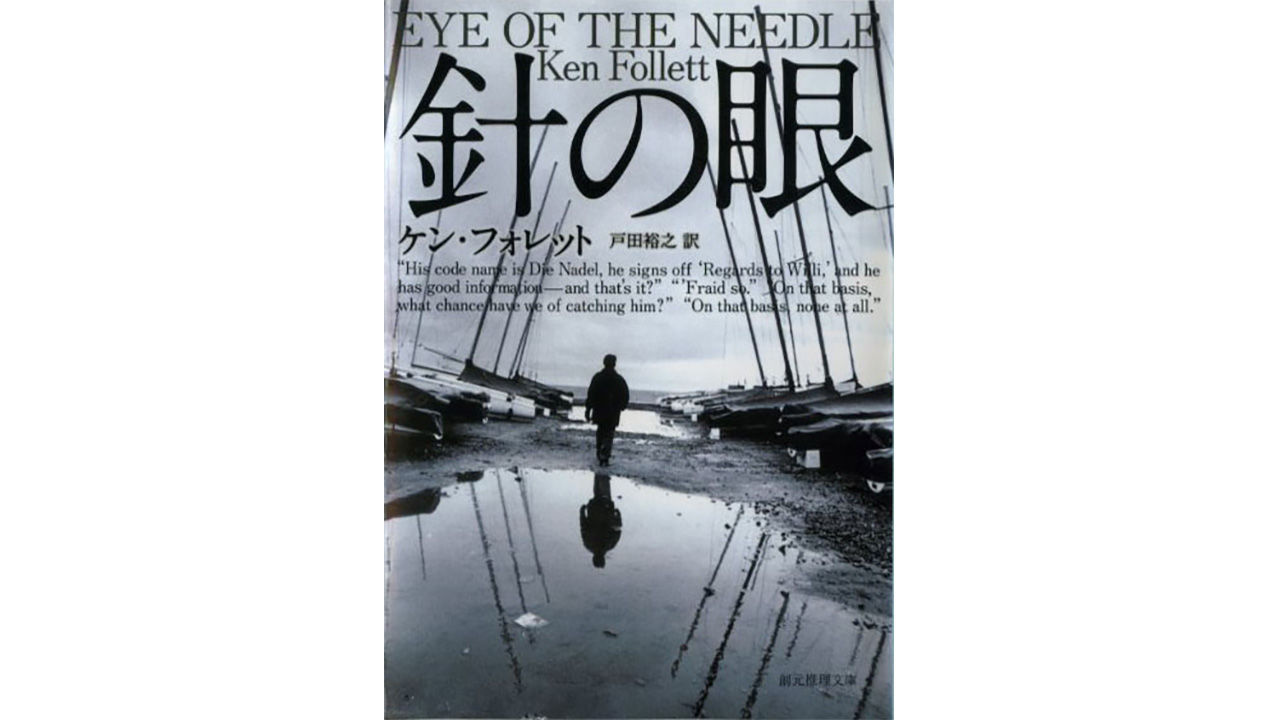
【書評】Dデイ欺瞞工作を描いた傑作スパイ小説(後編):ケン・フォレット著『針の眼』
Books- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
(前編から続く)
いよいよ、Dデイの上陸地点をめぐる英国情報部MI5と、独国防軍情報部アプヴェーアの情報戦が火蓋を切る。
「あの男なら、真実を発見する」
「針」はヒトラーがもっとも信頼するスパイである。
それを指し示す場面がこうだ。
1944年春、戦況はますます悪化し、年内のうちにも英米連合軍の反転攻勢が予想される。ヒトラー以下の幹部が「狼の巣」に集まり、上陸地点について協議。決め手となる情報がなく、カレーかノルマンディーか結論が出せないまま、「針」の報告を待って最終的に判断することが決まる。
ヒトラーは「針」を絶賛する。
「カナリス(注・ヴィルヘルム・カナリスのこと。海軍大将にしてアプヴェーア部長)が採用したなかで、唯一信頼に足る工作員だ。私の指示で採用したのだからな。私はあの家族を知っているが、強く、忠誠心堅固で、立派なドイツ人だ。そして《針》は素晴しい。実に優秀だ!私は彼の報告にすべて目を通している(略)」
カナリス失脚後、後任になったフォン・レンネ大佐が聞く。
「それは、《針》の報告を信じるということでしょうか」
ヒトラーはうなずいた。
「あの男なら、真実を発見する」
「針」には重要指令が下っていた。
ドイツ本国から潜入してきた情報将校がこう伝えている。
「パットン将軍がイングランドの東アングリアと呼ばれる地方にアメリカ陸軍第一軍を終結させつつある。それが侵攻部隊だとすれば、パ・ドゥ・カレーを経由して攻め込んでくるであろう」
「針」の任務は、その侵攻部隊の戦力を評価することにある。
任務を果たした後の脱出方法は、北海沿岸にUボートを潜航待機させており、「針」に与えられた無線周波数で呼べば艦が浮上し、彼を回収する。
かくして「針」は、戦力分析のために目的の地へ向かった。そこで目にしたものは、意外な真実——。
一通の無線傍受記録から
一方の英国情報部はどうしていたか。
いよいよDデイが迫る中、二十委員会からMI5に「アプヴェーアの工作員は一人たりともイギリス国内に放置してはならない」と厳命が下る。
南東部沿岸の擬装が発覚すれば、欺瞞工作はすべて水泡に帰す。
ゴドリマン教授と相棒のブロッグスの会話。
無能なスパイはことごとく逮捕したが、一通の無線傍受記録から、どうしても身許も居場所も特定できていないスパイの存在が判明する。
報告の通信文の最後に「ヴィリーによろしく」と付けるのがその特徴で、本国からの返信の宛名は「ディー・ナーデル」すなわち「針」となっている。「ヴィリー」とはアプヴェーア部長のカナリス海軍大将のファーストネーム。
「こいつはプロですよ。彼の通信文を見てください。簡潔で過不足なく、詳しい上にまったくあいまいな点がないでしょう」
とブロッグス。
「コードネームが《針》で、通信を《ヴィリーによろしく》で締めくくり、優れた情報収集能力がある——それだけしかわかっていないのかね」
とゴドリマンが尋ねる。
「それだけの情報で、われわれが彼を捕えられる可能性はどのくらいあるんだろう」
ブロッグスが肩をすくめて答えた。
「可能性は、ゼロです」
ここから知力を尽くした追跡劇が開始される。
ゴドリマンは、過去、国内で起こった未解決事件に目を付けた。
「スパイというのは何らかの形で法を破っているに違いない」
端緒は、ロンドンの街中で起こった性犯罪者の犯行とみられる殺人事件だった。そこから、根気強く、ひとつひとつ情報を潰していく。
その後、物語はどう展開していくか。
「針」は、戦時下で警戒厳しい監視の目を潜り抜け、イギリス沿岸部をたどる。幾多の困難を乗り越えて目的地に到達し、ある証拠を手に入れるまで。そしてそれと並行してゴドリマンらが「針」を追跡し、追い詰めていくまで。このあたりが本作の読みどころであり、読者は間一髪の逃亡・追跡劇の連続に目が離せなくなる。
インテリジェンスとは何か
そして、最後の最後の大どんでん返し。作者のケン・フォレットは、劇的なラストシーンを用意している。
「針」は小型漁船を奪い、証拠の品を携え、Uボートの待機する海域を目指すが、目前にして大嵐に巻き込まれ、絶海の孤島に流される。
万事休すか!と思うと、その島には、若き夫妻と彼らの世話をする羊飼いの老人の3人しかいない。しかも、夫は交通事故で下半身不随になっており、都合の良いことに、老人の住む家には無線機があった——。
「針」は脱出に成功するのか、はたまた英情報部は「針」の身柄を確保することができるのか。
作品の半分を占める、ここから先の冒険譚が著者フォレットの一番描きたかった場面なのだろう。
それは本編を読んでじっくり楽しんでいただくとして、本作は、情報機関の世界で言う「インテリジェンス」とは何か、という観点からも興味深く読める。
この業界では、「インテリジェンス」とは、国家が生き延びるための情報だと説明される。
『針の眼』では、戦時のイギリスがナチス・ドイツを打ち破るために、膨大で雑多な「インフォメーション」から「針」の行方を突き止めるための核心情報、すなわち「インテリジェンス」を歴史学の教授に紡ぎ出させている。
ブロッグスをはじめ情報部員が地を這うようにして集めた断片情報をもとに、パイプをくゆらせながらゴドリマン教授が分析する。
情報収集する者と分析する者。本作で描かれた役割分担は、まさに「インテリジェンス」の教科書通りである。
読者は、虚実とりまぜた欺瞞工作の内幕的な読み物として、十分スパイの世界を堪能できるはずだ。
それだけに、この作品が絶版状態であるのは非常に惜しまれる。