
グローバル化と日本の大学改革―国際競争力強化への課題
社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
第2次世界大戦後の1948年、米国の占領下に新しい大学制度が発足してから半世紀余りを経て、日本の大学はいま再び大きな変革の渦中にある。1990年代に入るころから始まった改革の嵐は、2010年代のいまも大学の世界を吹き荒れている。なぜ、大学改革なのか。その理由としては、3つの国際的なメガトレンドと、3つの国内的な変動要因を挙げることができるだろう。
3つのメガトレンド―「ユニバーサル化」「市場化」「グローバル化」
メガトレンドの第1は高等教育のユニバーサル化(universalization)である。米国の社会学者マーチン・トロウによれば、高等教育は同年齢人口比で見た就学率15%と50%を指標に、エリートからマスへ、マスからユニバーサルへと発展段階をたどるとされる。1970年代から80年代にかけてユニバーサル化した米国の後を追って、90年代に入ると先進諸国は軒並みマスからユニバーサルへの段階移行期を迎えた。日本についていえば70-80年代に36~7%で安定的に推移してきた就学率が、95年45.2%、2005年51.5%と急上昇を遂げ、2013年現在で55.1%に達している。これは大学・短期大学だけの数字であり、もう一つの中等教育修了後の教育機関である専修学校を加えれば、就学率は77.9%に及ぶ(図1)。こうした高等教育の急激な量的拡大、就学率の上昇は、高等教育システムと大学の質的変化を求め、もたらさずにはおかない。日本の大学改革はそうした世界的なトレンドの一環に他ならない。
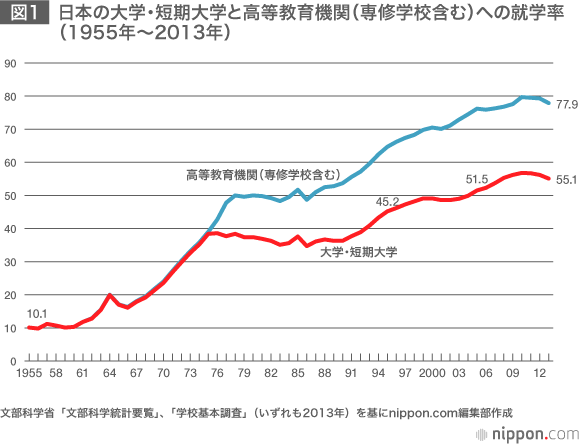
第2のメガトレンドは、「市場化」(marketization)である。高等教育はこれまで基本的に国家・政府の責任で維持運営されるべきものと見なされてきた。欧州諸国では国立大学が原則であり、有力私立大学を多数持つ米国は例外的な国である。その米国でも学生の80%近くが公立セクターに在学していることは周知の通りである。私立セクターの在学者が80%近くを占める日本は、従って、極めて例外的な国といってよい。その私立セクターは、それぞれの大学が資金や学生、優秀な教員などを求めて互いに競争せざるを得ないという意味で、基本的に「市場化」している。世界的なトレンドは、マス化・ユニバーサル化の進展とともに、その市場化の波が、高等教育の国立セクターにも及び始めた点にある。規模の膨らんだ高等教育財政の逼迫(ひっぱく)、限られた資金の効率的な活用の必要性、私立セクターからの平等化への要求などが、国立セクターについても、特に資金の獲得や大学経営に「市場原理」の導入を求めるようになった。その意味で市場化は「私学化」(privatization)と言い換えてもよい。後で触れる日本の国立大学法人化は、そうした世界的な市場化・私学化のトレンドの代表例に他ならない。
第3かつ最大のメガトレンドはグローバル化である。交通と情報伝達の目覚ましい技術革新は、経済や政治だけでなく、大学を中心とした教育研究の世界にもグローバル化の急進展をもたらした。いまはどの国の大学・高等教育システムも、全地球的なネットワークに逃れがたく組み込まれている。そのネットワークは知識や学問の持つ普遍性だけでなく、研究者や学生の国際的な移動によって支えられている。自然科学系やビジネス系を中心に学生や研究者の国際的な流動性は高まり、特に優秀な学生・研究者の国際的な獲得競争は激化の一途をたどっている。
その高等教育の「世界システム」の中核に位置しているのは、米国に他ならない。米国は、世界で最も成功した高等教育システムと大学を持ち、グローバルな知的資源や人的・物的資源の集散に中心的な役割を果たしている。このことは米国が、他の国々にとって高等教育システムや大学の改革についても、主要なモデルの提供者、あるいは輸出元となり、グローバル化が何よりも「米国化」(Americanization)として意識され、進行していることを意味する。学位制度や研究業績の評価制度にしても、ビジネススクール(経営学大学院)に代表される専門職大学院についても、米国は「グローバル・スタンダード」の提供者としての位置を占め、他の国々はそれに倣った改革を求められている。日本もまたその例外ではない。
3つの日本的要因―「人口減」「経済低迷」「規制緩和」
大学の変革を求める日本的要因はどうか。
第1に人口変動がある。1980年代以降、日本の高等教育は人口変動の大波に直面してきた。80年代中頃まで150万人台で推移していた18歳人口は、その後急増の局面を迎えて92年の205万人でピークに達した後、一転して2000年に151万人、2010年122万人と減少の一途をたどっている(図2)。この激しい人口変動は、巨大な私立セクターを持つ日本の高等教育システムに、大きな衝撃をもたらした。人口の急増期に収容力の拡大に努めた私立大学は、就学率の上昇にもかかわらず、急減期を迎えて十分な数の学生を集めることができず、90年代の後半以降、「定員割れ」の大学が続出し、いまでは全体の半数を超えるまでになっている。それは長い間、収容力を上回る進学希望者を集め、厳しい入学者選抜試験と激しい受験競争を特徴としてきた日本の大学にとって、まったく新しい経験である。その結果、大学はいまや入学者の募集や選抜の方法、入学後の指導や教育にとどまらず、教育研究と管理運営の組織、財務や経営の方針まで全面的な見直しを迫られるに至っている。
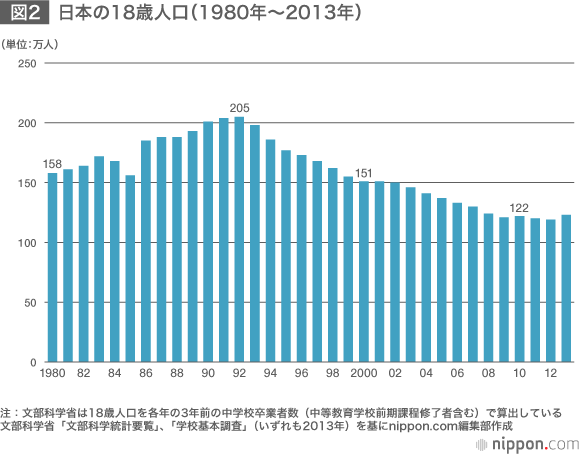
第2の要因は経済変動である。1990年代初めのバブル崩壊から、いまも続く経済の低迷もまた、大学改革に大きな影響を及ぼしてきた。経済の長期的な低迷は、日本が世界的な情報化とグローバル化の波に乗り遅れており、その遅れを取り戻すためには人材の質、さらには人材養成に当たる大学の質を高め、また大学における基礎・応用研究の水準向上が不可欠であることを、広く認識させる役割を果たした。その結果、政党も経済団体も競って、大学に焦点を当てた教育改革の構想を提言し、大学の教育研究活動の一層の開放化・活性化や、研究面での産学協同を中心に企業との交流の積極的な推進、さらには教育研究の水準向上や組織改革に向けた改革努力を、強く求めるようになった。大学が知識産業社会や学習社会の中核的な機関であり、大学での研究がグローバル化した先端科学技術競争を勝ち抜く上で、戦略的重要性の最も高い手段であることは、早くから指摘されてきた。バブル崩壊後の経済危機の中で、それがようやく大学改革の必要性と結びつけて議論されるようになったのである。
第3に、政策面での転換も重要である。1983年に発足した自民党政権の中曽根康弘内閣は、新自由主義的な立場を鮮明にし、「規制改革」と「構造改革」をキーワードに政策転換を図り始めたが、それは2001年発足の小泉純一郎内閣にも引き継がれ、大学改革に大きな影響を及ぼした。何よりも、こうした政策転換の下で、政府は大学に対する規制の緩和に乗り出した。その規制緩和は1990年代に入って、まずは大学の組織と教育の基本条件を定めた「大学設置基準」の大幅な改正により本格化した。大学はそれまで厳しく規制されてきた学部の教育課程について、大幅な編成の自由を認められ、その結果として新しい名称や教育課程を持つ学部が次々に新設されるようになった。大学の設置認可の条件も緩和され、90年に507校だった大学は、2000年には649校、2013年には782校へと急増を遂げた(図3)。
規制緩和による構造改革は、大学の組織面にも及び、特に文部省の直接の統制下に置かれてきた国立大学について、長い歴史を持つ講座制(学部内に専攻分野ごとに設置される、教授を筆頭とする研究・教育組織)の解体、教員の任期制の導入、副学長制の導入による執行体制の強化などが進んだ。研究費をはじめとする公的資金の配分にも、競争原理が導入され、また企業などからの外部資金の受け入れが奨励されるようになった。こうして大学はいまや国公私立を問わず、文部省による父権主義的な庇護(ひご)と統制から解き放たれ、教育研究面だけでなく、管理運営や経営面でも「自己責任」で改革を進め、一層の発展と生き残りをかけた競争に参加することを求められている。
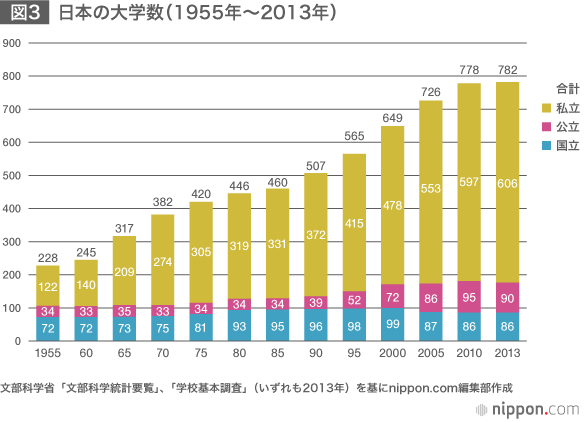
改革の象徴としての国立大学法人化
国立大学法人化は、変革を求める内外の要請に応えるべく推進され始めた、こうした一連の大学改革の方向性を端的に表すものといってよい。日本の国立大学は長い間、行政機構の一部として文部省(2001年からは文部科学省)の直接の管理下に置かれ、教員は国家公務員であり、予算額や人員配置をはじめ、運営上の自由を事実上認められてこなかった。そして、先に述べたグローバル化の進展による、国際的な大学間競争の衝撃を最も強く受けたのは、その国立大学に他ならなかった。
研究と自然科学系を主体とした専門職業人養成に特化した90校足らずの国立大学は、総数800に近い日本の大学の中で、最も質の高い大学群であり、大学院在学者の修士課程で57%、博士課程で69%を占めている。各種の世界の大学ランキングで上位を占めるのも、それら国立大学である。例えば2013-14年度版の英『タイムズ・ハイヤー・エデュケーション』誌のランキングによれば、日本の大学は23位の東京大学を筆頭に、400位以内に11校がランク入りしているが、そのうち公立は1校にすぎず、残る10校は戦前の旧帝国大学の継承校(7校)をはじめとする国立大学であった(2012-13年度版でランク入りした私立2校は、13-14年度のランキングに登場しなかった)。科学技術主体の国際的な経済競争を勝ち抜くために、日本は何よりもまず、その国立大学群の国際競争力を高める必要に迫られているのである。
大学側の反対を含む激しい議論の末、国立大学は2004年、文科省の直接の管理と庇護を離れて、独立の法人格を認められることになった。国立大学の「私学化」である。学長選考会議で選任された学長の下に、理事会が組織されて大学運営に当たり、また学長の諮問機関として、外部委員を加えた経営協議会と教員の選任による教育研究評議会を置く、というのが管理運営の基本組織である。政府は毎年、一定額の公的資金を「運営費交付金」として各法人に交付し、各法人はそれに授業料や付属病院からの収入、政府や企業などからの研究費、寄付金などの外部資金を加えて、大学経営に当たる。また各大学は文部科学省に6年間の中期計画を提出して承認を受け、実績について国立大学法人評価委員会の評価を受けるものとされた。
このように、国立大学に自律を認める一方で、政府・文科省は競争的に配分される公的資金の大幅な増額を図り始めた。その一部は国立大学のみを対象としているが、大部分は、国公私立の全ての大学に開かれ、応募と審査の結果に基づいて配分される。私立大学の設置認可の条件が大幅に緩和され、18歳人口の減少と関係なく、新設大学数を急増させる契機をつくったのも、国立大学法人化と同じ2004年であることを、付け加えておくべきだろう。「統制と庇護」に代わって、「自由と競争」が、日本の大学政策の新しいキャッチフレーズになったのである。それは、日本の高等教育の革命的な変革を目指すものであったといってよい。
英『タイムズ・ハイヤー・エデュケーション』誌 世界大学ランキング
日本の大学の順位(2013-14年度)
| 23位 | 東京大学(国立)* |
| 52位 | 京都大学(国立)* |
| 125位 | 東京工業大学(国立) |
| 144位 | 大阪大学(国立)* |
| 150位 | 東北大学(国立)* |
| 201-225位 | 名古屋大学(国立)* |
| 201-225位 | 首都大学東京(公立) |
| 276-300位 | 東京医科歯科大学(国立) |
| 300-350位 | 北海道大学(国立)* |
| 300-350位 | 九州大学(国立)* |
| 300-350位 | 筑波大学(国立) |
注:*は旧帝国大学の継承校
出所:『タイムズ・ハイヤー・エデュケーション』世界大学ランキング
1970年OECD教育調査団の指摘
その「庇護と統制」に代わる「自由と競争」というキャッチフレーズは、1970年に来日した経済協力開発機構(OECD)の教育調査団報告書『日本の教育政策』(1971年、邦訳1972年、朝日新聞社)の一節を思い起こさせる。
「大学は他の教育機関とともに、他に類を見ない日本の経済成長と近代化の担い手として、その名誉をわかち合ってきた。だが半面、こうした成長は、大学が依然として保ち続けている硬直性に、鋭い批判の目を向けさせることになった…日本の高等教育制度は、著しく階層的であり、その構造は急速な成長にもかかわらず今世紀の間ほとんど変化していない。多数にのぼる大学のうち、ごく少数だけが財政的基盤、社会的威信、その提供する教育水準などの点で、他からはっきりと区別されている。こうして形成される大学の構造は、頂点の鋭くとがったピラミッド状を呈し、ピラミッドを構成する各層の間で、学生や教師の移動は極めて乏しい…柔軟性に乏しい大学の階層的構造が、日本に現れつつある高度技術社会の要求する教育目標を、満たすことができないのは明らかである」(52-55ページ)
半世紀近く前の調査団報告書の指摘した課題は、すでに見てきたこの10年の大学改革の課題でもあった。ようやく推進され始めた一連の「自由と競争」政策のもとで、「統制と庇護」の下に持続されてきた高等教育の「硬直的で階層的」な構造は、どこまで「柔軟で多様性」に富んだものに変貌を遂げたのだろうか。19世紀後半の日本の近代化の開始から21世紀に入るまで、1世紀余にわたって持続されてきた制度の慣性を考えれば、10年という時間は、改革の成果を問題にするには短すぎるかもしれない。実際に改革はまだ途上にある。総括的にいえば、一連の「自由と競争」政策が、成果よりも新しい課題を次々に生み出し、認識させる役割を果たしてきたのが、この10年であったと見るべきだろう。
競争力強化に必要な大学の国際化
その新しい課題の中で、いま最も重要視されているのは、グローバル化に関わる大学の「国際化」である。国立大学の法人化と並行的に高まった、先にも触れた大学の世界ランキングに対する関心と、それに関連した「研究大学」の育成・強化論の登場は、その端的な表れといえるだろう。
先に見たように、世界ランキングに見る日本の大学の国際的な地位は、決して低くはない。日本が、欧米諸国以外で、唯一多数のノーベル賞受賞者を出している国であることは、あらためて言うまでもないだろう。しかし全体としてみれば、教育研究の水準が英米の大学には及ばず、また上位ランクに入る大学の数が少ないことは事実である。しかも、東アジアの国と地域の大学の追い上げの中で、そのランクは下降傾向にある。評価の最重要の対象となるのは、もちろん教育・研究活動の水準である。だが日本の場合、際立っているのは、外国人教員や留学生の比率といった国際化関連の指標の低水準であり、それがランクを引き下げる主要な理由になっていることが、いまでは広く認識されている。
先のOECD報告書の指摘にあるように、これまで日本の大学は、長期にわたって経済成長と近代化に大きく寄与してきた。それは、日本の大学が、短期間に教育と研究の欧米依存から脱却し、「自国化」に成功した結果といってよい。20世紀の初めにはすでに、日本の大学教育は完全に、自国の教員により自国語で行われており、理学・工学・医学などの分野では、数こそ少ないものの世界水準の研究成果を出すようになっていた。戦前期を通じて大学教員は、キャリアの早い段階で2~3年の留学をするのを慣例としていたが、それは欧米の最先端の学問に触れるためで、学位の取得を目的とするものではなく、留学生の数も著しく限られていた。教育の「自国化」は、低廉なコストで短期間に大量の人材養成し、供給することを可能にし、日本の近代化・工業化の成功に寄与してきたのである。
グローバル化の大波への対応の立ち遅れは、何よりもそうした日本の大学の自国化の成功に起因している。「硬直的で階層的な構造」はまた「閉鎖的な構造」でもあったといえるだろう。
毎年発表される世界ランキング入りする「研究大学」の数を増やし、ランクを高めるためには、日本国内での大学間競争を促進することが重要である。しかしそれだけでなく、諸外国の大学に伍し競争に打ち勝つためには、大学を開き、より多くの、しかも優秀な外国人の研究者や留学生を積極的に受け入れ、リンガフランカ(世界共通語)化した英語による授業や教育課程を増やし、さらには日本人研究者や留学生を海外に送り出し、教育研究の一層の活性化と水準向上を図らなければならない。「自国化」の道をひた走ってきた日本の大学は、いまや明治初期や終戦直後に続く「第2・第3の開国」の時を迎えているというべきだろう。
改革への新しい課題―「公的支出」「成人学生」「大学院」
国際化は、ランキングの問題だけではない。OECDが毎年公表するようになった国際比較のデータもまた、国際的な基準から見た日本の大学のさまざまな弱点、言い換えれば改革の新しい課題を認識させる役割を果たしている。グローバル化の波は、そのような形でも、日本の高等教育の構造変革を求め、圧力を及ぼしているのである。
例えば、巨大な私立セクターを抱える日本は、国内総生産(GDP)比で見た高等教育に対する公的財政支出が、OECD諸国の中で最低水準にある(図4)。それは、教育費の高い家計・個人負担率と、それがもたらす教育機会の不平等、さらには授業料収入に依存せざるを得ない私立大学の教育研究の水準の低さを示唆している。実際に、私立大学に対する公的助成は数十年間にわたって経常費の10%程度にとどまり、国立大学の場合にも、運営費交付金がこの10年で10%削減されている。公的財政支出の貧弱なままに進行する高等教育のユニバーサル化は、教育・研究の質の貧困化をもたらし、それを加速させる危険性をはらんでいるといわねばならない。
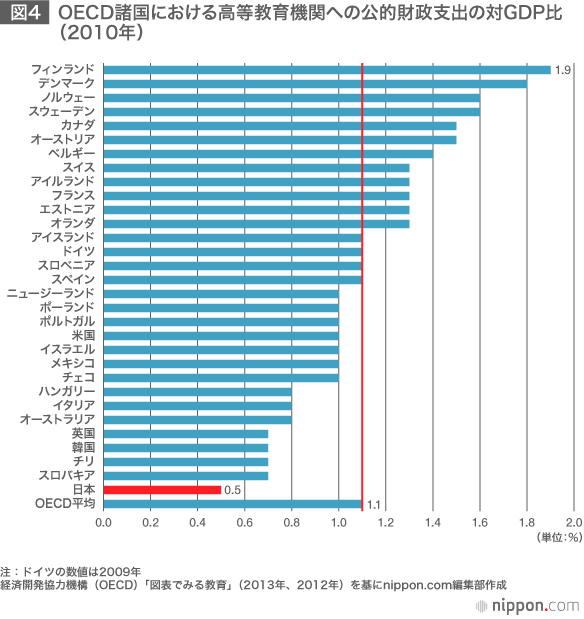
欧米諸国と比較するとき、高等教育在学者に占める成人学生の比率の低さも、際立っている。もっぱら新規高校卒業者を対象に、入学試験による選抜を重視してきた日本の大学では、学生の圧倒的多数を若者が占め、成人学生の数は限られている。文科省統計には、在学者の年齢別構成すら存在しないのが実情である。18歳人口が減少の一途をたどり、定員割れで経営困難に陥る私立大学が続出しているいまも、それは基本的に変わっていない。「生涯学習社会」の到来が言われる中、日本の大学は若者だけの世界であり、成人学習者の比率が着実に高まっている欧米諸国との違いは大きい。
それはさらに、大学院教育の発展の遅れとも深く関わっている。日本の大学では長い間、専門教育も専門職業教育も学士課程の役割であり、大学院は研究者養成の場と見なされてきた。第2次大戦後、大学院制度についても米国モデルの改革が行われたにもかかわらず、米国に特徴的な専門職大学院の制度が導入されたのは、ようやく2004年になってからであり、いまも修士課程在学者の1割弱を占めるに過ぎない。高度の専門教育を受けた人材需要の高まりから、学部卒業者を母数とした大学院進学者の比率は、1990年の6.4%から、200年の10.3%、2010年には12.9%と、上昇傾向にある。しかし欧米諸国に比べてその比率は依然として低い。最大の理由は、人文・社会系大学院の不振にある。2013年の修士課程在学者に占める人文・社会系の比率は17.8%にすぎず、理・工・農・医の自然系が56.5%、工学系だけで41.5%を占めている。こうした構成は、大学院の理工系以外の職業人養成機能が弱体であり、大学院が成人学習者に閉ざされた学習の場にとどまっていることを意味する。社会系大学院を代表するビジネススクールの不振は、そうした大学院教育における日本の立ち遅れを、象徴するものといってよいだろう。
注意深く見守るべき大学改革の行方
このように、グローバル・スタンダードの充足という意味での国際化もまた、重要な課題として残されている。OECD調査団が「高度技術社会の要求する教育目標を、満たすことができない」と、厳しく指摘した高等教育の日本的構造は、依然として基本的に持続されていると見なければなるまい。
経済成長の低迷の下で高齢化の進行する日本では、政府の公的財政に占める福祉・医療関連支出が増加の一途をたどり、国際水準から見て低位にある教育支出の増額どころか、抑制・削減が求められている。そうした厳しい状況下での高等教育における「自由と競争」は、特に研究面での競争力による大学間の格差を広げ、一握りの強者と多数の弱者を生む可能性が高い。その一方で、国立大学法人については、文部科学省の「直接の統制」は緩和されたものの、補助金などの財政的手段による「間接的な統制」が強化され、自律的な大学経営を制約しているという批判もある。
限られた資金投入の下での「自由と競争」は、「硬直的で階層的な構造」を根底から変革する力とはならず、制度の柔軟性や多様性をもたらすことなく、序列化の一層進んだ、より傾斜の大きいピラミッド状の高等教育の構造を拡大再生産するにとどまるのではないか。この20年余の「規制緩和」政策の下での一連の改革が、日本の大学を、高度技術社会・知識基盤社会・学習社会など、さまざまに呼ばれる近未来社会の多様な要請に応え得るものに、どこまで変革できるのか。改革の行方は、注意深く見守られなければなるまい。
タイトル写真=英・高等教育専門誌『タイムズ・ハイヤー・エデュケーション』世界大学ランキングウェブサイト
▼あわせて読みたい
 高等教育の“日本病” 高等教育の“日本病”グローバル化競争に乗り遅れた日本の大学 |  大学改革と教育基本法改正で、日本の教育は復活するか 大学改革と教育基本法改正で、日本の教育は復活するか |