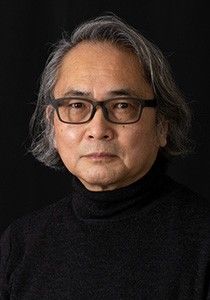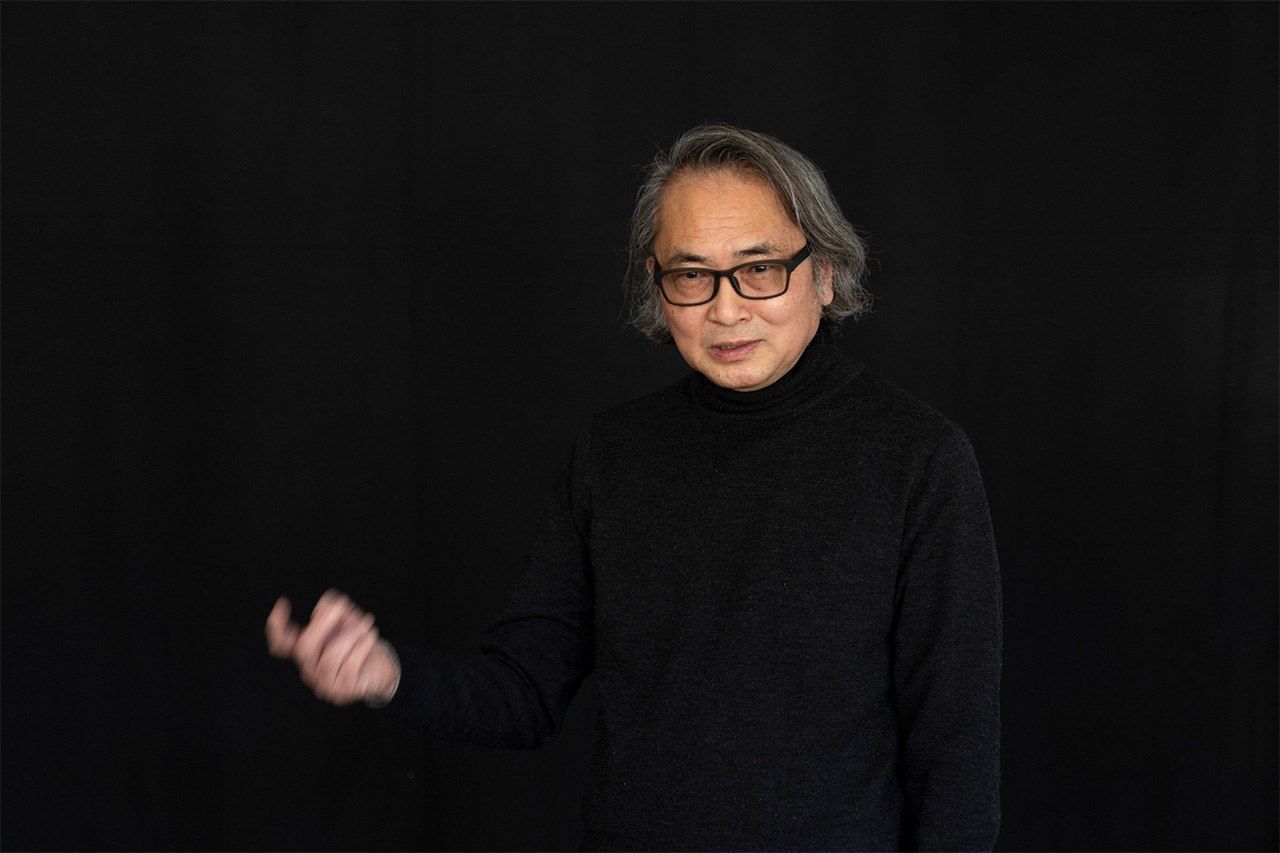波動を感じ、開示される「秘密」を撮らせてもらう―写真家・六田知弘氏
People 美術・アート- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
「撮るぞ」という意識が失せて
こめかみに浮き出る血管、口元のしわ、静かな眼差し…。自然光を受けて浮かび上がる「無著(むじゃく)菩薩立像」(運慶作、興福寺蔵)を捉えた作品は、六田氏の代表作の一つとなっている。生きた無著が立ち現れたようなリアルさが、見る者の心を揺さぶる。

無著菩薩立像
この表情との邂逅(かいこう)は、わずか10分間だった。六田氏は、意図しなかった撮影は特別な経験だったと振り返る。

無著菩薩立像をはじめ、優れた仏像が一堂に会す写真集『仏宇宙』
2017年秋に東京国立博物館で開催された「運慶」展のため、興福寺・北円堂で無著像を撮影した時のことだ。寺院や博物館のメンバー、そして撮影助手など十数人のスタッフを動員した午前の撮影で、「撮れた」と一応満足して昼休みに入った。
撮影中に着信のあった携帯電話を見ると、大学時代の友人から。折り返しの電話を入れた六田氏に、友人は「俺、右足を付け根から切断したんだ」と告げた。その知らせに呆然となって、スタッフが午後の手順を打ち合わせているのが、全く頭に入ってこなかった。
北円堂へ戻ると、午前中締め切っていた扉の1つがなぜか開いている。堂内に入ると、扉から差し込んでくる冬の低い陽光が床面に反射し、薄暗い中に無著像を浮かび上がらせていた。
「これや!」
スタッフは午後の撮影の準備に入っていて誰もいない。望遠レンズを使って1人で一気呵成(かせい)に撮った。この瞬間を狙っていた訳でも、計画していた訳でもない。「この仏像を、こういうように撮るんだ」というような意識は、まったく抜け落ちてしまっていた。無著像が開示する「秘密」を受け止めることができたと感じた瞬間だった。
「撮って良いよ」と言ってくれる
被写体が「秘密」を開示してくれる時は、「撮っていいよ」と語りかけてくれるのだという。その言葉に従い、撮らせてもらう。六田氏は「考えているよりも、被写体はもっと豊かなものを発信している。僕がそれを受け止める『受信機』になっていないといけない」と話す。
日常の意識を脱した「無心」ともいえる状態を、六田氏は「ニュートラルになる」「意識が下がる」と表現する。被写体に臨むにあたって常に志向する状態だ。仏像や美術品、建築物など、さまざまな被写体が語り掛けてくるものを、そのまま撮る。被写体が代わっても、その姿勢に変わりはない。
六田氏が受信機となって感じ取るものとは何なのだろうか? それは、被写体が内包する「祈りの記憶」と「時の記憶」だという。東日本大震災の被災地に残されていた遺物の撮影では、生前それを所有していた人の記憶、被災の前後に流れた時間の記憶、それらが強い波動となって感じられた。

2011年の東日本大震災の際に発生した津波にのまれ、水が引いた後に地面に残された遺物を撮った写真集『時のイコン 東日本大震災の記憶』より
数百年から千年以上もの時を経た仏像では、その記憶が一層濃厚になる。信仰者として仏像を制作した運慶、信仰の対象として仏像に手を合わせてきた人々、そうした記憶の堆積が発する波動に自身をシンクロさせ、受け止める。六田氏は「写真家は、それらをキャッチする受信機的なものを持っていることが必要だ」とも言う。
「写真は自己表現に向いていないメディア」
六田氏とて初めから、こうした境地に達していたのではない。早稲田大学の学生だった頃、新しい地平を切り拓いた写真家として尊敬する東松照明氏(1930〜2012年)に弟子入りを志願したが、あっさり断られた。だが、作品の講評を受けながら交流を続ける中で、ある時東松氏からこう言われた。「君は自己表現の手段として写真をやろうと思っているのか。写真は自己表現には全然向いていないメディアだ。小説や絵画の方がずっと自己表現できる」
「東松さんの写真こそ、自己表現そのものじゃないか。何を言っているんだ?」──そんな疑問が氷解したのは、それから2年がたってから。大学を卒業後、ネパール東部ヒマラヤ地方に暮らす少数民族シェルパの村にのべ18カ月滞在し、人々や風物を撮り歩いた時だ。
「自分の外側の世界の方が、圧倒的に広くて深いやないか。小さな僕が自己表現として、それを撮影するなんておこがましい。できる訳がない。モノが発する、言葉で捉えきれない部分を受信機となって写真に定着させるのが自分の使命だ」。それがシェルパの村での「自己の世界観を激変させる体験」(六田氏)を通じて得た結論だった。

ヒマラヤ山中のシェルパの村に暮らして撮影した処女写真集『ひかりの素足―シェルパ』より
「自己表現には写真は不向きだ」という東松氏の言葉。あの時、ようやく自分の腹にすとんと落ちて以来、六田氏の信条であり続けている。
光の粒子と一体になる
シェルパの村での作品を集めた処女作『ひかりの素足―シェルパ』(1990年)、中世ロマネスクの教会や修道院を題材とした『ロマネスク 光の聖堂』(2007年)『石と光 シトーのロマネスク聖堂』(2012年)『ロマネスク―光と闇にひそむもの』(2017年)。六田氏の作品集には光をタイトルとしたものが多い。
自然光での撮影を大切にする六田氏の原点は、小学生の頃に祖父に連れられて奈良の古寺を巡った経験にある。薄暗い堂内で、ぼんやりと仏像が浮かび上がるのを何時間も見続けた。そうすると、「光の粒子が見え、粒子の塊の中に僕が入り込む。そして対象物が発するものと僕とがいつもシンクロした」という。
それはシェルパの村での体験によって確信的となる。『ひかりの素足―シェルパ』の後書きで、六田氏は次のように記している。
そうした光の拡散と密集のめまぐるしい交錯のせいか、ぼくはしばしば奇妙な眩暈(めまい)に引き込まれた。カメラを構えて世界を覗(のぞ)き込みながら、なぜかぼくは異世界の入り口にいると感じた。そしてまた、この世界と異なる世界が、境界をおかして随所でこの世界に侵入してくるのを感じた。
六田氏が捉える光は、国境や宗教を超えて共感を呼ぶ。ロマネスクの教会建築を撮影した写真展をパリで開催した際、来場者からは「私たちが子どもの頃から教会で感じていた光が写っている」「東洋人のあなたが、なぜ私たちが感じる光を捉えることができたのか」と感嘆の声が多数寄せられた。
装飾がなく薄暗い修道院の堂内へと小窓から柔らかい光が差し込み、光と影の中に神を感じる―。800年以上にわたって人々が信仰してきた記憶の堆積が発する光の波動を六田知弘という受信機が受け止めた証ではないか。

ヨーロッパ中世・ロマネスク時代に建てられたシトー会の聖堂を撮った写真集『石と光 シトーのロマネスク聖堂』より
「宇宙の秘密のかけら」が写る
フィルムの時代に写真家としてのキャリアをスタートさせた六田氏だが、デジタルカメラの登場がターニングポイントとなったという。
フィルムカメラは、撮影したものをすぐに確認することができない。写せば写すほどコストがかさむので、事前に理想形をイメージしてから慎重にシャッターを押すことも少なくなかった。だが、デジタル時代となってそうした配慮は無用となった。余計なことを考えずに済むようになり、六田氏は「意識していては撮れない『宇宙の秘密のかけら』のようなものが、デジタルカメラならふっと写り込んでくれる」と話す。
初めてデジタルカメラで撮影したのは運慶の仏像だった。狭い堂内では大型のフィルムカメラが使えなかったためだが、仏像が発する「気」のようなものの動きを感じ、シャッターを切った。その場で液晶画面を確認すると、自分の感じたものがそのまま写り込んでいる。「うわー、凄いものが写ってきた!」と、思わず唸り声を上げてしまったのを今でもよく覚えているという。
展覧会などでは、多くの人に「光を待つのでしょう?」と尋ねられるが、「そんなことは絶対ない」と否定する。光の加減を事前に構想して撮ることはしない。「現場では被写体の周辺を歩き回りながら、ふとした瞬間に出会った光で無意識のうちに撮る」のだという。そのスタイルは一貫して変わらず、進化するデジタルカメラによって表現の可能性をさらに広げている。
意図せずに導かれ、被写体と共鳴した写真家の感動が作品を通じてさらに人々に共振し、広がっていく。そうした波動を受け止める「アンテナ」はますます鋭敏になり、これからも、見る者を秘密の異世界へといざなっていってくれるだろう。

中国三大石窟の一つ雲岡(うんこう)石窟の全貌を捉えた写真集『雲岡石窟 仏宇宙』より
インタビュー:近藤久嗣(nippon.com編集部)
構成・文 : 住井亨介(nippon.com編集部)
バナー・本文中インタビュー写真 : 川本聖哉
バナー写真=駒澤大学・禅文化歴史博物館で