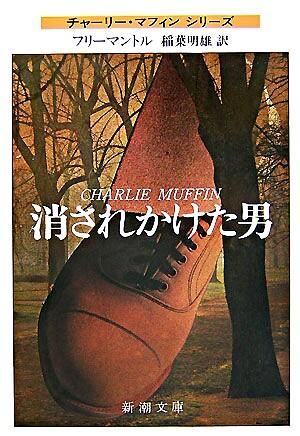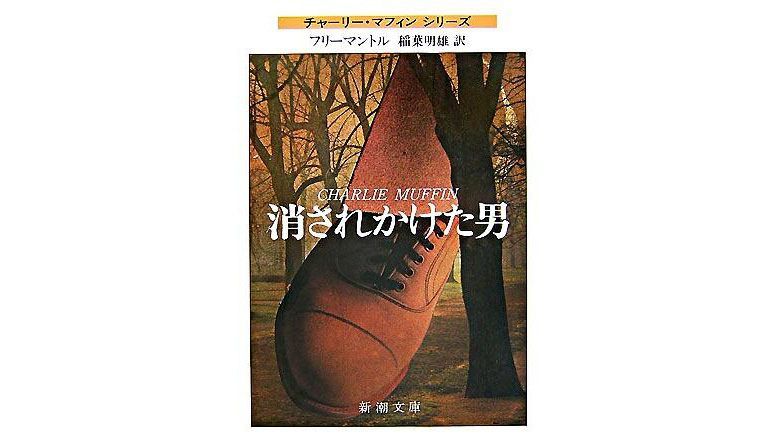
【書評】スパイが生き残る条件:フリーマントル著『消されかけた男』
Books 政治・外交 文化 エンタメ 国際- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
古参社員であるあなたは、組織のなかで有能なプロフェッショナルである。しかし、忠誠を誓った上司が派閥争いに敗れ、上層部の顔触れが一新された。あなたは職場に残れたが、新しいボスが連れてきた若手にポジションを奪われ、冷や飯を食わされている。
さて、それでも気に入らない上司の命令に従うべきなのか?
チャーリーの置かれた立場を、一般の会社に置き換えてみるとこんな感じである。彼はどのように行動したか。読者は、一見風采の上がらない主人公に感情移入しながら、作者が描くスパイの非情な世界へ、のめりこんでいくだろう。
この作品も、スパイ小説のジャンルで名作の評価が高い。イギリス本国では1977年に出版され、文庫の邦訳が出たのはそれから2年後だが、版を重ね、いまだに絶版になっていない。
物語はスピーディーに進み、娯楽性に溢れていながら、情報戦の仕掛けは緻密である。情報部の女性秘書との情事が折にふれ描かれているが、これとて、計算された伏線となっている。
最大の読みどころは、チャーリーが現体制に一矢報いるところ。普通なら拍手喝采となるのだが、作者は、読者が想像するような予定調和的な展開にはもっていかない。
唖然とさせる驚きの結末。読者それぞれに受け止め方は180度、異なると思う。どんな感想をもったのか、読んだ者どうしで議論したくなる小説である。
「時代おくれのプロなのだ」
それでは物語の世界へ。
時代は東西が鋭く対立した冷戦期から、デタント(緊張緩和)へ移行している。およそ1970年代後半の物語である。
まずは、主人公の横顔を紹介しよう。
<プロだ。とはいっても今どき流行らない時代おくれのプロなのだ、スネアは軽蔑まじりにそう考えた。>
前線に25年勤務したチャーリーは、今の情報部内ではそう見られていた。スネアとは、降格されたチャーリーの後釜である。
彼らからみると、過去の遺物のような男はこう見える。
<はき古したハッシュ・パピーのスエードの短ブーツ、何日もとりかえないマークス&スペンサーのシャツ、そして平板なマンチェスター訛りをしゃべる冴えない男>
しかしながら、彼にはソ連情報部(KGB)の大物スパイであるベレンコフ将軍を逮捕し、イギリス国内にはりめぐらされたソ連のスパイ網を壊滅させたという輝かしい戦歴があった。
当のベレンコフは、チャーリーを油断のならない男と観察している。
<この男の身には或る名状しがたい雰囲気(略)、血も涙もないしたたかさ、といった匂いがまとわりついている。>
チャーリーは、戦後に情報部入りした現地工作者だった。かつて、情報部は家柄のよいパブリックスクール出身のエリートを重用してきた。いわば上流階級で固めた組織だったわけだが、戦後は人材難から階級にとらわれず工作員が採用される。労働者階級出身のチャーリーもそのひとりで、彼は腕利きだった。
ところが、彼の能力を高く評価していた前部長が内部抗争で失脚し、右腕の次長も自殺に追い込まれた。
後任の部長カスバートスン卿は、上流階級主体の組織に戻そうと考えた。新しい次長も上司に忠実に仕える有能な公務員にすぎない。
彼らは目障りなチャーリーを抹殺しようと画策する。
一斉射撃の餌食になった
物語の冒頭部分はこうだ。
チャーリーと、若手のハリスン、スネア(2人は上司お気に入りの上流階級出身者)は東ドイツでの作戦を終え、東ベルリンにいる。
3人は、それぞれの方法で、帰国しようとしていた。
若手は何事もなく、すんなり「ベルリンの壁」を通過していった。
チャーリーは、1週間前に彼らが西側で借り、東ベルリンへ入ったフォルクスワーゲンで戻ってくるよう、部長から指示を受けていた。国境を越える書類は整っている。
しかし彼は、敏腕スパイならではの嗅覚から警戒した。ベレンコフ逮捕以来、検問は強化されているはずである。
<ほかに選択の余地はない。生き残れるかどうかの問題なのだ。(略)その手段、その方法がいかに受けいれがたいものであろうと(略)生き残らねばならないのだ。>
そう考えた。これがチャーリーの生き様を貫く哲学である。
彼は一計を案じた。東ベルリンでリクルートした亡命希望の学生がいる。彼に、本来自分が乗るべきワーゲンと偽造旅券を与えることにした。
若者は、嬉々として東西の境界へむけて車を走らせる。検問直前、突如、スポットライトの閃光を浴び、国家警察の車両に囲まれた。
狼狽した若者は、ドアを開けて飛び出した。「止まれ!」と拡声器で制止されたものの、逃げようとする。一斉射撃の餌食になった。
西側から、ハリスンとスネアがその光景を見ていた。やっかい者が死んだと思いこんでおり、若者が身代わりになったとは気づいていない。
やはりチャーリー出国の情報が敵方に漏れていた。彼は独力で手に入れた偽造旅券を用い、列車で国境を越えることにした。
そして、何食わぬ顔で情報部に顔を出したが、現体制からみれば邪魔者であることに変わりはない。
姿かたちを見た者はいない
この作品の面白さは、英国情報部とCIA、KGBとが三つ巴になって情報戦を繰り広げるさまが、巧緻に描かれているところにある。
欺瞞と擬装、敵味方入り乱れての騙し合いが始まる。
ソ連は、逮捕された祖国の英雄ベレンコフ将軍を、是が非でも、人質交換してでも取り戻したい。
その任にあたるのが、彼とは長年の盟友であるカレーニン将軍だった。しかし、無策のまま1年以上が過ぎ、彼は最高会議幹部会から責任を追及されそうになる。粛清される可能性があった。
カレーニンが、駐モスクワ米大使館主催の取るにたらないレセプションに現れた。これは極めて異例なことで、彼が西側の前に顔をさらすことはまずない。長きにわたりKGBの大幹部として、その存在は知られていても、姿かたちを見た者はいないのだ。
将軍はさりげなく、居合わせていたイギリス大使館員と言葉をかわす。
何らかのメッセージを送ったのか。
米国大使館の文化アタッシェに身分を擬装していたCIAの駐在員は、その様子を目ざとく見つけ、本国に緊急電を打った。
米国情報機関の動きは素早かった。部下の報告を受けて、CIA長官のラトガーズは、カレーニンに亡命の意思があり、と読み取った。
彼は、第二次大戦中、CIAの前身となるOSS(戦略情報局)の少佐として活躍した非のうちどころのないプロであり、野心家でもある。
カレーニンは、スターリンからいまのブレジネフの時代までを生き抜いた男。わが陣営に取り込むことができれば、その価値ははかりしれない。
歯がゆいのは、将軍が英国に亡命を求めたことだった。なんとか横取りしたい。 いまや落日の英国情報部に任せておくと、絶好のチャンスは失われてしまう。CIA長官は、国務長官を通じ、同盟国に協議を申し入れることにした。
CIAとの共同戦線
一方、英国情報部の部長カスバートスン卿も色めき立っている。カレーニンの亡命をわが手で成就させることができれば、未来永劫にわたって名を残す。
部長は、ハリスンとスネアに将軍の意向を確認させることにした。
ところが、偽装身分でカレーニンとの接触には成功したものの、ほどなくして身元が発覚し、ハリスンは逃走中に銃撃されて殉職。スネアは逮捕されてソ連の刑務所に監禁されてしまう。
どこかから、両名に関する情報が漏れていたとはいえ、所詮、この任務にあたるには、荷が勝ちすぎていたのである。
かくして、チャーリー・マフィンにお鉢が回ってくることになる。部長にとっては不本意だが、もはや、この男の剛腕に頼るほかない。
しかも、米国からの横やりで、CIAと共同戦線を張らねばならなくなっているのだ。
英米両情報機関の合同会議の様が面白い。互いに腹の探り合いで、容易に手の内をさらさない。
CIA長官は、国務長官にこう訴える。
「英国の連中は、信じられないくらい傲慢なのです。もういいかげんに自分たちが世界の強国であったことを忘れて、現在ではいかに重要さを失っているかを認識すべきだと思いますがね」
とはいえ、英米ともに、亡命者の身柄確保に前のめりになっている。
だが、チャーリーだけは冷静だった。そもそも、将軍の亡命希望は確かなことなのか。本人は仄めかしているが、それは西側をはめようとする罠ではないのか。
「二人ともまともな職業じゃない」
チャーリーは、敵地モスクワでカレーニンと接触し、亡命の感触を得る。
罠との疑惑もぬぐえないが、将軍はチェコスロバキアの国境を越えて、オーストリアに入り、ウィーンで西側情報機関が用意したセーフハウス(隠れ家)に駆け込むというシナリオ。亡命の見返りに50万ドルを要求してもいる。
英米共同で、用意周到な援護計画が練られた。史上最大の作戦の開始である。
<すでに百五十名の英米情報部員がウィーンに派遣されて、三トンの移動通信機器が空を運ばれ、アメリカ大使館に収納されていた。そしてこの日、さらに五十名の部員が送りこまれつつあった>
カレーニンを連れてくる役割を、チャーリーとCIAのモスクワ駐在員が担う。
「罠というやつは、すっかりこちらの周囲に張りめぐらされるまでは、順調にいっているようにみえるものさ」
と、チャーリーは相棒に言う。
しびれる場面が続く。
読者は、一気呵成に頁を繰っていくことだろう。
読後、「どうして?」という疑問が必ず浮かぶはずだ。
私の解釈。これは、チャーリーというプロフェッショナルならではの生き様なのだ。
本作の最初のほうで、チャーリーと、彼が逮捕したKGBの大物スパイ・ベレンコフとが刑務所で会話する場面がある。
ベレンコフはこう語っている。
「おたがいを見るがいい。異なった国に生れ、まったく正反対の立場に身をおいていることを別にすれば、われわれは瓜二つといっていい。それに二人ともまともな職業じゃない。前線にいながら、生きながらえ、もうすぐ五十歳に手がとどこうという二人のスパイなんて、ほかに聞いたことがあるかね」
確かに、二人は生きながらえる。
フリーマントルは、1936年、英国のサウサンプトン生れ。デイリー・メイル紙の外報部長を最後に作家生活に入った。
私は、作者の仕掛けにまんまと騙された。
消されかけた男
ブライアン・フリーマントル(著)、稲葉明雄(訳)
発行:新潮社
309ページ
初版発行日:1979年4月26日
ISBN:978-4-10-216501-0