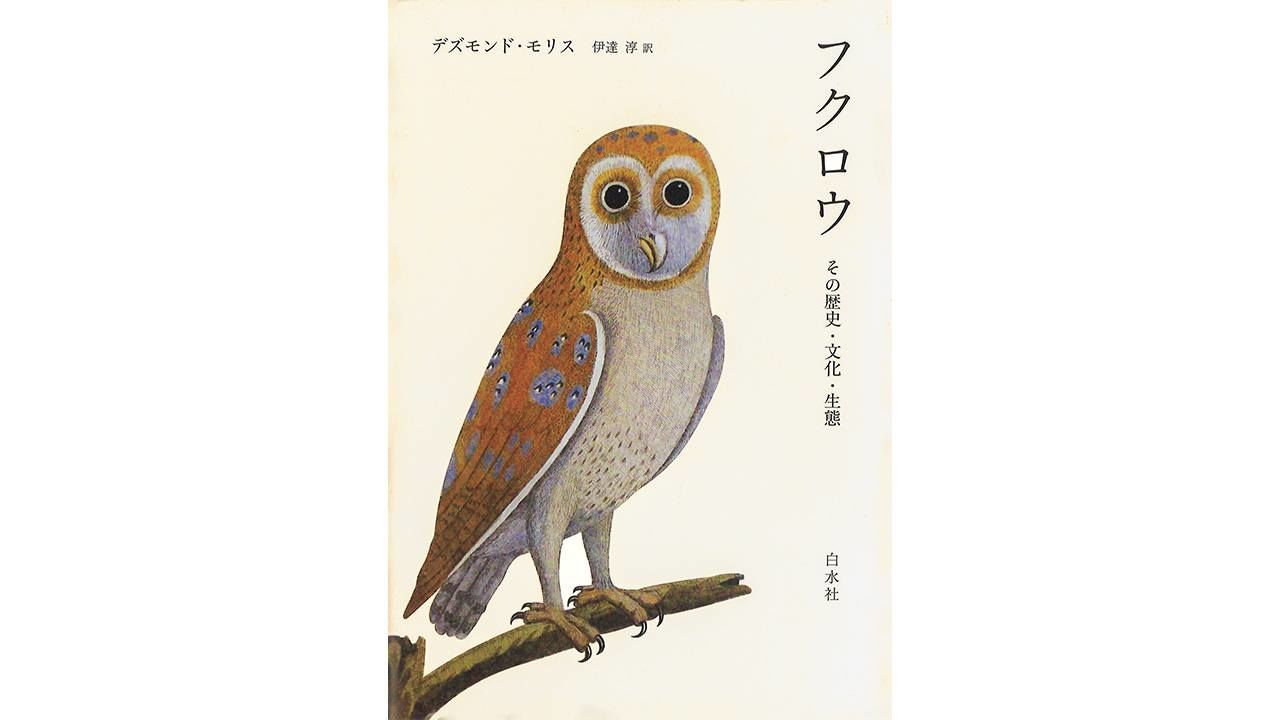
【書評】人類を魅惑する鳥:デズモンド・モリス著『フクロウ その歴史・文化・生態』
Books 社会 歴史 文化 美術・アート- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
戦争と人類への怒りが執筆の動機
著者は世界的ベストセラー『裸のサル』(The Naked Ape, 1967)などで知られる英国の著名な動物行動学者。今年91歳になった。少年のころ、フクロウとの衝撃的な出合いがあったことを本書の序文で告白している。
第二次世界大戦さなかの1942年のある夏の日、イングランド南西部のウィルトシャー州の寄宿学校に通っていた著者は、野原に横たわる血まみれのフクロウを見つける。瀕死の状態で、獣医に連れて行っても助かる見込みはない。
「このフクロウに怪我を負わせた人類に対して煮えくり返るほどの怒りを覚えていた。(中略)その日、ヨーロッパの至るところで負傷することになる無数の人々を象徴しているように思えた。あの時、どれほど人類を憎く思ったことか。容易な方法に逃げるわけにはいかないと思った」
見て見ぬ振りをするのは簡単だが、臨終のフクロウを見つめながら悩んだ末、大きな石を探してきて、息の根を止めたという。「苦しみを終わらせてやることはできたが、気分は最悪だった」と述懐する。
「この本を書こうと思ったのは、あの時の傷ついたフクロウに対する償いの気持ちによるところが大きいように思う。フクロウが生物学的にどれほど魅力的な存在であるか、フクロウが象徴してきたものやフクロウにまつわる神話がどれほど多様で豊かであるかといったことを紹介し、フクロウのために何かをすることで罪滅ぼしをしたいと思ったのだ」
「人間の顔をした鳥」は矛盾した存在
「フクロウのために最善を尽くす」との覚悟で執筆した原著『Owl』は2009 年にロンドンで出版された。本書は10章で構成され、生物学的な解説だけでなく、フクロウに関する古今東西の歴史や文化、蘊蓄(うんちく)が網羅されている力作だ。カラー・モノクロ図版が多く、ページをめくるだけでもフクロウの魅力に触れられる。
フクロウは化石の研究から、少なくとも6千年前に一つの種として存在していた。「鳥類の中で最も古い種の一つであり、その間に十分な年月をかけて、夜行性の肉食鳥として極めて特殊な変化を遂げた生態にさらに磨きをかけてきた」
平らな顔に大きな両眼を前に向けた丸い頭部は人間の顔を連想させる。そこから耳のように突き出た二つの羽角があるミミズクもフクロウの仲間だ。
本書によると、「古くには、フクロウのことを人間の顔をした鳥と呼んでいた時代もある」。だから思慮深い鳥と思われがちだが、最近の研究では「実際はカラスやオウムほど賢くない」。それほど知的ではないことがわかっている。
地球上にフクロウが何種いるかは専門家の間でも意見が分かれる。著者は純粋な種として198種を列挙する。本書巻末の付録として、世界各地に分布する198種の和名、学名、生息地域が10ページにわたり一覧表になっている。
フクロウは極地の不毛地帯を除けば、小さな島も含めて世界中にいる。だからこそ古代から人間との関係が深く、伝説、民話、文学、芸術、絵画、紋章やバッジ、看板、寓意画などのエンブレムの対象にもなったのだろう。
夜空を羽音もなく飛翔するため、一般人が野生のフクロウを目にすることは滅多にない。こうした神秘性からか、著者は「フクロウとは矛盾した存在である。最も知られている鳥であると同時に、最も知られていない鳥でもある」と定義する。
英知と邪悪、イメージは変遷の歴史
東京・永田町の首相官邸。レンガ造りの旧官邸の屋上にある国旗掲揚台には4羽のミミズクの石像があり、東西南北を見渡している。
首相官邸ホームページには「ミミズクはローマ神話に登場する知恵と武勇の女神、ミネルバの使いで、知恵の象徴として官邸の役割を表しているともいわれています。また夜行性なので不寝番として総理を守っているという説などもあります」と書かれている。
西洋では古来、森の賢者と呼ばれるミミズクを含め、フクロウは「英知」や「知恵」の象徴とされてきた。一方で、日が暮れてから活動するため夜盗のような「邪悪」な性質を備えているのではないかとの見方も少なくない。
著者は「人類とフクロウの関係を遡って検証してみると、フクロウは実際に、しばしば知恵と邪悪の象徴とされてきたことがわかる」と分析。そのうえで「数千年もの間、この象徴的な二つの属性は互いに優勢を保ったり劣勢になったりを繰り返してきた。すでに十分に誤解されているフクロウに関して、これもやはり矛盾した特徴である」と時代や地域によってイメージが変遷してきたことを指摘する。
本書では、中国の事例が紹介されている。殷王朝(紀元前1500-紀元前1045年頃)の時代、「尊」と呼ばれるフクロウを模った精巧なブロンズ製の酒器が盛んに作られた。著者は「これらの製造に使われたブロンズの重量を考えると、明らかに裕福な社会だった」などと記述、当時はフクロウが好まれていたと推定する。
ところが、古代の封建王朝時代から1千年ほど経った道教の時代になると、「フクロウは怪鳥で、雛は母鳥の目をくり抜いて食べてしまうと信じられていた」。フクロウは暴力的で恐ろしい存在へと様変わりしたのだ。
日本の先住民族、アイヌの人々はシマフクロウを神(カムイ)としている。しかし、著者は「アイヌの人々はフクロウのすべての種を守り神にしているわけではない。紛れもなく邪悪な存在だとされているフクロウもある」。フクロウは種によっては神の鳥であり、不吉な鳥でもある。
「猫頭鷹」は文学者や芸術家を魅了
フクロウは中国語では「猫頭鷹」と表記する。確かに、フクロウと猫の顔はよく似ている。ともに夜行性で肉食である。
本書では、19世紀の英国の詩人・画家、エドワード・リアの代表作「フクロウと仔猫」が紹介されている。フクロウと仔猫が小舟に乗って航海、結婚して、月明かりの中、最後にダンスを踊るというナンセンスな詩だ。リア自身が描いた挿絵もよく知られている。
著者は「リアの書いたフクロウはフィクションに出てくるフクロウの中では最も有名なものの一つになった」と評価する。
「二十一世紀の文学において、物語の展開上、重要な役割を担うものとしてフクロウを取り上げた唯一の作家はJ・K・ローリングだ」。1997年から2007年に刊行され、大ヒットとなった彼女の作品『ハリー・ポッター』シリーズで、メッセンジャー役として数種類のフクロウが登場したことは記憶に新しい。
フクロウをモチーフとした絵画は枚挙にいとまがない。著者は偉大な画家としてヒエロニムス・ボス、アルブレヒト・デューラー、ミケランジェロ、フランシスコ・デ・ゴヤ、パブロ・ピカソらを挙げ、彼らの作品も紹介している。
ピカソは「一連のフクロウの絵やデッサンを残していて、陶磁器の制作においても壺や瓶の題材としてフクロウを頻繁に取り上げている」。しかも「家でペットとしてコキンメフクロウを飼っていたこともある」と、フクロウの魅力に取りつかれた芸術家の姿を事細かに描写している。
著者自身もフクロウをめぐる森羅万象を集大成した本書の執筆を通じて、その魔力に改めて開眼したのではないか。
フクロウ[新装版] その歴史・文化・生態
デズモンド・モリス(著)
伊達 淳(訳)
発行:白水社
四六版 230ページ
発行日:2019年3月10日
ISBN: 9784560096925
