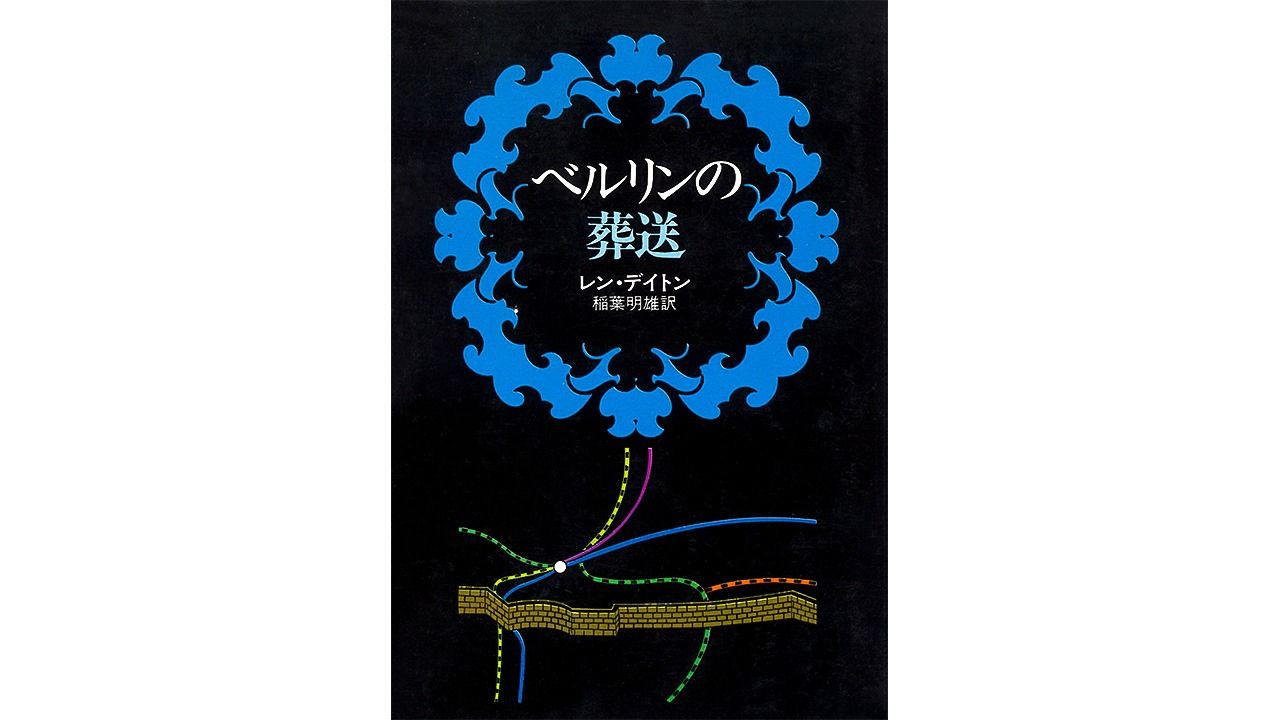
【書評】敵味方が曖昧な諜報戦の闇:レン・デイトン著『ベルリンの葬送』
Books 政治・外交 社会 文化 国際- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
冷戦期を描いたスパイ小説のなかで、ジョン・ル・カレの『寒い国から帰ってきたスパイ』(1963年に出版)を最高傑作とするならば、ここに紹介するル・カレと同世代の英国人作家レン・デイトンの『ベルリンの葬送』(1964年)もベストセラーとなっており、是非お薦めしたい一冊だ。
いずれの作品も「ベルリンの壁」をはさみ、東西両陣営の情報機関の暗闘が見事に活写されているが、まったく作風がちがうだけに読み比べてみると面白い。
しかし惜しむらくは、本作が絶版となっていること。ネットを通じるなどして入手することは可能だが、そこでの市場価値は、少々くたびれた文庫本でありながら1000円以上!の値が付いている(私が手にしている当時のハヤカワ文庫の価格は520円)。いまでも、それだけ評価の高い作品というわけである。
一人称で語られるスパイの世界
本作の主人公は、「わたし」という一人称で登場する。
物語の時代背景は1960年代初頭。彼は、英国の内閣直属の情報機関「WOOC (P)」と表記される組織に所属している。
本作は、この、「わたし」の目を通してスパイの世界が描かれているところに妙味がある。一人称の語りゆえのことなのか、独特な雰囲気が醸し出されており、クセになりそうな味わいがある。
この作品のもうひとつの特徴は、日付と場所によって細かく章立てがなされていることだ。場面展開がはやく、読みやすい。始まりが10月5日のロンドンで、結末が11月10日。やはりロンドンでの休戦記念日で終わっている。
このわずか1か月のあいだに、ある作戦が実行される。「わたし」は、ロンドンから東西ベルリンを行き来し、チェコのプラハやスペイン国境に近いフランスの海岸を訪ねもする。獅子奮迅の活躍ではあるのだが、彼はたんたんと任務を遂行していく。
そして、この作品の最大の読みどころというべきか。面白さは読み進むにつれて、誰が味方で誰が敵なのか、わからなくなってしまうところにある。
読者は、皮肉屋である「わたし」のシニカルな視点のおかげで、あらゆることが信用できなくなってしまう。だから、最後まで結末が予想できない。とにかく読者は、「わたし」とともに魑魅魍魎が跋扈する諜報戦の世界を突き進んでいくしかないのである。
その先に見えてくるものは何であるのか――。
暗号名は「キング」
それでは、「わたし」の世界に飛び込んでみよう。
彼に課せられた使命は、ソ連の高名な化学者を亡命させることだった。そのためには、ベルリン駐在の連絡員の手を借りなければならない。
その連絡員の名は、ジョニー・ヴァルカン。東西ベルリンを股にかけて暗躍する切れ者のスパイである。
しかし、「わたし」の上司はヴァルカンが気に入らない。いちおう、英国情報機関のために働いてはいるが、彼は多額の報酬を要求し、金のためなら東側の手先となって動くこともある、やり手の一匹狼。要するに、忠誠心に疑問符のつく男というわけだ。
彼の経歴は謎めいている。物語の進行にしたがって、じょじょにその正体が明らかになっていき、それが驚愕のラストシーンにつながっていくことになるので、主人公とともに最重要の登場人物である。
ヴァルカンはギャング的な魅力に溢れている。
黒のキャデラック・エルドラドを乗り回し、着ている服は「上等なベルリン仕立てで、生地は英国製のピンヘッド・ウーステッド」、金無垢の腕時計に、足元は「手縫いのオックスフォード靴」といういでたちである。
「わたし」が観察するところ、ヴァルカンは、
<自分の意志と相談ずくで年をとっているように思える男だった。とても四十の坂をこえたとはみえず、頭髪はつやつやと光り、ひたいは褐色に日灼している>
精悍でしゃれ者という印象。金払いがよく、女性に、よくもてる。
彼は、スパイの世界では一目、置かれる存在で、西ドイツのゲーレン機関からは「キング」という暗号名で呼ばれている。
KGBの大佐が登場
本作では、各国の情報機関がそれぞれの思惑で、「わたし」の任務にかかわってくる。
ゲーレン機関は西ドイツの情報機関のひとつで、創設者の名前をとってそのように呼ばれていた。
旧プロイセン出身のゲーレンは、ヒトラーが政権奪取する以前から、国防軍の諜報機関に身を置いていた。ナチス時代にも、ソ連を担当して目覚ましい実績を残し、ドイツ敗戦直前、すすんで米軍に投降し、戦争犯罪に問われることなく、戦後もスパイの世界で暗躍した。同機関はドイツ連邦情報部(BND)となる。
ストーリーに戻れば、結局は上司もヴァルカンに頼らざるをえないことを認め、「わたし」はベルリンを訪れる。
ヴァルカンとともに東ベルリンへ潜入した「わたし」は、彼から今回の作戦に必要な重要人物を紹介される。
東側の大物スパイ、KGB所属のシュトーク大佐であった。やはりヴァルカンは敵国とも通じていたことになる。
ともあれ、ソ連の高名な化学者を亡命させるためには、大佐の力を借りるしかないという。
この物語には、魅力的な悪役が3人登場する。ヴァルカンについで、もうひとりがこのシュトーク大佐だ。あとひとりは、赤毛の長い髪の美女。彼女は某国情報機関のスパイだが、もう少しあとに登場する。
シュトーク大佐は、骨格の大きい男で頭髪をうんとみじかく刈りこんでいる。彼は、化学者を連れ出すのと引き換えに、巨額の金銭を要求する。
「わたし」は、大佐の意のままに化学者を亡命させられるのかと疑うが、化学者本人に関する手紙類の複写と電話の盗聴記録を見せられる。
大佐は、化学者が勤務する生化学研究所の保安部長も務めており、この資料をもとに彼を粛清することもできる。つまり、彼は大佐の命令に従わざるをえないというわけだ。大佐は言う。
「きみとわたしは友達になれる。おたがいに信用しなくてはならん」
快適な引退生活を送るため、私腹を肥やすに余念がない相当な悪党である。
こののち、味方のはずのシュトーク大佐は、つねに「わたし」の上手を行き、手強い相手となっていく――。
雌兎のような眼つきの女
ともあれ、化学者を連れ出すことはできる。ベルリンの壁を超える算段は、シュトーク大佐がつける。西ドイツに入ってから英国に送り出すまでをどうするか。
「わたし」はゲーレン機関の力を借りることにした。彼らは協力的だ。
ここでゲーレン機関の工作員から、化学者の亡命に必要な書類を要求される。ヴァルカンの指示で、下記のような人物名で作成してほしいという。
姓名 ルイス・ポール・ブルーム
国籍 英国
職業 農学者
出生地 プラハ
「わたし」は疑問を感じる。「ブルーム」とは何者なのか。架空の人物なのか。
ここで、もうひとりの悪役、美貌の女スパイが現れる。
帰国した「わたし」はロンドンのバーで、謎の女性と出会う。
<赤い髪をひっつめた若い女が、高さ十インチほどのテーブルにのって、髪の乱れるのもかまわず、ものに憑かれたような妖美な身ぶりでツイストを踊っていた>
いかにも蠱惑的な女性のようで、
<口はどちらかというとぽってりして大きめで、罠にかかった雌兎のような眼つきをしていた>
名前はサマンサ・スティール。アメリカのパスポートを所持しているが、その正体は、イスラエルの情報機関のスパイ。
この出会いの場面はなかなか官能的で、頁をめくるのももどかしくなるだろう。
むろん、サマンサは「わたし」の身分を知ったうえで偶然を装って接近してきたし、「わたし」も鼻の下をのばしただけのバカではない。罠(ハニートラップ)と知ったうえで、女スパイの意図を探ろうとする。のちに明らかになるが、彼女は、ヴァルカンとも親密な関係にあった。
このあたりの三者の駆け引きが、たっぷりと書き込まれていて楽しめる。
さあ、主要な役者は出揃った。
「ブルーム」は実在したのか
作戦は順調に進んでいるかのように思えた。
だが、「わたし」には、なにかがひっかかる。なぜ、化学者の名前が「ブルーム」でなければならないのか。ヴァルカンがその名義にこだわっている。
「わたし」はその人物が実在したのかどうか探ってみる。そのために、チェコのプラハに飛んだ。
そこで意外な事実を知ることになる。
第二次大戦末期、ワルシャワ郊外の強制収容所にいた囚人で、ブルームという名のユダヤ人がいた。しかし、彼は、別の収容所へ移動する最中に、殺害された。犯人は、護送していたドイツ兵でヴァルカンという名であったという。
そこからなにを読み取るか。
本作のなかで興味深いセリフがある。「わたし」が、ヴァルカンに向かってゲーレン機関の工作員を揶揄していうセリフ。
「ゲーレン機関の連中の抱いている野心といったら、せいぜい、ソヴィエト連邦の首相を誘拐することぐらいさ。ところが、わが機関の目的は、ソ連の首相をわれわれのために働かせることにあるのだ」
それがイギリスの情報機関がめざす作戦の真髄であろう。こののち、本作戦に関わったゲーレン機関の工作員は、シュトーク大佐の指示で殲滅された。
そして、「わたし」もヴァルカンも、ゲーレン機関の工作員同様に、任務遂行のためのひとつのコマにすぎない。
組織を監督する内閣の高官は、こう言ってヴァルカンを見殺しにする。
「きみは機関直属の公務員だ。ところがヴァルカンは間接的な手先にすぎない。ヴァルカンの責任をとるのは、きみの上司の役目で、きみ自身ではないのだよ」
直属の上司も、
「きみはなにもこんなところに腰をすえて、あれこれ判断をくだす必要はないんだ(略)きみはヨーロッパじゅうに面倒の種をまきちらかしていればいいんだ」
これもまた、現場仕事の工作員の、活動の本質を言い当てたセリフだろう。
にもかかわらず、本来、課せられた任務以上に、「わたし」が「ブルーム」の謎にクビを突っ込んだおかげで、敵味方の区別が曖昧となり、かえって事態は混沌としていく。
ともあれ、それぞれが思惑を抱え、作戦は決行される。
シュトーク大佐は、化学者を棺に隠し、葬儀に向かうと見せかけて検問所を東から西へ、なにごともなく通過させる。
この化学者は、神経ガスの専門家であった。イスラエルの情報機関は、周辺の敵国が所持する生物化学兵器に対抗するために、この化学者の身柄が必要だった。英国から横取りするために送り込まれたのが、女スパイのサマンサ。では、ヴァルカンの狙いはなんだったのか。たんなる報酬だけではなかった――。
ここから先は、本作を読んでのお楽しみである。
相手を出し抜こうとした結果、それぞれが直面する熾烈な運命。「わたし」は難局を乗り切れるのか。
ベルリンの葬送
レン・デイトン(著)、稲葉明雄(訳)
発行:早川書房
文庫版:447ページ
初版発行日:1978年10月31日
