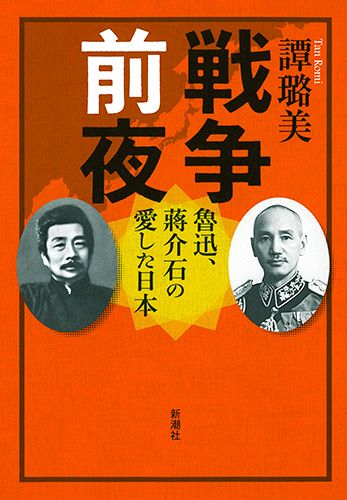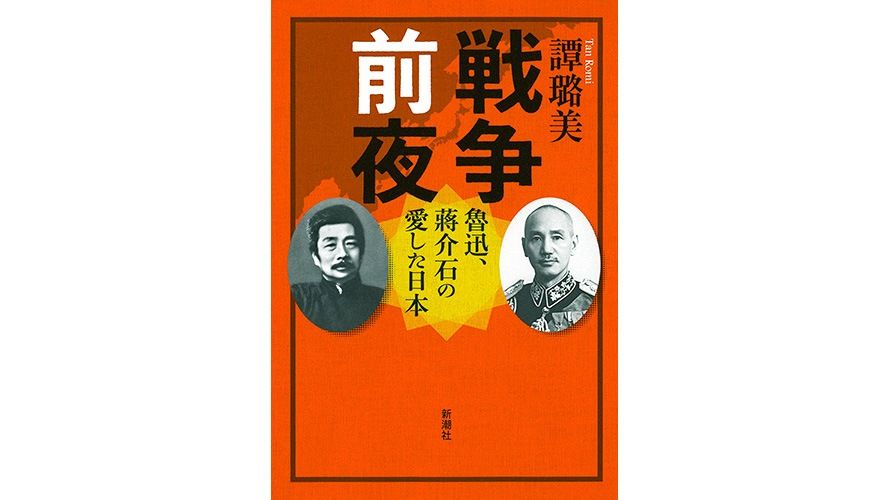
【書評】日中関係はあざなえる縄のごとし:譚璐美著『戦争前夜 魯迅、蔣介石の愛した日本』
Books 社会 国際 歴史 政治・外交- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
電報や電話が連絡手段の「暗殺の時代」
日清戦争の後、中国人の日本留学ブームが起きた。明治維新に成功した日本への憧れも引き金になった。本書の主人公、作家の魯迅(本名周樹人、1881~1936年)と中華民国総統まで上り詰めた軍人政治家の蔣介石(1887~1975年)も、儒教文化が根強く残っていた旧体制の中国(清)からの日本留学組である。
中国革命の父、孫文(1866~1925年)とも深いかかわりがあるふたりに共通しているのは「中国を近代国家に生まれ変わらせようと奮闘した」ことである。著者は「ふたりに日本人の身内がいたことはあまり広く知られていないが、日中関係が悪化するなかで、家庭内にどのような摩擦と葛藤が生じたのだろうか」と家族の微妙な問題や恋愛事情にまで踏み込んで、「ペンと剣の闘い」を繰り広げた魯迅と蔣介石の人生の軌跡を交互に活写していく。
日本側は芥川龍之介、太宰治、横光利一、藤野厳九郎、内山完造、頭山満、宮崎滔天、梅屋庄吉、犬養毅、寺尾亨、松井石根、渋沢栄一、三上豊夷、増田渉、鎌田誠一、羽太信子ら。中国側は章炳麟(しょうへいりん)、許寿裳(きょじゅしょう)、秋瑾(しゅうきん)、黄興、張群、宋教仁、宋子文、袁世凱、汪兆銘、周恩来、瞿秋白(くしゅうはく)、周作人ら著名人や要人が入れ替わり登場し、国境を越えた友情や複雑で濃密な人間模様が浮かび上がる。重厚なノンフィクション作品だが、生々しい会話や秘話も多く小説的でさえある。
本書は、清朝を打倒した1911年の辛亥革命の前後と1920~30年代の東京、北京、上海、広東などを主な舞台にしている。東京は、孫文が1905年に反清朝の「中国同盟会」を結成するなど革命の海外拠点でもあった。
この時期は世界経済の枠組みが大きく変化した。世界最強の国、米国の経済は空前の活況を呈し、1920年初頭、魔都・上海は金融バブルに沸いていた。しかし、1929年の世界大恐慌のあおりで日本も経済不況に見舞われ、市場と資源を求めた中国大陸への進出を加速した。
本書は、日中間で数々の事件が起きて摩擦が増大し、1937年の日中戦争へと突入するまでの「嵐の前の静けさ」の実態も暴いている。その時代背景として、日中間の借款や企業進出、中国の通貨統一、上海交易所開設など経済問題について詳述、近代化に向けた教育改革に関しても健筆を振るっている。
躍動する主人公たちの最先端の連絡手段は電報や電話だった。日本に留学した陳独秀らが中心となって1921年7月、上海で中国共産党を結党してからは、国民党と「抗日で合作」したり、「国内で対立」したり、軍閥争いも起きた。中国では陰謀が渦巻き、裏切りも日常茶飯事で、暗殺やテロが横行する重苦しい空気が漂う時代でもあった。
魯迅の膨大な著作、「ペン」の闘いの証
魯迅は1902年(明治35年)4月、20歳のときに官費留学生として初来日した。嘉納治五郎が開校した清国人のための日本語学校「弘文学院」に第一期生として入学した。嘉納とは、NHKで放送中の大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺(ばなし)~』に登場する東京高等師範学校の校長、講道館柔道の創始者である。
1904年、魯迅は小説『藤野先生』の舞台になった仙台医学専門学校に入学する。ここで医学の道から、志を文学に転じて退学した。その理由として自著で、授業の合間に見た幻燈のある場面を挙げている。だが、著者は残存する幻燈用ガラス板の画像にそのような場面は見当たらないと指摘、「作り話」かもしれないとの仮説を提示する。
いずれにせよ、魯迅は武装闘争ではなく「国民の精神改造を目指して、文芸の力で世間に訴えかける」文学の道を選んだ。仙台から東京に移ると、尊敬する夏目漱石が住んでいた本郷の貸家で暮らしたこともある。しかし、帰国した魯迅は生活のためもあって、故郷の紹興から北京、アモイ、広東、そして上海へと移り住んだ。
1930年に結成された「左翼作家連盟」の常務理事に選出された魯迅は否応なく政治闘争の渦に巻き込まれた。共産党は宣伝工作の拠点として同連盟を利用した。これに対し蔣介石・国民政府は左派の若手作家たちを次々に逮捕、拷問、殺害していった。「暗黒の時代」に魯迅はペンで闘い続け、国民政府を激しく批判したのである。
毛沢東は共産党に箔をつけるため、魯迅を「聖人」に祭り上げて味方の陣営に引き込んだ。しかし、魯迅自身はあくまで作家として「革命の同伴者」を自任していた。興味深いのは1936年10月19日に死去した魯迅の葬儀に、蔣介石国民政府と中国共産党双方から弔電が届いたことだ、と著者は指摘する。
文豪ともいわれた魯迅は『狂人日記』『阿Q正伝』『故郷』などの小説のほか、時事評論や論文に当たる「雑文」を精力的に執筆した。本書にはノーベル文学賞推薦の打診を本人が「私はそれを望んでいません」と辞退したエピソードも出てくる。
『魯迅全集』全16巻のうち、小説は2巻にすぎず、雑文は6巻もある。あとは小説史、文字研究、書簡類、日記などだ。膨大な著作を重ねたことについて著者は「生活のためでもあったが、記録を残すことが最大の目的だったのではないか」と主張、こう続ける。「『剣』の脅威に怯えつつ、『ペン』で対抗しつづけた証」であり、「作品を書くのは話題づくりのためではなく、百年後に残るものを書くためだ」と。
蔣介石、済南事件を機に日本と決別
蔣介石は1906年4月、初めて日本の土を踏んだ。18歳だった。しかし、陸軍士官学校への入学資格がないことがわかり、日本語学校「清華学校」に入学したが、いったん帰国。その後、清国政府からの正式派遣の留学生として再び来日、日本陸軍が運営する清国人専用の東京振武学校に入学した。
日本滞在中、義兄弟となる革命家の陳其美と出会う。孫文と蒋介石がいつ初めて対面したかについては諸説あるが、本書によると、1910年6月、振武学校の3年生になっていた蔣介石は陳其美の紹介でハワイから日本に到着した孫文に会い、「自分も同盟会の一員として、是非とも軍事面から革命に加わりたいです」と伝えたという。
「革命成功! すぐ帰れ!」——。1911年10月16日、上海にいる陳其美から蔣介石宛の至急電報が届いた。辛亥革命を知らせる電報で、10月10日に武昌での初戦に勝利した革命軍が、次の武装蜂起の準備をしていることを伝えていた。振武学校を卒業した蒋介石は当時、新潟の高田市(現・上越市)に駐屯する陸軍第十三師団に配属されていた。
師団長の長岡外史中将は蔣介石ら軍事留学生を将校クラブに招き、「故国の風雲急を告げて、諸君は酒ものどへは通るまい。日本では生きて帰らぬ武士の別れは水杯だ。さあ、水杯を……」と杯を回した。蒋介石はぐっと飲み干すと、「閣下、大いにやります」と返答し、正式な除隊手続きを踏まないまま帰国して革命に身を投じた。
それから16年後の1927年11月2日、長岡外史は都内の自宅で蔣介石を迎え、日本語で会話して旧交を温めた。当時、蔣介石は下野していたものの、国民革命軍を率いる軍人政治家として頭角を現していた。持参した白い絹地に「不負師教」(恩師の教えにたがわず)と揮毫して長岡に手渡し、直立不動で日本陸軍式の敬礼をしたという。
蔣介石にとって最後の日本訪問となったこの旅で、長岡との再会は心温まる一幕だった。しかし、11月5日に田中義一首相と会談した蒋介石は嫌悪感と憎悪を抱いたという。日本は満州の権益を確保するため、蔣介石の革命の成功を許さず、革命軍の北伐を妨害し、中国の統一を阻止しようとしていると、受け止めたからだ。
著者は「この田中・蔣会談こそ、両国の間に深い亀裂を生じさせ、その後敵対させる決定的な要因になった」と分析する。
さらに1928年5月の「済南事件」が追い打ちをかける。蒋介石の国民革命軍が北伐を再開して山東省の省都・済南に入ったのに対し、田中義一内閣が第二次山東出兵を断行したことで起きた武力衝突事件である。死傷者は数千人といわれている。
田中義一首相が強硬な態度で停戦条件を出してきた同年5月20日、蔣介石は日記に、日本を蔑称の「倭」と呼んで呪いの言葉を書き連ねた。そのころから日記には毎日「雪辱」の二文字が綴られ、なんと1972年7月21日まで続いた。日本への憎しみは晩年まで消えることがなかったのである。
「済南事件をきっかけにして、中国は日本と決別し、欧米に急接近していく」。著者は蒋介石の心境をこう読み解く。一方で、田中・蔣会談と済南事件をめぐっては「ふたつの出来事こそ、日中両国の長い親善関係を断ち切り、やがて戦争へと導く決定的な要因となり、日中近代史上の大きな転換点となった」と結論づける。
この百年余を振り返れば、日中両国の関係は悪化と改善を繰り返してきた。20世紀初頭の日本留学ブームのころは蜜月時代だったかもしれない。日中戦争、第二次世界大戦は最悪の期間だ。1949年の新中国成立を経て、1972年の日中国交正常化から1978年の日中平和友好条約締結のころまでは再び「友好」の時代が訪れた。
中国が2010年に日本を抜いて世界第2の経済大国として台頭し、米国に次ぐ世界第2の軍事大国にもなった今、中国の海洋進出が世界中の脅威になっている。日中の間には尖閣諸島領有権問題や歴史問題などの難題が横たわり、日本には倦中ムードが広がる。著者は「これらの問題は、見方によっては過去の繰り返しだと言ってもよいだろう」と看破する。歴史は繰り返すのだろうか。
革命の主人公らを支えた女性たち
儒教文化など封建的な社会から、近代国家への脱皮を目指した広い意味での革命。その主人公、魯迅と蔣介石の共通点は親の決めた結婚という古いしきたりに縛られたことだ。ふたりとも新しいパートナーを求めたが、そこには純愛もあれば打算も交錯していた。
魯迅は1906年の夏、一時帰国して紹興で3歳上の朱安と結婚式を挙げた。親同士が決めた結婚だった。本書によると、朱安は纏足(てんそく)をして、文字が読めず、従順で古風な女性だった。魯迅は内心では中国の古い風習に憤り、周囲に暗黙の抵抗を示すために、実家には4日間滞在しただけで、日本に戻った。
北京女子師範大学の非常勤講師を務めた魯迅は教え子である進歩的で聡明な許広平と文通を重ねるうち愛をはぐくみ、1926年8月、駆け落ちさながらの恋の逃避行に踏み切った。当時、魯迅45歳、許広平28歳。その後、上海で同居していたとき、長男、海嬰(かいえい)も生まれた。献身的に秘書の役割も果たした許広平は魯迅を看取った後、著作を整理して『魯迅全集』を刊行した。
蔣介石の父親は早世した。母親が1901年、14歳になった息子に嫁をとらせた。相手は5歳上の毛福梅。蒋介石は黙って母親の意思に従った。同居はしなかったが、1910年に長男、蒋経国(後の中華民国総統)が生まれた。因みに蒋介石の次男の蒋緯国は養子で、実父は日本留学組の戴季陶、母親は日本人といわれている。
辛亥革命後、蔣介石は上海で美貌の歌姫、姚冶誠(ようやせい)と同棲していた。ところが、1919年のある日、蔣介石は孫文とともに訪れた上海の資産家の邸宅で当時13歳の陳潔如(ちんけつじょ)を見初めた。連日の電話攻勢で求婚、1921年12月、上海で“幼な妻”と結婚式を挙げた。
1927年12月、40歳になった蔣介石は26歳の宋美齢と上海で挙式した。宋美齢は、クリスチャンで浙江財閥の実業家でもあった宋嘉樹(チャーリー宋)の「宋家三姉妹」の三女。孫文にも親が決めた妻がいたが、再婚した宋慶齢は次女である。富豪の娘を娶ったのは「政略結婚」ともいわれた。
蔣介石は「国家」の立場から、魯迅は「国民」の立場から、「それぞれ別個にアプローチした末に、はからずも、『民主国家の国造り』という究極の一点で、結びついた」。ふたりとも中国の封建的な慣習を振り払おうと、もがきながらも親に「孝」を尽くして望まない結婚をした。その矛盾を内包したまま、革命に奔走した。そしてパートナーとなった女性たちはいろいろな思いを胸に秘めながらも、陰に陽に革命の主人公を支えた。
「戦争前夜」に生きた人々の複雑で微妙な心の動きを浮き彫りにし、国家と国民の関係についても考えてみたい――。著者は集大成ともいえる本書執筆の意図をこう明かす。日中の相克の歴史が自身の血に流れている著者だからこそ、臨場感あふれる人間ドラマを描けたのだろう。
戦争前夜 魯迅、蔣介石の愛した日本
譚 璐美(著)
発行:新潮社
四六版変型 415ページ
初版発行日:2019年3月15日
ISBN:978-4-10-529708-4