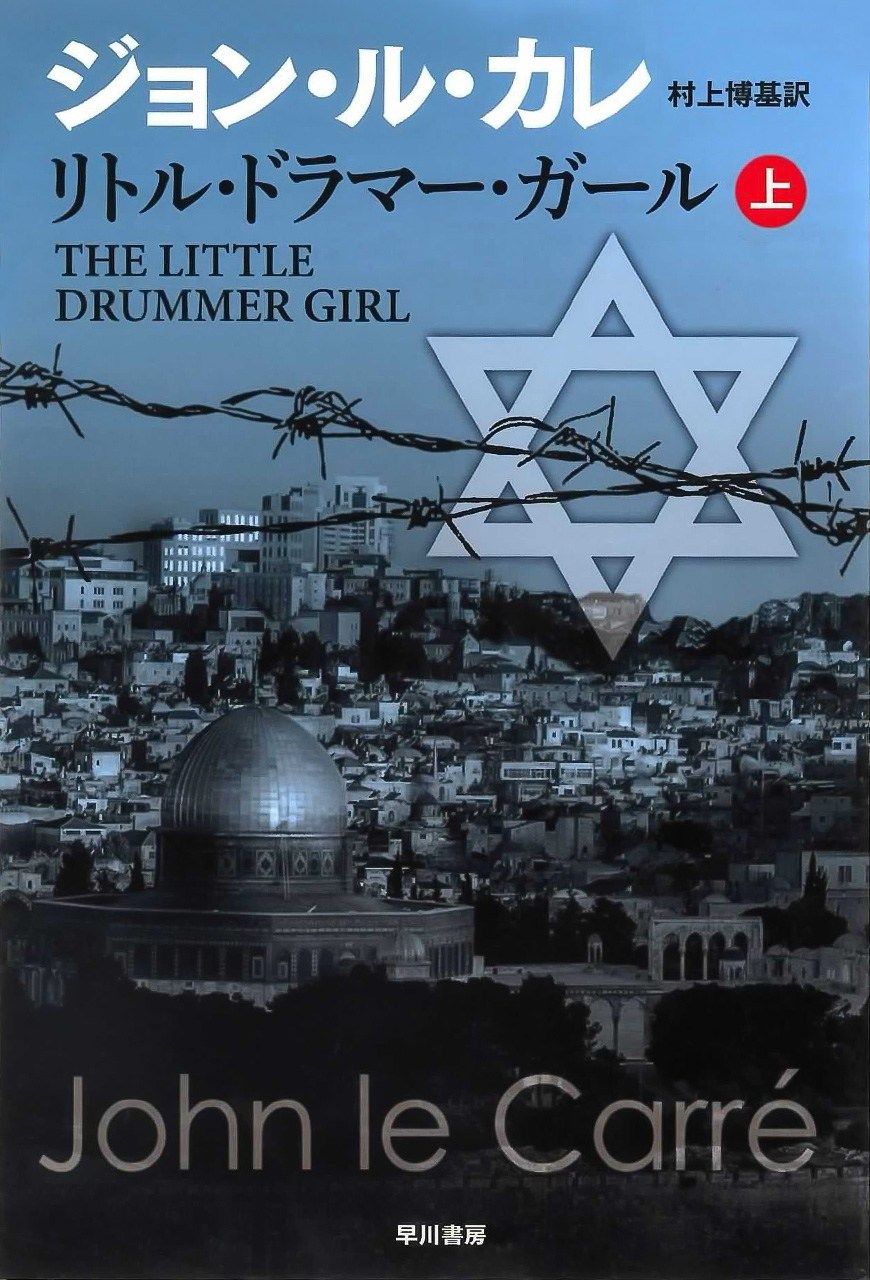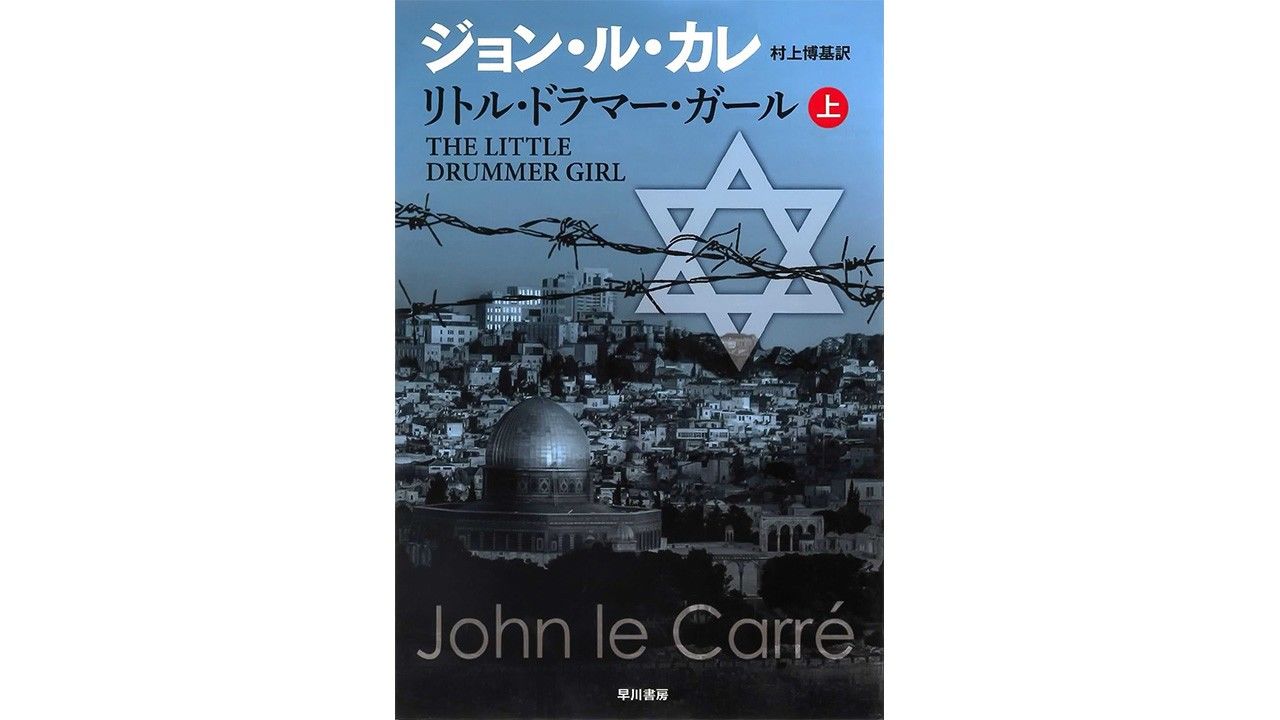
【書評】「正義」はどちらの側にあるか:ジョン・ル・カレ著『リトル・ドラマー・ガール』(前編)
Books 国際 政治・外交 歴史 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
その爆破事件は、旧西ドイツの暫定首都ボンの郊外、バート・ゴーデスベルクで起こった。この街には、各国の外交官や官僚たちが多く住み、時限爆弾が仕掛けられたのはイスラエル大使館に勤務する大使館員の自宅であった。
爆発したのは月曜日の朝8時半頃。家の主はすでに出勤したあとだったが、妻が片足を失う重症を負い、小さな息子が死んだ。
爆弾は、どうやってこの大使館員宅にもちこまれたのか。
事件の前日夕、この家にはスウェーデンの女子学生がホームステイしているが、彼女の友人と称する20代前半の金髪美女が訪ねてきた。
その美女は、「ボン大学に入学する」のだそうで、そのついでの折にと「彼女の母親から頼まれて」、彼女の衣類と好みのレコードの入ったスーツケースを届けに来たという。
たまたま、彼女はボーイフレンドと旅行中で不在だっため、家主は不覚にも荷物を預かり、彼女の部屋へ置いておいたのだ。
これが翌朝、爆発した。
くるくる巻き付けた配線コード
事件の捜査にあたっては、西ドイツの警察当局とともにイスラエルから調査団が派遣されてきた。彼らは情報機関に所属している。
現場検証の結果、時限装置はそれほど複雑なものではなかった。使用された爆薬はソ連製の標準的なプラスチック爆弾、それが5キロと推定された。
一見して、犯人につながる証拠は見つからない。しかし、現場から集められた残留物のなかに、西ドイツの関係者は気がつかなかったが、イスラエルチームの目を引くものがあった。
くるくる巻きつけた配線コードの残骸。これまであった爆破事件のなかに、同じ形状のものが現場で発見された例がいくつもあった。起爆装置を作る際に、余ったコードを巻いて時限爆弾のなかに残しておく。これがこの犯人特有の癖である。イスラエル情報機関は、これを爆弾犯の「サイン(署名)」と呼び、専従班を組んでこの男を追いかけていた。
やがて、おぼろげながら、正体が見え隠れしてくる。
1967年の第三次中東戦争のあと、パレスチナ西岸地区にあるブドウ栽培の村から脱出した難民だった。犯行グループの中核は4人の兄弟で、長男がリーダーであり、爆弾を製造する。まんなかの二人はすでに戦死し、末弟はまだ若かった。
現在の所在地は不明。数か月前から、ヨーロッパに潜伏しているという情報があり、その最中に起こったのが今回の事件だったのである。
現代まで続く紛争の系譜
これが『リトル・ドラマー・ガール』の冒頭の要約である。
爆破事件の在り様は、今日の爆弾テロとそれほど変わりはない。しかし、この作品は、過去のものである。
1972年9月、ミュンヘン五輪の開催期間中に、パレスチナの武装組織が選手村に乱入、イスラエルの選手を人質にとり11名を殺害した。
物語は、それから10年後という設定である。
本作は1983年7月に発表された。その前年の1982年6月、イスラエル軍はレバノンに軍事侵攻し、パレスチナ難民キャンプで大量の死傷者が出た。この武力行動の残虐性が、この作品には色濃く反映されている。
翻って、1948年のイスラエルの建国以来、1973年までの間に、イスラエルと周辺アラブ諸国とのあいだには、つごう4次にわたる戦争があった。
国家間の戦いだけでなく、イスラエルとパレスチナゲリラとのあいだでは、血で血を洗うテロ、報復による殺戮の応酬が繰り返されていた。
この紛争の系譜は、現代まで続いている。
今日に目を向ければ、昨年5月、トランプ米大統領が「イスラエルの首都はエルサレム」と明言し、米国大使館をテルアビブから同市に移転したことで、情勢は一気にキナ臭くなっている。
わたしは、単行本の邦訳が早川書房から出た当時、すぐに手にして読んだ。中東情勢は複雑すぎて、新聞報道だけではわからない。かつて日本の過激派が、すすんで中東の武装勢力に共鳴し、紛争地に向かったことも理解できなかった。
なにがわたしを混乱させたか。それは、どちらの側に「正義」があるのか、という難問だった。わたしには答えがみつからなかった。
本作で、ル・カレはある解答を示している。
今回、あらためて文庫版を読んでみたが、わたしはその思いを強くした。この物語は、今こそ読まれるべきものであると思うのだ。
引退から呼び戻した英雄
物語は続く。
今回の爆破事件の捜査を担当するイスラエルのチームリーダーは、「クルツ」と名乗った。第一印象はこうだ。彼は、
<歴戦の勇士に見えた。齢は四十から九十のあいだ、ずんぐりしたスラブ風の頑健なからだつきで、分厚い胸板、レスラーのような歩幅、だれにも安心感をいだかせる雰囲気は、ヘブライ人よりはよほどヨーロッパ人といえた>
クルツは、イスラエルの情報機関に所属するが、アウトサイダーでありエリートの経歴とは無縁だった。彼はサーブラ(海外からの移住者ではなくイスラエル生まれの人)ではなく、キブツ(イスラエルの共同体)の出身でも軍人として一流連隊に所属したこともない。彼は自分の腕一本でのし上がってきた。その赫々たる戦歴が、ときに彼の表情を年齢以上にみせている。
クルツは、西ドイツの捜査官にこう言った。
「テロ組織はむだな人間をかかえないんだ。彼らに対しては、特別の浸透作戦が必要だ」
クルツは、祖国の情報機関の上司にこう訴えていた。
「きょう日、ターゲットたるテロリストをたたこうと思ったら、まずこちらがテロリストを用意せねばならぬといっていいでしょう」
そこで彼は、前代未聞の極秘作戦を立案した。
クルツは6人の部下を選びチームを作った。さらに、今は引退の身である元軍将校のギャディ・ベッカーを呼び戻した。彼は中東戦争を戦い抜いた英雄で、対テロリストの専門家でもある。彼ほどパレスチナに精通する人物はいない。
彼はクルツとともにイスラエル側の重要な登場人物となるが、影のある魅力的なタフガイとして描かれる。
内から透けて輝く性的魅力
そして最後に、この作戦に必要不可欠な人材として、クルツは、イギリス人のある女優に目をつけた。彼女の呼び名は「チャーリィ」。
初出で、こう紹介されている。
<しばしば“赤のチャーリィ“といわれるのは、髪の色とちょっと異常なラディカル志向のためで、それがこの世への彼女の心の寄せかたであり、世の不正に対する姿勢であった><彼女は女優陣のなかでけっして美人ではなかったが、内から透けて輝く性的魅力があった。その度しがたい善意もまた、どんなポーズをもってしても隠しおおせなかった>
彼女は売れない女優で、アルバイトをしながら地方での舞台公演を主な活動の場としている。
思想的には急進的な左派ということになるが、これは演劇人特有のポーズであって、さまざまな政治集会に顔を出すことはあっても、そこで特定の勢力と結びつくほど根が深いものではない。覆面姿のパレスチナのテロリストがイギリスで行った講演を聴きに行ったこともあるが、ことさら反イスラエルというわけではなく、基本的に彼女は正義感の人で、あらゆる戦争を憎み、平和を愛している。
彼女が作戦の主役に選ばれたのには理由がある。ユダヤ人ではないので、上層部からは忠誠心に問題があるとして反対された。だが、彼女でなければならない決定打があった。それはここでは明かせないが、物語を丹念に読んでいくと、中盤のある場面で衝撃を受けることになるだろう。
彼女の名演なくしては、極秘作戦の成功はありえない。
作戦の概要をこれから説明する。
爆破事件にかかわっている若い男が判明した。彼は、イスラエルの大使館員宅に時限爆弾を運んだ金髪女性を操っている。
だが、グループのなかではまだ小者だ。その上に、幹部がいて、最後に指揮官がいる。名前は「ハリール」。
クルツとしては、このグループを一網打尽にしたい。
リクルートしたチャーリィに、クルツはいった。
「ハリールはだれにも頼らず、きまった女も持たない。おなじベッドに二晩つづけては寝ない。人々から隔絶している。生活の基本的必要物をぎりぎりに切り詰め、ほとんど自給自足に近い。賢明な活動家だ」
彼の逮捕が最終目標であるが、居所は依然不明で、その素顔を見た者すらいない。
そんなハリールをどうやって炙り出すのか。
テロリストの恋人という役柄
判明した若い男「ヤヌカ」は、ハリールの末弟だった。金髪美女はオランダ人の過激派で、彼のセックスフレンドでもある。
ヤヌカは、ボンでの爆破事件のあと、ミュンヘンに潜伏していた。ヨーロッパの都市を転々とするヤヌカの暮らしぶりは、享楽的でスキがあった。そこにイスラエル情報機関は目をつける。
作戦は静かに動き出した。
<拉致そのものについては、あまりいうこともない。手慣れたチームにかかれば、きょう日そんなことはまたたく間に、ほとんど儀礼的に、いや、それすらもなしにおこなわれる。ただ、獲物の持つ可能性の重大さが、行動にある種の緊張をあたえた。物騒な撃ち合いも、なんの不快事もなく、トルコ-ギリシア国境のギリシャ側三十キロの地点で、ワイン・レッドのベンツ一台と、その運転者の、あっけない奪取があっただけだった>
チームは、ヤヌカをミュンヘンの選手村跡地にある隠れ家に運んだ。ここで尋問が繰り返し行われ、彼の経歴、思想信条、爆破事件の詳細、長兄のハリールについて、彼とかわした会話など、貴重な情報が絞り出された。
チャーリィの役割は、ヤヌカの恋人に成りすますことだった。彼女は、恋人の思想に共鳴し、パレスチナのため共に戦うと誓っている。
そして敵方の懐深く潜入する。いずれ「ハリール」にたどり着くことだろう。
これが作戦の要諦である。
教育係として彼女を徹底的に鍛えたのが、先に紹介したパレスチナ通のギャディ・ベッカーである。
ヤヌカは、ヨーロッパで活動している際には「ミシェル」と名乗っていた。彼の恋人というチャーリィのカバーストーリー(擬装身分)を見破られないために、二人が知り合った場所、きっかけ、一緒に行動したルートなど架空の物語が作られる。それに沿って、ベッカーがミシェル役に扮してチャーリィと足跡を残していく。いずれ敵方が調査に乗り出したときに、リアリティをもたせるためだ。
あるいはまた、ミシェルが話す彼の思想を彼女に植え付ける。完璧に、なにを聞かれても破綻なく話し、心底、アラブに同情しているとふるまえるように。
敵地に潜入すれば、ほんとうに彼の恋人だったのか、苛酷な尋問にさらされることになるだろう。
カバーストーリーは、緻密に練り上げられたものだ。敵方を欺く痕跡も残した。あとは、彼女がうまく演じ切れるかどうか―――。(後編に続く)
リトル・ドラマー・ガール(上)
ジョン・ル・カレ(著)、村上博基(訳)
発行: 早川書房
初版発行日:1991年12月15日
ISBN:978-4-15-040641-7