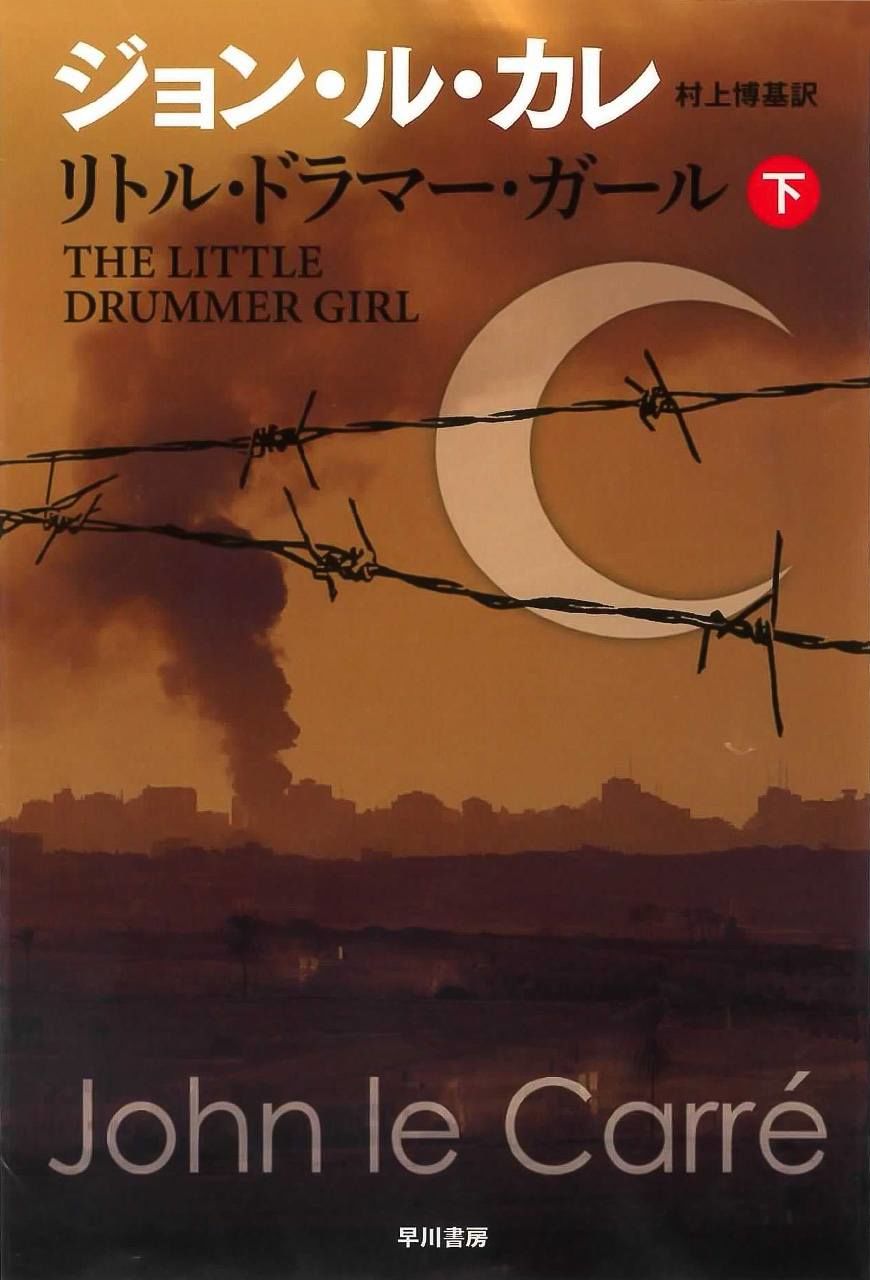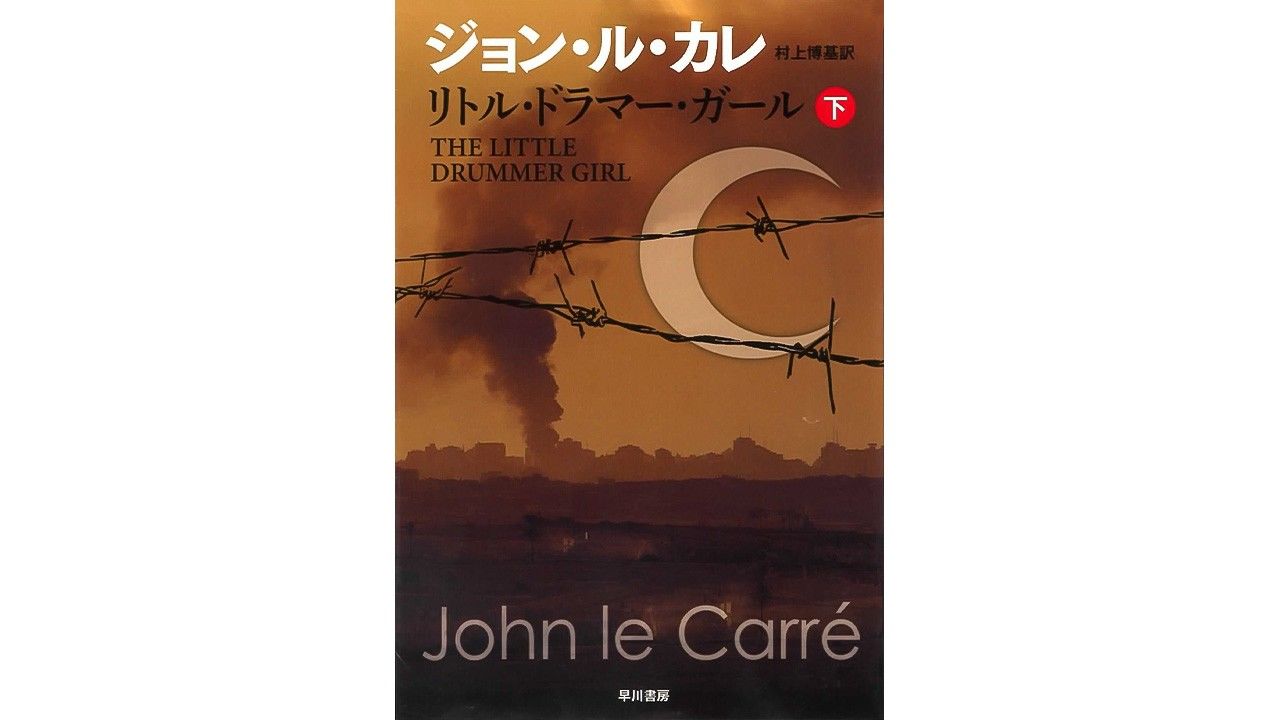
【書評】「正義」はどちらの側にあるか:ジョン・ル・カレ著『リトル・ドラマー・ガール』(後編)
Books 国際・海外 政治・外交 歴史 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
イギリスの女優チャーリィは、テロリストの首謀者の弟ミシェルの恋人になりすましていた。
ミュンヘンでイスラエル情報機関に拉致されていたミシェルは、尋問を受けたのち、アウトバーンで車ごと爆殺された。
西ドイツの警察当局の発表では、爆薬を満載しており、事故による自爆とされた。
チャーリィは、死んだミシェルの残された恋人となった。
彼の死因を不審に思ったパレスチナのグループは、チャーリィの存在を割り出し、彼女と接触する。クルツら専従チームがまいた餌に、敵方が食いついてきたのだ。
いよいよ、クルツの立案した計画が、本格的に動き出した――。
「自然な人間味に訴えたい」
物語の紹介は、このあたりまでがギリギリだろうか。
本作には、いく通りもの読み方があると思う。チャーリイはとても魅力的な女性に描かれている。彼女は無事に使命を全うすることができるのか、ハラハラドキドキしながら彼女が困難に立ち向かっていくストーリー展開を楽しむのもそのひとつだろう。
著者は、登場人物たちの会話のなかに、それぞれの立場を丁寧に書きこんでいる。わたしは、そこに感銘を受けた。
わたしが求めていた疑問に対する解答のヒントが、いくつも散りばめられている。ここから先、いくつか要約して紹介したいと思う。
チャーリィの立ち位置は、中立的である。物語が進行するにつれ、彼女もまた、どちらの側に「正義」があるのか、思い悩むようになる。彼女の心の内が揺れていく様は、読者の共感を呼ぶのではないか。
そもそも、チャーリィは自らすすんでイスラエルの手先になったわけではない。
彼女はリクルートされた際、チームリーダーのクルツに食ってかかる。
「わたしはただ、かわいそうなアラブをそっとしといてほしいと思うだけよ・・・彼らのキャンプを爆撃するのをやめなさい。彼らを土地から追い払ったり、村をブルドーザーでつぶしたり、迫害するのをやめなさい」
当時、パレスチナ人への迫害が連日ニュースになっていただけに、彼女の同情論は無理もない。
チャーリィの激しい反発に、クルツは静かにこう諭す。そこでのやりとり。
「中東の地図を見たことがあるかね」
「もちろんあるわよ」
「地図を見たとき、きみは一度でも、アラブがわれわれをそっとしておけばいいと思ったことがあるか」
クルツは情の厚い男に描かれている。部下への思いやり、祖国に残している妻とのエピソードがそれを物語っている。しかし、目的のためには手段を選ばない非情さをもちあわせている。彼は、敵対するパレスチナ人について、
「人が死なねばならぬには、よくよく罪深くあらねばならないとするのが、われわれの考えである」
と語っている。チャーリィは尋ねる。
「たとえばだれよ。あなたがたが西岸地区で撃ち殺すかわいそうな連中のこと?それとも、レバノンで爆撃する相手のこと?」
「人間の絆を完全に断ち切ってしまう連中のことだよ、チャーリィ」
これが誰を指すか。イスラエルの存在を認めず、テロを仕掛けてくる連中である。クルツはきっぱりと言う。
「彼らは死ぬに価する」
それでも納得のいかないチャーリィに、クルツはこう訴えかける。
「われわれはきみのなかの、自然な人間味に訴えたいだけだ。きみの善良で真摯な人間の心に訴えたい。きみの情感に。きみの正義感に・・・」
もともとは「ジョゼフ」という偽名で貿易商をかたり、直接チャーリィをリクルートしたのはギャディ・ベッカーだった。彼女は、彼に恋心を抱くようになっていた。擬装のための訓練中にも、信頼感が増してくる。二人のやりとり。
「彼はユダヤ人を殺してるわね」
「ユダヤ人を殺し、ユダヤ人でもなく闘争になんのかかわりもなかった、罪なき第三者を殺している」
「一方、あなたはアラブ人を殺してるわね」
「むろんだ」
「大勢?」
「必要数」
「でも、正当防衛なんでしょう。イスラエル人はけっして、正当防衛でしか人を殺さない」
彼女は逡巡しながらも、イスラエル情報機関のスパイになることを承諾する。
「一生ここにいてもいいと思った」
パレスチナの側の主張はどうか。批判の矛先は、イスラエル建国の原因をつくった大英帝国、そしてイスラエルへ向かう。
クルツのチームに拉致され、囚われの身となったミシェルは言う。
「イギリスは下の下だよ・・・イギリスは米帝国主義の手先だ。イギリスは悪のすべて、その最大の罪はおれの国をシオニストに売ったことだ」
クルツが立案した今度の作戦には、西ドイツとイギリス双方の情報機関が、お互いに利害あってのことだが、裏で協力している。
イギリスの対テロ専門家で、伝説的存在になっている情報機関の部長は、クルツに向かって冷ややかにいった。
「ま、それですむと思わぬことだ・・・やがて殺されたパレスチナ人の霊が、生涯きみらにとりつくんだ」
死んだミシェルの仲間に導かれ、チャーリイはパレスチナへ潜入する。そこから、難民キャンプをめぐり、パレスチナの惨状に触れていく。
彼女を見張っているのは少年兵ばかりであり、とても親切だった。
<こちらの愛情には愛情でこたえてくれたが、なにも個人的なこと、なにも出すぎたことは要求しなかった。いかにも内気な、しつけのきいた寡黙を守り、いったいどういう権威が彼らを支配しているのだろうかと、ふしぎな思いがした>
ある難民キャンプでは、母親たちと一緒に奉仕活動を行った。チャーリィはがぜん人気者になる。
<たちまち彼女の小屋は、朝から晩まで子どもであふれた。英語をしゃべりにくる子もあれば、彼女に歌と踊りを教えにくる子もいた。なかにはただいっしょにいるのが誇らしくて、彼女の手をとって通りを行ったりきたりする子もいた・・・一生ここにいてもいいと思った>
やがて彼女はパレスチナに受け入れられ、彼ら彼女らと共に戦う同志となる。
イギリスに帰ったチャーリィは、ヨーロッパのある国で、とうとう爆弾テロの首謀者ハリールと出会う。彼はこういった。
「シオニストがわれわれを爆撃するとき、いい人たちのことを考えるだろうか。考えまい。われわれの村をナパームで焼き、女たちを殺すとき、考えるだろうか。大いに疑わしい。イスラエルの人殺しパイロットが、上空の操縦席で、“あの気の毒な民間人、あの罪なき犠牲者たち“と思うとは、とうてい考えがたい」
そして、爆弾テロをこう正当化する。
「シオニストたちは、わたしとは比較にならないほど大勢殺している。だが、わたしが殺すのは、愛のためだ。パレスチナのため、パレスチナの子らのためだ・・・シオニストは恐怖と憎しみから殺す・・・パレスチナ人は愛と正義のために殺す。この違いを忘れないでくれ。大事な点だ」
チャーリィの正体を知って驚愕するハリール。
「きみは、わたしの国を売り渡したのと同じイギリス人なのだな」
彼は、<目で見ているものを信じかねるように、ものしずかにそういった>
「私がみずからに課した仕事・・・」
ル・カレは、本作からおよそ30年後、2016年に発表した自伝的回想録『地下道の鳩』のなかで、作品執筆の舞台裏を詳細に披露している。
著者は、ベイルートでPLO(パレスチナ解放機構)のアラファト議長に会い、イスラエルも訪ねている。そうした対立する両者の綿密な取材に裏打ちされて、この力作は世に送り出された。
ル・カレは回想録でこう記す。
<パレスチナ人を裏切るために送られた彼女は、そのパレスチナ人の苦境に対する同情と、ユダヤ人が祖国で暮らす権利を認めるべきという考えのあいだで引き裂かれる>
それが本作の主要なモチーフになっている。だからこそ、
<私がみずからに課した仕事は、彼女とともに旅をすることだった。双方からの主張を聞き、チャーリィが葛藤したように葛藤し、決して両立することのない忠誠心、希望、絶望の数々をできるだけ経験するのだ>
ラストシーンに、読者は救われた気持ちになることだろう。
リトル・ドラマー・ガール(下)
ジョン・ル・カレ(著)、村上博基(訳)
発行: 早川書房
初版発行日:1991年12月15日
ISBN:978-4-15-040642-4