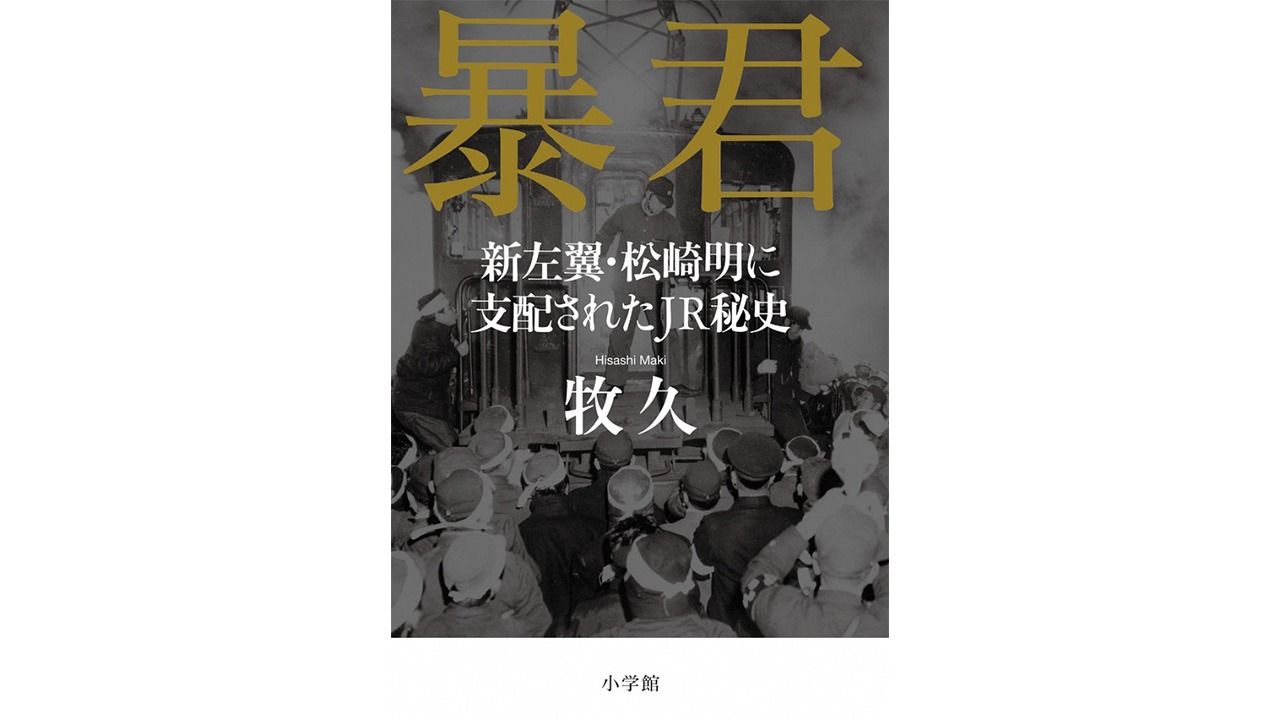
【書評】JRを生きた妖怪:牧久著『暴君』
Books 社会 仕事・労働 歴史 経済・ビジネス- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
77歳でこの世を去る間際まで、実質的にJR東日本の一部労組の実権を握り、一時は会社の経営をほぼ意のままに操った松崎明。
松崎自身が著した本も含めて関連書は数多くあるが、本書の特筆すべき点は、数多くの資料や証言を用いながら松崎の生き様と、国鉄及びJRの変化とを至極冷静に描いている点だ。
詳しくは本書に書かれているが、週刊文春や週刊現代といったマスメディアが、松崎とJR東日本という大きな獲物に挑んだものの、駅内の売店「キオスク」での販売拒否や50件もの訴訟など、激しい言論弾圧に遭ってきた。そしていつしか、松崎の存在はメディアでタブーとなってしまったのだ。
著者は日本経済新聞で国鉄担当記者を務め、国鉄記者クラブにも常駐していたジャーナリスト。既に国鉄分割・民営化についての著書もあるが、いずれ「平成時代のJRの真実」、つまり松崎明について書こうと決めていたと本書のあとがきで記している。80歳間近である自身の集大成でもあり、心に残っていた宿題でもあったのだろう。
旧知の記者をはじめ、JRの関係者にも改めて数多く取材しており、非常に読み応えのある一冊になっている。
驚愕するほどの事実を淡々とした筆致で描くことにより、かえって松崎という“妖怪”の異常さやJR東日本が彼と共に築いた関係の異様さ、そして当時のマスメディアや社会が口をつぐみ続けた背後に潜む恐怖が際立ち、読者へと迫ってくる。
「のりこえ」と「もぐりこみ」
1955年に臨時雇用員として国鉄に採用された松崎は、翌年正規の国鉄職員となり、機労(機関車労働組合)に加入。高校時代から民青で活動し、臨時雇用員時代に共産党に入党していた松崎は、その時点ですでに「労働組合への強い関心が生まれていた」。
機労はその後動労(動力車労組)と名を変えるが、弁舌が立ち、機労の頃から頭角を現していた松崎は、動労でも着実に権力を拡大し、1985年には委員長に就任する。
労働環境や社員のバックグラウンドが多様な当時の国鉄には動労の他にも複数の労働組合が存在しており、恒常的に労使間の交渉は難航。長時間のストも珍しくなかった。
1985年に中曽根内閣により分割民営化の方針が決まると、いずれの労組も猛反対する中、松崎率いる動労は突如JR東日本の執行部と手を握り、組合の生き残りに成功する。いわゆる、松崎の“コペルニクス的転換”である。
こうしたJRをめぐる時間軸に、「革マル」という別の軸が加わり、話は大きく展開していく。内ゲバによるリンチ殺人、尾行に盗聴、盗撮など、フィクションでもここまでは想像しないであろう出来事が次々に起こっていくのだ。
革マル創立メンバーのひとりでもあった松崎のコペルニクス的転換は、面従腹背以外の何物でもなかった。
分割民営化を成し遂げるために松崎と組んだJR東日本は、「労使協調」の名の下に、いつしか松崎の意に沿わない経営判断ができないところまで骨抜きにされてしまう。革マルでいう「のりこえ」と「もぐりこみ」の戦術を、松崎は徹底して実践したのだ。
著者によれば、「大衆運動に参加する人たちを組織的に”洗脳“して、組織の一員に育て、新たな革命闘争の戦闘委員として投入していく」ことが「のりこえ」であり、「味方の力が弱い時は、強力な相手の内部に潜り込んで、その内部を変質させ、相手の組織を『食い破っていく』のが「もぐりこみ」戦術である。
愕然とするのは、社会のインフラであり、人々が毎日のように利用しているJR東日本という大企業において、社会にほぼ察知されることなくこれほどの事態が起きていた事実だ。
人事異動に組合がいちいち異議を唱え、経営陣が陳謝する。組合の大会に幹部が登壇し、松崎を持ち上げる。
異論を唱える者は関連会社や閑職へと左遷され、メディアは口をつぐまされる。まさにJR東日本は、松崎明という一人の人間に「食い破られて」いたのだ。
「松崎という男には情がある」
読んでいると、「なぜ誰も止められなかったのか」という疑問が当然ながら浮かんでくる。
その答えは直接書かれてはいないが、本書に出てくる数多くのエピソードから感じるのは、松崎には、抗い難い魅力があったのではないか、ということだ。
「松崎という人間には情があり、決断力のある男でした。私は松崎がたとえ革マル派であっても、信頼して同じ船に乗り込める男だと判断しました」
分割民営化当時のJR東日本常務であり、その後社長に昇進して松崎と「蜜月関係」を築いた松田昌士の言葉だ。
本書で描かれる松崎の鬼のような言動を知ってからこの言葉を読むと、東大出身者がずらりと並ぶJRのエリート層にどんな顔を見せればいのか、松崎はすべて計算していたのではと恐ろしくなる。相手の情感を揺さぶるような会話をしながら、腹の中ではペロリと舌を出していたのではないか。
松田同様に松崎の魅力に心酔し、彼の指示に盲目的に従って「戦闘委員」となった人間が、動労内にも数えきれないほどいたのである。
だが、永遠に続くかに見えたこの世の春にも終わりが来る。
JR東日本やJR東労組(JR東日本内の動労系労働組合。長年松崎がトップを務める)に起こる幾多の変化が終焉へと導いていくのだが、その最大の要素は社会の変化ではなかっただろうか。
平成に入り、社会の認識も、JR東日本の社員の感性も、そして組合の存在意義も大きく変わった。
時代を察し、権力を操ってきたはずの松崎が、歳を重ね、欲に溺れ、いつしか社会の変化についていけなくなったのではないか、と感じてしまうのである。
いつしか松崎の下からは、かつての盟友が一人二人と去り、反旗を翻す動きが広がっていく。激しく咳き込みながら病床で俳句を詠むその最期は、一抹の寂しさを感じさせる。
欠席できない“レク”
本書を読みながらふと思い出したことがあった。
2000年代前半、JR東海に就職した大学時代の友人を大阪に訪ねた時のことだ。週末なので京都にでも遊びに行こうかと話していたが、突然、その日は出かけられなくなったと連絡が来た。理由を問うと、“レク”と呼ばれる組合のイベント(確かバーベキューだった)があり、休むわけにはいかないのだという。
当時私が働いていた会社に組合はいわゆる「御用組合」ひとつしかなく、数カ月に一度組合費を徴収される時を除けば、日常生活で組合の存在を意識することがないどころか、自分が組合員であることすら忘れていた。
なぜ友人の会社は、組合のイベントが週末にあるのか。
そして欠席できる雰囲気ではないとは、いったいどういうことなのか。
そもそも組合とは、それほど大事なものなのか。
その時は「まあいいか」で終わっていたこれらの疑問が、15年以上の時を経て甦り、頭の中で本書とつながっていった。
友人が加入していた組合は、動労系ではない。
当時のJR東海の社長は、1991年、松崎に「葛西、君と闘う。堂々と闘う。そして必ず勝つ」と名指しで宣戦布告された葛西敬之。葛西は、松崎の「コペルニクス的転換」の裏には、動労の勢力を拡大し、JR東日本を操りたいという“本心”があることを早々に見抜き、JR東海が脱・動労へと舵を切った結果、動労系の組合は切り崩され、勢力を削がれていた。その過程で動労系以外の組合でも、結束を強めようという動きがあったのだろう。
友人が経験した“レク”とは、その名残ではないか。そんな気がした。
働き方改革と組合と
平成が終わり、日本の企業や働き方は、かつてないほど大きく変容している。かつてのような大企業信仰は弱まり、ベンチャー企業に就職する学生も増えた。起業する若者も多く、副業も進んでいる。人材の流動性は高まり、大企業であっても、定年まで勤める人数は減りつつある。「働き方改革」とも相まって、この変容は今後もますます加速するはずだ。
松崎明が強大な力を手中に収められた背景には、国鉄、そして分割民営化された後のJRもまた、社会の中で大きな力を持っていたという事実がある。
妖怪・松崎明の飽くなき欲望を満たすだけのパワーを会社が持っていたからこそ、共喰い関係が成立していたのだ。
だが、時代は変わった。
JR各社が今後、松崎の“亡霊”といかに対峙し、組合とどのような関係を築いていくのか。
そしてまた、日本社会の中で、組合はいかなる存在として機能していくのか。
本書を読んでから、この2つの問いについて考え続けている。(敬称略)
暴君
牧久(著)
発行:小学館
480ページ
初版発行日:2019年4月23日
ISBN:978-4-09-388665-9
