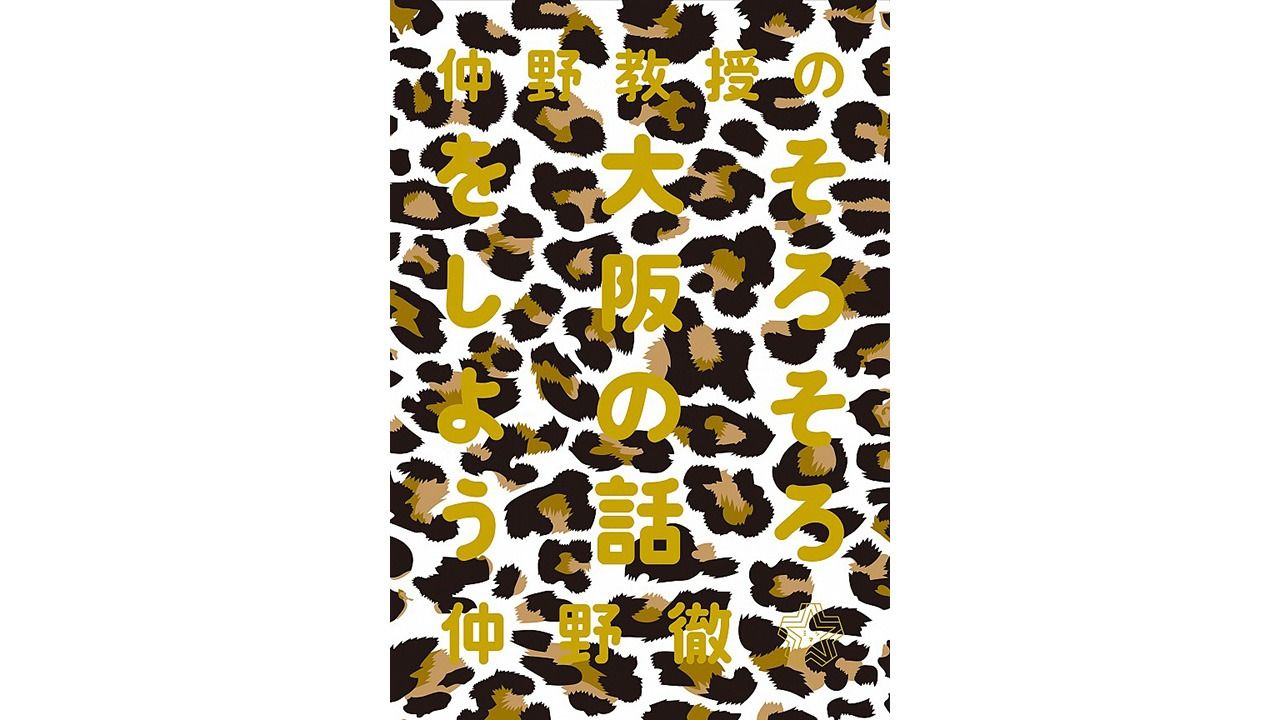
【書評】「ホンマの姿」を求めて:『仲野教授のそろそろ大阪の話をしよう』
Books 文化 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
近頃の大阪関連のニュースと言えば、4月の大阪府知事・市長のダブル選挙、夏の参院選で連勝した大阪維新の会と“闇営業” 問題も含め吉本興業に関するネタが多い。維新の会と吉本はタッグを組み、2025年大阪万博、またカジノ招致に向けて奮戦中だ。「大阪都構想」を巡る議論も再び息を吹き返した。大阪の新たな繁栄を目指すのは結構だが、華々しい拡大路線ばかりで大丈夫ですかと思ったりもする。大阪庶民の本音はどうなのかと少し気になる。
もちろん、大阪だろうと東京だろうと、感じ方、考え方は人それぞれ、人生いろいろである。ひと言ではくくれない。維新や吉本とは離れて、ステレオタイプではない「大阪の人ですら普段気付かないような大阪」の面白さを追求するのが『仲野教授のそろそろ大阪の話をしよう』(ちいさいミシマ社)だ。大阪大学大学院の仲野徹教授と大阪を深く知る12人の対談集で、これはとてもおもろい。
B級グルメとソース文化
仲野教授は「いろんな細胞はどうやってできてくるのだろうか」を研究する病理学者ながら、自称「お笑い系研究者」だ。とは言っても、『エピジェネティクス』(岩波新書)、『こわいのもの知らずの病理学』(晶文社)などの著書は、病理学を身近に感じてほしいという気持ちが伝わる真面目な本。今回もお笑い系ではないが、大阪弁の飛び交う気軽な(でも内容の濃い)おしゃべりを、こちらも肩の力を抜いて聞いている気分だ。
12人の対談相手は学者から元芸妓(げいぎ)、芥川賞受賞作家など多彩で、大阪弁、食、私鉄、上方落語、浪花音楽とさまざまな切り口で大阪を熱く語る。ふぐ料理のコースを食べ、ひれ酒をすすりながら(全国のふぐの50〜60%は大阪で消費されているとか)、あるいはお好み焼きを食べながらのうらやましい対談もある。
食に関しては、編集者・文筆家の江広毅さんが「うますぎる」大阪B級グルメを語り、イベントプロデューサーで『大阪ソースダイバー ―下町文化としてのソースを巡る、味と思考の旅』という著書がある堀埜浩二(ほりの・こうじ)さんが奥の深いソース文化を解説する。お好み焼きは東京でもよく目にするが、大阪では「中学校の校区ごとにお好み焼き屋があって、校区が違うお好み焼き屋にはその地域に住んでいる友達と一緒やないと入られへん」とか…。そして、串カツ同様、メーカーが店側の要望に応じて独自のソースを作るそうだ。そんな背景もあってか、関西にはさまざまな「地ソース」メーカーが存在する。ちなみに大阪ではポテトサラダにウスターソース(とんかつソースではないことがポイント)をかけるのが普通らしく、天ぷらにもかけるらしい。機会があれば、さまざまな地ソースで試してみたい。
「立派な大阪のおばちゃん」
対談相手によって見えてくる「大阪らしさ」はさまざまだが、一番関心するのは、独特なコミュニケーション力だ。例えば、バブルの頃パリの有名ブランドの店員さんが唯一覚えた日本語が「まけてぇな」だったという逸話を、日本近世史が専門の高島幸次さんが紹介する。「値切るのはケチやからやなくて、コミュニケーションを取るため」で、お店の人とやり取りをするのが面白いから値切る。大阪で値切る文化が少なくなったのは、値段が固定されて、お客との対応がマニュアル化されている百貨店やコンビニ、ファストフードの店が「悪い」と断言、「値切る文化を残してほしい」と言う。また、東京では宅配便の配達人と言葉を全く交わさない人もいるが、大阪では世間話が普通とか。大阪・大正区出身の芥川賞受賞作家の柴崎友香さんも、大阪でのコミュニケーションは「意思を伝えることじゃなく、会話を続けることが目的」だと言う。柴崎さんの大阪の友人が東京に来て電話でピザの宅配を頼んだところ、配達のギリギリ範囲外の地域だった。「家の前に出てエリア内に立っとくから」と粘ったが、「決まりですから」とにべもない。「ピザは熱々やけど、心は冷たいんですね」と言ったのに、聞き流された。友人は、そのことがピザを配達してくれないことより悲しかったらしい。
ちなみに柴崎さんは、最近「ああ、立派な大阪のおばちゃんになりたいな」と思うようになった。「立派な大阪のおばちゃん」に関しては、「全日本おばちゃん党」代表代行で法学者の谷口真由美さんが、その「極意」を紹介する―感謝されたいからではなく自分がそうしたいから、でも結果的に相手のためになるお節介をすること。ただ最近ではよいお節介と悪いお節介の区別がつかなかったり、はっきりと、しかしやんわりとものを言えるおばちゃんが少なくなったそうだ。それが「大阪の活力がなくなった原因なんやないか」と仲野教授は考える。
経済成長ではだけではなかった「大大阪」
現在の「大阪都構想」の背景には、かつての「大(だい)大阪」の記憶がある。大正末期から昭和の初めにかけて、関東大震災で打撃を受けた東京より人口が多く、経済も活況を極めていた時代があった。大阪大学の橋爪節也教授(著書『大大阪イメージ』)によると、当時の市長、關一(せき・はじめ)による都市計画が大きな成果を挙げていた。ただし、忘れてならないのは、關市長が目指したのは経済格差がなく、文化施設の充実した「住み心地良き都市」。結局戦争で理想的な文化都市づくりは中途半端に終わってしまった。単に「大大阪を目指せば景気がようなって、暮らしがようなる」と考えるのは「歴史的に間違いだし、アブナイ」と橋爪教授は警鐘を鳴らす。前述の高島幸次さんは、大阪は古代の難波宮(なにわのみや)の時代から現代まで、変貌し続けてきた都市だと振り返る。「政財界の人たちが経済的に復活せなああかんとばかり言っている。大阪は何も経済ばかりで生き抜いてきたわけじゃない。今まで経験したことのない〇〇都市に生まれ変わってもいいのになあ」
生粋の大阪人も知らないこと
本書を紹介するにあたって仲野教授に、対談で語られた中でそれまで知らなかったことはありましたかと聞いてみた。「いっぱいありました。一番は大阪城のこと。通っていた高校(府立大手前高等学校)が大阪城の真ん前で、よく知ってると思ってたのに、びっくりでした」とのこと。大阪城天守閣館長の北川央(ひろし)さんとの対談で改めて、豊臣秀吉の大阪城を地中に埋めた後に徳川幕府が大名を動員して現在の大阪城を造った経緯などが解説されるが、大阪人の間でもいまだに秀吉の城という認識が強いそうだ。
そして、「今やほとんど知られてないのは、やっぱり花街でしょう。語り継ぐ人すら絶滅しそうです。(大阪・北新地で名妓(めいぎ)として活躍した)西川梅十三(うめとみ)さんには、聞き書きでいいから本を出したらどうです、っていうてるんですけどね」
対談相手のうち、自称「鉄道楽者」の黒田一樹(いつき)さん(大阪の私鉄が対談テーマ/対談後まもなく逝去)以外は皆大阪人。サービス精神旺盛で、「むっちゃようしゃべってくれはりました。なんかしゃべってたら満足、みたいなところがありますね。知らんかっても、さぞ知ってるかのように話すこともあるけど」。もちろん、12人の達人は話が尽きないほど知識が豊かである。念のため。
仲野教授のそろそろ大阪の話をしよう
仲野 徹(著)
発行:ミシマ社
B6判変形並製
発行日:2019年7月20日
ISBN:978-4-909394-24-8 C0095
