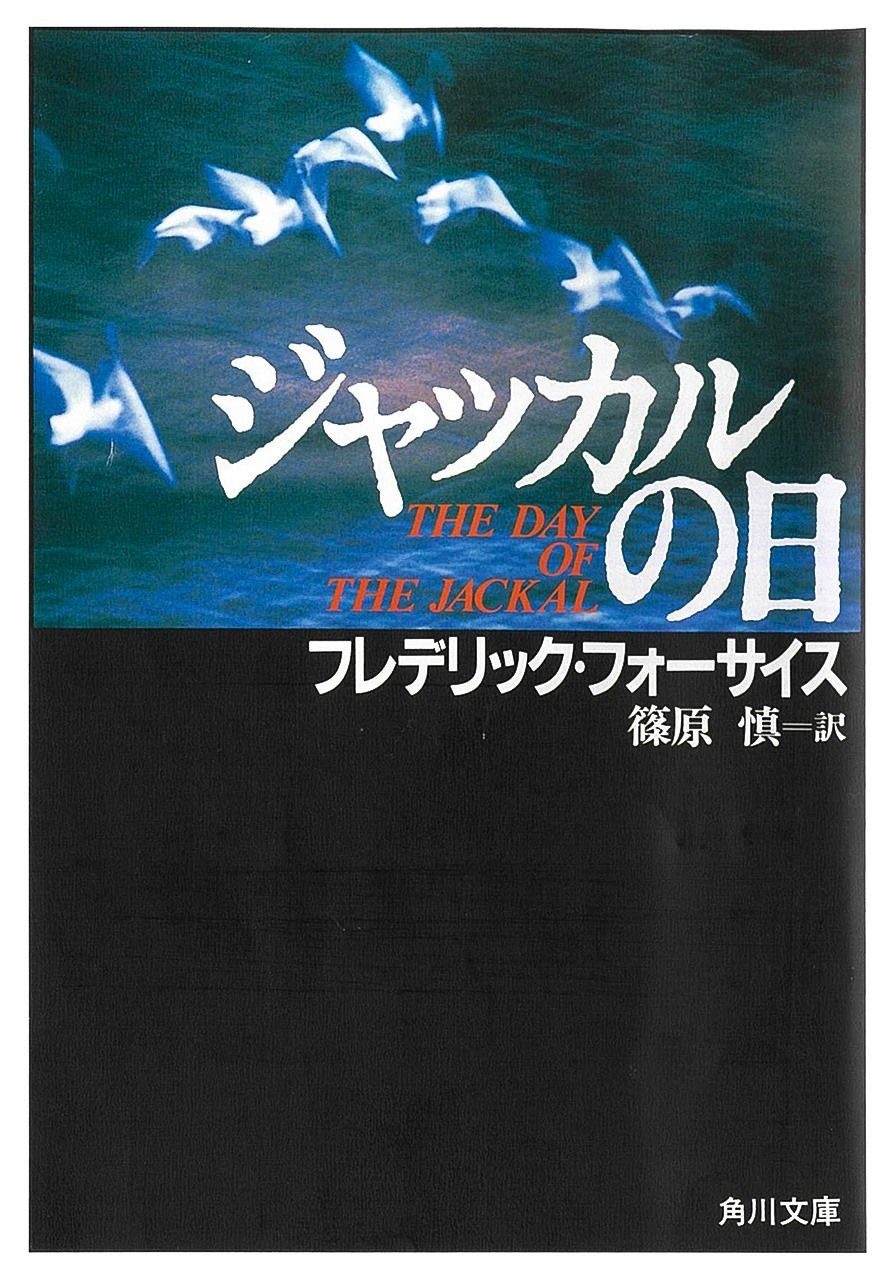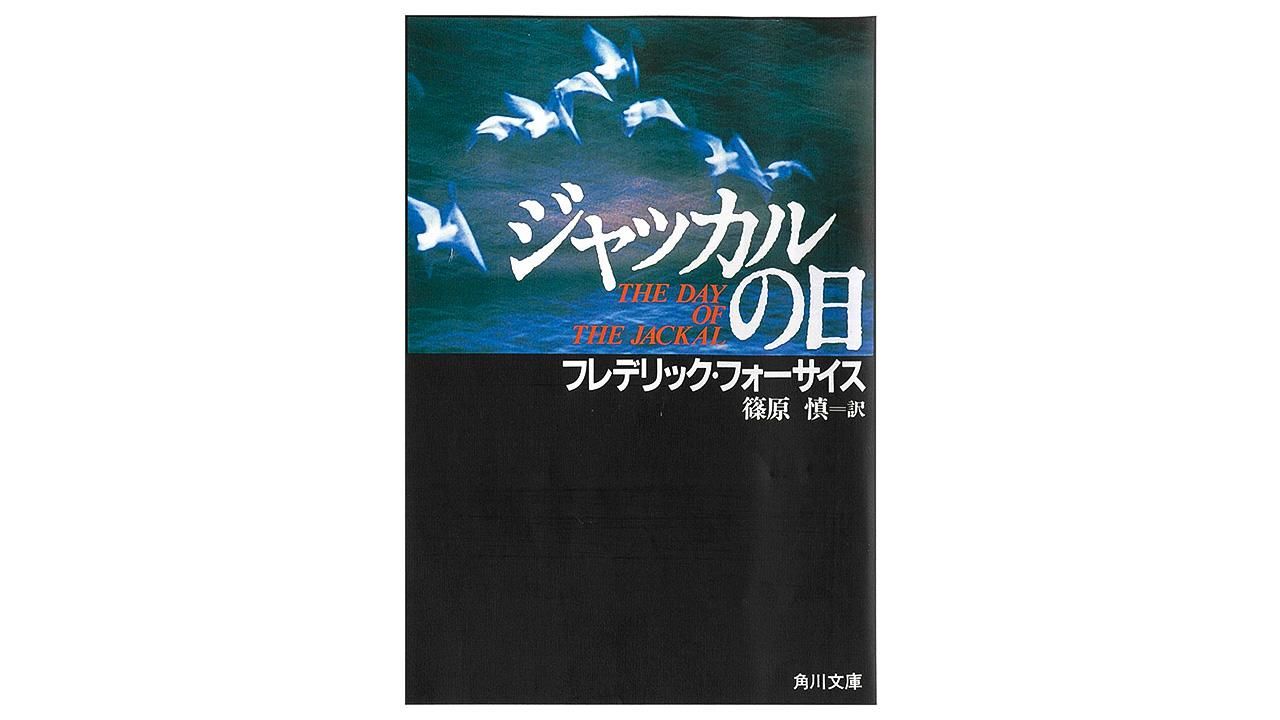
【書評】「狩る者」と「狩られる者」:フレデリック・フォーサイス著『ジャッカルの日』
Books 政治・外交 社会 国際 歴史- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
狙撃を生業とする暗殺者を描いた作品はいくつもあるが、私は、本作がそのジャンルでは最高峰にあると思う。
著者フレデリック・フォーサイスは、文庫の「日本語版に寄せて」にこう記している。
<本書の興味は、ジャッカルという暗号名をもつ一匹狼の殺し屋が、どのようにして目標に接近したか、そして奔命に疲れたルベル警視が最後にいかにして暗殺を阻止したか、その緊迫したつばぜりあいにあるといえます。>
殺し屋のターゲットは、フランス大統領のシャルル・ドゴール(1890年~1970年)である。現実世界では、ナチス・ドイツに占領された祖国に再び栄光をと願った大統領は、凶弾に倒れたわけではなく長寿をまっとうしている。
しかし、なんども暗殺未遂事件があったことは史実が物語っており、本作はそのうちのひとつ、表沙汰にならなかった事件の迫真の発掘ノンフィクションであるかのように思わせる。それほど細部にいたるまでリアリティがあり、密度の濃い描写の連続なのである。
著者が、本作を発表したのは1970年のこと。邦訳の文庫は、いまだに版を重ね続けている。なぜ、読者にそれほど支持されているのか。
著者の言葉をかりれば、「本書の主要な登場人物とテーマが普遍的だから」(日本語版に寄せて)ということになる。暗殺の対象となる人物は、誰もが知る歴史上の大物。そして普遍的なテーマとは、
<いつも人間の心をとらえる、狩る者と狩られる者、本書ではフランスの大統領を殺そうと決意している人間と、彼を阻止しようと決意している人間、の相克です。>(同)
読者は本作を読了後、「なるほど」と納得することだろう。
暗殺未遂事件で銃殺刑
それでは、まずは「狩る者」を紹介しよう。
1960年代、フランスの植民地政策はインドシナで躓き、続くアルジェリアでも迷路に入り込んでいた。軍の圧倒的な支持に推されて大統領に就任したドゴールは、当初、植民地を手放すことなく、アルジェリアの民族独立運動を鎮圧する決意を示していた。
ところが、アルジェリアの内戦が長期化するにつれ、フランス国民の人心は荒廃し、本国の経済も疲弊するにおよび、さしものドゴールも植民地の放棄を決断する。
しかし、現地で激しい戦闘に明け暮れていた駐留軍人の一部が、本国の命に背いて反乱を起こす。
過激派将校や、本国の出世レースとは無縁のエリート階級からはみ出した軍人、さらに戦場でなければ生きていけない傭兵たち。彼らは、なんとしても植民地を死守しようと誓い、「OAS」(秘密軍事組織のイニシャルからそう呼ばれる)を組織した。
彼らは、ついにはドゴール大統領への反乱を試み、暗殺を企てる。
ここでは「狩る者」はOASであり、「狩られる者」とはドゴールだ。
物語の冒頭は、1963年3月11日の早朝、OAS幹部の処刑シーンから始まる。
彼らは、公用車で移動する大統領を襲撃する計画を立て、実行にうつすが、ちょっとした手違いで撃ち洩らしてしまう。
犯行グループは現場から逃走したものの、次々と捕えられ、裁判ののち、首謀者の中佐がこの日、銃殺刑に処せられたのである。
ここまでのくだりは、史実を下敷きにしたドキュメンタリーのようだ。
秘密情報機関のなかの殺戮集団
そして、「狩る者」と「狩られる者」は攻守ところをかえて、めまぐるしく入れ替わる。
大統領の暗殺に失敗したOASは、今度は「狩られる者」となり、追い詰められていく。OASを「狩る者」とは、その頭文字をとって「SDECE」と略称されるフランスの秘密情報機関である。
彼らの任務は海外での諜報活動や国内のテロリストの取締りなど様々だが、OASを標的とする部署が第5部、通称アクション・サービスと呼ばれる部局である。そこに数百名の男たちが所属するが、彼らは荒くれ者の殺戮集団だった。
本書ではこう描かれている。
<この男たちはほとんどがコルシカ人であるが・・・彼らはまず基礎訓練として肉体の限界ぎりぎりまで鍛えられたあと、サトリへ移され、特別訓練班であらゆる格闘技術をたたき込まれる。小火器を使っての戦い、素手の格闘、空手、柔道など。さらにまた無線通信、爆破と破壊工作、尋問、拷問、放火、暗殺など・・・彼らは任務遂行中に人を殺す権限を与えられてい、しばしばそれを行使した。>
むろん、過激な軍人の集団組織であるOASも、暴力ではひけをとらなかった。彼らはアクション・サービスの工作員を憎悪している。
アルジェ市内でくりひろげた戦闘では、OASは捕虜にした工作員らを拷問したあげく、惨殺した。
<数日後彼らは耳と鼻をそがれた死体となって、バルコニーや電柱からぶら下げられた。>
作者はこう記述している。
<OASのメンバーの多くはピエノワール(アルジェリア生れのフランス人)で、コルシカ人と同じ気質を持っていたので、両者の戦いはときに同胞相食むという様相を呈した。>
しかし、秘密情報機関(SDECE)が圧倒的に有利に戦いをすすめ、OASの組織は壊滅的な打撃をこうむる。なかでも破壊活動を指導する大幹部がアクション・サービスによって拉致・逮捕されるにおよび、ドゴール暗殺作戦は頓挫するかにみえた。
そこへ登場するのがOASのなかでも天才的な戦略家といわれるマルク・ロダン大佐である。彼が作戦の指導者となることで、あらたな暗殺計画がスタートするのである。
イギリスから来た暗殺者
物語はいよいよ動き出す。
ロダン大佐は、ウィーンの山中にあるペンションの部屋を借り、腹心の部下2人を密かに呼び寄せ、次の暗殺計画を謀議していた。
いまや敵方は巧妙にOASの組織に裏切り者を送り込んでおり、彼らの密告で最高幹部による会議の内容さえ筒抜けになっている。暗殺チームを組織のメンバーで編んでも、すぐに情報は洩れ、たちまちのうちに摘発されてしまうのだ。
ロダンはこう言い放った。
「残された唯一の方法は、外部の人間を雇うことだ。もうそれ以外にない」
条件は、まず第一に外国人であること。身内の組織のメンバーではなく、フランスの警察・情報機関の記録に載っていない人物であること。
「真のプロフェッショナルでなくちゃいけない。そしてそういう人間は金のためにだけ働く。多額の金でね」
ロダン大佐は、独自の調査でうってつけの殺し屋を見つけ出し、その人物をペンションに呼んで交渉する。射撃の腕は超一流で、身許は割れていない。
ここからのくだりが序盤のおおきな読ませどころである。
暗殺者と向き合うロダン大佐。
<数秒間、彼はロンドンから来た男をみつめた。彼は人間を見る目に自信を持っていたが、イギリス人の印象は期待を裏切らなかった。ブロンドの客人は身長約一メートル八○、年齢は三十過ぎで、運動選手のように筋肉が引き締まっていた。>
このイギリス人の殺し屋は、政治がらみの案件を専門にしており、高額の報酬で暗殺を引き受ける。直近の仕事は3カ月前にエジプトで行った狙撃だった。
その仕事ぶりがさらりと記されている。
<彼があとにしてきた遠いエジプトの砂漠には、きれいに脊髄を撃ち抜かれた、三人のドイツ人ミサイル・エンジニアの死体が、怒り狂ったエジプト警察の手で葬られて眠っていた。彼らの死によって、ナセルのアル・ザフィラ・ロケットの開発が数年の遅れを余儀なくされ、ニューヨークのユダヤ人億万長者は、出費に見合う結果を得て満足した。>
「一生に一度の仕事・・・」
しかし、たびたび暗殺の標的になっているドゴール大統領は、厳重な警備に守られている。ロダン大佐は、この仕事が可能かどうか、目の前のイギリス人に尋ねる。
彼は即答した。
「暗殺者の銃弾から完全に保護されている人間など、この世界に一人もいない」
「ドゴールを暗殺してくれるかね」
「いいでしょう。しかし高いですよ」
彼は、この仕事を最後に引退するという。「一生に一度の仕事・・・ドゴール派の復讐から身を守れるだけの金を得ないと、とうていペイしないですからね」
彼が要求する報酬は、いまのOASが所有する資金ではとでも賄いきれない巨額なものだった。しかし、もはや選択の余地はなかった。これが最後の暗殺計画になる。適任者は彼をおいて他にはいない。
ロダン大佐らは、要求された金額を指定された口座に振り込むことを承諾する。前金の半額の振込が確認されたときに、彼の暗殺計画はスタートする。
ただし――。
彼の付けた条件は、秘密が露見しないよう、一切、単独で行動する。暗殺の日時、方法ともすべて自分に任せてもらう。この計画を知るロダン大佐と腹心の部下2人は、絶対に当局に逮捕されてはならない。もし、捕まれば、そのときには企みが露見したものとみなし、白紙にする。
商談は成立した。
「最後に一つだけ。呼び名のことだが・・・」
稀代の凄腕スナイパーは答えた。
「この仕事はいわば狩りですから、“ジャッカル“なんていかがでしょう」
モンパルナスの駅前広場
ここまで物語の入り口を紹介したが、ここから先の展開は、息つく暇も与えず読者を緊迫した世界へ引き込んでいくこと請け合いである。
ジャッカルはいかなる方法で厳重な警備の目をかいくぐり、狙撃銃の望遠照準器のなかに大統領の姿を捉えようとするのか。
そして暗殺に成功したのち、その場からどのようにして、無事、脱出しようとするのか。
ジャッカルは、あることから警備上の盲点を発見した。
そこから狙撃する日時と場所が決まり、狙撃と脱出方法の検討へとうつる。このあたり、暗殺者が計画を練り上げ、周到に準備していく様におおくのページが割かれていくが、この細部にわたるプロセスが興味津々。読者は、なるほど、こういう手があるのかと感嘆するにちがいない。たしかに、これなら暗殺は成功するかのように思えるのである。
ここまでが物語の前半部分にあたる。
そして後半に突入すると、「狩る者」と「狩られる者」とがまた入れ替わる。
あることがきっかけで、「SDECE」(秘密情報機関)はこの暗殺計画を察知することになる。
報告を受けたドゴール大統領の側近は、大統領に公の場に出ることを控えるよう進言するも、拒絶される。
<大統領は、ものものしい身辺警備を極端にきらい、警備の都合で自分のプライバシーが犯されようものなら、烈火のごとく怒り狂う。>
作家の人物描写は巧みである。ドゴール大統領の人柄とはかくや、と思わせる秀逸な場面がある。
ドゴール大統領は、側近の助言を強い口調で退ける。
「大統領がけちな殺し屋の脅威におびえないことこそ、フランスの国益にかなうことなのだ」
SDECE長官はじめ治安に関わる高官たちは鳩首協議する。正体不明の暗殺者をどうやって見つけ出すのか。そしてまた、誰がその任を負うのか。
司法警察刑事部長が発言した。
「名前を探ること、しかもそれを隠密裏にやること、これは純粋に刑事の仕事です」
適任者はいるのか。
「フランス一の刑事は、なんといってもうちの次長、クロード・ルベル警視ですよ」
もうひとりの主役が、いよいよ登場する。
ここから先、姿の見えない暗殺者「ジャッカル」とルベル警視との、本物のプロ同士の智略をつくした戦いになっていく。
見過ごしがちな断片情報から暗殺計画の全体像を探っていく。根気のいる情報収集と分析の繰り返し。本作にはインテリジェンスの世界の醍醐味がある。
1963年8月25日の日曜日は猛烈な暑さだった。
この日の午後4時、モンパルナス駅の駅前広場で、解放記念日の式典が開催される。1944年、パリがドイツの占領軍から解放された日だ。
予定された時刻に、ドゴール大統領は現われた。これから、レジスタンスの元戦士たちへの勲章の授与式が挙行される。
ジャッカルは引金に指をかけた――。
ジャッカルの日
フレデリック・フォーサイス(著)、篠原慎(訳)
発行:角川書店
文庫版540ページ
発行日:1979年6月10日
ISBN:978‐4-04-253701-4