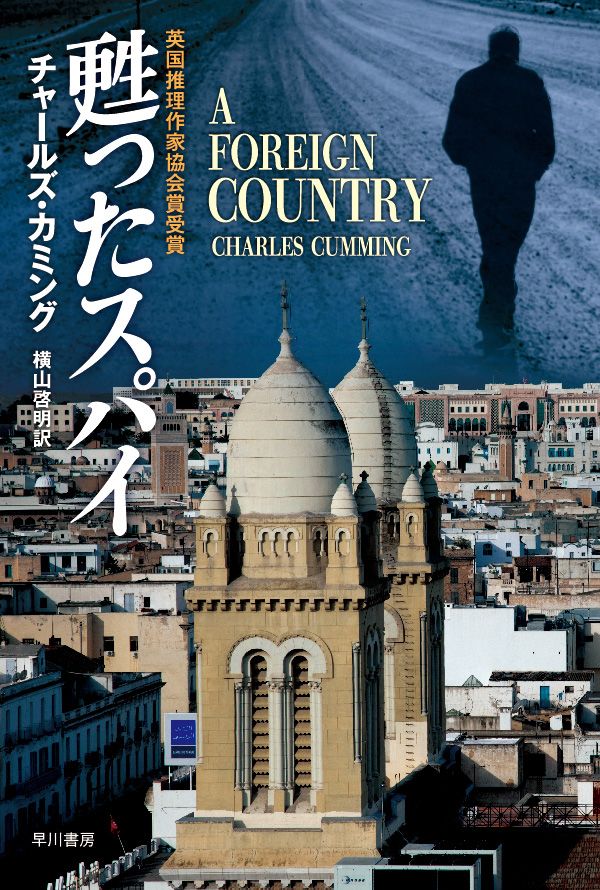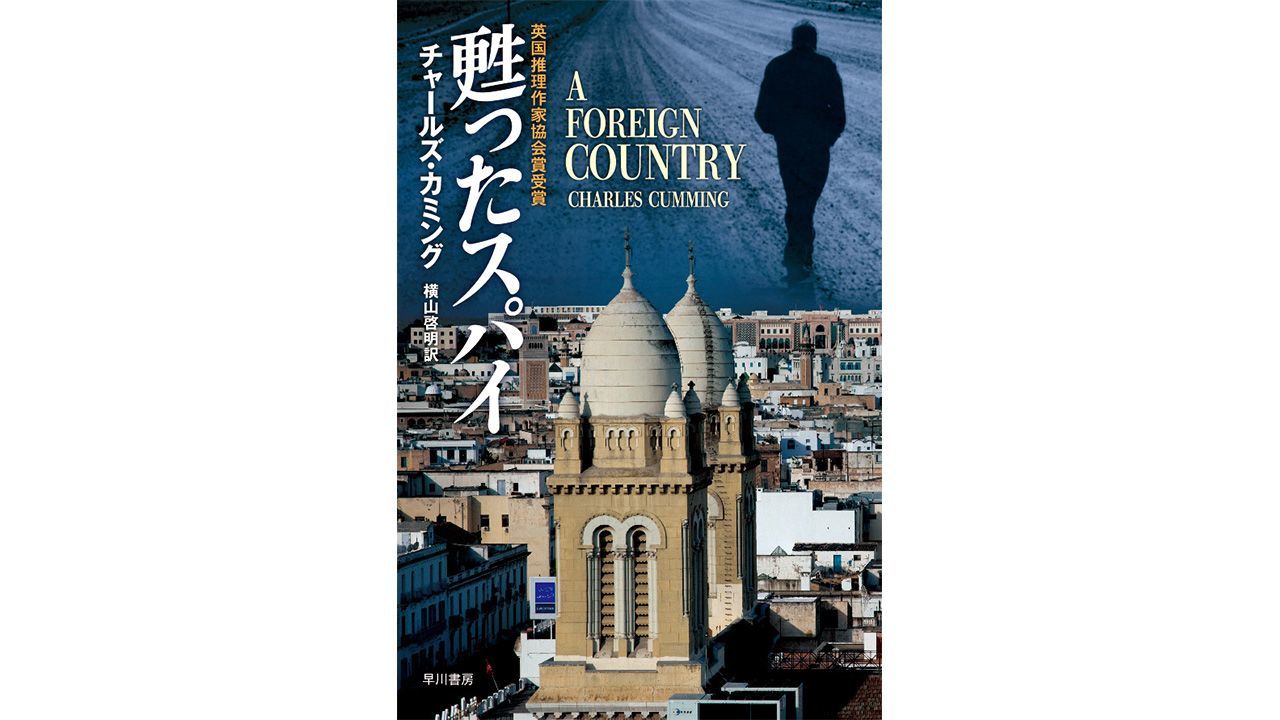
【書評】傷心のスパイよ、いま再び!:チャールズ・カミング著『甦ったスパイ』
Books 政治・外交 国際・海外 社会 エンタメ- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
キャリアを積んで一人前のプロフェッショナルになっていくにつれ、組織の中に理想とは違う不公平、さらには不正が巣食っていることが見えてくる。そんな現実を前に、黙って見過ごすのか、あるいは決然とした姿勢で糺していこうとするのか。
だが、上司は必ずしも味方になってくれるとは限らない。それどころか、責任のすべてを押し付けられてしまうこともある。
本作は、理不尽な理由で組織を追われ、傷ついてしまった中年男性の「再生の物語」だ。これはスパイという特殊な職業をもつ者に限った話ではない。常の企業で真面目に勤め上げ、組織のために尽くしている我々の身にも降りかかってくるかもしれない。
この物語の主人公は、長年にわたって培ってきた本物のプロならではのスキルを駆使し、再び立ち上がっていく。それが吉と出るか凶と出るか。「再生」に向けてのプロセスが本作の最大の読みどころである。
アフガンでCIAと共同作戦
<「国と友人のどちらを裏切るか問われたら」E・M・フォスターの言葉を思い出した。「国を裏切るだけの心意気を持ちたいものだ」
生まれてはじめて、この言葉の意味がよくわかった。>
主人公が再び戦いを挑もうと決意した瞬間、そのときの心情を描写した場面である。彼は誰のために国を裏切ろうとしたのか?
その人の名はトーマス・ケル。英国秘密情報部SIS(通称M16)をクビになって8か月が過ぎている。
今年42歳になるが、妻との関係はうまくいっておらず、いまは別居中。子供はいない。スパイという職業柄、突然の出張が多く家庭では不在がち、その理由を妻に明かせないことが不仲の原因だった。
元の職場への未練はある。だから、まだ定職についてはいない。
ケルは有能な現地工作員だった。なぜSISを追われたのか。
本作で、私にとって一番印象に残った場面を紹介しよう。
2001年9月11日、アメリカは同時多発テロにみまわれた。同年暮れ、ケルはCIAとの共同作戦でアフガニスタンへ潜入した。アルカイーダに反撃するためだ。
それからの3年間、ケルはパキスタンとアフガニスタンを7回訪れた。
2004年、CIAはパキスタンで、ある男の身柄を拘束した。容疑はアルカイーダの訓練キャンプに参加していたというもの。
男はイギリス人と主張し、それを証明するパスポートを所持している。彼はカブールにあるアメリカの施設に連行され、尋問された。ケルも立ち会った。
彼の過去にまつわるこのくだりは、物語の中盤あたりで明らかにされる。全体のボリュームからいうと、ほんの数ページさかれているだけである。
これは本筋の陰謀とは直接関係のない、主人公ケルの背景を淡々と記述しているにすぎないのだが、私にはここで語られるエピソードが胸にこたえた。
グアンタナモの収容施設
拘束された男の名前「ヤシーン」は、イギリスの防諜機関M15の記録にテロリストの疑いがあるとして記載されていた。
彼はリーズ在住の21歳の若者で、尋問に対してパキスタンへは「友人を訪ねてきただけだ」と主張している。
しかし、CIAは証拠写真を握っていた。そこにはヤシーンが訓練キャンプでロケット砲を発射する姿が映っていた。
ケルは若者に忠告する。「イギリス政府になにもかも話すのがいちばんであり、そうすれば展望が開ける」「潔白であるふりをするなら、アメリカ人がやろうとしていることを止める権利は、おれたちにはなくなるんだ」
若者は容疑を認めなかった。彼はグアンタナモの基地に送られた。
キューバのグアンタナモ湾にある米軍基地には、テロリストを収容する施設があり、アフガン紛争以降、続々と容疑者が送り込まれていた。
のちに、赤十字国際委員会やアムネスティ・インターナショナルから、拷問や苛酷な尋問などの人権侵害で告発される、いわくつきの収容所である。
ヤシーンは口を割らなかった。
「アメリカ人が手荒なまねをしたとだけ言っておこう」
と、ケルは述懐しているが、彼はアメリカ人の仲間をかばった。「拷問はしていない」と。彼のセリフは泣かせる。目をつぶっているわけにはいかないのだ。
「イギリスは政治的にも情報の面でもアメリカと同盟関係にあるが、誰もが思っているよりもその絆は強固・・・アメリカの仲間が、認めることのできない手段に訴えることを知ったら、イギリスの秘密工作員はどうしたらいいだろう?・・・居心地が悪いから帰りたいと直属の上司に訴えるのか?おれたちが戦っているのは戦争だ。アメリカ人は友人なんだよ」
SISは生贄をさしだした
しかし、世論は容赦しない。
イギリスのメディアは、ヤシーンがイギリス人であることを強調し、推定無罪の立場からアメリカに身柄を引き渡したことは違法だと政府を非難した。
その矛先が、外務大臣の責任問題に及ぶにいたり、SISは生贄をさしだした。すなわち、尋問に立ち会った工作員に問題があった、と。
ケルは親しい仲間に嘆いて言う。
「左翼の連中はたいていが、自分たちの口当たりのいい主義主張、非の打ち所のない道徳的な行動を要求し、それを訴えることにしか興味がない。連中が安心してベッドで眠れるように戦っている者たちが犠牲になっているというのにな」
ケルは自問自答する。
「やつのせいで地下鉄が爆破されたらどうする?・・・グラスゴーでバスが爆破され、上の階に乗っていた老人が跡形もなく吹っ飛んでしまった・・・ショッピングセンターで自爆テロを引き起こし、生後六か月の男の子が死ぬかもしれない・・・ヤシーンのような経歴の持ち主は、旅行作家のロバート・バイロンの足跡を求めてパキスタンへ行くことなどありえないだろう」
ケルはひとり責任を背負わされ、SISを追放された。このときの長官ヘインズと副長官トラスコットとは、もともとソリのあわない関係だったのだ。
はたしてアフガニスタンやパキスタンでの工作活動は、正当化できるものだったのか。ケルは深い自己嫌悪に陥っている。
正義と信じてやったこと。しかし、組織の上層部からは切り捨てられた。
どうすることが正しかったのか、考えさせられる場面である。
パリからニース、チュニジアへ
物語の本筋はこうだ。
冒頭、2つのエピソードが手短に語られる。
エジプトに観光旅行に来ていた老夫婦が、海岸を散歩中に惨殺された。
パリの路上で、「ホルスト」と名付けられた若い男が、アラブ人の犯行グループに拉致された。これらの事件はなにを意味するのか?
SISは、初めて女性を長官に据えようとしていた。彼女の名前はアメリア・リーヴェン。中東や北アフリカでの作戦の指揮をとり、ワシントン勤務の経歴もある。エリートコースに乗ったやり手である。
しかし、副長官のトラスコットは面白くない。てっきり、自分が後任に就けると思い込んでいたのだから。
そして長官就任直前、アメリアは突然休暇を願い出て、パリへ出立する。副長官は不審に思い、パリ支局員に監視させるが、彼女は姿をくらましてしまう。なにかの事件に巻き込まれたのか?彼はスキャンダルを期待している。
アメリアとケルは、公私にわたって昵懇の間柄だった。副長官の腹心の部下で、かつての同僚が連絡してくる。「手を貸してほしい」
ケルはむろんお断りだが、用件を聞いて引き受けることにする。
再びケルはスパイの世界へ舞い戻ってきた。アメリアの足跡を追って、舞台はパリからニース、さらに北アフリカのチェニジアの首都チュニスへ。
当初の指令は、アメリアの居場所を特定するだけでよかったが、彼は新長官を陥れようとする国際的な陰謀をかぎつける。
突破口は、ある人物の監視だった。この男を追いかけていけば、黒幕にたどり着き、全貌が明らかになる。ケルは、長年の経験で培ったスキルで、ひとつひとつ謎を解いていくが、そこへたどり着くまでのスパイの手法は読み応え十分。
<スパイするとは、すなわち待つことである。>
派手な立ち回りは必要ない。
本物のプロの仕事とは、かくあるべし!
もうひとりの再生の物語
読みどころをもうひとつ、紹介したい。
本稿の最初に、中年男性の「再生の物語」として読める、と書いた。これはケルのことだ。しかし、読み進むにつれて、もうひとりの登場人物の再生物語でもあることに気が付いた。
アメリア・リーヴェンは、過去に深い傷を負っている。SISにリクルートされる以前の、まだ若かった頃の罪であり、痛恨の出来事だった。しかし、彼女はそのことを隠し、出世街道を邁進した。
女性初の長官になろうとする今、暴かれると一大スキャンダルになる。
アメリアは自らの過去と向き合うことになる。彼女は、古傷を隠ぺいすることで「再生した」と信じていた。あらたな人格を築いた、とも。
しかし中年の域にさしかかり、あることが引き鉄となって、それは過ちだったのではないか、と揺らいでいく。
どうすべきなのか。決断するために、彼女は休暇を取ってパリを訪れた。
そして思案する。自ら抱えてきた秘密を告白し、組織のトップにまで上り詰めたキャリアを捨ててでも、人生をやり直すべきではないのか。
それこそが、敵の狙うところであった。敵方は誰か、ここでは明かさない。某国の秘密情報機関とだけいっておくが、彼女の過去に、陰謀の核心があった。
ここで、エジプトの老夫婦殺害事件とパリでの拉致事件がつながってくる。
この作品は、読者にとって、自らの、職業人としての生き方をふりかえるきっかけになるかもしれない。私は、ケルの決意に励まされた。
<できることと言えば、長年やってきた仕事しかない。秘密工作員としての技術以外に自分にはなにもないのだ。>
自分のキャリアに自信をもつことだ。ケルは再生した――。
甦ったスパイ
チャールズ・カミング(著)、横山啓明(訳)
発行:早川書房
文庫版515ページ
発行日:2013年8月25日
ISBN:978-4-15-041287-6