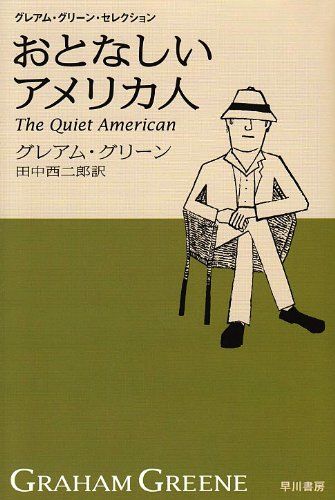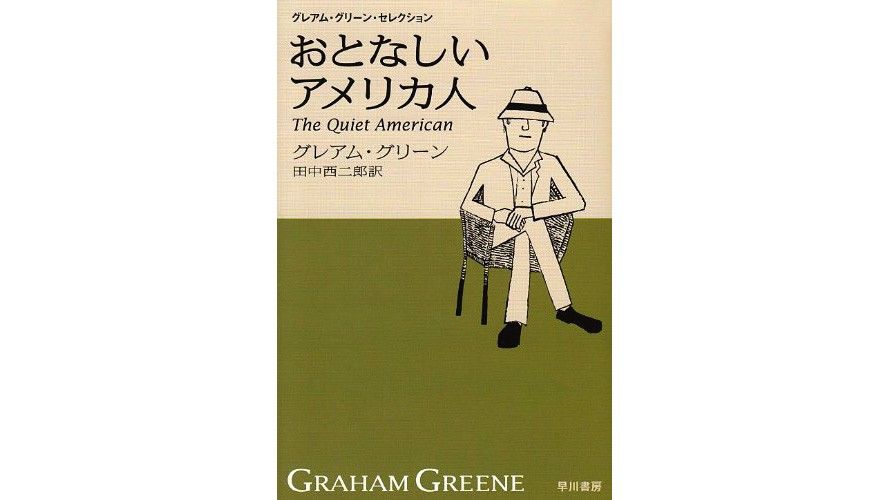
【書評】「老獪」なイギリスと「無邪気」なアメリカ:グレアム・グリーン著『おとなしいアメリカ人』
Books 政治・外交 社会 国際 歴史- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
中東や北朝鮮をめぐるトランプ大統領の外交政策に、日本は翻弄されている。その有様は、外交の駆け引きに長じた老大国イギリスにはどう見えるだろうか。
本作は1955年に発表されたものだが、今日でもじゅうぶん、読み応えがある。主人公であるイギリス人特派員は、アメリカ人をシニカルに観察している。イギリス人のアメリカ観―-、その内容はアメリカという国の本質を突き、われわれにとっても非常に示唆に富む。
舞台は、1950年代初頭におけるフランス植民地下のヴェトナムである。当時、この国の北部は中国共産党に支援されたホー・チミン率いるヴェトミン軍が支配し、南部を拠点とするフランス軍とヴェトナム政府軍に盛んにゲリラ戦を仕掛けていた。
主人公のイギリス人特派員トマス・ファウラーは、サイゴンに赴任してもう何年にもなる。すっかり現地の生活に溶けこんでおり、若い現地の娘フォンと半同棲し、鴉片(あへん)を常用している。彼には本国に残した妻がおり、夫婦仲は冷え切っているが、宗教上の理由で離婚は拒否されている。子供はいない。
英国人作家の巨匠、グレアム・グリーン(1904~1991)について、いまさらいうこともないだろう。私にとってこの作品は、彼が残した数々の作品のなかでもベスト3に入る。
「共産主義の魔手にかかった」
物語は、現地のアメリカ公使館に赴任してきた若者が、何者かによって殺害されたところから始まる。
彼の名は、オールデン・パイル。ボストンの出身で父親は大学教授。彼自身も優秀な成績で学位を取っており、ヴェトナムへは経済援助使節団の一員として派遣されてきた。赴任してからまだ滞在数か月、今年32歳になる独身である。
死体は、サイゴン市内を流れる川の橋の下で発見された。<日が暮れれば、川向うはヴェトミンの便衣隊の手中に入るから、夜はこの橋を渡るのは危険>といわれる場所である。
ファウラーは、その日の深夜、内縁のフォンとともに現地駐在のフランス警察から呼び出され、パイルの死を知る。
彼は、パイルの数少ない友人のひとりだった。
フランス人の警察幹部は、捜査報告書に「被害者は共産主義の魔手にかかった」と記した。「おそらくは、アメリカの援助に対する反抗運動の手はじめであろう」と推理している。
「得意な題目はデモクラシー」
ここから、物語はファウラーが初めてパイルに出会った頃にさかのぼる。
サイゴン市内にあるコンティネンタル・ホテルのバーは、外国人のたまり場になっている。なかでも形勢不利なフランスを援助し、ヴェトナムにおけるプレゼンスを高めているアメリカの存在感は日に日に増していた。
古参のファウラーは、アメリカ人記者が気に入らない。
<尊大で、騒々しくて、みんないい年配なのに子供っぽくて、いろいろと文句はつけられても結局はこの戦争の当事者にちがいないフランスのアラ探しばかりやってる連中だ。>
しかし、シニカルな彼の目にも、パイルはまだましに映った。彼の印象が、「おとなしくて、謙虚」だったからである。
「おとなしいアメリカ人」というのが、もっぱらの彼の評判だが、彼自身は、ヴェトナムの民族独立に貢献したいとの理想に燃えている。
むろん、共産主義国ではなく、自由主義、デモクラシーの国として。
<“民主主義のディレンマ“や“西欧の責任“で、頭のなかはもう一杯だった。>
それがファウラーには煩わしかった。
<おれが極東に住んだ数年ぐらいの月数しか住んだことがないくせに、おれに向かって極東問題の講義をするのによく悩まされたものだ。もう一つの得意な題目はデモクラシーで、アメリカが世界のためになしつつある貢献について、自信たっぷりに断定的な意見をまくしたてるので、やりきれなかった。>
鬼気迫る戦場シーン
当時の情勢は、ヴェトミン軍が攻勢をかけていた。
ベテラン特派員のファウラーが見るところ、
「中共がヴェトミン軍を助けに来なければ、フランスはどうにか持ちこたえるかも知れない。ジャングルと、山と沼地の戦争だ。水田に入ると肩まで泥につかる。敵は武器を地面に埋めて農夫の服を着るから、たちまちわからなくなる」
あるときには、こう言って切り捨てる。
「要するにこんなものは下らない植民地戦争だよ」
ファウラーは、フランス軍との間で築いたコネを使い、ときに従軍して戦闘地を取材する。本作は、作者グレアム・グリーンが1950年から55年の間にヴェトナムを取材旅行した見聞が下敷きになっている。それだけに、戦場の描写には鬼気迫るものがある。
一端を記せば、ファウラーが目にしたものはこうだ。
<運河には、死体が充満していた。いまおれが思いだすのは、肉ばかり多すぎるアイルランド風のシチューである。折り重なった死体。そのなかから、ブイのように水の上へ突き出ているアザラシ色の、囚人のように剃られた一つの頭。血はなかった。もうずっと前に洗い流されてしまったのだろう。どのくらいの数か、おれには見当がつかない。>
そうした惨状を目の前にして、生きている兵士もファウラー自身も虚無的になる。兵士は、
<一人のこらず、“どうせお互いさまだ”という考えが浮かんだに違いない。おれもまた顔をそむけた。だれもが、いかに自分というものが物の数でないか、いかに簡単に、いかに迅速に、闇から闇へ、死が襲うものであるかを思わせられた。>
あるときには、フランスの小型爆撃機に同乗し、空から戦場を目撃する。深い谷とジャングルに囲まれた小さな村落に若いパイロットは爆弾を落とし、機銃を掃射していく。稲田に流れる川に一艘のサンパンを見つけると、降下して曳光弾を浴びせかけ、小舟はたちまち火に包まれる。
その襲撃に意味があるのか、とファウラーは言う。パイロット自身も、無意味であることは十分承知しているから、こう答える。
「あなたはジャーナリストです。われわれが勝てないことは、ぼく以上によく知っているでしょう(略)しかし、ぼくらは職業軍人です、政治家たちがやめろと言うまでは戦いつづけなくちゃならない。たぶんやつらは寄り集まって、緒戦の頃に話し合いがついたと同じ講和条件で折り合うでしょう、この数年間の戦争は全部ナンセンスになるわけだ」
「あれは民族デモクラシーではないよ」
こうした泥沼のインドシナ紛争が、ヴェトナム戦争へと続いていく。
さて、パイルの役割である。
彼の正体は、OSS(CIAの前身となる情報機関)の工作員で、与えられたミッションは、ヴェトミンでもフランスでもない「第三の勢力」を支援し、育成することだった。
サイゴン周辺には、「第三の勢力」として、どちらの側にも与しない独立系の軍勢がいくつか存在した。パイルはそのなかでも有力とみられる「テエ将軍」と接触するようになる。
これがのちに、大きな悲劇を生む。
それとなくパイルの身分を察したファウラーは、彼に忠告する。
「おれたちは古風な植民地主義の国民だがね。パイル、しかしおれたちは幾らか現実を心得ていているから、火遊びはしないよ。例の“第三勢力”というやつ――あれは本のなかから出て来たもので、それ以上のものじゃない。テエ将軍は僅か数千人の手下を従えた山賊にすぎない。あれは民族デモクラシーではないよ」
しかし、パイルには、陰謀をめぐらしているという意識はない。あくまでもアメリカの原理、主義を植え付けることで、ヴェトナムの人民は幸福になると信じている。
だからときに、パイルとファウラーは口論となる。
「個人の尊厳」と、金科玉条のようにパイルは言う。共産主義は個人の自由を認めていない、と。だが、ファウラーにとっては机上の空論にしか思えない。彼は反駁する。「だれが田圃ではたらく男の個性について心配したかね――彼らを人間として取り扱っているのは共産党の政治委員たった一人だよ。あれだけは農民の小屋へ入って行って、名前を聞いて、不平や不満を聴いてやっている。(略)この国ではきみたちは悪い方の立場に立ってることに気がつかないかね」
アメリカはデモクラシーの理念ばかりを唱え、現実の貧しい農民の生活を助けようとはしない。親身になって農民の味方になっているのは、むしろ共産主義者の方ではないか、というわけだ。
イギリスの老ジャーナリストと、理想主義のアメリカの若者との議論は、ついに折り合うことがない。
頭を切りとられた鶏のように・・・
そしてとうとう悲劇が起こる。
サイゴン市内の繁華街で小規模な爆弾騒動が繰り返され、ついに大規模な爆弾テロが引き起こされる。
誰によって?
とある日の午前11時、国立劇場前の広場で爆発があった。ファウラーは現場近くにいた。
<バラバラになった自動車の残骸が広場に散らばり(略)一人の女は彼女の赤児の遺骸を膝の上に抱いて、地面にすわっていた(略)花壇の縁の脚のない胴体は、頭を切りとられた鶏のようにまだピクピク動いていた。その男のシャツの様子から判断すると、輪タクの車夫らしい>
パイルが茫然と現場に現れた。ファウラーは怒りにまかせて言う。
「いまや女や子供がいつも出さかっている時刻だ――買い物の時間だ。なぜ特別にこんな時刻をえらんだのだ?」
パイルは、<自分の善意と無知とで、絶対堅固に武装していた。>だから自らの非は認めない。
ファウラーは、思う。
<二百ポンド爆弾は、相手に一々差別をつけない。大佐が何人死んだからといって、民族デモクラシー戦線を育成するために子供や輪タク車夫を殺すことを正当化できるか?>
パイルの存在は、反対勢力から目をつけられるようになる。
ファウラーも、もはやシニカルな傍観者ではいられない。そうせざるをえない理由。ここで詳しく述べるわけにはいかないが、彼はこう結論づけた。
<言ったって何になる?この男はいつも無邪気なのだ。無邪気な者を批難することはできない(略)彼らはつねに罪がないのだ(略)無邪気は狂気の一種なのだ>
「この男」を、アメリカに置き換えてみてはどうだろう。グレアム・グリーンにとって、アメリカは「この男」そのものに見えていたのではないか。
「おとなしいアメリカ人」
グレアム・グリーン(著)、田中西二郎(翻訳)
発行:早川書房
文庫版:367ページ
価格:960円(税抜き)
発行日:2004年8月15日
ISBN:978-4-15-120028-1