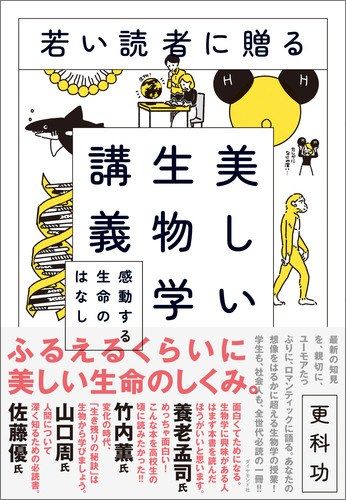【書評】ヒトの“立ち位置”を知る:更科功著『若い読者に贈る美しい生物学講義』
Books 科学 環境・自然 歴史 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ヒトは大型類人猿の一種
本書の魅力は、生物学の観点から「ヒトとは何か」を多面的に描き出したことだ。例えば「何億年も前の私たちの祖先は、魚だった」、「ヒトは進化の最後の種ではない」……。軽妙な文章とイラストや図で時空を超えた人類史のストーリーが展開されている。
人類の出現は約700万年前とされる。日本の少子高齢化とは対照的に、地球上の人口は増え続けて現在約77億人。著者は人類の長い歴史の中で、私たちが今、どのような位置にいるのかをわかりやすく説いてくれる。
著者によると、私たち人類、すなわちヒトは動物であり、進化的には尾がない大型類人猿の一種だという。ヒト以外の大型類人猿はチンパンジー、ボノボ、ゴリラ、オランウータンである。
大型類人猿5種の系統(種が分かれたのが古いほど遠縁で、新しいほど近縁)をチンパンジーの立場から見ると、一番近縁なのはかつてピグミーチンパンジーと呼ばれていたボノボ。二番目に近縁なのがヒトだ。三番目はゴリラで、四番目がオランウータンとなる。
とはいえ、見た目ではチンパンジーとヒトはかなり違う。遠縁のゴリラやオランウータンの方がよほどチンパンジーに似ている。
「チンパンジーとボノボとゴリラとオランウータンは、みんな毛むくじゃらだし、脳は五〇〇㏄以下と小さいし、普段は四足歩行だし、牙がある。しかし、ヒトだけは、体毛が薄いし、脳は約一三五〇ccと大きいし、二足歩行だし、牙がない」
直立二足歩行と小さな犬歯
ヒトには四つの特徴がある。「直立二足歩行」、「牙を失ったこと」、「体毛が薄いこと」、「脳が大きいこと」である。
「どれが最初に進化したかは、化石から推測できる。それは『直立二足歩行』と『牙を失ったこと』である。この二つがほぼ同時に進化したことによって、ヒトの祖先は、他の類人猿から分かれたのである。(中略)つまり、二足歩行と牙の消失が、人類という生物を誕生させた」
両足で歩く生物なら、ニワトリなどたくさんいる。直立二足歩行の定義は「体幹(頭部と四肢を除く胴体の部分)を直立させて、二本の足で歩くことだ」。他の二足歩行と違うのは「頭の位置だ。止まったときに頭が足の真上に来るのが、直立二足歩行である」
「これは本当に驚くべきことだが、人類以外に直立二足歩行をする生物はまったくいない。およそ四十億年にもわたる生物の進化の歴史の中で、人類の出現(約七百万年前)以前には、ただの一度も直立二足歩行は進化しなかったのだ」
チンパンジーの犬歯は大きい。言い換えれば「牙」である。オス同士の争いで、相手を殺してしまう凶器ともなる。ところが、人類の犬歯は小さい。人類は進化の過程で、犬歯が小さくなり、牙がなくなったとの仮説が成り立つ。
著者の見解はこうだ。「人類の犬歯が小さくなったのは、犬歯を使わなくなったからだ。犬歯はおもに仲間同士の争いに使われていたのだから、人類は仲間同士でほとんど殺し合いをしなくなったのだろう。つまり、人類は平和な生物なのだ」
700万年前に「一夫一妻」社会
多夫多妻的な群れを作るチンパンジーの争いで最も多いのは、メスをめぐるオス同士の争いだという。これに対し人類は類人猿から分かれて進化したときに、オスとメスの関係が変化したようだ。
「約七百万年前の人類は、一夫一妻的な社会を作るようになったので、オス同士の争いが減り、犬歯が小さくなったのではないだろうか」。これが著者の仮説である。
一方で、直立二足歩行には重大な欠点がある。四足歩行に比べ、走るのが遅いことだ。ヒトは多くの動物に強烈な劣等感を持っている。他の肉食獣に追いかけられるリスクも伴う。それでも直立二足歩行には「両手が空くので食料が運べる」という利点がある。
一夫一妻的な社会でオスの子育てを考える場合、「ペアになったメスが産んだ子は、ほぼ自分の子と考えてよい。したがって、直立二足歩行によって食物を運んで生存率を高くしてあげた子は、たいてい自分の子だ。自分の子には直立二足歩行が遺伝する。だから、直立二足歩行をする個体は増えていく」
「約七百万年前に人類は一夫一妻的な社会を作りつつ、直立二足歩行と小さな犬歯を進化させたのだろう」――。著者は「現時点では、これが最良の仮説と考えられる」と結論づけている。
地球の生物多様性を守ろう
「どんな生物でも、一人で生きていくことはできない。生物は必ず生態系の中で生きている。だから生物にとっては、生態系が崩壊せずに安定して存在し続けることが大切だ。そのためには、いろいろな種類の生物がいた方がよい」
何よりも地球の「生物多様性(biodiversity)」を守ることが重要なのである。人類は約700万年前に誕生してから、何種もの系統の人類が同時に地球上にいたが、約4万年前にネアンデルタール人が絶滅すると、人類はヒト一種しかいなくなった。「現在の人類の種の多様性は、非常に低い状態」である。
しかも、現在の地球でもっとも深刻な問題は、ヒトが爆発的に増加していることだ。著者は「地球という生態系は、著しく不安定になっている」と危惧する。
人々がいろいろな意見を持つこと自体も、生物多様性だという。「すべてのヒトが同じ意見を持つのは危険なことなのだ。それはヒトを含む生態系を危うくさせるから」と著者は警鐘を鳴らす。
人類は進化の頂点なのか
私たちの祖先は海に住んでいた。魚類の一部が陸上に進出して、途方もない時間をかけてヒトへと進化した。そして魚類でも両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類でも現存する種は、生命が誕生してからおよそ40億年という同じ長さの時間を進化してきた生物である。
その意味ではヒトは進化の最後に現れた種でもない。今を生きている生物は「あの生物はより高等で、この生物はより下等だ、なんてこともない」。そもそも、あらゆる条件で優れた万能の生物というものは、理論的にありえない。
「私たちは、すべての生物の中で、ヒトが一番偉いと思いがちである」。しかし、何を基準にするかによって、「優れた」とか「進歩」とかの物差しは変わってくる。仮に走る速さを基準にすれば、サバンナに住むチーターなどヒトより速い動物はいくらでもいる。ヒトは進化の頂点に立っているわけではない。
「実際、人類の進化を見ると、脳は一直線に大きくなってきたわけではない。ネアンデルタール人は私たちヒトより脳が大きかったけれど、ネアンデルタール人は絶滅し、私たちヒトは生き残った。その私たちヒトも、最近一万年ぐらいは脳が小さくなるように進化している。これらの事実が意味することは、脳は大きければ良いわけではないということだ」
ダーウィン「方向性選択で進化」
あらゆる条件で優れた生物がいない以上、「進化」は必ずしも「進歩」とはいえない。生物は、そのときどきの環境に適応するように進化するだけだ。
本書によると、『種の起源』で知られるチャールズ・ダーウィン(1809-1882年)の最大の功績は進化が進歩ではないと理解し、「生物が自然選択によって進化することを発見した」ことだ。
著者は自然選択の条件として①遺伝する変異(遺伝的変異)があること②遺伝的変異によって子どもの数に違いが生じること――の二つを挙げる。自然選択には「安定化選択」と「方向性選択」があり、前者は生物を変化させないように働くが、後者は生物を変化させるように働く。ダーウィンはこの「方向性選択」を見つけ出したのである。
「方向性選択が働けば、生物は自動的に、ただ環境に適応するように進化する。たとえば気候が暑くなったり寒くなったりを繰り返すとしよう。その場合、生物は、暑さへの適応と寒さへの適応を、何度でも繰り返すことだろう。生物の進化に目的地はない。目の前の環境に、自動的に適応するだけなのだ。こういう進化なら明らかに進歩とは無関係なので、進化は進歩でないとダーウィンは気づいたのだろう」
地球には現在、さまざまな生物があふれている。40億年という気の遠くなるような時間をかけて奇跡的ともいえる生物多様性を作り上げたのは、まさに方向性選択による進化の賜物である。
生物学は人生を豊かにする
生物学とは「生物に関係するものごとを科学的に調べることだ」。本書は「生物学に興味を持ってもらいたくて書いた」という著者は1961年東京生まれの博士(理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業、民間企業を経て大学に戻り、東大大学院理学系研究科修了。専門は分子古生物学で、『宇宙からいかにヒトは生まれたか』(新潮選書)など著書も多い。
本書では先ず、大本の科学について論じている。「科学は一つである」が持論だ。「物理学、化学、生物学、地学などと分けることもあるが、それはあくまで便宜的なものだ。(中略)それぞれの分野は密接に絡み合っている。というか、もともと一つで分けられないものを、分けたつもりになっているだけだ」と断ずる。科学全体に広い視野を持つことこそ、大切だというわけだ。
「科学では、決して一〇〇パーセント正しい結果は得られない」と著者は強調する。科学では推測による仮説を立て、観察や実験で検証できれば「より良い仮説」になる。何度も何度も支持されてきた仮説は「理論」とか「法則」と呼ばれるようになるが、それでも100パーセント正しいわけではないことを丁寧に説く。
著者はこうした科学の限界を頭の片すみに置きながら、生物学をめぐる新しい発見や物語を紹介していく。平易な言葉で小気味よく綴っていく手法は新鮮でさえある。
「生物とは何か」の定義から始まり、実際の細菌や動植物の話、人口知能(AI)と人類、不老不死とiPS細胞との関係などテーマは多岐にわたる。「遺伝のしくみ」、「花粉症はなぜ起きる」、「がんは進化する」、「一気飲みしてはいけない」など身近で切実な話題も豊富だ。
「生物学を面白いと思うことは、きっとあなたの人生を豊かにしてくれる」。著者はこう語りかける。人生を生きていくうえで視野が広がったとの読後感や世界観は、若者だけではなく、幅広い世代に共有されるのではないか。高齢の評者もその一人である。
若い読者に贈る美しい生物学講義――感動する生命のはなし
更科 功(著)
発行:ダイヤモンド社
四六判:328ページ
価格:1600円(税抜き)
発行日:2019年11月27日
ISBN: 978-4-478-10830-7