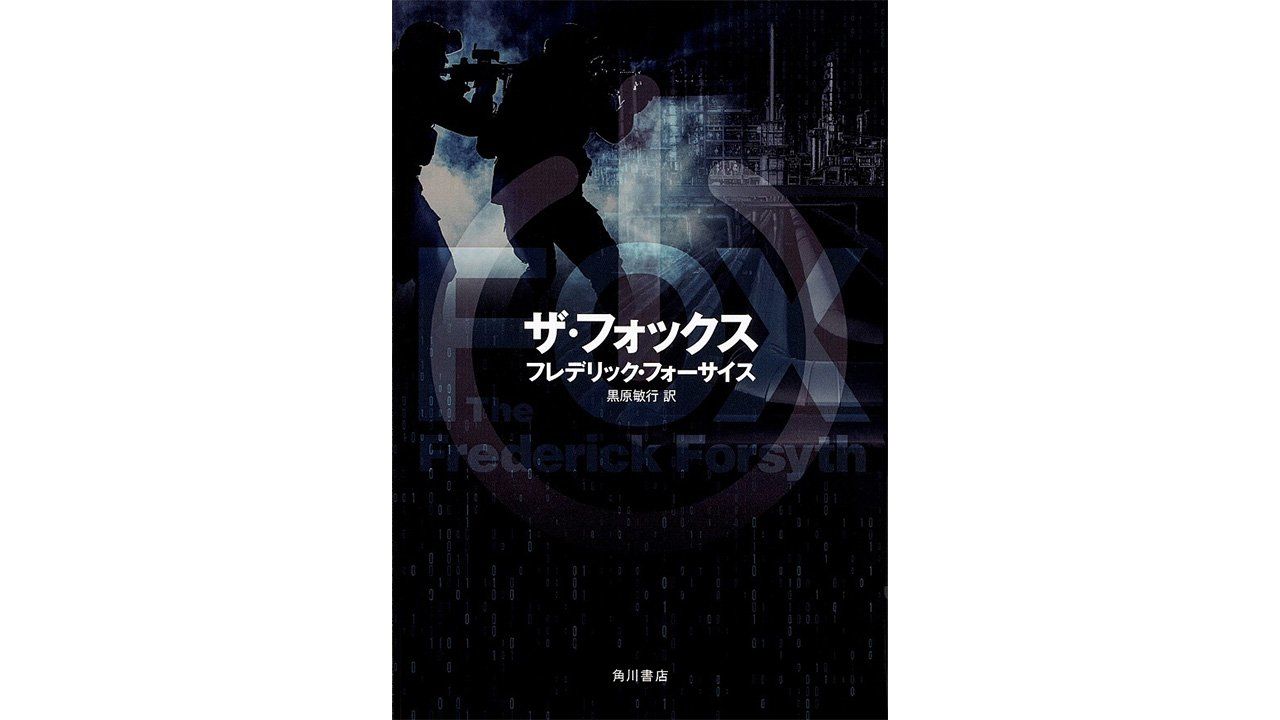
【書評】これがインテリジェンス・ワールドの最前線だ!:F・フォーサイス著『ザ・フォックス』
Books 政治・外交 国際・海外 エンタメ 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
主役は、イギリスの情報機関(SIS、別名MI6)に所属していた元工作員で、副長官を務めたのち引退、いまは首相の国家安全保障に関するアドバイザーを務めるサー・エイドリアン・ウェストンだ。
本作は、このSISが、ロシア、イラン、北朝鮮の3か国を相手に、熾烈な諜報戦を展開していく3部構成になっている。
しかも、いずれも現実に起こった近年の出来事を下敷きにしているだけに、おおいに関心がもたれるところ。
2018年3月、英国で起こった亡命ロシア人スパイの毒殺未遂事件。同年5月、トランプ大統領が発表した、イランとの核合意からの離脱。さらに同6月、シンガポールで行われた米朝首脳会談が俎上に載っている。
このとき、表向きの外交交渉の裏側で、情報機関はどのように動いたのか。各国情報機関と太いパイプを持つ、フォーサイスならではの秘話が展開されていく。果たしてどこまでが事実で、どこまでが作家の創作なのか、興味は尽きない。
おまけに、米国、ロシアの大統領が、実名こそ記されていないが、それぞれトランプ、プーチンを思わせる人物描写になっている。さらに、イランでは最高指導者のハメネイ師、北朝鮮では金正恩が実名で登場する。彼ら国家の最高指導者を作家はどう料理するのか。
これは見ものである。
米国の電子情報収集の総本山
それでは物語を紹介しよう。
発端は、米国のメリーランド州フォート・ミードにある国家安全保障局(NSA)のコンピューターに、何者かが不正に侵入したことだった。
この地は、「米国の電子情報収集の総本山」であり、コンピューターには、米国の安全保障にとって死活的に重要な機密情報がデータベース化されている。それだけに、あらゆる防護措置が施されていた。
それがいともたやすく破られた。しかも、犯人は足跡をたどられるような電子上の痕跡を残していない。
ハッカーは、「きわめて高度な技術を持った外国の破壊工作員グループ」を想像させる。
ところが、奇妙なことに、侵入者はなにもデータを盗んでいかなかった。部外者ではアクセス不可能なはずの、難攻不落の壁(ファイアーウォール)を乗り越えながら、ただ、中身を覗いていっただけなのだ。それはなにを意味するのか。
精鋭12名が寝込みを急襲
米国は、同盟国の英国とともに、共同で捜査を行った。英国側は、フォート・ミードと同レベルの実力がある「政府通信本部(GCHQ)」が担当する。
が、容易なことでは犯人を特定できない。追跡チームはこのハッカーを、うまく逃げて捕まらないことから、「狐(フォックス)」と呼んでいた。
3か月後、英国チームは、ひょんなことから犯人の居場所を特定した。ある手がかりから、ロンドン郊外に根城をもっていることが判明したのである。
一見、無害そうに見える民家だが、武装集団が潜伏している可能性がある。午前2時、完全武装した英国陸軍の特殊空挺部隊(SAS)と米国から派遣された海軍特殊部隊(SEALs)の精鋭12名が寝込みを急襲、発砲するまでもなく、室内にいた人物を制圧した。
SASの隊長には信じられない光景が目に飛びこんできた。家にいたのは4人家族の一般市民で、ただ、ぐっすり眠っていただけである。
一家の主は公認会計士で、妻と18歳、13歳のふたりの男の子がいた。
隊長は、作戦司令にこう報告する。
「どうもこいつは信じられないようなことですよ・・・・・・」
ハッカーは、まだ高校生の長男ルークだった。自閉症を患い、普段は屋根裏部屋に閉じこもっている。唯一の生きがいがパソコンをいじることだった。
しかし、彼が扱っている装置は、スーパーコンピューターではなく、郊外の家電量販店で売られているような一般的な機種だった。それに本人の手で、いくつか改良が加えられている。これでどうして、高度なデータベースをハッキングできたのか?
作戦名は「トロイの木馬」
ルークは、まぎれもなく天才だった。彼は、安全保障にかかわるデータベースの中身には、なんの関心もなかった。ただ、ガードが堅いコンピューター・システムの中に、入ってみたかっただけなのだ。
彼の特殊な能力には、政府通信本部(GCHQ)の専門家もたじたじだった。誰も彼のパソコン操作をマネできない。彼は、世界に一人しかいない才能の持ち主だった。そこに英国情報部は目をつけた。
ここで、本作の主人公、先に紹介した英国首相のアドバイザーを務めるウェストンが登場する。
米国は、ルークの身柄引き渡しを要求する。とりわけ大統領は激怒していた。犯人は終身刑にすべし。なにしろ、ハッキングされたことでシステムを再構築する必要があり、巨額の損失を被ったのである。
英国は要求を拒否した。その代わりに、ウェストンは英国首相の名代としてホワイトハウスを訪れ、米国大統領にある取引を申し出る。
大統領執務室でのやりとりは愉快だ。
ウェストンは、さりげなく言う。
「わたしも『取引の芸術』(邦題「トランプ自伝―不動産王にビジネスを学ぶ」)を拝読しました・・・」
〈大統領は顔を輝かせた。自慢の著書を賞賛されれば上機嫌になるしかない。〉
「ブロンドの髪をいただく大きな顔」の大統領は、取引に応じた。
取引の内容は、英国の情報機関は、この天才ハッカーを使って敵対する国家のコンピューター・システムに侵入する。そこで得られた成果を、両国で共有しようというもの。
ウェストンに全権委任されたこの作戦は、「トロイの木馬」と命名され、前代未聞のサイバー戦が展開されることになる。
敵を騙し、裏をかき、出し抜く方法
物語の冒頭部分を紹介したが、ここまで読んだ本稿の読者は、ハイテク技術満載のスパイ小説と思われるかもしれない。
なるほど、作家は〈現代の諜報戦においてはサイバースペースが主要な舞台となっている〉と記しており、各国の情報機関が最先端の電子機器を用いて、いかに情報収集しているか、その有り様を詳述している。
しかし、それが本作の読みどころではない。
ハイテク技術は、情報収集のための手段にすぎない。その情報をもとに、いかなる作戦を展開していくか。敵国の思惑を潰すために、各国情報機関の工作員が命を賭けてしのぎをけずっていく。そこに生身の人間ドラマがあり、フォーサイスは彼らの暗闘を、見事に活写している。それこそが本作の醍醐味である。
なかでも、主人公のウェストンは魅力的に描かれている。
〈堅実な家庭の出、パブリック・スクール出身、優秀な学業成績、落下傘連隊勤務〉、彼は情報部にはうってつけの人材で、もっぱらソ連と東欧衛星国を担当していた。
現役時代の彼が得意としていたのは、欺瞞工作である。
なぜ、そうなったか。作家はこう書いている。
〈長きにわたって彼の主要な敵はKGBだった。ソ連が崩壊したあとは、あの後継組織だった。KGBとその後継組織にとって、殺人、拷問、残虐行為は通常の手段である。ウェストンは、効率的に結果を出すために敵と同じ手法を使いたいという誘惑にはげしく抵抗しつづけてきた。〉
そのために、
〈ウェストンが選んだのは、敵を騙し、裏をかき、出し抜く方法だ。〉
今回の「トロイの木馬」作戦でも、敵方が暴力的な手法で反撃してくるのに対し、彼はひたすら知力を絞り、対抗していく。
だからこそ、主人公に惹きつけられる。
復活した冷戦
こののち、ウェストンと10代の天才ハッカーのコンビがどのような諜報戦を仕掛けていくか、それは是非、本作を読んで楽しんでいただきたい。
わたしが関心をもったのは、フォーサイスならではの国際情勢の分析が随所に披瀝されていることだ。
作家は、登場人物の会話のなかに自らの考えを滲ませている。
英国首相が招集した閣僚との秘密会議の場面。
外務大臣はこう発言する。
「しかし、自爆テロで人々を脅かすとは言え、イスラム過激派が主要な脅威なのではありません。・・・現在、核爆弾とそれを搭載できるミサイルを保有する国は十二か国あります。・・・三か国は対内的に独裁的、対外的に攻撃的です。北朝鮮とイランがそこに含まれますが、その中でみずからリーダーの役割を引き受けているのはロシアです。スターリン時代が終わって以来、ここまでひどい状況になったことはかつてありませんでした」
この発言を受けて、国防大臣も言う。
「外務大臣のおっしゃるとおり、冷戦が復活しているのです。われわれではなく、ロシアがその道を選んだのです。西側諸国はあらゆるレベルで挑発に見せかけた秘密攻撃を受けています」
本稿の最初に、英国で起こった亡命ロシア人スパイの毒殺未遂事件と書いたが、少しだけ補足しておく。
2018年3月、英南部ソールズベリーで暮らしていたセルゲイ・スクリパリ氏が、公園で倒れているのを発見された。彼は、英国で亡命生活を送るロシア情報機関の元大佐だった。手口は、住居のドアノブに「ノヴィチョク」という神経剤が何者かによって噴霧されていたことで、それに触れた元大佐と娘が被害にあった。
彼らは、英国が開発していた解毒剤によって一命をとりとめた。英国は、ロシアの工作員の犯行であるとして、駐英ロシア大使館員を国外追放。逆にロシアは陰謀であるとして英国を非難した。
本作では、ロシアは原子力エンジン搭載の巨大ミサイル巡洋艦をドーヴァー海峡に派遣し、英国に対して圧力行動に出る。英国はこれにどう対抗したか。
2015年、米国やEUなどは、イランが高濃縮ウランの製造を行わない見返りとして、経済制裁を緩和するとの合意をかわしていた。
そのイランとの約束を、2018年、トランプ大統領は一方的に破棄したとして、同盟国からも批判の声があがったが、フォーサイスは、〈イランは密かにこの合意を破っていた〉と断じている。
イランは砂漠の地中深く、極秘のうちに建設した巨大な施設で、兵器級のウラン濃縮を続けていた。〈それは非常に深いので大型の地中貫通爆弾にも耐えることができる。〉と作家は書いている。
北朝鮮が爆破したのは瓦礫の山
北朝鮮との諜報戦のくだりは、日本の読者にとって身近であるだけに、興味深く読めるだろう。
トランプ大統領は金正恩・最高指導者と頂上会談を行い、北朝鮮は非核化に協力したかのように、豊渓里にある核開発施設を爆破、その映像を世界に流してみせた。われわれにとって、まだ記憶に新しいところである。
英国首相とウェストンの、北朝鮮の核開発をめぐる意見交換の場面。要約してお伝えしよう。
ウェストンはこう断じる。
「・・・残念ながら、アメリカは自己欺瞞の海で泳ごうとしているように思えます」
首相が尋ねる。
「北朝鮮は完全な非核化などするはずがないということですか?」
「あれはペテンです・・・じつに巧妙な詐欺です・・・」
「なぜですか?アメリカには優秀な頭脳の持ち主もいるのに」
「しかし何人も馘になっています。ホワイトハウスの主はノーベル平和賞が欲しくてたまらないので、信じたい気持ちが勝ってしまう。詐欺が成功する前触れとしてお決まりのものです」
「なぜ西側諸国は騙されたのですか?」
「正確に言えば、アメリカの国務省とホワイトハウスが騙されたのです」
「彼らはなぜ騙されたのです?」
「騙されることを選んだからですよ、首相」
核開発施設があるとして知られた豊渓里は、すでに用済みのものだった。
「まったく無価値で、もう核実験場ではなくなっていました。世界が喝采しながら見守る中で彼らが爆破したのは瓦礫の山にすぎなかった・・・」
ウェストンの入手した情報では、北朝鮮は別の場所で核開発を進めており、あとは大陸間弾道ミサイルさえ完成させれば、いつでも西側世界を脅迫できる段階まできている。そのミサイルのロケットエンジンを供給しようとしているのが、冷戦時代に逆戻りしたロシアだったのだ。
つねに自分の勘を信じてきた
ウェストンは、彼らの野望を阻止しようとする。
ところが敵もさるもの、ロシアは、英米両国に潜ませていた二重スパイの報告から、天才ハッカーの存在を突きとめ、抹殺しようとする。
その情報は、まずイランに伝えられ、ハメネイ師はイスラム革命防衛隊所属の特殊部隊を派遣、次いで、ロシアから特殊部隊(スぺツナズ)史上、最高の狙撃手が送りこまれてくる。
このあたりの攻防は、読み応えじゅうぶん。
ウェストンは、どうやって危機を乗り越えるのか。
フォーサイスは書いている。
〈ウェストンはコンピューター到来以前にキャリアを築いた人間であり、今の諜報界では若い連中のあいだに交じる古参にすぎない。だが、昔から変わらないものもある・・・・・・ソ連の支配下にある東欧の石畳の裏通りですれ違いざまに手紙や物をやりとりするような時代は過去のものと思えるかもしれないが、適切な場所で適切な時に提供される適切な情報は今でも歴史を変えうるのである。〉
〈ウェストンは多くの危険をくぐり抜けてくるあいだ、つねに自分の勘を信じてきた。そして今までのところ、勘に裏切られたことはなかった。〉
いつの時代も、最後は個々人の力量にかかっている。
オールド世代のわたしは、主人公のアナログな活躍に、拍手喝采することしきりであった。
「ザ・フォックス」
F・フォーサイス(著)、黒原敏行(翻訳)
発行:株式会社KADOKAWA
四六版:285ページ
価格:1800円(税別)
発行日:2020年3月3日
ISBN:978-4-04-108878-4
書評 本・書籍 北朝鮮 ロシア 米国 イラン トランプ大統領 インテリジェンス フォーサイス 本 諜報機関 英国 MI6 トランプ
