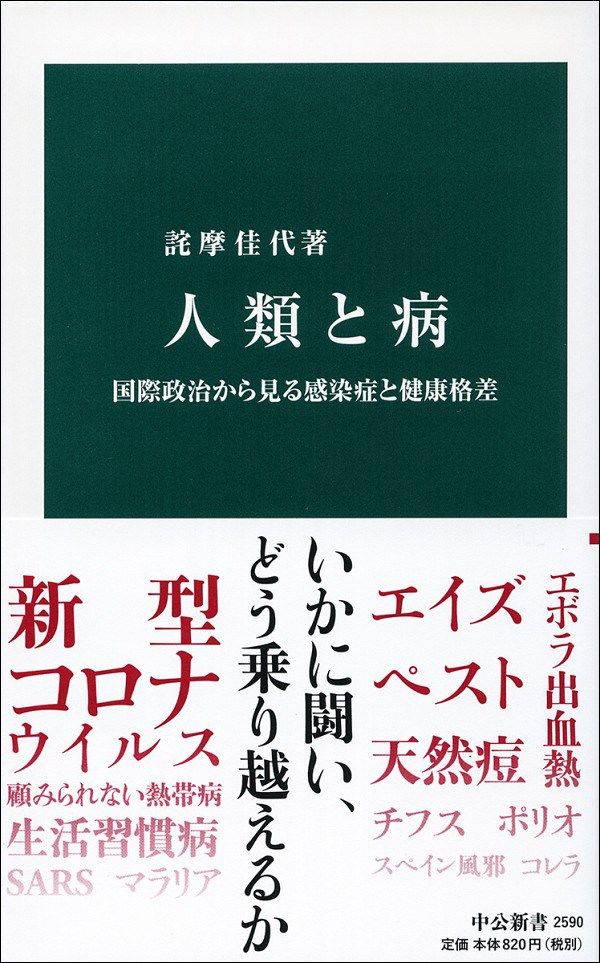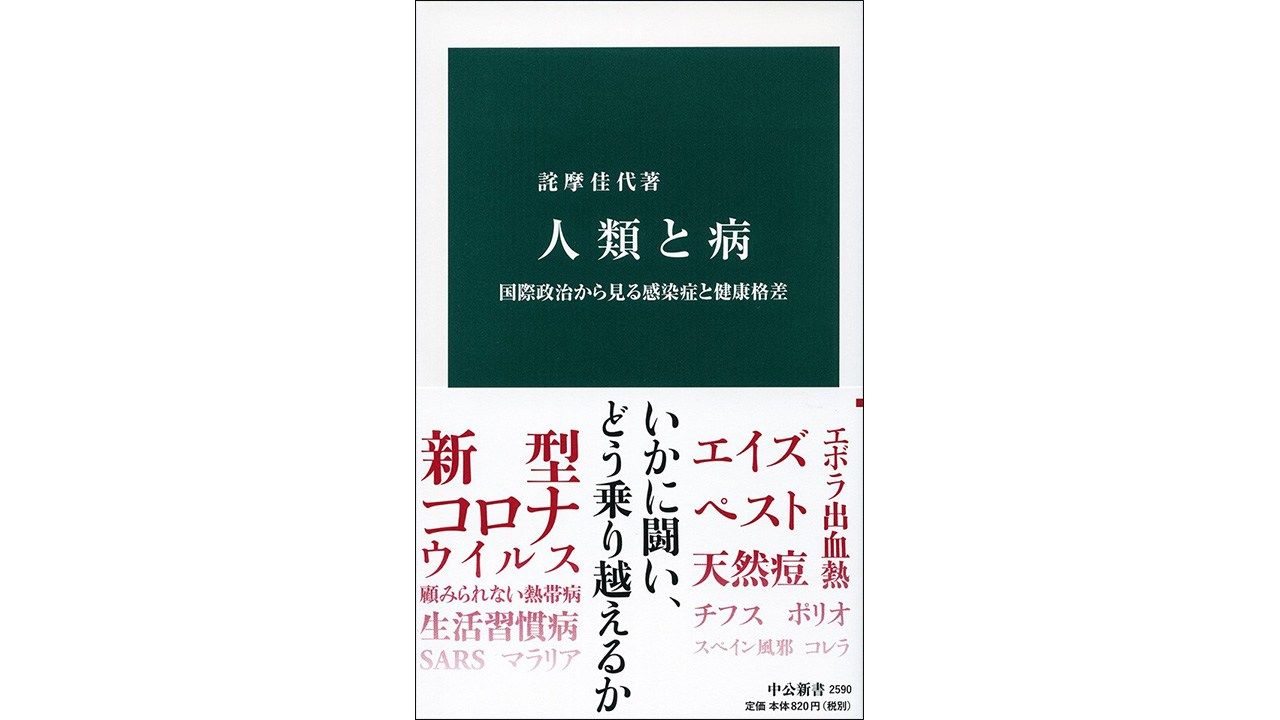
【書評】vs感染症、われらかく戦えり:詫摩佳代著『人類と病』
Books 社会 国際 医療・健康 政治・外交- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
表面化した自国第一主義
新型コロナウイルスで緊急事態宣言が出された4月以降、事態の推移とは別に、「これで世界はどう変わるか」にも関心が集まった。例えば、社会学者の大澤真幸氏は、感染症への有効な対処は国民国家のレベルでは難しいとし、「『国家を超えた連帯』のチャンス」と述べた(4月8日付朝日新聞オピニオン欄)。
先進諸国がとりあえずは第一波をやり過ごした現時点で振り返ってみると、見える風景はそれとはほど遠い。WHOへの影響力をめぐる米国と中国との対立、単一国家を目指す欧州連合(EU)でもにわかに個々の国家像が前面に出た。仕方ないことではあるが、それぞれの自国第一主義である。
目に見えぬ感染症の恐怖は、大陸、国境、州・省・都道府県、市町村、居宅…すべての「境界」を鮮明にし、世界が「グローバリゼーション」から一転、「ローカリゼーション」(局地化)に回帰してしまったかに見える。
そうした新型コロナによって見えた風景に合わせたかのように出版された『人類と病』。感染症関連の旧著の復活版が書棚に並ぶ中、国際政治や国際関係を通じて医療・福祉政策の在り方を探った新刊だ。著者は1981年生まれの研究者、東京都立大大学院教授(国際政治)で、ほかに「国際政治のなかの国際保健事業」などの著作がある。「あとがき」によれば、企画は5年前のもので、出産や子育てなどの事情で仕切り直し、今春の出版にこぎ着けた。
グローバリゼーションとともに
人類社会と感染症との歴史は古く、紀元前から続く。本書で様々な感染症が取り上げられているが、中世以降のペストとコレラを例に戦いぶりを概観する。
現在のカザフスタン辺りの風土病だったペストは14世紀以降、ヨーロッパに伝播し、多数の犠牲者を出した。ペスト菌の発見が1894年、ペストや結核に効く抗生物質ストレプトマイシンの開発が1943年だから、中世では科学的な根拠に基づく対策を望むべくもなく、汚物の処理や患者の隔離などがせいぜいだった。
その後もたびたびヨーロッパで流行し、17世紀の英国での様子は「ロビンソン・クルーソー」で知られるダニエル・デフォーの『ペスト』に詳しい。ロンドン市長が患者宅や患者との接触者の家を閉鎖(自宅監禁)したため、監視員を暴行したり、家から逃走したりする者もいたという。コロナ禍での都市封鎖や外出制限と変わらない。ワクチンや特効薬がなければ、人類が採り得る手段は今も昔も知れている。
19~20世紀に英国の植民地インドにまん延した時には、ドイツやフランスが検疫強化や禁輸で自国への侵入を防止する対抗措置を取った。英国はこうした国際圧力を受けて1897年に伝染病法を制定し、患者探索のための家宅捜索や家屋という強硬手段を取った。これはインド民衆の英国への反抗を強める結果をもたらした。
一方、コレラもヨーロッパで度々流行し、こちらは都市部での上下水道整備やし尿処理など公衆衛生インフラ整備を促す要因として働いた。
背景の一つには1869年にスエズ運河が完成して、人や物の移動条件が大きく変わったこと。本格的なグローバリゼーションの始まりである。実際、83年にコレラ菌が発見されたことで、84年の仏マルセイユでの流行がインドから英国船で持ち込まれたことを、英国も認めざるを得なくなり、経済活動への影響から検疫に消極的な姿勢に批判が集まった。感染症問題はすなわち国家間問題である、と世界ははっきり自覚したわけだ。
国際防疫体制
その結果、1851年にパリで初めて国際衛生会議が開かれ、ペスト、コレラ、黄熱病に対する措置が話し合われた。会議はフランスなどの主導で継続し、1903年には初の国際衛生協定(全184条)が締結され、領域内での発生確認時の相互通知、水際での検疫、違反行為への制裁措置など、現在のWHO体制下の防疫システムの基礎が築かれた。さらに4年後、パリに国際公衆衛生事務局も置かれた。安全保障上の国際組織が第一次世界大戦後、1920年の国際連盟設立であることを考えると、人類にとっての感染症の脅威の大きさを物語る。
さらに第一次世界大戦時のマラリア、スペイン風邪、チフスなどの感染拡大を経験して国家間協力体制は国際連盟保健機関へと強化された。第二次大戦のさなかも、優れた国際官僚の献身的な努力もあり、同機関が感染情報の提供を中心に超然的な専門組織としての立場を貫いた。
戦後、48年のWHO設立に至る経緯、そして天然痘の根絶、ポリオとの闘いなど感染症との戦いぶりが興味深く綴(つづ)られる。「二つの戦争を通じて、人類は病との闘いにおいて、国際保健協力と医学研究の重要性を認識」したと著者が言う通りだ。
戦後、この体制と機能はWHOに引き継がれた。エイズや新型インフルなどの新たな脅威と直面する中で、グローバリゼーションの限りない進展、インターネットによる情報環境革命、プライバシーなどの問題が、複雑化する国際政治とも絡んで難題を突き付け、対象感染症の拡大、WHOへの通報迅速化などの規則改正も行われてきた。そして、2020年の新型コロナウイルスである。
対立と協調
国際情勢の中にあって、感染症をめぐるWHOの対応には国家間対立や国際社会のパワーバランスが大きく投影されざるを得ない。その理由を、著者はグローバル化時代の感染症の二つの特徴に求める。
「一地域で発生した感染症が瞬く間に広がり、経済、産業、安全保障等に多面的なインパクトを与える」からであり、とりわけ「安全保障に影響を与えるということは政治指導者による政治的な関与が増えることを意味する」からである。WHOへの分担金の多寡、核開発を巡る米・イラン対立、貿易を巡る中米対立、中台問題などの緊張関係が反映されるのは仕方ないことだと言う。
それでも、「感染症の管理は国際社会において、数少ない共通項となるので、関係国の協力を深める貴重な契機となる」と指摘するように、国家間対立をはらみながらも人類共通の脅威に立ち向かう意味は大きい。歴史的にも、戦前の日本が国際連盟脱退後も連盟保健機関と協力したし、冷戦期の米ソもポリオワクチン開発で協力したように、とその例が引かれる。
ただ、健康問題もあくまで国家間関係の一側面であり、基本的には相互信頼の有無やその中身の問題だろう。これも国際政治のリアルである。重要なことは「協力することでいずれの国も利益を得やすい」ことであり、理由のいかんを問わず、あらゆる人間の生命に直接関わる問題は共通の最優先事項である。小舟での殴り合いも、舟底に穴が開けば布や木っ端を持ち寄って塞ぎ、その後に殴り合いを再開するようなものなのか。
この部分に当たる本書3章の4「新型コロナウイルスと国際政治」は時期的に、脱稿直前に急きょ書かれたものだろう。混沌の新たなステージを迎えている現在の国際環境にあって、世界的な感染症対策は最優先課題である。この新型コロナ禍がひと段落したところで、あらためて、このテーマに絞って経緯を検証し、提言するような論考をぜひとも期待したいと思う。
人類と病
詫摩佳代(著)
発行:中央公論新社
新書判:256ページ
価格:820円(税別)
発行日:2020年3月6日
ISBN:978-4-12-102590-6