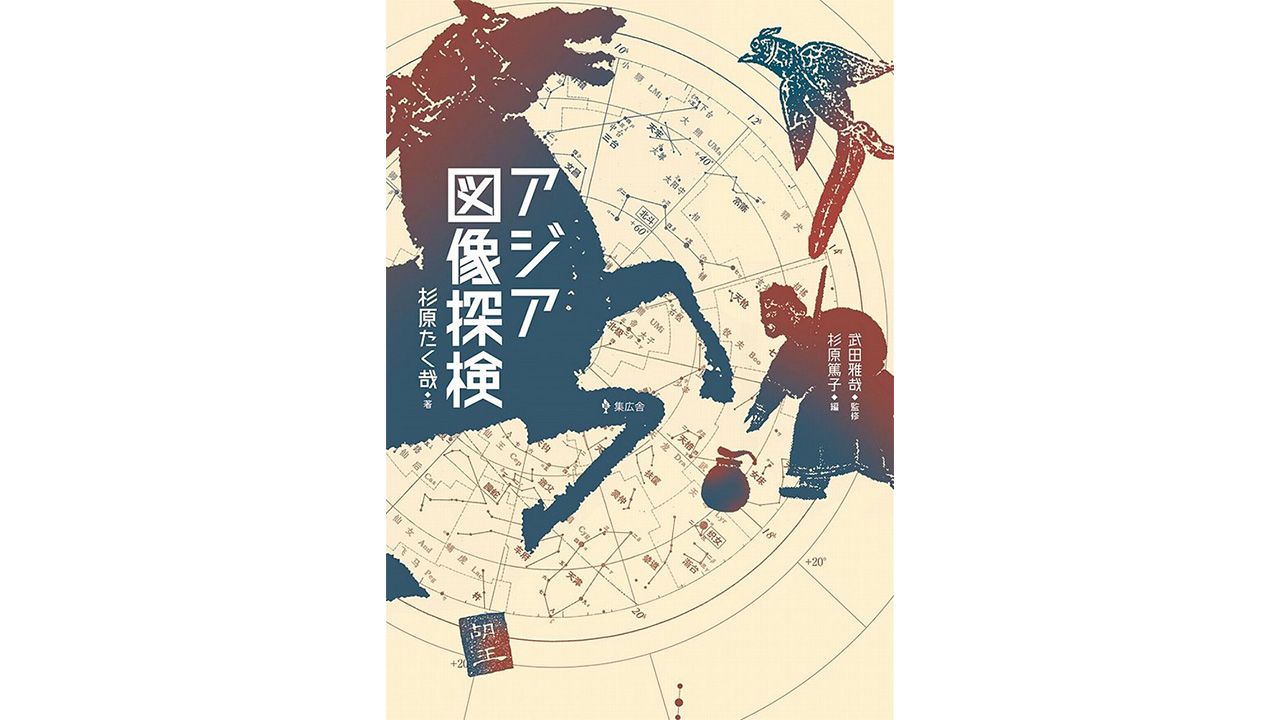
【書評】古今東西の美術を渉猟した遺作:杉原たく哉著『アジア図像探検』
Books 文化 歴史 国際 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
“婦唱夫随”による同志愛の結晶
図像とは、人間が図で表現した視覚的な「かたち」を意味する。日本では仏像、曼荼羅(まんだら)など仏教図像を指すこともある。西洋ではイコンと呼ばれることが多い。図像は歴史的にキリスト教など宗教や文化とも密接な関係がある。
著者、杉原たく哉氏は中国の美術を軸に古代から中世、近世、近代、現代へと時空を超越して「図像学(イコノグラフィ)」を探求したことで知られる。対象とする図像の範囲も広い。中国の漢代の墓など石材に浮き彫りや線刻を施した画像石とその拓本、肖像画、彫刻、建造物などを丹念に観察する“眼力”は鋭い。同時に、古今東西の美術に関する文献や史料を丁寧に渉猟する正統的な研究姿勢を貫いた。
人類の長い歴史において、美術が主に担ってきたのは「権力メディア」としての役割だったというのが著者の持論。言語や画像などのメディアは「命令と支配のために人類が生み出した文化ツール」と喝破し、こうした観点から図像学に挑んでいた。
ところが、2016年5月31日、がんのため61歳でこの世を去った。それから4年。本書が刊行されるまでには曲折があった。
杉原篤子夫人は遺作を何とか本の形にしようと決意したものの、出版社探しなどで難航した。こうした中、著者を学究の「大哥(あにき)」と慕っていた武田雅哉氏(北海道大学大学院教授)が監修者として手を差し伸べた。その結果、4年目の命日、発行に漕ぎつけたのである。
著者は生前、篤子夫人と共同で論文を発表している。図像研究の同志であり、本書の編者となった夫人はあとがきで「この本を亡き夫、杉原たく哉へ捧げます」と記す。
本書はいわば夫婦愛、同志愛が結実したものだ。
軽妙洒脱な連載エッセイが魅力
故杉原たく哉氏は1954年東京生まれ。早稲田大学大学院博士課程を修了した。早大文学部助手・講師をはじめ、お茶の水女子、多摩美術、北海道などの各大学・大学院で非常勤講師を務めた。
図像学の研究成果を遊び心も交えて分かりやすく伝える術にも長けていた。『中華図像遊覧』(2000年、大修館書店)、『いま見ても新しい古代中国の造形』(2001年、小学館)、『しあわせ絵あわせ音あわせ――中国ハッピー図像入門』(2006年、NHK出版)、『天狗はどこから来たか』(2007年、大修館書店)など一般向けの著書も少なくない。
今回、遺作をまとめた本書は二部構成になっている。第一部は、月刊『書道界』(藤樹社)に2004年2月号から16年4月号まで12年間にわたり連載した「アジア図像探検」である。全147回に及んだ。1回500字ほどの口語体のショート・エッセイで、図像、拓本、模写、写真、地図など何らかの図版がほぼ毎回掲載されている。
第二部は「論文選」で、「七星剣の図様とその思想」、「漢代画像石に見られる胡人の諸相 胡漢交戦図を中心に」、「神農図の成立と展開」など五篇の論文が収められている。
監修者の武田教授は次のように指南する。
「あえていうならば、第一部は『軟(なん)』、第二部は『硬(こう)』であろうか。硬とはいえ、門外漢を寄せつけぬたぐいの『論文』でないことは、一読すればおわかりであろう。硬と軟、どちらから読んでもよろしいし、どちらかだけ読んでもよろしい。だが、両者を併読して見えてくるのは、軽妙洒脱なエッセイの根底には、信頼できる研究活動によって保証された学問的根拠がしっかりあるということである」
「アジア図像探検」は、短くて軽めの文章ですが、その中に様々な知識やアイデアが凝縮されています――。
篤子夫人があとがきでこう説明しているように、147篇の連載エッセイには「隠れた文字」、「桑から生まれた子供」、「馬は飛ぶか」、「三国志と日本」、「毛沢東のイメージ論」、「『かな』の文化発信力」など、おやっと驚く学説や面白い逸話が次々に登場する。これが本書の最大の魅力だろう。
モン・サン=ミシェルと安土城
著者自身は「アジア図像探検」の内容について「奇想天外、驚天動地の愚説の開陳(かいちん)」と諧謔的に謙遜するが、歴史の新解釈やユニークな異説は光彩を放つ。そのいくつかを紹介したい。
筆頭は、安土城の「モン・サン=ミシェル祖型説」である。織田信長が天下統一を目標に、天正4年(1576年)から約3年の歳月をかけて琵琶湖の東岸に築城したのが安土城。「標高二〇〇メートルの山上に建つ、六階建て高さ約五〇メートルほどの高層建築」だった安土城は、「天主」と呼ぶ本格的な天守閣を初めて設けた日本建築史上、画期的な城となった。
このモデルになったのが、世界遺産(文化遺産)に登録されているフランスのカトリックの巡礼地、モン・サン=ミシェルだというのだ。小島にそびえ立つ壮麗な修道院は、大天使ミカエルのお告げで708年に最初の礼拝堂が建てられたと伝えられる。増改築を重ね、英仏百年戦争(1339~1453年)の際には要塞化された歴史がある。
「モン・サン=ミシェルとは『聖ミカエルの山』という意味です。ミカエルはキリスト教の大天使の一人。悪魔や悪龍と戦い撃退する頼もしき戦闘神・守護神です。古来、イスラエルやキリスト教徒の守護神となり、英仏百年戦争のときにはフランスの守護神でもありました」
「この大天使ミカエルが『日本の守護神』でもあることをご存じでしょうか。一五四九年に来日したフランシスコ・ザビエルがそう決め、以来キリスト教世界では常識となっています」
ザビエル来日後、ポルトガルからやってきたイエズス会宣教師ルイス・フロイスは永禄12年(1569年)、キリシタンへの支援を得ようと岐阜城で信長に面会した。著者はそのときの様子をこう推理する。
「おそらくフロイスは、ここぞとばかりに、信長を日本のミカエルと讃え、百年戦争勝利のシンボルであるモン・サン=ミシェルの情報も伝えたと私は想像しています」
旧「ポルトガル領」日本に警鐘
大航海時代、スペインとポルトガルが1494年のトルデシリャス条約で、世界を両国で東西二分割することを決めた史実は人口に膾炙(かいしゃ)している。しかし、日本がかつてポルトガル領にされていたということは意外に知られていない。
「十六世紀後半のヨーロッパでは、日本人の知らないうちに、立派にポルトガル領として認知されていたのです」
「一五七五年にローマ教皇グレゴリウス十三世が大勅書によって、日本がマカオ司教区の管轄下にあることを認定し、日本のキリシタン教会の保護者がポルトガル国王であることを確定しています」
その“宗主国”ポルトガルは1755年、大地震に襲われた。欧州史上最大の自然災害といわれる「リスボン大震災」で、首都リスボンには大津波が押し寄せた。多くの人命が失われ、建築群が崩壊する破壊的な打撃を受けた。
「海洋帝国ポルトガルは、艦船と港湾設備も失い、世界史の表舞台から退場していきました」
「アジア図像探検」連載の第99回(初出は『書道界』2012年4月号)では、大地震と大津波でポルトガルの王宮などが崩壊していく図版を掲載。この回で著者はこう警鐘を鳴らす。
「最近日本の報道では、首都直下型地震が遠からず起こるといわれています。国家財政は火の車、東日本大震災の痛手、ここに首都圏壊滅(かいめつ)が加われば、日本史上最大の危機となるはずです。『想定外』ではすまされぬ、国家存亡の瀬戸際に、いま私たちは立たされているのです」
新たなバーナード・リーチ像
日本の民芸運動に大きな影響を与えたイギリス人陶芸家、バーナード・リーチ(1887-1979年)の新たな人物像を浮かび上がらせたことも特筆に値する。
「バーナード・リーチと漢代画像」と題する連載は、「アジア図像探検」で12回(第135~146回)続いた。香港で生まれ、日本やシンガポールで育ち、英国で教育を受けたリーチは、白樺派の武者小路実篤や柳宗悦、浜田庄司らとの親交が厚かったため、日本とのつながりを強調されがちだが、実は中国との関係が深いという。
リーチは1914年から16年にかけて、中国の北京に妻子とともに滞在した。この時期に漢代の墓のレリーフ「画像石」に出合う。拓本に写し取られた画像石の絵柄や文様などが、リーチの陶芸作品の“元ネタ”になったというのが著者の仮説である。
リーチの作品である陶板「Bird」と画像石の厨房図、代表作「生命の樹」と画像石の扶桑樹(ふそうじゅ)、「魚乗勇士図陶板」と画像石の戦闘部隊の兵士……。リーチ作品の写真と画像石の拓本をそれぞれ対比して掲載し、次々に元ネタを実証的に解き明かす手法は小気味よい。1991年に中国山東省で仏教史蹟を調査するなど、漢代画像石に詳しい著者のまさに真骨頂である。
リーチの陶芸には「東洋と西洋の融合」というテーマが通底しているとも指摘する。例えばリーチが作ったタイルの一つに、仲良く並んで泳ぐ二匹の魚が描かれている。この作品の元ネタは有名な画像石に登場する比目魚(ひもくぎょ)だが、「西洋では双魚文(そうぎょもん)は星座の魚座のシンボルであり、またキリスト教も意味しています」。比目魚は中国では「仲の良い夫婦」の象徴となり、日本では「ひらめ」とも読む。
未完の大作「東洋と西洋の融合」
著者の絶筆は「アジア図像探検」連載の第147回(『書道界』2016年4月号)で、見出しは「自然観の東西①」である。この中で「自然」に対する考え方が西洋と東洋とは大きく異なっていると問題提起した。
「東洋では、自然のなかに神や真理が宿っており、それを絵に写し取ったり、その絵を飾ることによって、崇高なるものに近づくことができると考えていました。人間よりも自然の方がはるかに偉大だと思っていたからです。道教の『無為自然』もそんな考え方から出てきました」
そして、こう続ける。「それが西洋では正反対、自然の地位は極めて低いものでした。(続)」。これが最後の一行である。著者が「自然観の東西②」以降の続編を書く意思があったのは明らかだ。
「アジアの図像探検」から、バーナード・リーチを踏襲して「東洋と西洋の融合」という世界規模のテーマに足を踏み入れようとしていたのかもしれない。
未完の大作「アジア図像探検」について、監修者の武田教授は本書末尾の「解説にかえて」でこう弔詞を送る。
「杉原氏の脳内に描かれていた、これから執筆すべき大いなる仕事のための構想メモのようにも読める。バーナード・リーチはじめ、いくつかのテーマは、将来的に、それぞれが一冊の本として上梓(じょうし)される予定だったのではあるまいか。あれこれ想像するにつけ、まだまだこれから、いくつもの大業を成しえたであろう、氏の早すぎる旅立ちには、無念を叫ぶしかない」
アジア図像探検
杉原 たく哉(著)、武田 雅哉(監修)、杉原 篤子(編)
発行:集広舎
A5判:288ページ
価格:2200円(税抜き)
発行日:2020年5月31日
ISBN:978-4-904213-92-6
