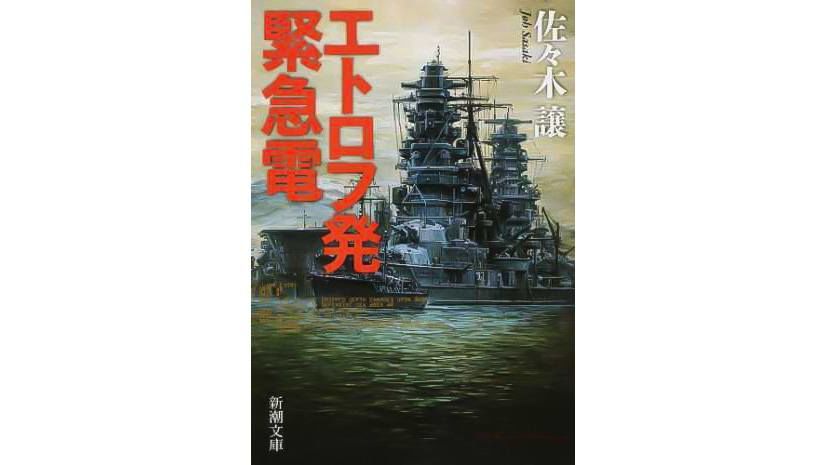
【書評】太平洋戦争前夜の日米諜報戦を描いた傑作:佐々木譲著『エトロフ発緊急電』
Books 政治・外交 社会 歴史- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
〈雪がちらついている。暗鬱な曇り空の下、霧が単冠湾の海面からわきたっていた。〉
斉藤賢一郎は、停泊する艦船を見つめている。
〈空母赤城の艦橋上では、しきりに信号灯が点滅していた。鈍いうなり声のような音が、霧を通して響きわたってくる。(略)駆逐艦が白く波をけたてて前進を始めた。とうとう出撃のようだ。その奥で、戦艦や航空母艦も微速前進を始めている。〉
時あたかも、昭和16年11月26日払暁のことだった。
このあと、賢一郎はすばやく行動を開始する。そこに今回の任務のすべてがかかっていた。
これが、この物語のクライマックスとなる場面である。
今年8月に終戦75年を迎えるにあたり、佐々木譲の「戦争三部作」を紹介したい。本作は第二部にあたるものだが、初出は平成元年11月。その後に文庫化されて、現在も版を重ねている傑作である。
昭和16年夏、もはや開戦は必至と見た米海軍の情報機関は、日本に工作員を送り込み、戦端の火蓋がいつ、どこで切られるのか、軍部の動向を探っていた。
その一方で、日本の憲兵隊はスパイ活動の取り締まりを強化し、ついには、ひとりの男を追い詰めていく。その熾烈な攻防戦が、本作の読みどころである。
それでは物語の世界に入っていこう。
キリスト教宣教師が工作員
1941(昭和16)年1月のことである。
東京・芝区三田松坂町の屋敷町の一角に質素なキリスト教会がある。
宣教師の名前は、ロバート・スレンセンという。米国のプロテスタント教団から派遣されてきたスウェーデン系の青年で、今年30歳になったばかりだ。
ある日、役人風の中年男性が密かにスレンセンを訪ねてきた。男は驚くべき情報を口にする。
「日本海軍は対米戦が始まるとき、奇襲先制で米国海軍を叩くでしょう」「攻撃目標は、ハワイの真珠湾です」
彼は、その情報を「ぐうたら野郎(グーフボール)」に伝えてほしいと告げた。
グーフボールは、米国海軍省情報部に所属するアーノルド・テイラー少佐のニックネームである。スレンセンは、少佐の手配で東京に送り込まれた米国の工作員だった。
中年男性は続けて言う。彼は日本の行く末を憂いている。
「不幸にもこの作戦が成功したら、逆に帝国の破滅は避けられません」
このうえは、米国の力を借りてでも開戦を阻止するしかない。それが極秘情報を漏らした意図だった。
おそらく作戦内容を知る、中央官庁の高官なのであろう。
男はついに名乗らず、「反っ歯(バッキ―)」とだけ言った。彼はアメリカ駐在時代に、テイラー少佐にリクルートされた協力者であった。
この開戦情報は、ただちに本国の海軍省に伝達されたが、同省の幹部は荒唐無稽と黙殺する。ただひとり、テイラー少佐は真珠湾奇襲情報の真偽を確かめるべく、スレンセンにメッセージを送った。
これが物語の発端である。
「無政府主義者」でニヒリスト
テイラー少佐は、スレンセンの元に工作員を送ることにした。
それが本稿の冒頭に登場した本作の主人公、ケニー・サイトウこと斉藤賢一郎である。
彼は1911年米国生まれの日系2世で、開戦の年に30歳となる。
両親は米国永住権を持つ移民、父親の職業は庭師だった。
賢一郎は、地元の高校を卒業後、ワシントン州シアトルで船員となった。1935年、船員組合の活動中、暴行事件で逮捕歴あり。37年内戦中のスペインに渡り国際義勇軍に参加、内戦終結後の40年初頭に帰国し、今ではサンフランシスコの暗黒街で殺し屋になっていた。
情報部対日工作チームのテイラー少佐は、日本に送る工作員の候補として賢一郎に目をつけていた。外見が日本人で不自由なく日本語を話せる、しかも腕の立つ男。
〈頬がこけ、蒙古人特有の高い頬骨が目立っていた。肌は赤く陽に灼けている。暗いまなざしの、どこか人を拒むような印象のある男だった。〉
彼は「無政府主義者」でニヒリストだった。大学進学を望んでいたが、日系人に対する差別で奨学金を受けることができず、父親の細々とした稼ぎでは諦めざるをえなかった。スペイン内戦では味方の裏切りを経験した。もはや彼が忠誠を誓う国はどこにもなかった。
賢一郎は、依頼によって港湾労働者組合を牛耳るボスを射殺、その直後、監視していた海軍情報部員によって身柄を拘束される。
そのまま殺人の容疑者として警察に引き渡されるか、さもなければテイラー少佐の指令を受け入れて、スパイとなって日本に潜入するか。自由の身となるためには、賢一郎に選択肢はなかった。
どこか細長い島の一部
賢一郎の任務は、「日本海軍の動向、それも艦隊の移動に関わるような情報」を探ることだった。真珠湾を奇襲するのであれば、艦隊はどの港から出航し、どの航路をたどってハワイを目指すのか。
1941年9月末、賢一郎は、マニラから貨物船で横浜港に到着した。
港で金森と名乗る男が出迎えた。
〈鼻が曲がり、眉がないのは、あるいはひどく殴られたり虐待された名残なのかもしれない〉
金森は朝鮮半島から日本に渡り、九州の炭鉱で働いていたが、過酷な労働に反逆し、脱走して東京に潜伏していた。
この男は、祖国を滅ぼし、家族を引き裂いた日本という国への復讐心から、自らの意志で米国の工作員になった。
賢一郎は金森から身分証明書と配給手帳を受け取り、地方から東京へ職探しに来たという偽装身分で、ひとまず金森と同じ浅草の下宿屋に住むことになる。
翌々日、賢一郎はテイラー少佐の指示に従い、宣教師のスレンセンと会う。彼もまた、悲しい過去を背負い、工作員になっていた。1937年12月、中国の南京にYMCAの英語教師として派遣されていたとき、日本軍が南京を攻略。彼には中国人の美しい婚約者がいたが、日本兵に虐殺されていたのだった。
ここから先、日本海軍の出撃地を探るまでが、物語前半の焦点である。
10月ある日の未明、賢一郎と金森は、東京・麻布にある軍令部勤務の中尉の自宅に侵入した。黒い革鞄のなかに、海図の青焼きと通信封鎖と機密保持に関する書類が入っていた。海図は、
〈どこか細長い島の一部のようだ。大きな湾が中央にあり、細かく数字が書きこまれている。水深を意味する数字なのだろう。〉
これは機動部隊の集結地なのか。地名が印刷されているが、賢一郎には読めない漢字だった。持ち出すわけにはいかないので、記憶にしっかりと焼き付けた。
青森から青函連絡船で・・・
同月、警視庁特高部の手によりソ連のスパイ組織が一斉検挙され、首謀者のリヒャルト・ゾルゲが18日に逮捕された。
特高部だけでなく、憲兵隊のスパイの取り締まり、監視の目は日を追って厳しいものになっていく。
金森は、かねてより不審者として憲兵隊にマークされていた。
そのために、賢一郎は苦難の単独行を強いられていく。
賢一郎は、記憶をたよりに日本の地図を凝視した。日本列島の海岸線をくまなく調べ、やがて見覚えのある島を見つけ出した。
〈千島列島の、南側から数えてふたつ目の島だった。択捉島。奇妙な数字が書きこんであった湾には、単冠湾、と記されていた。〉
11月15日、スレンセンの教会に身を隠していた賢一郎に、テイラー少佐から新たな指令が下される。
「たったひとつだけ。日本海軍主力部隊の動きを見張ることです。見張って、その動きを米国へ打電することです」
と、スレンセンは賢一郎に伝える。
行先は、択捉島。
〈どうやらこれが、自分の最終任務になりそうだ。テイラー少佐から指示されていたのは、日本海軍の動向についての決定的な通報一本でもいい、とのことだった。米国海軍基地の奇襲攻撃に向かう艦隊の出撃を通報することは、まちがいなくその決定的な一本と言えるだろう。〉
賢一郎は旅立った。スレンセンが準備していた携帯型無線機を携えて。電源は現地で調達するしかない。
予定では、上野から夜行列車で青森に向かい、青森から青函連絡船で函館に行く。そこから択捉島行きの連絡船に乗るか、漁船をチャーターするか。
ところが、その道行は変更せざるをえなくなる。
賢一郎が出立してまもなく、東京憲兵隊の秋庭少佐と磯田軍曹が教会を急襲した。スレンセンが金森と密会しているところを目撃されていたのだ。
屋根裏部屋から、賢一郎が青森に向かったことを示唆するメモが見つかった。秋庭中佐は命じた。
「磯田。お前にはすぐにでも東京を離れてもらうことになる」
スレンセンには過酷な運命が待っていた。
ここから、日本の防諜機関による追跡劇が始まる。途中、追われていることに気づいた賢一郎は、知力と体力を振り絞り、ひたすら択捉島を目指していく。
追手をどうかわすのか。どうやって絶海の孤島にたどり着こうというのか。いくつもの難関が待ち受けている。このあたりの展開は読者に息つく暇を与えない、本作の大きなヤマ場である。
ロシア人船員との間に生まれた娘
舞台は択捉島へと移る。
本作の重要な登場人物のひとり、岡谷ゆきは、択捉島の東海岸、単冠湾に面した小さな漁村で生まれた。
彼女はたくましくも、暗い影のある美しい女性として描かれる。
ゆきは、母親とロシア人船員との間に生まれた混血児だった。父親の名は、戸籍にない。ゆきの母親が身籠ったとも知らず、故国へ帰っていったのだ。
世間体を慮って、彼女は伯父の家に預けられて育った。6歳のとき、実家で駅逓を管理する祖父が脳溢血で倒れ、母親は自殺した。
駅逓とは国の施設である。権利を買った取扱人が、宿泊用の建物と官馬を預かり、運営する。馬しか交通手段のない孤島には欠かせない制度であった。
彼女は駅逓を継いだ伯父夫婦とともに、実家で暮らすようになる。世帯20戸ばかりの小さな集落だった。産業といえば、夏場だけ操業する鯨の解体処理と缶詰のための工場があるだけだ。
根室の高等女学校を卒業したゆきは、実家に戻り、駅逓の仕事を手伝っていた。19歳のとき、泊り客だった妻子ある写真家を追って函館に出奔する。村では母親の血を引いていると揶揄された。
しかし、幸せは長続きせず、カフェの女給などをして糊口をしのぐうち、伯父の訃報に接し、5年ぶりに帰郷する。
そのまま、ゆきは駅逓の権利を引き継ぎ、クリル人の青年宣造とともに家業を切り盛りするようになっていた。
択捉島には、これまで海軍の小さな航空部隊がおかれているだけだった。開戦前夜、機密保持のため島は完全に封鎖される。海上交通を遮断され、湾に通じる道路はすべて通行止め、電話、無線など外部との通信手段も一切、閉ざされた。よそ者が入り込む隙はない。
1941年12月26日の単冠湾
いよいよ物語はクライマックスへ向かう。
賢一郎は、瀕死の状態で択捉島に漂着し、ゆきの駅逓で介抱されていた。彼女は賢一郎の素性を知らないし、遭難した船員だと思っている。やがて、東京憲兵隊の磯田軍曹も、この島にたどり着く。
帝国海軍の機動部隊が、続々と単冠湾に集結し始めた。
はたしていつ出航するのか。そのとき、賢一郎はどうやって目撃情報を米国に送信するつもりなのか。
いくつも乗り越えなければならない試練がある。追手はすぐそこまで迫っていた――。
佐々木譲の出世作となった戦争三部作のうち、第一部の「ベルリン飛行指令」は、欧州戦線で苦戦するヒトラーに、日本海軍が零式戦闘機を送るという冒険譚である。その任務を負った敏腕パイロットが、単身ベルリンをめざして零戦を駆り、決死の飛行を試みる。
第三部の「ストックホルムの密使」は、終戦工作をめぐる諜報戦である。敗戦必至の情勢下、あくまで本土決戦を主張する軍部に対し、スウェーデンの海軍駐在武官が、原爆投下とソ連参戦の情報、さらに同国王室による和平仲介工作を本国に伝達するため密使を立てる。
この三部作には、共通する人物が何人か登場するが、それもお楽しみのひとつである。この夏の読書に、是非お勧めしたい。極上のエンタメを味わえると思う。
本作に戻れば、
〈単冠湾の海面には相変わらず小雪が降りしきり、霧は湾の外洋を隠している。灰色の濃淡だけで描き分けることのできる冬の景色。単調で湿ってぬくみのない、辺境の島の冬の朝の光景だった。〉
これが、斉藤が最後に目にした11月26日の単冠湾である。
本作には、悲しい過去を背負った人々が、それぞれの使命に従い懸命に生き抜いていく様が、生き生きと描かれている。
そしてまた、この作品をより味わい深いものにしているのが、択捉島の四季折々の風景を作家が見事に写し取っていることだ。
本書を読むと、是非、旅してみたくなる。
それはいまのところ叶わない願望にすぎない。われわれが、その荒涼たる風景を目にすることのできる日は来るのだろうか。
「エトロフ発緊急電」
佐々木譲(著)
発行:新潮社
文庫版:741ページ
価格:990円(税抜き)
発行日:1994年1月25日
ISBN:978-4-10-122312-4
