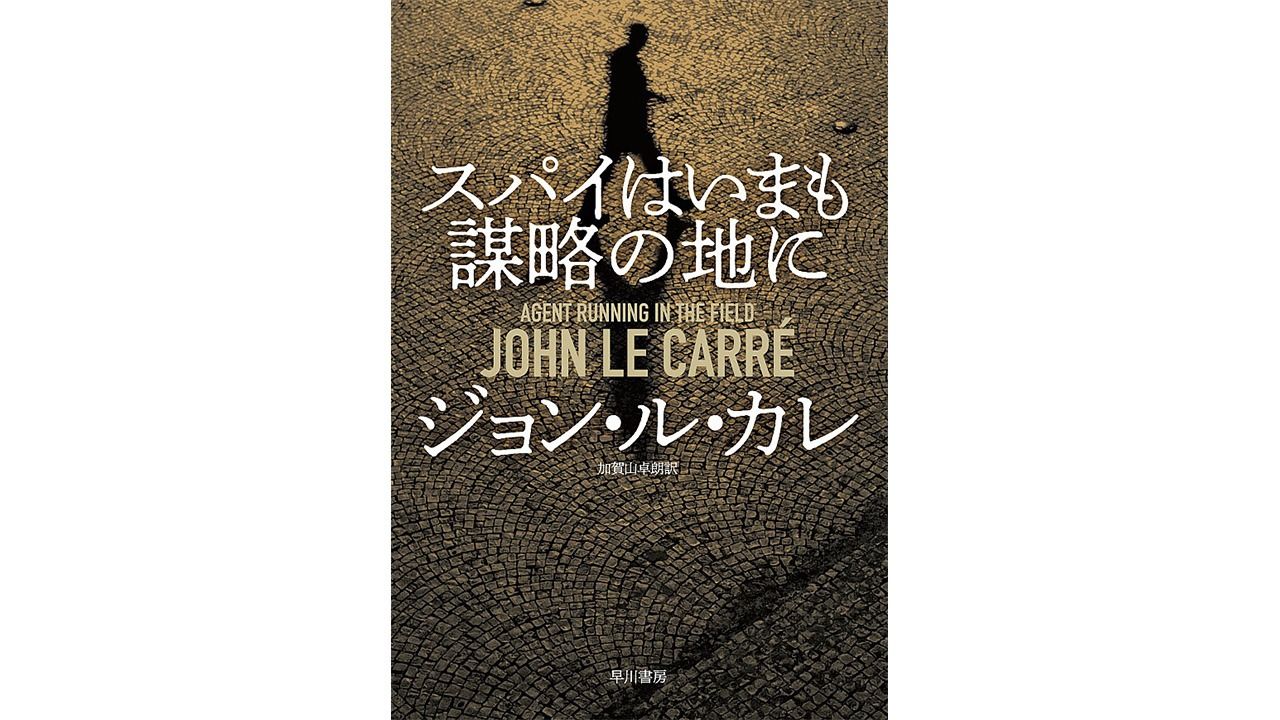
【書評】熟練スパイの流儀:ジョン・ル・カレ著『スパイはいまも謀略の地に』
Books 政治・外交 国際 エンタメ- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
スパイ小説の巨匠ジョン・ル・カレの最新作が邦訳された。88歳にしてその筆致はいささかも衰えず、老練な味わい深い作品に仕上がっている。これはファンならずとも、必読の書といえるだろう。
主人公のナットは40代後半、そろそろ一線から身を引く年齢にさしかかった熟練のスパイだ。
デスクワークが大嫌いで、もっぱら現場の情報部員として、モスクワをはじめ周辺諸国の大使館に外交官と偽って20年以上、主にロシアを標的にした諜報活動に携わってきた。成果は十分に上げている。
しかし、ついに年貢の納め時がやってきた。ナットは本国に呼び戻される。
時あたかも、イギリス国内はブレグジットで揺れていた。アメリカのトランプ大統領はブレグジット推進派を後押しし、ロシアのプーチン大統領はロンドンでのスパイ活動を活発化させていた。これが物語の背景である。
ちなみに、イギリスが正式に欧州連合(EU)から離脱するのは、2020年1月31日のことだ。
ナットの勤務評価には「規律に素直にしたがうほうではない」と記録されているが、彼には現場一筋に歩んできたスパイとしての矜持がある。各勤務地で、
〈あらゆる種類の秘密要員をリクルートし、運用してきた。政策決定のハイ・テーブルには呼ばれたことがなく、それを喜んでいる。生まれながらの要員運用者は一匹狼だ。ロンドンから命令は受けるかもしれないが、現場に出れば、己の運命と配下の要員の運命をみずから決する。〉
それが彼の、仕事の流儀である。
停泊地は残されていない
帰国まもなく、ナットは本部の人事課に呼ばれる。
覚悟は決めていた。
〈・・・現役時代が終われば、年季の入った四十代後半の熟練のスパイにたいした停泊地は残されていない〉
ナットは人事課のモイラに、ダメ元で聞いてみる。
「経験豊富な珍客は必要ないかな?ネイティブ並みにロシア語が話せて、指示ひとつでどこへでも飛んでいき、誰もロシア語をひと言も話さない駅にひょっこり現れたロシアの潜在的な亡命者や諜報員に最初に対応する、私みたいな人間は?」
しかし、モイラの返事はつれないものだった。彼女は言う。
「ロシア課の平均年齢は、ブリンを入れても三十三歳。たいてい博士号を持っていて、全員活発な頭脳の持ち主で、全員コンピュータの達人よ。いくらあなたがあらゆる点で完璧でも、そうした基準は満たしていない。でしょう、ナット?」
ブリン・ジョーダンは、ナットより10歳年上のボスで、ロシア課を牛耳る実力者である。
いまの組織は、若くてITに習熟した人材を必要としているのか。
ナットは、ブリンと交渉しようかと考えるが、モイラが先手を打つ。
「ブリン・ジョーダンは、いまこのときもワシントンDCにどっぷり首まで浸かってるわ。トランプ大統領配下の諜報コミュニティとの〃特別な関係〃をブレグジット後も存続させるために、ブリンしかできないことをしている。だから何があっても邪魔してはいけない」
そしてモイラは、こうダメ押しをする。
「ブリンからは、あなたに哀悼の意を表し、くれぐれもよろしくということだった」
万事休す。これまでの稼業とは無縁の、民間の働き口を斡旋してもらうしかないのか。ところがモイラは、意外なことを言う。
「ひとつだけ空きがあるの。・・・」
ロンドン総局のなかの閑職
それがイギリス国内全域をカバーする、ロンドン総局のなかの「安息所」(ヘイブン)と揶揄される部署だった。
そこは、お払い箱になったスパイの吹き溜まりで、長い間、開店休業状態。年老いた管理者の後任として、組織を立て直してほしいというのが上層部の要求だが、つまりは閑職にちがいない。
ナットを呼んだのは、新たにロンドン総局長に就任したドム・トレンチだった。まだまだ利用できる駒と踏んだか。
ドムは、ナットがブタペストに勤務していたときの直属の上司である。なかなかに腹黒く、部下の手柄を横取りする策士である。彼の妻は貴族で、保守党の財務責任者であり、裏では富裕層だけを顧客とした資産管理会社も経営する。早い話、タックスヘブンの国々での、マネーロンダリングを主要な業務としている。このことが、のちにヘイブンの作戦に影を落とす。
ナットは、渋々、ドムの申し出を受け入れ、ヘイブンに勤務することにした。ナットの妻は、夫が情報部の勤務を続けることにはもろ手を挙げて賛成というわけではない。
彼女はかなりリベラルな弁護士で、大手製薬会社を相手にした集団訴訟を手掛け、また無償奉仕の弁護活動に力を入れている。大学生の娘がひとり。結婚当初、ナットが初めてモスクワに赴任した際には、スパイの夫を支える献身的な妻だったが、出産後は、勤務地に付いていくことはなくなった。夫婦仲は悪いわけではないが、微妙な距離感がある。
物語の終盤、夫妻の立ち回りが緊迫した事態の打開に大きなカギを握ることになるので、ここで彼女についても触れておいた。
エドとフローレンス
さて、主要な登場人物を紹介したが、この物語に欠かせない重要人物が、あとふたりいる。
ひとりが、20代半ばのエドと呼ばれる謎の若者である。
ナットは趣味としてバドミントンに打ち込んでおり、自宅近所の会員制スポーツクラブに所属していた。腕前はたいしたもので、体力は衰えながらもクラブチャンピオンの座を維持している。
本作の書き出しは、エドがクラブにふらりと現れたことから始まる。
<眼鏡をかけた身長百八十センチを超える不格好なこの若者が、どことなく孤独な雰囲気を漂わせ、当惑して半笑いを浮かべている。〉
それが第一印象だった。
エドもバドミントンに腕の覚えがあり、クラブチャンピオンのナットに挑戦状をたたきつけたのだ。
老獪なプレーヤーのナットは、エドの弱点を見抜いて勝利する。
〈・・・すべて終わってみれば、エドは意外にも品位ある態度で戦って敗れたと言わざるをえなかった。・・・試合が終わるとすぐに、どうにかにっこり笑ってみせた。・・・悔しがってはいるが、あくまで堂々としていて、予期していなかっただけにいっそういい笑顔だった。〉
ナットはエドに好感をもった。そこからふたりの奇妙な友情が始まるのである。
重要人物のもうひとりが、ナット直属の部下となる若き女性フローレンスだ。才気煥発でロシア語に堪能。少々、未熟なところがあるという評価により、見習いとしてヘイブンに配属された。
「若々しく凛とした不敵な面立ちの」彼女は、
〈ポニーに乗りながら育った上流階級の子女のひとりで、胸の内で何を考えているのかわからない。・・・眼は大きく、茶色で、笑っていない。職場では体型を隠すためにゆったりとしたウールのスカートを好み、底の平らな靴をはいて、化粧はしない〉
そのフローレンスが、有望なネタをつかんできた。ロンドンの高級アパートに、ロシアの新興財閥の有力者が住んでいる。モスクワ・センター(秘密情報部)とも深いつながりを持ち、ロンドンでは巨額の資金を運用し、マネーロンダリングに手を染めている。その金はどこに流れているのか。
彼女は、有力者の愛人に食い込んでおり、室内で交わされた会話などを聞き出している。なかには看過できない情報もあった。そこで本部の潜入チームを駆り出し、盗聴器などを仕掛けることを進言する。不法侵入だけに、SIS(秘密情報部)の幹部だけで構成される運営理事会の許可がいる。
「ローズバッド」と名付けられた作戦が、動き出した。
トランプの解毒剤
ナットは、フローレンスの後見人を務めつつ、合間を縫ってエドとのバドミントンの試合に興じている。
ナットは、数か月の間に、エドと15回、試合をすることになる。ゲームが終わると、クラブのバーでビールを飲むのが習慣になった。
互いの職業については詮索しない。ナットは曖昧に、
「とりあえず、古い友人のビジネスを手伝っているところだ」
と、口を濁していたし、エドは自分の仕事を、
「調査。なんというか、材料が入ってきて、仕分けして、それを顧客に渡す」
とだけ説明した。付け加えて、
「ドイツで二年ほど働いたんですよ。・・・あの国は大好きだったけど、仕事はあまり好きじゃなかった。だから帰ってきました」
これだけである。
ただし、エドのドイツに対する憧憬が、のちにとんでもない事態を引き起こすことになる。さりげない会話のやりとりだが、この場面には深い意味がある。
むろん、ナットはスパイであるだけに、エドとのビールを飲みながらの会話にも慎重である。対してエドは、あけすけに議論を吹っ掛けるようになる。〈いつもの席で、エドがそのときの火急の政治問題について独演会を始めない日はなかった。〉
一部を紹介する。
エドは主張する。
「イギリスとヨーロッパ、ひいては世界中の自由民主主義にとって、ドナルド・トランプの時代にイギリスがEUから離脱し、結果として、根深い人種差別とネオファシズムにまっすぐ向かっているアメリカに全面的に依存することは、まぎれもなく、最低最悪の大くそ災害だ・・・この意見にあなたは大筋で賛成しますか?」
ナットは、無難な返事しかしないが、内心ではこう思っている。
〈私自身もブレグジットにはずっと腹を立てていた。ヨーロッパで生まれ育ち、フランス、ドイツ、イギリス、旧ロシアの血を受け継いで・・・ヨーロッパ大陸に懐かしさを覚える人間だ。トランプのアメリカで白人至上主義が優位になっているという、より大きな問題についても、まあ、エドと対立する立場ではない〉
エドは、トランプ大統領がイランとの核合意から離脱したこと(注・2018年5月8日)に激怒している。
「われわれイギリス人は、アメリカとの貿易を欲するあまり、はい、ドナルド、いいえ、ドナルド、なんでも仰せのとおりに・・・」
ついには、
「誰かが勇気を出してトランプの解毒剤を見つけなければ、ヨーロッパはひどいことになる」
こうしたエドの思想信条が、のちに彼を、ある行動へと駆り立てるのだ。それは何であるのか。物語後半の大きな読みどころとなる。
「もう夢なんて誰もみない」
「ローズバッド」作戦は、上層部の意向で頓挫する。利権が隠されていた。フローレンスは、「もう腐りきった嘘はたくさん」と吐き捨てる。彼女は最後に、ナットの有能な助手となる。
ナットに新たなミッションが持ち上がった。ヘイブンが担当するロシアからの若き亡命者。モスクワ・センターが、いずれ役立てることを前提に休眠状態にさせていた工作員に、本国から指令が下る。
いずれ、大物スパイがロンドンに送り込まれてくるという。
イギリスの二重スパイになっていた若者は、ナットにそのことを告げる。彼の熟達の経験が、大きな獲物を嗅ぎつける。
大物スパイとは誰なのか。ナットには思い当たる人物がいた。その真偽を確かめるため、かつて二重スパイとして運用していた元KGBのベテラン情報部員と接触する。
ここはわたしが本作でもっとも気に入っている場面だ。
元KGBのベテラン情報部員は、再びロシアに寝返り巨万の富を築いていた。しかし、故郷のジョージアを蹂躙したプーチン大統領に幻滅し、いまはプラハでボディーガードに囲まれ隠遁生活を送っている。
互いに腹の内を探りながら、ナットは彼から必要な情報を引き出していく。老練なプロフェッショナル同士ならではの、息詰まる会話を堪能してほしい。
「代金は、おれのスイスの無記名口座に・・・」
「すまない・・・うちはいま破産中だ」
〈なぜか私たちは微笑んでいる。〉
「満足したか?」
別れ際に放った、元KGBのセリフが泣かせる。
「戻ってくるな・・・。もう夢なんて誰も見ない、わかるな?あんたを愛してるよ。今度来たら殺してやる。約束だ」
ブレグジット後のヨーロッパ
大物スパイをロンドンに潜入させたモスクワ・センターの狙いは何なのか。ロシアは巧妙な罠を仕掛け、ひとりの人物を取り込もうとしている。SISは総力を挙げた作戦「スターダスト」でこれを迎え撃つ。
ストーリーを紹介できるのはここまでだ。
本作を読んでいると、「正義」と「不正義」、「官僚主義」と「組織内での遊泳術」そして「個人の思想信条」と、では「行動すべきか否か」といった問題を鋭く突きつけられる。
ナットはどうしたか。
〈それまで人生にめったに出会ったことのないものが、よりによってこれほど若い人間のなかにあることに気づいたのだ――すなわち、利得や嫉妬、復讐、権力拡大といった動機のない真の確信、本物の、交渉条件なしの確信が。・・・エドから与えられた道徳観が、良心への訴えのように自分に影響していたことを思い出したのだ。〉
この心理描写があるからこそ、最後にナットが選択した大胆不敵な作戦が腑に落ちる。
ロシア課に君臨する実力者ブリン・ジョーダンは、ワシントンでCIAの幹部と協議している。ブレグジット後のヨーロッパをどう切り分けるのか、トランプ大統領のアメリカと密約を結んでいる。
「さっさとくそ仕事をしろということだ。これ以上時間を無駄にするな」
ブリンは電話越しにナットを追い詰める。成果主義の有能な管理者がよく口にする物言いだ。早く結果を出せ、とばかりに。だが、現場の事情に通じたナットは、強く反発する。
「いまの彼の気分ではとてもじゃないが管理はできない。以上。地上におりてくるまで彼には近づけない」
エドとは何者だったのか。
――現場に出れば、己の運命と配下の要員の運命をみずから決する。
最終ページを閉じたとき、読者はきっと、ナットの仕事の流儀に拍手喝采することだろう。
「スパイはいまも謀略の地に」
ジョン・ル・カレ(著)、加賀山卓朗(訳)
発行:早川書房
四六版:350ページ
価格:2300円(税別)
発行日:2020年7月25日
ISBN:978-4-15-209953-2
