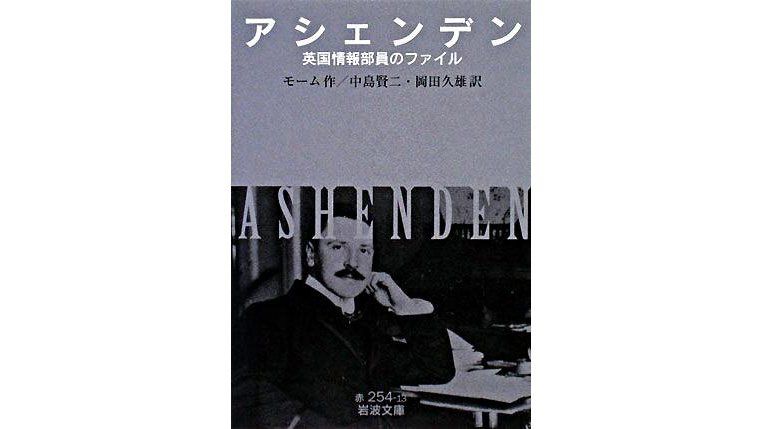
【書評】冷戦史上最強スパイの愛読書:サマセット・モーム著『アシェンデン』
Books 政治・外交 国際 エンタメ- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
以前この書評で、英国のノンフィクション作家ベン・マッキンタイアーによる『KGBの男』(中央公論新社)を紹介した。
この作品でフォーカスされたKGBの中佐ゴルジエフスキーは、冷戦末期の1980年代、英国情報部にとって最強の二重スパイであった。彼は西側に貴重な情報をもたらし、核戦争の危機を回避させたのだ。
作家はこう記している。〈世界を変えた優秀なスパイはほんの一握りしかおらず、オレーク・ゴルジエフスキーはそのひとりだった〉と。
同書によれば、ゴルジエフスキーは、イギリス文化を学ぶため、英国人作家の執筆した書籍に没頭した。なかでもモームの作品を読み耽ったという。作家はこう書いている。
〈数々の登場人物の中でも、とりわけゴルジエフスキーが夢中になったのは、十月革命中のロシアへ派遣されたイギリス人工作員アシェンデンだった。〉
『月と六ペンス』で知られるモームは、第一次大戦中、英国情報部に勤務していた。『アシェンデン』は1928年に出版されているが、自身の体験をもとに書かれた作品である。
エリートの道を歩んでいたゴルジエフスキーは、家族を偽り二重スパイになることを決断した。離婚、再婚も経験し、最後は妻子を故国に残し、イギリスに亡命する。そんな彼が夢中になったスパイ小説とはどのような物語なのか、興味津々ではないか。
作家は好都合な隠れ蓑
主人公のアシェンデンは英国人の作家である。
物語は、彼と情報機関の幹部との出会いから始まる。
第一次大戦が勃発してまもなく、アシェンデンは、あるパーティーで英国陸軍情報部に所属する大佐Rと知り合った。
Rはこう語りかける。
〈・・・きみみたいな人は特に情報活動が向いているんじゃなかろうか、と言いだした。ヨーロッパの数か国の言語に通じているし、作家という職業も好都合な隠れ蓑になる、本を書くための取材を口実にすれば、注意を引くこともなくどこの中立国へも行くことができる。〉
作家という職業柄、好奇心からアシェンデンは申し出を受けることにした。ただし、別れ際、Rはこう忠告する。
「お引き受け願う前に、一つだけ了解しておいてもらいたいことがあるんです。どうか、その点は絶対に忘れないようにお願いしたい。もし成功しても、どこからも感謝はなし。もし厄介な事態になっても、どこからも助けもなし。これでいいですかな?」
Rの指示で、アシェンデンはスイスのジュネーブに拠点を置き、スパイ活動に従事することになる。
ここから物語は動き出す。中立国のスイスでは、英・仏・露ほか伊・米・日などの連合国と、敵対するドイツ・オーストリア=ハンガリー帝国・オスマン(トルコ)帝国など中央同盟国との間で、熾烈な諜報戦が展開されていた。
ドイツに雇われた英国人スパイ
本作は、16章からなり、いずれもアシェンデンを主人公にして、一話ごとに完結する短編連作形式になっている。
それぞれの章に、国籍、人種、身分や置かれた境遇が様々な人々が登場する。その人物の内面にまで踏み込んだ圧巻の描写、そこに本作の最大の読みどころがある。
それでは、そのなかから私が興味をもった物語を紹介しよう。
「裏切り者」(第10章)とタイトルの付けられた章は、もっともスパイ小説らしい筋立てになっている。
アシェンデンはRの指示で、スイス中部の都市ルツェルンを訪れた。
この地に、ドイツに雇われた英国人のスパイがいる。名前はグラントリー・ケイパー45歳。妻は敵対国のドイツ人であり、そのため母国には居づらくなって、中立国スイスのホテルに居住しているという触れ込みである。
英国の情報部は、このスパイの存在を把握していた。とはいえ、Rが見るところ、排除するほどの危険な男ではなかった。泳がせておいて、彼と接触する工作員をあぶり出し、また、敵側に摑ませておきたい偽情報を彼に流すなど利用価値がある。
しかし、事情が変わった。最近、イギリスの情報機関に加わったゴメスという名の若いスペイン人がいた。
ケイパーはゴメスに近づき、自分が英国人であることで相手を信用させ、彼のスパイ活動を聞き出していた。ゴメスは、「私欲のない有能な情報員」だったが、〈たぶんこのスペイン青年は、自分を大物に見せたいという、ごく人間的な願望から、勿体ぶった口を利いた程度のことだったと思われる。〉
それが仇になった。ゴメスは、ケイパーの通報により、ドイツに潜入した際、逮捕され、銃殺刑に処せられたのである。
人がスパイになる動機
イギリスは、当然、ケイパーに報復すべきである。しかし、Rはこうも考えた。
〈ケイパーが金のために祖国を売るような男ならば、それ以上の金のためなら、雇い主を裏切るのではないか〉
アシェンデンの受けた指示は、男と知り合いになり、彼を二重スパイとして操れるかどうか確かめることだった。
アシェンデンは、ケイパーと同じホテルに滞在する。英国政府の仕事をしているが、病気療養のためしばらく静養していると偽装し、男に近づいた。
彼はどうやってケイパーを篭絡(ろうらく)していったか。そこが本章のヤマ場である。
この章には興味深い記述がある。人がスパイとなる動機はなにか。
〈ケイパーに裏切られた若いスペイン人のゴメスは・・・冒険好きな勇み肌の若者だった。危険な任務を引き受けたのも、金が目的ではなかった。ロマンスに憧れていただけだった。〉
ケイパーも金目当てではなかった。アシェンデンの見立てでは、
〈ケイパーは、まっすぐな道より正道を外れた道を意図的に選び、同国人を欺くことに複雑な喜びを見出すタイプの人間だったのかもしれない。〉
ならば、彼を札束で口説き落とすことは不可能だろう。アシェンデンは報告する。しかし、Rは、とうにそれを見越していたのかもしれない。アシェンデンは男と親しくなることで、ほぼその任務を達成していた。Rは、あらかじめ巧妙な奸計を仕掛けており、ケイパーを陥れることに成功したのである。
ラストシーンの情景、ケイパーの妻の慟哭と愛犬の遠吠えが切ない。
「やってみるだけの価値はある」
『アシェンデン』は、スパイ小説のジャンルを超えた文学作品である。
なかでも、「英国大使閣下」(12章)は、趣を変えた物語に仕立てられている。
密命を帯びて某国の首都に入ったアシェンデンは、駐在英国大使ハーバート・ウィザースプーン卿と接触する。
同期のなかでもスピード出世した彼は、家柄、教養、社交術、どれをとっても非の打ちどころのない厳格な人物だった。
ある情報を提供したお礼に、アシェンデンは卿から大使公邸での晩餐に招かれる。大使とのふたりきりの会食だった。
食後酒を飲みながらの歓談で、将来を嘱望されていたパリ駐在のエリート外交官の失脚に話題が及ぶ。彼は、社交界で常にゴシップの中心にいる悪名高い美女の踊り子と交際し、結婚する意志を固めていた。当然、外務省を辞めなければならないだろう。
アシェンデンは、卿がその人物に同情を示すとは考えられず、「あの男は救いがたい馬鹿者だと思っています」と迎合した。結婚は長続きせず、破綻するだろうと。
ところが、卿の反応は意外なものだったのである。
ハーバート卿は、問わず語りに身の上話を始めた。その内容については詳しく触れないが、長々と続くモノローグが読ませる。
かつて人生の転機となったかもしれない、自分とは身分の釣り合わない場末の女性との恋の物語である。そう書くと陳腐なようだが、一筋縄ではいかないところにモームの才がある。
今日、卿は申し分のない家柄の細君を手に入れ、地位は安泰である。しかし、深い悔恨がある。
卿は、パリの同僚の結婚に触れ、静かに話を締めくくる。
「それが五年しか続かなくても、出世の見込みがなくなっても、その結婚が破局に終わろうとも、やってみるだけの価値はあるはずです。本人はそれで満足でしょう。やるだけはやったんですから。」
「我々が手を出すような仕事じゃない」
「コインの一投げ」(13章)は、ひとつのコマとして酷使される現場の工作員の悲哀を見事に描いている。
オーストリアにある、敵方の武器弾薬製造工場を爆破する計画がもちあがった。実行する工作員を指揮するのがアシェンデンである。この爆破には、非戦闘員の労働者が巻き込まれる可能性があった。
〈だが、政府の上層部は、もちろん、こういうことに手を出したがらなかった。彼らは、名前を聞いたこともない一介の工作員たちの働きで上げた成果を喜んでも、汚い仕事は一切見ないですませて、清潔な手を胸に置き、名誉ある人間にふさわしからぬことは何もしていない自分を言祝(ことほ)ぐというわけなのだ。〉
バルカン半島にある国の支配者、B国王の暗殺計画が、ある工作員からアシェンデンにもちこまれた。国王は、イギリスと敵対している。成功の可能性は高かった。
アシェンデンはRに報告する。反応はこうだ。
「そいつは我々が手を出すような仕事じゃないな・・・なんてったって、わしらは紳士なんだからな・・・そんな提案はわしのところへ持ってきたりしないで、きみはもう少し利口に振る舞えなかったものかね?」
「B国王を消してしまうというのは、連合国側にとって、たしかに、べらぼうに美味しい話ではあるな・・・そのことと国王暗殺を認めることとは天と地ほどの違いがあるんじゃないのかな・・・」
「・・・自分で責任をしょいこんででも連合国を助けたいという人間がいるなら、そりゃ、そいつの自由だから。」
〈アシェンデンは肩をすくめた・・・上のほうはみんなこうなのだ。結果はほしいが、手段のところで二の足を踏む。既成事実を利用するに吝(やぶさ)かではないが、その事実を作り出すまでの責任は他人に転嫁したいと思っている。〉
作家の透徹した観察眼
モームは、アシェンデンの人柄をこう表現している。
〈善きものを讃えることでは人後に落ちなかったが、悪しきものに憤慨するというところもなかった。アシェンデンが、第三者を愛着の対象というより興味の対象にしているといって、彼のことを冷酷な人間と見なす人もままあった。〉
アシェンデンは作家の分身でもあるのだろう。透徹した観察眼をもっているからこその、味わい深い傑作である。
(ここでは岩波文庫版を紹介したが、新潮文庫からも『英国諜報員アシェンデン』として出版されている)
「アシェンデン」
サマセット・モーム(著)、中島賢二、岡田久雄(訳)
発行:岩波書店
文庫版:481ページ
価格:1140円(税別)
発行日:2008年10月16日
ISBN:978-4-00-372504-7
