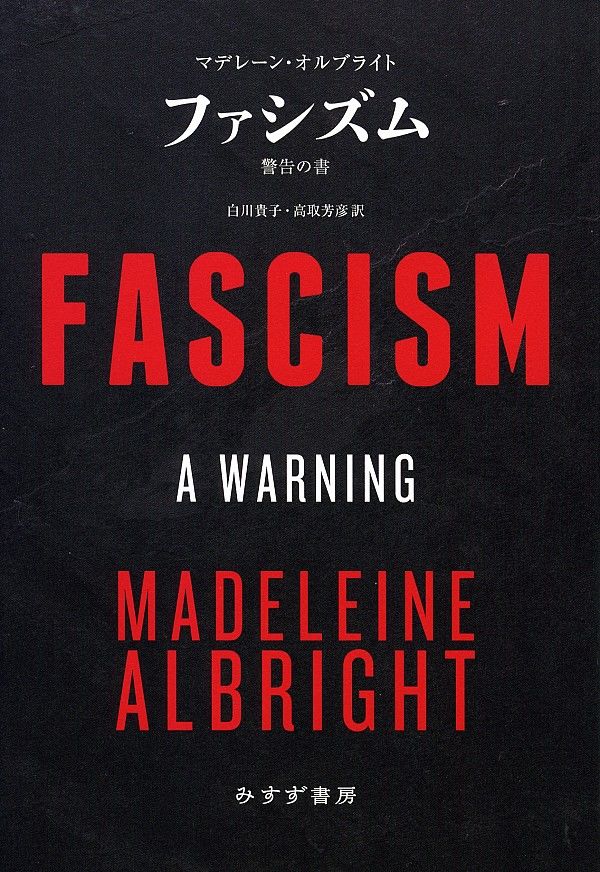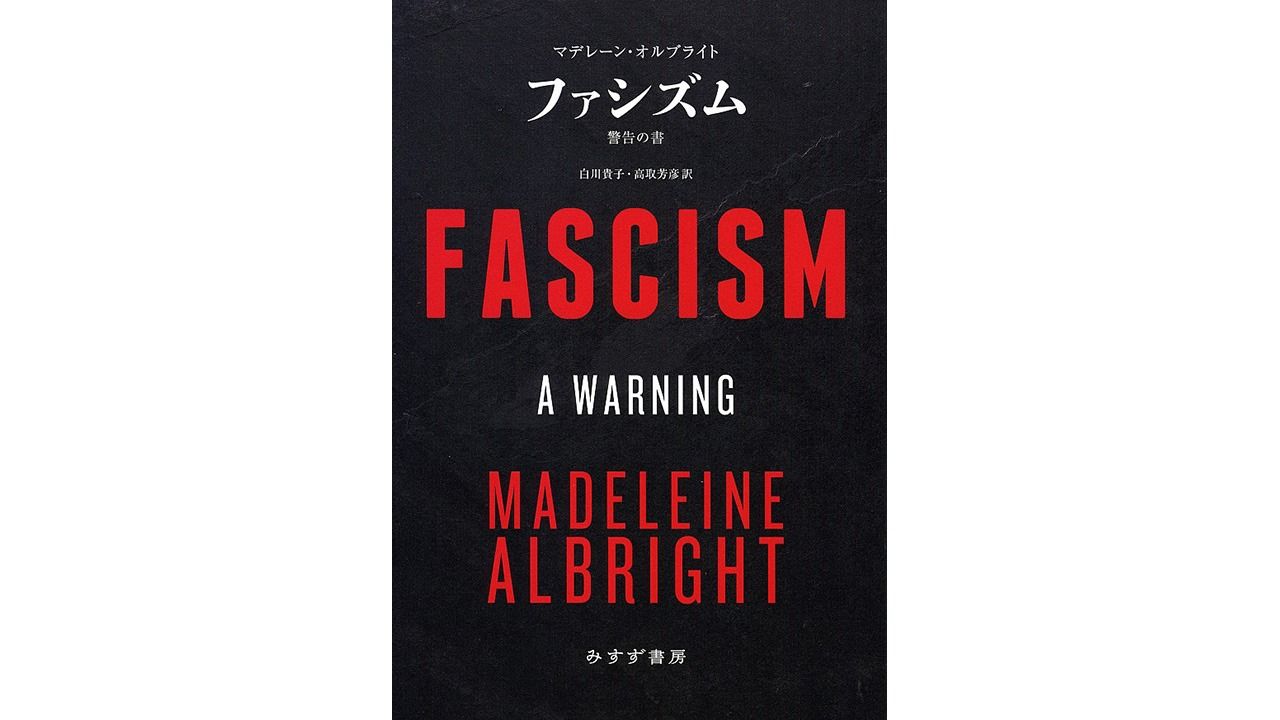
【書評】原体験を踏まえ“トランプ後”の世界を占う:マデレーン・オルブライト著『ファシズム 警告の書』
Books 政治・外交 社会 歴史- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
幼少期から2度の亡命を体験
原書の初版発行は2018年4月。今回の日本語版は新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)のさなか、米大統領選挙を間近に控えた10月に出版された。
2年半前に米国で上梓したのは「アメリカの影響力の低下が一因となり、世界の自由、繁栄、平和に対するファシズムとファシスト的政策の脅威が、第二次世界大戦が終わって以降、類を見ないほど深刻化している」との強い危機感からだった。
著者は1937年5月15日、チェコスロバキアのプラハでユダヤ系家庭に生まれ、カトリック教徒として育てられた。「よちよち歩きを始めたばかり」の1939年3月、国民社会主義ドイツ労働者党(ナチス)のアドルフ・ヒトラーが率いるドイツが侵攻してきたため、父母に連れられて英国のロンドンに避難した。
第二次大戦後、一家は母国に戻った。しかし、チェコスロバキアはソ連のスターリンの圧力を受けて共産化したことから、外交官だった父ら家族と米国へ政治亡命したのである。著者は当時11歳。亡命申請は1949年6月に認可された。
その後、米国籍を得てウェルズリー大学を卒業、コロンビア大学で政治学博士号を取得した。カーター政権で国家安全保障会議(NSC)スタッフ、カトリック系の名門ジョージタウン大学の教授などを経て、クリントン政権で1993年に国連大使、1997年には国務長官を歴任した。米国で女性が外交のトップに立ったのは初めてだ。
幼少期と少女時代、ナチズムとスターリニズムというファシズムの脅威から逃れるため2度の亡命を余儀なくされた著者には辛い思い出がある。ナチスによるユダヤ人大虐殺であるホロコーストでは何百万人もが犠牲になったが、著者は「三人の祖父母をはじめ、おじ、おば、いとこたちが何人も含まれていた」と明かす。
ファシズムは20世紀初頭に出現
ファシズムは20世紀の初頭に出現した。第一次世界大戦後の経済的な混乱の中、1920年代のイタリアでベニート・ムッソリーニに率いられたファシスト党の活動から起こった。結束主義とも訳されるファシズムの語源は、イタリア語で「束(たば)」を意味するファッショ(fascio、単数)とされている。
ファシズムは、政治家が民衆の不安や不満をすくい上げる形で権力を掌握し、嘘や暴力まで行使して統治するような政治運動、体制を指す。言論を統制し、巧みな宣伝や脅しで自由主義や共産主義を排撃する。全体主義、軍国主義、民族主義的な特色もある。対外的には帝国主義的な侵略政策を取ることが多い。もともとはムッソリーニの政治運動だったが、独裁的、非民主的な政治体制の総称となっていった。
ドイツでは1930年代に反ユダヤの偏狭な民族主義を掲げるヒトラー政権が誕生、ナチズムと呼ばれた。共産党や自由主義への抑圧、言論統制、親衛隊(SS)や秘密国家警察(ゲシュタポ)などによる反対派への弾圧を続け、ついには第二次世界大戦に突入、敗北した。
ファシズムを主義とする政治家は「ファシスト」と呼ばれる。著者によると、ファシストとは「特定の集団や国家に自分を重ね合わせてみずからをその代弁者とみなし、人々の権利に無関心で、目標達成のためには暴力も辞さずにどんなことでもする人物」である。
「ムッソリーニとヒトラーはファシズムの体現者だった」。著者はこう指摘するともに、ファシズムと反ファシズムの国際的な対決の場ともなったスペイン内戦、「イギリス・ファシスト同盟(BUF)」、「アメリカ銀シャツ隊」、ハンガリーの「矢十字(アロークロス)党」など、さまざまな形態のファシズムの事例と歴史を幅広く分析している。
「ファシズムと共産主義は正反対の概念なのだろうと考えることができそうだが、両者の差異はそのように単純なものではない」。共産党一党独裁だったソ連のスターリンは反対派とみなした68万人の粛清を命じたともいわれる。「共産主義者はナチスとほとんど変わらない程度に、国家を恐ろしい殺人マシンにすることができたのだ」
米史上初の反民主主義的大統領
著者自身は2016年11月の米大統領選前から「世界中の民主主義国が直面している試練や罠について本に書く」ことを決めていたが、共和党候補のドナルド・トランプ氏が大方の予想を覆して当選を果たしたことで執筆意欲は一段と高まったという。
トランプ大統領は「米国第一主義」を標榜し、移民やイスラム教徒を敵視している。報道機関への攻撃など民主的な制度や価値観に反する言動も多いだけに、著者の評価はことのほか厳しい。
「彼のやり方はデマゴーグ〔扇動政治家〕のそれだ。現状分析を語らせれば、嘘やナンセンスに満ちた主張を次々がなり立てる。議論をさせれば、不安を利用して怒りをかき立てようとする」
「人生を不毛な生存競争ととらえるトランプの見解は、複雑な相互依存関係でできた世界をとらえ損ねている。この世界では多くの場合、力を合わせなければ、与えられた状況から最大限の成果を得ることはできない」
そして「トランプを知性に欠けた人間とみなす向きもあるが、私はそうした非難には与しない」としながらも、「現代アメリカ史上初の反民主主義的な大統領である」と断じる。
各国指導者のファシスト化懸念
著者は、トランプ大統領が他国の指導者にとって最悪のロールモデルになることを懸念している。「世界中の指導者たちは、互いを観察し、互いから学び、互いを真似する。(中略)ヒトラーがムッソリーニに続いたように、彼らは他の指導者のあとに続く。こんにち、この群衆はファシストへの道を歩んでいる」と看破する。
こうした指導者としてベネズエラのマドゥロ大統領、トルコのエルドアン大統領、ロシアのプーチン大統領、ハンガリーのオルバーン首相、フィリピンのドゥテルテ大統領、そして「唯一の真正のファシスト」である北朝鮮の金正恩委員長を名指しで列挙する。
6人の共通点は「頑なな性格で、国家指導者の地位に就くことを暫定的な特権ととらえず、強制的なやり方によってできるだけ長く欲求を満たす手段と考える」、「全員が自国に不可欠な『強い指導者』を自任し、『国民』を代弁していると主張し、互いを当てにしながら、同類を増やそうとする」などだという。
「この暴君の集団さえ出現していなければ、トランプによる憂鬱な影響は、一時的で、御しやすい、ちょっとした体調不良にとどまっただろう。もともと健康であれば、すぐにでも回復できたはずだ。しかし、法にもとづく国際秩序はかねてさまざまな病理と闘っていて、免疫が低下している。私たちはそういう危機に直面しているのである」
世界の現状は1世紀前を彷彿
国際社会では今、“ミニ・トランプ”のような指導者が次々に台頭し、強権体制の国家も目立つ。その背景について統計的な数字を示しながら解説する。
「世界では労働人口の三分の一以上がフルタイムの仕事に就けていない。ヨーロッパでは若者の失業率が二五パーセントを超えており、移民の失業率はさらに高い。アメリカでは若者の六分の一が就学しておらず、仕事も得られずにいる。実質賃金は一九七〇年代から停滞している」
「これらの数字はどの時代であっても不穏だが、成人年齢に達した人々が仕事を始めたいと思っているにもかかわらず、多くの国で実際にそうする機会が持てない状況は、特に気がかりである。(中略)多くの国に見られるこうした傾向は、イタリアとドイツにファシズムを誕生させた一〇〇年前の風潮を思い起こさせる」
1世紀前の国際社会は第一次世界大戦後の経済的混乱で、極めて不安定になっていた。米国は国際連盟の設立(1920年)を提唱しながら、自国は加盟せず、国際舞台から一時身を引いていた。1929年秋のニューヨーク株式市場の大暴落に始まる世界経済恐慌のあおりで、各国には失業者もあふれた。
現在の世界と当時との大きな違いは、テクノロジー革命でインターネット、ソーシャルメディアなどが普及したことだ。インターネットを通じて「ほかの人は持っていて自分は持っていないものがあると知った人々は、怒りをかきたてるだろう」と著者は指摘する。貧富の差などをめぐる人々の不満、社会の分断はより増幅する。
それだけではない。「世論操作の工作員を編成してインターネットに情報を氾濫させる国は年々増えつづけ、北朝鮮、中国、ロシア、ベネズエラ、フィリピン、トルコは、こうした悪質な手段を操る代表的な国々になっている」という現状がある。
民主主義の危機と中国主導の恐れ
ファシズムの予兆のような現象が世界各地に広がっていることは、裏返せば民主主義の危機である。著者は英経済誌『エコノミスト』の民主主義指数(Democracy Index)を引いて、自由の国と呼ばれた米国でさえ民主主義が退潮していることに警鐘を鳴らす。
2006年から毎年調査している民主主義指数は、167カ国・地域ごとに10点満点で評価する。評価の基準は選挙過程と多元性、政府の機能、政治参加、政治文化、市民的自由の5項目である。国・地域ごとのスコアによって「完全な民主主義」「欠陥のある民主主義」「混合政治体制」「独裁政治体制」に4分類してランキングもつけている。
本書によると、2017年に発表された民主主義指数で米国は「これまでの『完全な民主主義』のレベルが初めて『欠陥のある民主主義』に代わってしまった」。つまり格下げになったのである。
トランプ現象に象徴される世界の行方はどうなるだろうか。著者は「こんにちのアメリカや世界に働いている凄まじい力は、ひとりが引き起こしたわけではないということだ。この潮流は、トランプが表舞台を去ってからも長いあいだ感じられることだろう」と予測する。
一方で、世界第二の経済・軍事大国で「独裁政治体制」の中国にも言及している。習近平国家主席については18世紀の清王朝の最盛期以来、「最も強力な指導者として台頭してきた」との見方を示す。
「次のアメリカ大統領が引き継ぐ世界では、経済問題だけでなく、労働条件やメディアの自由、宗教の自由、人権といった重要分野における基準の引き下げが、中国主導で進んでいるのではないかと危惧している」
学者で政治家の警句と人物月旦
ファシズムの原体験を背負って学者、政治家となった著者は本書に、歴史の教訓や警句を数多くちりばめている。
「ファシズムは政治的なイデオロギーとしてよりも、権力を掌握する手段としてとらえるべきではないのか」
「一九二〇年代のイタリアや一九三〇年代のドイツでは、共産主義への恐怖がファシズムの台頭をうながした」
「反民主主義的なやり方が一定期間にわたり、それが自分たちの利益になると考えられる場合には特に、一部の人々に歓迎されることが少なくない事実についても、十分承知しておくことが大切である」
「ファシズムには、もうひとつ覚えておくべき特徴がある。たいていの場合、目立たないかたちで登場するということだ」
「ファシズムは一気に飛躍を遂げるのではなく、徐々に根を張る」
「歴史が教えているとおり、ファシストは選挙を通じて高い地位につくことができる」
超大国の外交を指揮しただけに、各国指導者の人物月旦や交渉の裏舞台についての証言も本書の魅力になっている。
ロシアのプーチン大統領の第一印象は「小柄で青白く、爬虫類のように冷たい」。プーチン大統領の祖父はスターリンの「シェフのひとりだった」というエピソードも紹介している。
「プーチンは完全なファシストではない。そうなる必要を感じていないからだ。その代わり、首相や大統領として、スターリンの全体主義の教科書をめくり、都合良く使えそうな部分にアンダーラインを引いてきた」
北朝鮮の核開発問題で、国務長官として2000年10月に同国を初めて訪問したときの詳細な記録も外交史料として価値がある。金正日総書記(当時)については「ごく普通の人物だった。温かみがあり、感情を完全にコントロールしていた」などと回想している。
この訪問は結局、核問題の解決にはつながらず、クリントン大統領(当時)の訪朝も実現しなかった。だが、後日譚がある。「それから年月を経たあと、私の誕生日パーティーに来たクリントンは、他の出席者に聞こえない場所で後悔を口にした」。その言葉は「北朝鮮に行くんだった」だという。
「欠陥のある民主主義」日本の行方
本書では日独伊三国同盟(1940年)当時の日本については「東条英機の軍国主義の日本」との記述があるくらいで、天皇制ファシズムも直接取り上げていない。
しかし、著者には日本との接点がある。河野太郎規制改革担当相(前外相)はジョージタウン大学の教え子だ。父の河野洋平元衆院議長(元外相)はかつてカウンターパートだった。

オルブライト元米国務長官と河野太郎外相(当時)、出典:外務省ホームページ
本書出版後、2019年の民主主義指数は世界平均で5.44となり、調査開始以来、最低となった。167カ国・地域のランキングで日本は24位、25位の米国とともに「欠陥のある民主主義」に分類されている。因みに「独裁政治体制」の中国は153位、北朝鮮は最下位だった。
日本では菅義偉首相が9月に就任したばかりだ。その直前の自民党総裁選の期間中、政策に反対する官僚は「異動してもらう」と発言した。首相になってからは、日本学術会議が推薦した会員候補のうち6人の任命を拒否して物議を醸した。菅首相の政権運営の行方をどう占うか、碩学たる著者の見解を聴いてみたい。
ファシズム 警告の書
マデレーン・オルブライト(著)
白川貴子・高取芳彦(訳)
発行:みすず書房
四六判:304ページ
価格:3000円(税抜き)
発行日:2020年10月1日
ISBN:978-4-622-08943-8