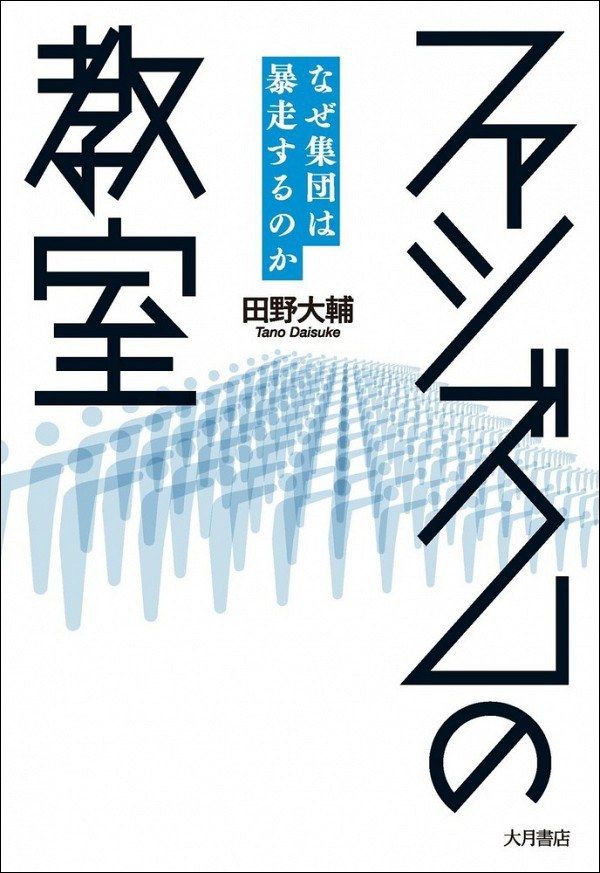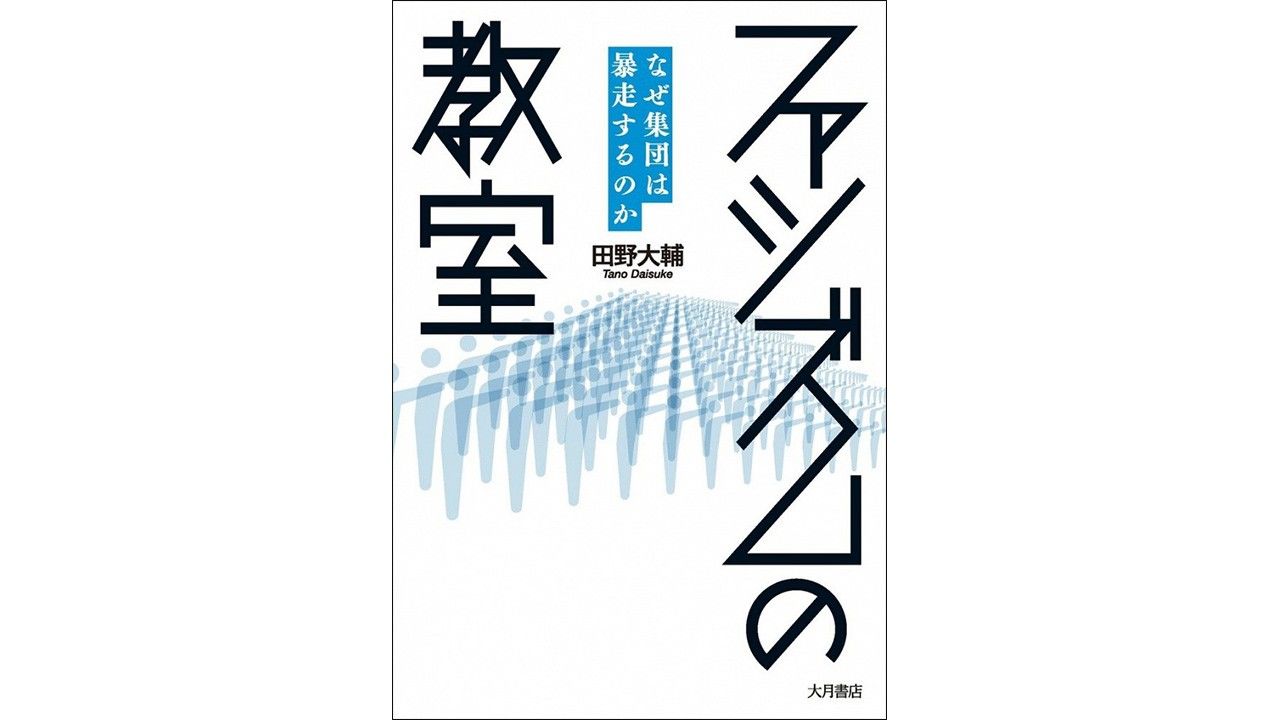
【書評】「わが身」の覚醒のために:田野大輔著『ファシズムの教室―なぜ集団は暴走するのか』
Books 社会 教育- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
用意周到に「暴走」回避策
ファシズムは政治学用語にとどまらない。まして過去の歴史、特殊な国での出来事ではない。現代社会にもヘイトスピーチやいじめなど、むしろありふれた形でその芽は生きている。
著者がこうした授業に取り組もうとしたきっかけは、同僚のドイツ人語学教員に教えられた映画「The WAVE/ウェイヴ」(2008年、ドイツ)。1960年代、米カリフォルニアの高校での実話に基づく小説が原案で、「独裁とは何か」との問いに対する生徒の反応の鈍さを危惧した教師が、「独裁はいつでもどこででも生まれる」と教えるため学級を独裁国家に見立てて生徒を集団行動に導く。
生徒たちは集団の意思や行動の強さに順応して万能感を抱くようになり、自ら独自の敬礼やロゴマークをつくり、ついには教師の想定を超えて暴走し始める…、という内容だ。
ナチズムを研究テーマとする著者は、この映画にいたく刺激を受けた。学内の了解を取り付け、何より恐れる「暴走」を招かないよういくつもの“安全装置”(例えば、攻撃対象者を「サクラ」にする)を仕込んで周到に準備した。
また、事前に学習目的をよく説明し、授業からの途中離脱も当人の自由に任せ、個人の倫理観が集団の中ではいかにはかないものかを心理学の「ミルグラム実験」(服従実験)などで学ばせもした。集団行動などの実習自体は90分×2回の2コマだが、事前説明や事後のデブリーフィング(被験者=学生への十分な解説)にも力を入れた。そして、実習後に映画を鑑賞させた。
迫真のナチス追体験
最初の実習時、著者はまず学生に拍手で承認させて自ら「総統」に就任した。次いで独裁には支持者の団結や規律による統一行動が不可欠であることを理解させ、起立や「ハイル・田野」の唱和を何度も練習させた。声はそろい、次第に大きくなった。席替えで友人・知人と切り離し、教師の指示や全体に合わせ易い環境もつくった。翌週の2度目の実習には、予め指定した通りほぼ全員がジーンズに白ワイシャツをインした「制服」姿に。私語をやめない学生ら(もちろんサクラ)を前に引き出し、罪状を記したボードを首に掛けさせて全員で非難した。
その後、キャンパスに出て、分列行進で気勢を上げ、いよいよ「リア充」を謳歌する“カップル狩り”に出かける。無論これもサクラで、それに気付いている学生もいるが、訓練通り2人を取り囲んで「リア充、爆発しろ!」と何度も叫んで糾弾する。
3組目のひざ枕カップルで攻撃は最高潮に達し、2人がたまらず退散すると、全員が高揚感に浸って「勝利宣言」する。この糾弾場面は映画になく、教育効果を追求する著者のオリジナルだという。今はやっかみの対象だが、自分も同じ立場に入れ替わり得る糾弾対象を選んだのは慧眼だろう。
いや増す「一体感」や「達成感」
大事なのはこの後。当然だが、学生たちはこれが授業の一環であることをよくよく理解しており、擬ナチス体験を通じて自分や周囲の意識、行動にどんな変化が生じるかをよく観察するよう指導されている。つまり、ロールプレイイングを自覚し承知の上で演じているのだが、それでも実際に何らかの変化が起き、それをしかと感得して学ばせるところが授業の肝である。実際、学生の事後リポートからはほぼ共通して以下のような変化の気づきが読み取れたという。
すなわち、組織に属して行動することの誇りや一体感が湧いてきて(「集団の力の実感」)、上からの指示で他と同じ攻撃的な行動をとることに抵抗がなくなり(「責任感の麻痺」)、周囲に合わせて規律に従うのが「正しい」ことだという感覚がどんどん高まった(「規範の変化」)―ことである。「いったん従う気に包まれたら、従わないメンバーに苛立った」「いつの間にか本気になった」「何だか分からない達成感があった」「『やってやった』感が出ていた」などだ。
よく分かるのは、同じ格好で同じ行動を取ること自体が快感を呼ぶという単純な事実。生物の本能に根差すものかはさておき、このエネルギーが深い理由もなしに異質なものへの悪感情や攻撃に転化するのは容易に想像できる。軍隊という武装集団に制服が不可欠である理由の一つはまさにこれだろう。学校という教育の場でも制服が採用される意味も改めて考える必要がある。
集団の中で薄れゆく「責任感」
だが、集団への同化と陶酔だけではない。著者が最も言いたいのはファシズムの心理的メカニズムである。それを端的に言い表したのが「集団の中でただ従えばいいという気楽さと責任感の薄れがあった」との学生リポートの自覚的な感想だろう。上からの指示、皆もやっているから…。こんな気持ちが個人としての判断を停止させ、普段なら気が咎めるようなことも平然とできるようになる、ということだ。
多くの学生が、こうした感情に何がしかの既視感を抱くのは、小学校の運動会や中学・高校での制服、あるいはいじめ体験(当事者だったかどうかはともかく)があるからかもしれない。著者の言葉を借りれば、「指導者や仲間たちに責任を丸投げし、指示されるまま周りに流されて行動しているうちに、他人を傷つけることへの抵抗感がなくなるばかりか、ただ状況に身を任せる気楽さが快く感じられるようになる」ということなのである。
あぶり出された日本の病根
本書の各章末尾に挟まれたコラムは、「愛と欲望のナチズム」(講談社)などの著作がある研究者の解説として興味深い。その一つにナチズム研究の現在についてのものがある。
簡単に言えば、ヒトラーという強烈なリーダーに統制された党や国家によるものという従来のナチズム理解ではなく、家族や職場、地域といった日常生活レベルまで掘り下げた研究によって、一般民衆が自らの慣習や価値観を保持した主体的な関りの中でナチスの支配を下支えしていた、と見る「合意独裁」という視点が今は一般的だという。庶民によるユダヤ人密告などが好例だ。確かに、「アンネの日記」一つとっても、その見方はよく理解できる。
戦後、ドイツはヒトラーとナチ党に戦争責任を引き受けさせる形で再出発し、「人間の尊厳」に至高の価値を置く憲法による人権国家として欧州連合(EU)でも指導的な地位を占めている。同じファシズムの枢軸国、日本はどうか。
連合国、とりわけ米国の思惑で、大元帥であった昭和天皇の戦争責任を封印し、直接の戦争指導者として政治家や軍人を処刑・処罰し、多くの国民は「戦争被害者」として今を生き、やがて戦争の直接体験者が消えんとする状況だ。幸か不幸か、ヒトラーのように突如現れた強烈な戦争指導者が見当たらず、神風や戦艦・大和の悲痛な特攻作戦さえ「空気」や「流れ」で決まった、との説明で済まされている。ドイツが「合意独裁」なら、日本はいったい何となすべきか。
後書きに当たる「おわりに」によれば、この授業がウェブ雑誌で取り上げられた2018年7月、「中国地方の右派の地方議員」から電話で「この授業はまずい。衆院や参院の委員会で問題にすることもできる」と強く“改善”を求められた。著者は大学当局とも協議し、行進など集団行動を人目につきにくい体育館に移し、メディア対応にも配慮するなど善後策も考えた。だが、結局は「10年間の実践で一定の成果はあった」として、19年を最後に授業を休止した。
この顛末自体がまさに日本社会伝統の「空気」や「流れ」であり、ほとんど宿命的に根深い体質である。「ナチスばかりの話ではなかろう」というのが偽らざる読後感である。この勇気あるファシズム実習授業の試みと挫折という一連の経過こそ最も教育的な体験であった、と言うべきかもしれない。
ファシズムの教室―なぜ集団は暴走するのか
田野大輔(著)
発行:大月書店
四六判:208ページ
価格:1600円(税別)
発行日:2020年2月21日
ISBN:9778-4-272-21123-4