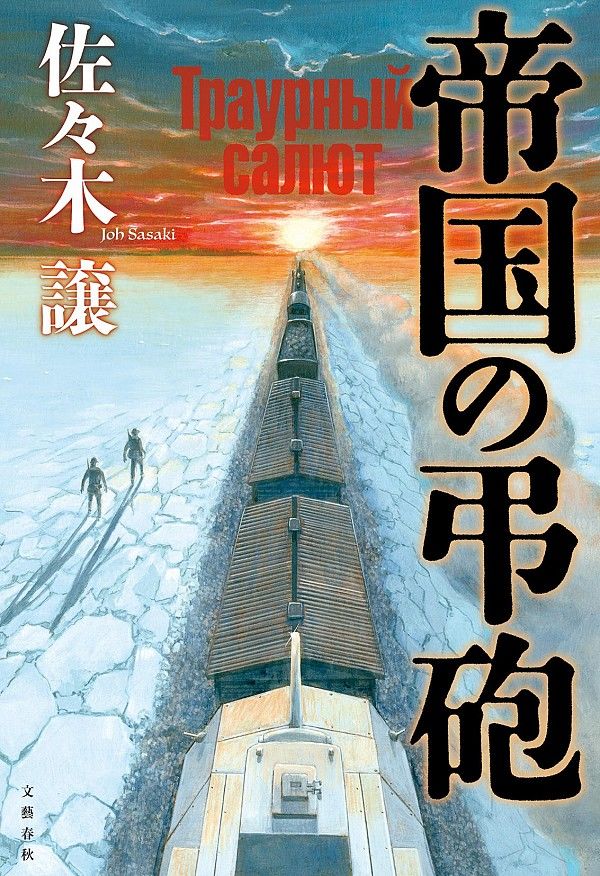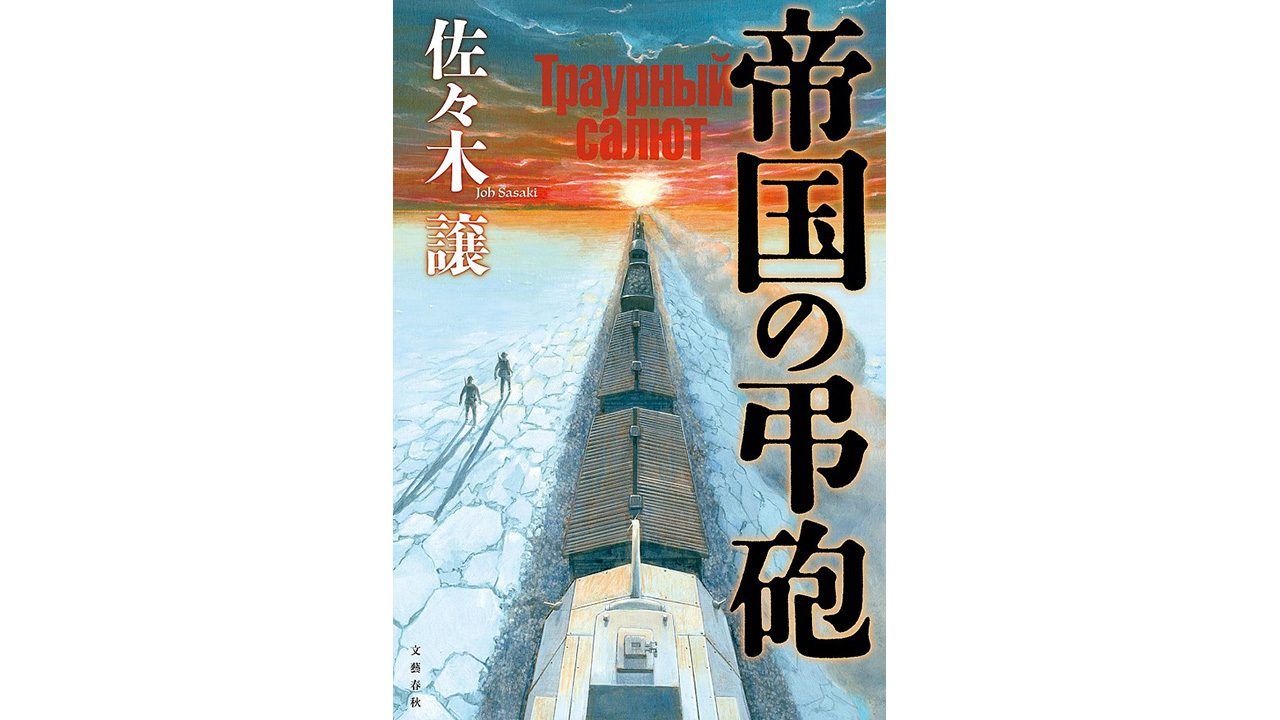
【書評】ロシア革命に翻弄された開拓農民の運命:佐々木譲著『帝国の弔砲』
Books 政治・外交 国際 歴史 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
墨田川の下流に架かる勝鬨橋は、昭和15年6月に完成した。水運を確保するため可動するようになっており、一日のうち何度か中央から跳開し、大型の船舶がその下を航行できるようになっている。
物語はその一年後から始まる。
〈昼前、十時過ぎである。その日二度目の橋が跳開するこの時刻、登志矢は仕事の手を休め、月島の路地を五十メートルばかり歩いて、ここで一服するのを習慣としていた。〉
おりしも、二艘の艀がタグボートに曳かれ、勝鬨橋にさしかかっていた。幌がかけられた荷は、帝国陸軍の零式戦車の車体である。この先、竹芝桟橋から輸送船に積み替えられ、満州の旅順港に向かう。関東軍の戦車連隊に配置されるのだ。
主人公の小條登志矢は月島に小さな作業場兼自宅をかまえ、近隣の漁師を相手に、細々と小型漁船の焼玉機関の整備をしていた。彼は口数の少ない修理工として、ひと目を避けてひっそりと暮らしている。何故か。
登志矢にはサチという三十代の内縁の妻がいる。身寄りのない彼女は、月島の洗濯屋で雑役係として働き、夜は酒場の下働きをしていた。以前、大工と所帯をもったことがあるというが、不遇であった。
サチが洗濯屋の仕事で登志矢の家事全般を手伝うようになってから三カ月後の正月、彼女が「登志さん、あたし、今夜ここにいちゃいけませんか?」と震える声で尋ねてきた。これまで、女性と関わりを持つことは避けてきた。しかし、
〈その寒い夜、だめだ、帰れ、と追い返すことは自分にはできなかった。非情になりきれなかった。〉
登志矢は「これは大きな過失になる」と確信しながらも、それ以来、三年半一緒に暮らしている。
勘の良いサチは、登志矢が大きな秘密を抱えていることに気づいていた。時々、行先を言わずに出かけて行くし、何日も帰ってこないことがある。それでも彼女は理由を聞かず、献身的に尽くしていた。いずれ、別離が来ると覚悟もしていた。
「眠っていた」男
登志矢はいったい何者であるのか。
墨田川で戦車を積んだ艀を眺めていたときに、彼は述懐する。
〈自分も、戦場で戦車を間近に見たことがあった・・・考えたら、あれはもう二十四、五年前のことになる。ポーランド西部、それにガリツィアの平原の戦線だった。〉
第一次大戦下のヨーロッパの戦場である。
〈あれからずいぶん時が過ぎた。眠っていろ、と命じられたのは、それから六年後だ・・・命じた男は眠っている期間をはっきり言わなかった。〉
そして、「眠っていた」男に、一通の電報が届く。文面は「チチキトク、サブ」の七文字だけ。そこから運命の歯車が動き出す。折しも、ヨーロッパではドイツが独ソ中立条約を破ってソ連に侵攻を開始、破竹の勢いで旧首都のレニングラードに迫っていた。
ほどなく、登志矢の正体が明らかになる。電報は、「隼」(サブ)という暗号名のソ連のスパイとの接触を示唆したものだった。「サブ」とは隼を意味するロシア語に由来して付けられている。
スラブ系の男「隼」は、登志矢にロシア語で告げる。
「いよいよだ。緊急だが、これが最後の任務になる」
「もう東京にいる必要はなくなるんですね」
「むしろいられなくなるだろう。未練はあるか?」
「いいえ」
「隼」は登志矢に、ある政府高官の暗殺を命じた。それは誰で、理由は何なのか。そして、「隼」は事が成就したら大連に逃れるよう付け加えた。「向こうに支援するルートがある」と。決行する期限は明後日の朝。残された時間は少ない。
はたして登志矢は、任務を果たすことができるのか。そして、サキとの関係はどうなる?
これが物語の入口、「プロローグ」の章でいきなり最初のヤマ場がやってくる。
ロシアに入植した開拓農民
作者の佐々木譲氏については、もはや多言を要しないであろう。『警官の血』や『笑う警官』、直木賞受賞作『廃墟に乞う』など警察小説の名手である。そして本作は、以前に本欄でも紹介した『エトロフ発緊急電』に代表される、同氏が自家薬籠中のものとするもうひとつのジャンル、戦争など激動の時代に材を取ったミステリーとして書き上げられたものである。
本作でも、作者は20世紀初頭のロシアと日本を舞台に、壮大な物語を編んでいる。主人公の登志矢は、何故、日本に潜伏するソ連の工作員になっていたのか。それが、これから始まる物語の本編である。
1895年、登志矢はロシアの沿海州に入植した日本人開拓農民の次男として生まれた。
この物語は、1891年、滋賀県大津で来日中のロシア帝国皇太子ニコライが警備中の巡査に斬りつけられた事件に端を発し、ロシアとの戦争を回避するため日本政府が1万2000人の開拓民を東シベリアに送り、鉄道建設や開墾など未開地の開発に協力したという設定になっている。
開拓農民の生活は厳しいものだった。極寒の気候と地主の搾取。それでも入植から6年を経ていくばくかの作物を収穫できるようになり、両親と兄、妹の登志矢の家族は、貧しいながらもそれなりに幸福な生活を送れるようになっていた。
しかし、祖国日本とロシアとの間で戦争が勃発し、日本からの移民は敵国民として農地を取り上げられ、収容所に送られることになる。ここから、一家の流転が始まった。
ろくに食事も与えられない過酷な収容所生活は、1年3カ月続いた。母親は衰弱死してしまう。
「改変」された歴史
ところで、この作品には工夫がある。
それは、実際の史実と異なる展開で物語を進めていることだ。
作者は一昨年『抵抗都市』で同様の意匠をこらしており、名手にして新たな挑戦を試みているわけだが、
「そのままでも魅力的な歴史事象を少し変えることで、さらに面白いものにできる。一作書き終えたことで、読者に受け入れられる改変の度合いがわかってきました」(『オール讀物』3・4月合併号)
と、作者は語っている。
本作では、日本が日露戦争で敗北し、ロシア帝国の属国になっている。収容所の所長は、日本人開拓民にこう告げる。
「戦争が終わった。お前たちは、自由となる。帝国の領土内で、あらためて働くことができる」
のち、登志矢は第一次大戦で、ロシア帝国民のひとりとして、ヨーロッパの過酷な前線に従軍することになるのである。
こうした歴史の「改変」が登場人物の運命をどのように変えていったか。これが本作のおおきな読みどころになっている。
鉄道少年工科学校に進む
もう少し、物語を進めてみよう。
戦後、収容所から解放された一家は、沿海州の地方都市で暮らすことになった。土地をもたない開拓民は、安い賃仕事で生計を立てるしかない。
登志矢は工場で雑用仕事をしながらロシアの初等国民学校に通う。苦学しながらも優秀な成績をおさめ、卒業後、ウラジオストクにある鉄道少年工科学校に進むことができた。全寮制で学費や生活費は無料、鉄道会社で働きながら技術を学ぶことができる。将来の夢は、鉄道技師になり一家を支えることだった。
3年後、卒業を控え、成績優秀者上位3名にご褒美として銀色のバッジと7日間の卒業旅行が与えられる。登志矢は見事に選ばれた。
しかし、時代は暗転していく。帝国内では革命運動に火がついていた。鉄道会社では、非合法の組合活動が活発になっていく。
卒業式の日、恩師のコースチャ先生が、革命運動にかかわっていた疑いで、秘密警察に引っ張られていった。
卒業旅行は、ウラジオストク駅からシベリア鉄道でハバロフスクまで向かう。
登志矢らが乗車した蒸気機関車には、数名の巡査と政治犯たちが同乗していた。彼らは刑務所へ護送される。そのなかに、コースチャ先生と社会民主労働党の活動家サポフスキーがいた。
「自分は生きる側を選ばねばならない」
登志矢らを乗せた機関車は、途中、武装した覆面姿の男たちに急襲される。巡査と機関士は逃げ、政治犯は奪還された。彼らは、機関車を乗っ取り、針路を変えてハルピンに向かい、清国領内に逃亡する計画だった。
しかし、機関士が逃げたことで機関車は動かせない。このままでは追跡してくる軍に捕まるであろう。どうするか。
一味は、乗客のなかから、機関車を操縦できる者を探す。
事態は緊迫している。登志矢は考えた。
〈・・・ここで知らんぷりをすることができるだろうか。自分はどちらにも共感しないと、冷笑でやり過ごすことはできるだろうか。自分はこの場で、何もできない木偶の坊というわけにはいかないのだ。〉
政治犯のなかには恩師がいる。彼は決断した。
〈自分は生きる側を選ばねばならない。自分の技能を通じて、自分の働き方を通して、自分が生きるべき側を。〉
見習いとはいえ、登志矢は機関車を動かせる。彼は名乗りをあげた。そして、道中、彼の機転によって軍の追撃をかわし、政治犯たちを無事、国境沿いの駅まで送り届けることができた。
このときの左翼活動家サポウスキーとのわずかな出会いが、のちに登志矢の運命を大きく変えていくことになるのだ。
ここは、本作のなかでも私がもっとも気に入っている場面である。
黙していれば、その後の登志矢の人生は全く違ったものになっていたことだろう。この先、彼は何度も試練を迎えることになる。それは決して自身が望んでいた人生ではなく、苦難の連続の茨の道であった。しかし登志矢は、その都度、自らの信念に従って決断し、力強く生き抜いていくのである。
死屍累々たる塹壕戦
ここから先の展開は、本作をじっくり読んで楽しんでいただきたい。
おおまかにガイドしておけば、第一次大戦が勃発し、ロシア生まれの登志矢は帝国民のひとりとして徴兵され、沿海州からはるか西、ハンガリー・オーストリア帝国と戦火を交える最前線に兵士として送られることになる。
ここからの戦場の描写は圧巻である。
それは死屍累々たる終わりなき塹壕戦の繰り返しであり、戦況は停滞している。そのなかで、登志矢は持ち前の技能を買われ、ある作戦遂行のための特殊部隊に選抜され、戦功をおさめる。
だが、それも戦局を大きく変えることにならなかった。
時代は大きく変転していく。厭戦気分が前線を支配するなか、本国では革命が起こる。その波紋は前線まで伝播し、終戦後も革命軍と反革命軍とが殺戮を繰り返す内戦状態に突入していく。そして、登志矢もまた、激動の渦に否応なく巻き込まれていくのである。
本作もまた、読者の期待にたがわず、作者は時代の流れに翻弄される人々を見事に描き切っている。彼ら彼女らが、運命に抗いながら懸命に生きていく様は胸を打つ。登志矢の家族はどうなったのか。何故、彼は日本に潜伏していたのか。サチには幸せになってほしい。
「帝国の弔砲」
佐々木譲(著)
発行:文藝春秋
四六版:445ページ
価格:1600円(税別)
発行日:2021年2月25日
ISBN:978-4-16-391331-5