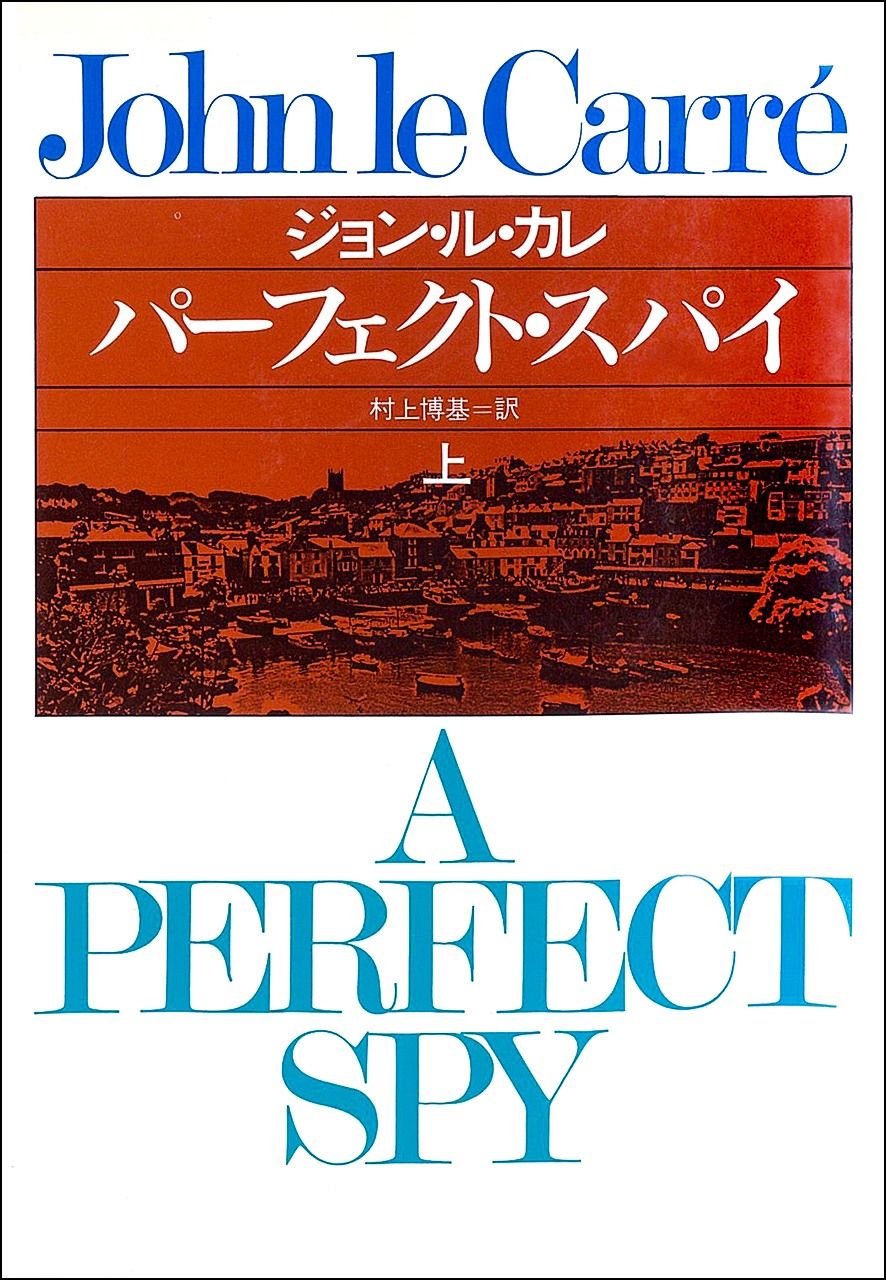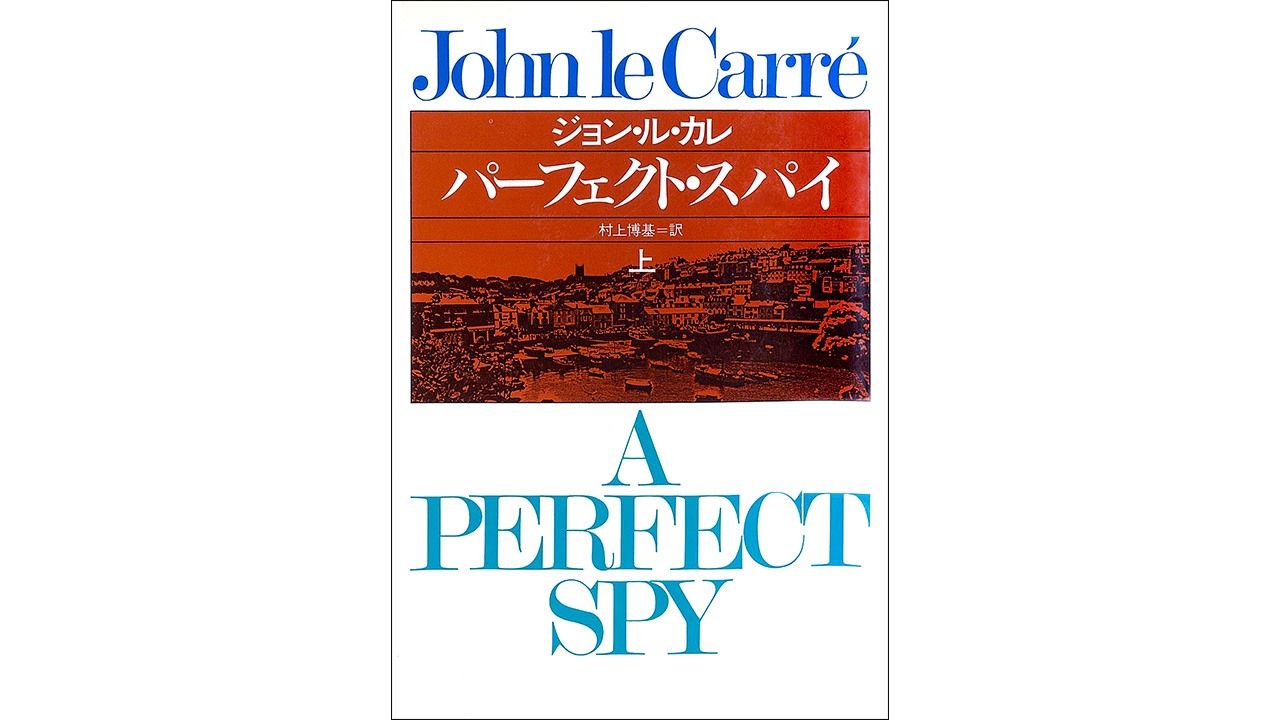
【書評】巨匠が描くスパイという人間像:ジョン・ル・カレ著『パーフェクト・スパイ』
Books 政治・外交 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
「自由の身になったよ」
ピムが妻のメアリーにぽつりという。
「リックが死んだんだ」
彼女にはその意味がぴんとこない。
「どういう意味よ――自由の身って」
謎の言葉を残したまま、ピムは姿を消してしまう。
ピムは、ロンドンから遠く離れたウェールズにある海辺のB&B(ベッド&ブレックファースト)に潜伏していた。ここは彼にとって情報部の目の届かない秘密の隠れ家で、これまでにも何度か訪れている。オーナーは年老いた未亡人で、気に入った常連客しか泊めない。
〈ピムはハンサムな男だった。ボーイッシュでいて、そのくせ貫禄がある。五十すぎの男盛り、真剣味と熱意にあふれ、ついぞそれらと無縁の場所であっても、それは変わらない。〉
オーナーの目から見て、
〈彼のいちばんいいところは、そのすてきな笑顔で、それはこの上もないあたたか味と誠実味をふりまいて、彼女を安堵させてくれるのだった。〉
ピムは、この隠れ家に籠って、わが身の半生を振り返ることになる。それがこの物語の始まりである。
まさに円熟期の作品
冷戦期のスパイの実像を描いた本作が、英国で出版されたのは1986年である。不朽の名作『ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ』にはじまるスマイリー3部作を世に送り、あらたにパレスチナ紛争に材を取った『リトル・ドラマー・ガール』を出版してから3年後、著者は50代半ばにさしかかっており、まさに円熟期の作品といえる。
どこが自伝的小説であるのか。「リック」とは本作の主人公であるピムの父親である。そして、リックは著者ル・カレその人の実在した父親ロニーをモデルとして創造されたものなのだ。むろんピム自身にも著者の半生が投影されている。
ル・カレは、本作から30年を経て、85歳のときに初めての回想録『地下道の鳩』を上梓しているが、そのなかで父親についてこう記している。
〈ロニーのことが書けるようになるには長い時間が必要だった。ロニーは詐欺師で空想家、ときどき刑務所にも入った男で、私の父親だ。〉
この、本作でリックと名付けられた父親とその息子ピムとの愛憎が全編をつらぬくテーマである。父親の存在が、若き日のピムの、その後の人生を変えていく。長じてピムは英国情報部のスパイとなり、頭角を現していくが、どうして失踪劇につながっていくのか。そこにもリックの影がある。
チェコ製のスパイ道具
物語を続けてみよう。
ピムは、外交官という身分に偽装してオーストリアの首都ウィーンの英国大使館に勤務しているが、ほんとうの顔は情報部のウィーン支局長である。
そこに本稿の冒頭で紹介した場面、父親の訃報が届く。彼は、本国の情報部に無断で赴任地を離れ、密かに帰国する。なんのために?
ピムが突然行方をくらましたことで、英国情報部は大騒ぎになる。かねてより、同盟国アメリカの情報部から、彼には二重スパイの疑いがかけられていた。しかし、英国側は証拠がないと否定していた。その矢先の失踪だったのである。
英国情報部はかつて二重スパイ事件で深手を負い、米国の情報部から一時、絶縁状を突きつけられたことがある。そのため、真相がはっきりするまでピムが行方不明となった事実を米側に秘匿したまま、当局は追跡を開始する。彼は本当に裏切り者だったのか?
情報部の幹部でピムの上司ジャック・ブラザーフッドが数名の捜査官を引き連れ、本国からウィーンを密かに訪れる。彼はこの物語の鍵を握る重要な登場人物である。ピムの住まいの家宅捜索と妻メアリーの尋問。彼は問い詰める。ピムに怪しい行動はなかったのか?メアリーは、かつてはブラザーフッドの部下であり、愛人でもあった。
ピムは、東欧圏を担当し、多数の現地工作員を操っていた。住居からはチェコ製のスパイ道具が発見される。と、同時に、情報部のウィーン支局の保管庫から、機密書類廃棄箱(バーン・ボックス)が紛失していることが明らかになる。それは支局長が重要書類をしまい込む金属製の箱で、いざという場合には中身が燃える(バーン)仕掛けになっている。そのなかに何が入っていたのか。それは物語の最後まで明かされない。
「宮廷の王侯貴族」
情報部の混乱をよそに、ピムは、海辺の町の隠れ家で過去を振り返っている。
父親のリックは、ある意味、大物の詐欺師だった。大がかりな事業を吹聴しては投資家を募り、巨額の資金を集めていく。話術が巧みで、人を惹きつける魅力があり、周囲には政治家やスポーツ選手、芸能人が群がってくる。気前よく金をばらまき、女とパーティーが大好きだ。リックとその配下の一味は、さながら「宮廷の王侯貴族」のような暮らしぶりだった。
とはいえ、詐欺話は当然のように破綻するのだが、その都度、リックはしたたかに甦り、性懲りもなくまた虚構の投資をもちかけては被害者の山を築いていく。
ル・カレはリックの行状を、少年ピムの目を通して、ときにシニカルに、またときには滑稽譚として詳細に綴っていく。
そうした環境下で、ピムはどう育っていったのか。彼自身もまた、絶対君主のように振るまう父親の浮き沈みによって、人格形成におおきな影響を受けていくのである。
「神は彼にふたりの聖人を・・・」
ピムはなぜスパイになったのか。
彼は18歳のとき、父親の命を受けてスイスのベルンを訪れる。怪しげな遺産相続話の片棒をかつがされたのだ。
しかし、ピムは国外に出たことをきっかけに、父親から離れることを決意する。
年齢と資格を偽り、スイスの大学に留学生としてもぐりこむ。アルバイト先で出会った篤志家に、嘘偽りででっちあげた不幸な身の上話を聞かせ、その人物の家に転がり込んだ。
そこで運命的な出会いがあったのだ。
〈ただ一度のクリスマスに、神は彼にふたりの聖人をもたらしてくれたのだ。一方は逃亡者で、ひとり歩きできず、他方はハンサムなイギリス軍人・・・〉
と、ピムは回想している。
ひとりは、東欧圏から国境を越えてきた不法滞在者のアクセル。彼もまた、ピムが世話になっている篤志家の家に寄寓していた。最初の出会いの場面。
〈・・・アームチェアの上に、やせた男がまるくなっている、はっきりしない姿が見えた・・・黒いベレー帽をかぶり、両端のたれた口ひげを生やしていた。足は見えないが、からだ全体が、なにか骨ばったものを変に折り曲げたというふうで、折りたたむ途中でつかえてしまった三脚を思わせた。〉
足を引きずって歩く痩せぎすで不健康な男。しかし、哲学と文学を饒舌に語るアクセルに、ピムは次第に惹きつけられていく。
もうひとりが、英国人が集まる教会で知りあった駐ベルン英国大使館付陸軍情報部の大尉、若き日のジャック・ブラザーフッドであったのだ。
〈・・・そしてジャック、きみはツィードの似合う、二十四歳の、登攀不能のイギリスの山という印象だった。戦争と平和という点から見れば、七年の年齢差は世代ひとつ、いや、ふたつぐらいの差があった。それはまたアクセルとの差でもあった。〉
ピムはブラザーフッドから上司を紹介され、ちょっとした仕事を依頼される。ピムは外国人学生の左翼系政治フォーラムに出入りしており、亡命学生の動向に詳しい。当時、中立国スイスには亡命者を装った東側のスパイが入り込んでいた。彼は、ブラザーフッドに気に入られたいがために、外国人学生に関する情報を提供するようになる。
そんなある日、突然、アクセルが行方不明になる。ピムは、親友がいなくなったのは、自分の情報提供が原因ではないかと思い悩む。このときの負い目が、生涯、彼につきまとうのである。
謎の美女ザビーナ
ル・カレの文体は難解である。本作もまた同様で、過去と現在とが複雑に入り組んでおり、じっくり腰をすえて読み込んでいかなければ、物語がどこへ向かって進んで行くのか迷路にはまったような気分になる。しかし、ここで投げ出してはいけない。
物語後半に入っていくと、ページをめくる手は一気に速くなる。
帰国したピムは、再びブラザーフッドの誘いを受け、正式に情報部員となりスパイの道を本格的に歩んでいく。
1950年代初頭、若き日のピムは、オーストリア第2の都市グラーツに駐在している。当時、東欧からの亡命者はオーストリアになだれ込んでいた。ピムの仕事は、難民収容所で亡命希望の彼らを事情聴取し、身元を確かめることだった。共産圏のスパイの疑いがあれば、オーストリア警察に引き渡して強制送還させるか、または二重スパイになるよう懐柔する。
このとき、チェコ語の通訳を務める謎の美女ザビーナから、チェコからの亡命希望者を紹介される。その人物は、ソ連東欧の極秘情報をもたらしてくれるという。密会場所に指定された郊外の納屋に現れたのは誰か。
かつて自分の密告によって姿を消したと思っていた生死不明の親友、まさにそのアクセルが姿を現したのである。
アクセルはピムに、ある取引を申し出る。彼は東側のスパイだったのだ。
この再会をきっかけにピムは出世の手がかりをつかみ、ベルリン支局を経てワシントン支局次長のポストにまでのぼりつめる。その影には、常にアクセルの存在があった。ふたりはなにを結託していたのか。彼は、ピムを「パーフェクト・スパイ」と評していた。
「われわれは公認の悪だ・・・」
スパイとはどういう職業であるのか。印象に残る場面がある。ピムのカウンターパートである、ウィーン駐在の米国情報部員レダラーは、ピムに好意をもちながらも、二重スパイの疑いを捨てきれず告発側に回る。そのレダラーが、ブラザーフッドにこう告げる。
「おいおい、ジャック、わたしはただ、われわれは公認の悪だといってるんじゃないか。われわれの職業とはなんであるか。知ってるかね、われわれの職業とはそもなにか。自分の盗っ人の天分をお国のご用に供するのがそれだ。だからマグナスが少々薬の配分を間違えたからといって、なぜ彼にたいする気持ちを変えなきゃならん。そんなことはできんよ・・・」
もうひとつの興味、ジャック・ブラザーフッドはピムを捕捉することができるのか。彼は、ピムと関係の深かった人物に次々と当たっていく。そこでの事情聴取を通じて、ピムのスパイ活動の足跡が、おぼろげながら浮かび上がってくる。この追跡劇は興味津々であり、ここから先は実際に物語を読んで楽しんでほしい。
ピムは苦悩と葛藤を背負って生きてきた。「自由の身」になった彼が、下した結論とは―――。
本作について、ル・カレは回想録『地下道の鳩』でこう記している。
〈最終的に『パーフェクト・スパイ』になる小説の最初期の草稿は、自己憐憫にまみれていた――やさしい読者の皆さん、暴君の父親に踏みにじられて感情が損なわれた少年を見てやってください。私は父の死によって完全に解放されてから、ようやく執筆を再開し、最初からすべきだったことをした。息子の罪を父親の罪よりはるかに重くしたのだ。〉
詐欺師の罪より重いものとして。息子は二重スパイとして描かれている。ル・カレの愛読者なら、本作の主人公ピムを英国スパイ史上最大の二重スパイだったキム・フィルビーとかさねあわせて読むこともできるだろう。
そして、年老いた巨匠は、こう述懐するのであった。
〈机の前で悪事を思い描いて白紙のページに綴る男(私)と、毎朝きれいなシャツを着て、想像力以外に何も持たず、犠牲者をだまそうと出陣していく男(ロニー)とのあいだに、はたして大きなちがいはあるのだろうか。〉(『地下道の鳩』)
(本作の文庫は、残念ながら絶版になっている。本稿は、手許にあった単行本の初版をもとに執筆したものである)
「パーフェクト・スパイ」
ジョン・ル・カレ(著)、村上博基(訳)
発行:早川書房
四六版:上巻293ページ、下巻250ページ(上下巻とも2段組)
発行日:上下巻とも1987年4月30日
ISBN:上下巻とも4-15-207647-X