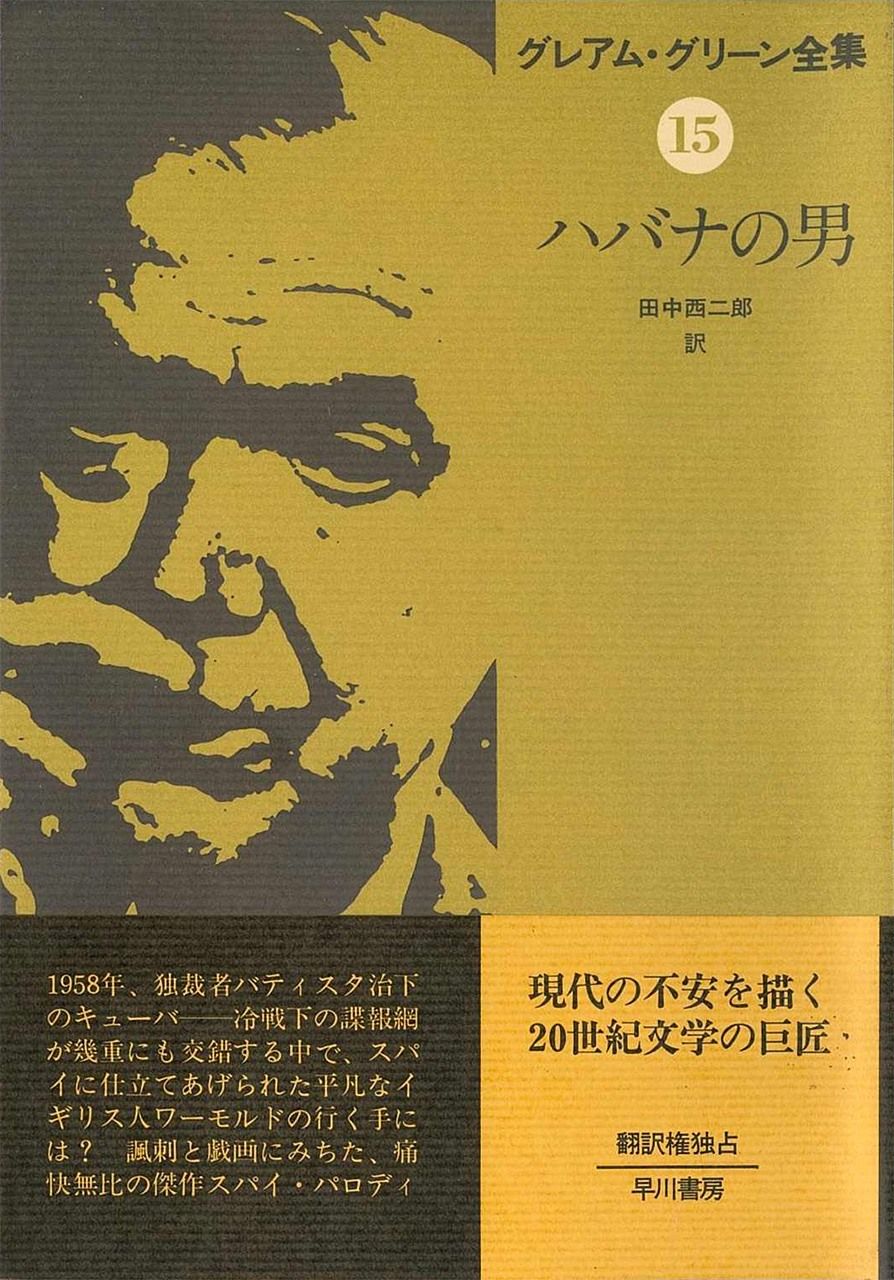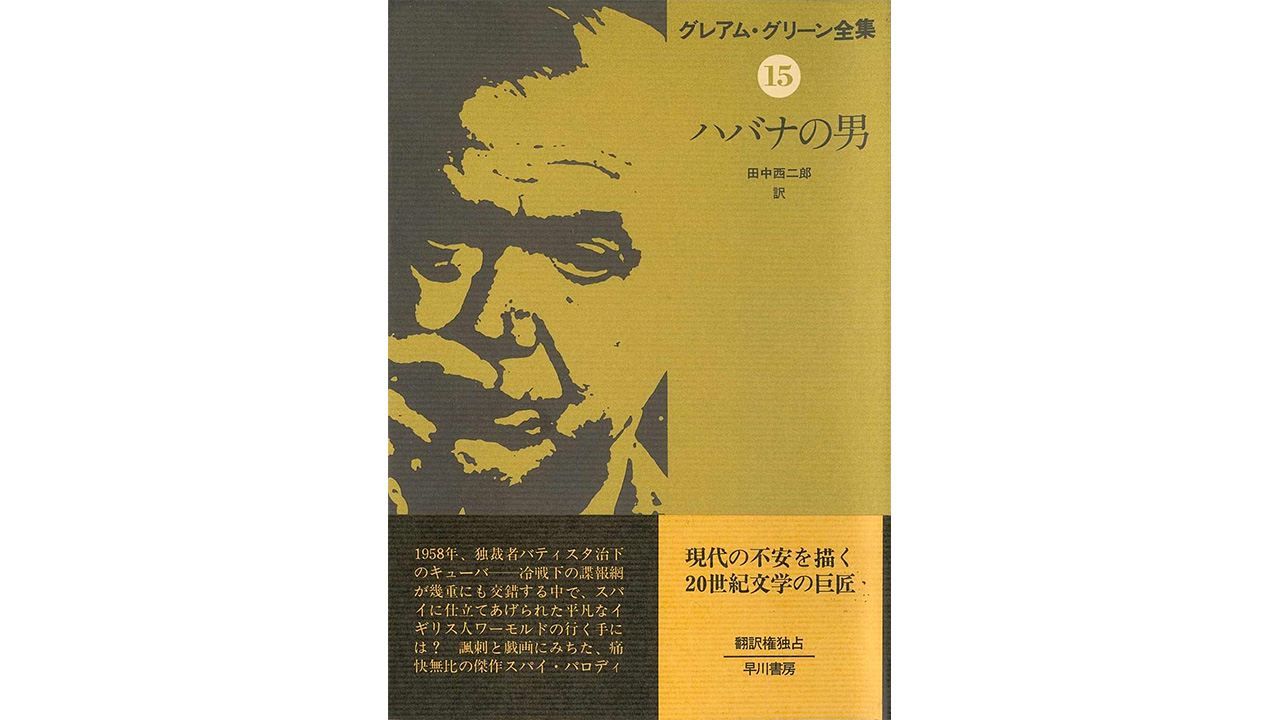
【書評】偽情報に踊らされたスパイを描く古典的名作:グレアム・グリーン著『ハバナの男』
Books 政治・外交 国際 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
以前、この書評で私の好きな英国文壇の巨匠グレアム・グリーンのスパイ小説ベスト3として、『ヒューマン・ファクター』(1978年)と『おとなしいアメリカ人』(1955年)を取り上げた。もう一つがここに紹介する『ハバナの男』である。
本作が発表されたのは1958年のこと。舞台は独裁者バティスタ統治下のキューバであり、カストロによる革命前夜にあたる。冷戦真っ只中のこの時代のキューバは、欧州のベルリンとともに東西両陣営による諜報戦の最前線となっていた。
この物語では、双方が相手の出方を窺い、ある情報をめぐって疑心暗鬼に陥っていく。そこから教えられることがある。不穏な社会情勢下における人間の心理というものは、いつの時代にあってもそれほど変わらないということだ。人は、見たいと思う対象しか眼に入らないし、欲しいと思う情報しか信じないのである。そこに諜報戦の大きな落とし穴がある。今でいうフェイクニュースとは、そうした素地から生み出されるのであろう。
「赤い禿鷹」と異名をとる曲者
それでは物語に入っていく。
主人公のワーモルドは英国民だが、本国の電気掃除機販売会社からハバナにただ一人の駐在員として派遣されている。使用人を一人雇って小さな店を営み、滞在歴は長きにわたる。年齢は45歳で離婚歴あり、16歳の愛娘ミリィと暮らしている。
美人の誉れ高いミリィは、カトリック系の学校に通っている。まもなく17歳の誕生日を迎えようとするとき、彼女はプレゼントとして社交クラブの厩舎にいた栗毛の馬を父親にねだる。それは分不相応に高価なもので、最初、ワーモルドは反対するが、結局のところ涙目で訴える娘の懇願に負け、借金をして買い与える羽目になる。彼の人生にとっては、娘の存在こそがすべてだったのだ。
この娘にからんで、物語の主要な人物が現れる。
社交クラブの入会などの便宜を図ったのが、地元の名士である警察署長のセグーラ警視であった。彼はミリィにぞっこんで、警察車両で彼女の学校の送り迎えを買って出るほどのご執心だったが、ワーモルドは気に入らない。歳の差もさることながら、この男は囚人を拷問することで有名な「赤い禿鷹」と異名をとる曲者だったのだ。
ここで影の主役というべき人物が登場する。
ある日、上品だが見馴れぬ英国紳士がワーモルドの店をのぞきに来た。この男は、英国の諜報機関から派遣されてきたのだが、平凡な人生を送ってきたワーモルドにとっては、この出会いが波乱の幕開けとなる。
「書物暗号法」を伝授する
後日、観光客向けのバーで、ワーモルドはこの人物と再会する。彼は「ホーソーン」と名乗り、ジャマイカを拠点にしてカリブ海の諜報網を操る責任者と自己紹介する。そして、ワーモルドに仕事を持ちかけるのだ。
「仕事など、ほしくありませんよ。なぜあんたはわたしに白羽の矢を立てたんです?」
と、迷惑顔で尋ねるワーモルドに、ホーソーンはこう答える。
「愛国的なイギリス人。この土地に長く住んでいる。ヨーロッパ商社連合会の立派な会員。われわれはハバナにわれわれの担当者が必要なことはおわかりだろう・・・祖国に奉仕するのを拒むんですか?」
ホーソーンはワーモルドに政治経済など現地の事情を調査するよう依頼し、一冊の書物『シェイクスピア物語』を手渡した。この本のページと行から暗号文を作成して報告するようにと、「書物暗号法」を伝授する。
ワーモルドは逡巡する。しかし、娘のことを考えてみるとこの先、なにかと金がかかるであろう。電気掃除機のセールスではそれほど稼げそうにない。彼は、報酬目当てにホーソーンの申し出を渋々承諾するのであった。
もうひとり、肝心な場面に必ず登場する重要人物がいる。ワーモルドとは15年来の友達付き合いになるドイツ人のハッセルバッヒャ医師だ。彼はハバナに30年以上、暮らしている。ベルリンで生まれたというが、その過去は謎だ。
ワーモルドにとっては人生の大先輩で、よき相談相手でもある。しかし、ホーソーンはワーモルドに、「用心して相手にすることだ」と忠告する。
一時帰国したホーソーンは、部長にワーモルドを「信頼できる人物」として報告している。「葬儀屋のような印象」の隻眼の上司は承認を与え、こう返答する。
「・・・一つ、つついてやることだな、そうすればどのくらい役に立つ男か、判定できるだろう・・・ハバナは一つの要衝になりそうな土地だ。共産主義者はかならず紛争の多い場所へ出て来るからね・・・」
部長はワーモルドのことを「われわれのハバナの男」と呼んだ。
ここまでが、物語のお膳立て部分である。
「でも、これはいい本だ」
ところで――。
スパイ小説の巨匠ジョン・ル・カレは、回想録(『地下道の鳩』)のなかで、本作にまつわるエピソードを紹介している。ル・カレがまだ情報部員だった頃のこと、彼は情報部の顧問弁護士から『ハバナの男』には公職守秘法に触れる描写があり、訴追の可能性があると聞かされた。元情報部員のグレアム・グリーンは、戦時中の現役時代に知り得た情報を元にして、「英国大使館にいる支局長と現場の諜報員との関係を正確に」書いていたという。
このときの顧問弁護士の感想がふるっている。
〈「でも、これはいい本だ」彼は言った。「文句なしにいい本なんだよ。そこが困るところでね」〉
グリーンはこの作品で、東西が核開発競争に明け暮れて、不安に煽られ、ありもしない情報に振り回される人々の愚かしさを描いている。主人公が扱う電気掃除機の新製品が「原子炉クリーナー」という商品名であるなど、随所に風刺が効いており、物語は悲劇に向かっていくのだけれど、登場人物たちの行動は、どことなく滑稽に映る。ストーリーは掛け値なしに面白い。
さて、スパイ活動に気乗りのしないワーモルドは、ハッセルバッヒャ医師に相談をもちかける。
「相手はぼくに諜報員を獲得しろというのです。どうすれば諜報員なんか獲得できますかね・・・?」
医師は、「でっちあげればいい」とアドバイスする。「もしそれが充分に秘密のものなら、あんた一人しか知らないわけだ。あんたに必要なのは、いささかの想像力をはたらかせることですよ・・・」そしてこう付け加える。
「しかし、これだけは憶えておきなさい。嘘を教えている限り、あんたは何らの害をもなさないということを」
ワーモルドは、娘ミリィの部屋から社交クラブの名簿を持ちだした。そこから諜報員にむきそうな人物を3名選び、スカウトに成功したと嘘をつき、さらに政府報告やハバナの日刊新聞を参考にして適当なレポートをまとめ、暗号文で本国に送った。一週間後、英国領事館経由で、給与と経費が届くのだ。
まるで監房のなかの鼠のように
ここから波紋が広がっていく。
ある夜、ハッセルバッヒャ医師の自宅に何者かが侵入し、散々、部屋を荒らした挙句、彼の大事ななにかを奪っていった。悲嘆に暮れる医師。そのことを聞いたワーモルドは、自責の念にかられる。
〈・・・ワーモルドは罪悪感が、まるで監房のなかの鼠のように、からだのあちこちを噛むのを感じた。おそらく、まもなくこの鼠とおれとは仲良しになって、〃罪〃はおれの掌から餌を喰うようになるんじゃないか。これはおれと同じような人間どものやった仕事だ――〉
〈どうせゲームをやるなら、渋々いいかげんな気持ちでやって、何の役に立つか?すくなくとも、金をはらったやつらが楽しめるようなもの、やつらの書類綴りに綴りこむにしても、経済リポートなんぞよりましなものを、くれてやるべきだろう〉
ワーモルドは、壮大な嘘をでっちあげ、本国に報告する。その内容はざっとこんな具合――、サンチャゴを旅行中、重要な情報を耳にした。東部州の山間に巨大な軍事施設が建設されている模様。これはホテルの酒場で酔った「キュバナ航空」のスペイン人操縦士から聞き出したものである。
この情報により、自身も現地へ赴いた。そこには大規模なコンクリート砲床のようなものがあり、怪しい機械が運び込まれていた。その見取り図を送る。
ワーモルドは電気掃除機を解体してバラバラにした。それぞれの部品を見ながら精密な図面を描き、巨大な機械であるかのように大げさな寸法を書き込んだ。
急ぎ、ホーソーンが本国に呼び戻される。
「われわれのハバナの男が、最近、容易ならんものをもち出してきた・・・」
部長は興奮している。
「・・・ぜひ写真を手に入れなきゃならん。どんな危険を冒してもだ・・・これはな、わしの信ずるところでは、水爆ですらごく古くさい兵器になってしまうほどバカでかいものにぶつかったのかも知れんぞ・・・ソヴェートでは何か新しい着想で研究しているという噂は、きみも聞いとるだろうが・・・・」
部長は、ホーソーンの手柄と褒める。
「・・・一度わしは他人から、きみの人間に対する判断がなっていないと言われたことがあるが、わしはわし個人の判断を頼りにした。よくやったぞ、ホーソーン」
ふたりには出世の野心がある。もはや疑問をはさむ余地なく、彼らはワーモルドの偽情報にすがっていくことになる。ワーモルドの諜報活動を補助するために、あらたに2人の要員をハバナに送り込むことも決めた。
ここから先、事態は急展開していくのである。
英国の動きを探っていた東側
あと少しだけ物語に触れておけば、予期せぬ殺人事件が次々と起こる。ワーモルドが本国に報告していたスペイン人のパイロットや諜報員が、謎の死を遂げるのだ。確かに実在する人物だが、彼自身一度も会ったことのない、架空の情報源であったにもかかわらず。それは何故か?ここからの展開が最大の読みどころであり、ワーモルドは東西両陣営の陰謀に巻き込まれ、窮地に追い込まれていく。
ここでの警察署長のセグーラ警視の役回りが秀逸である。
「ぼくの仕事はハバナで起こりつつあることを知ることであって、どちらの味方についたり、情報を提供したりすることじゃありません」
と、警視はワーモルドに言う。彼は東西両陣営の諜報戦に通じている。謎解きの一端を明かせば、英国の動きを探っていた東側も、ワーモルドの偽情報に振り回されていた。セグーラ警視は冷ややかに言う。
「・・・あんたの電信の一つに、あんたがロンドンへ送った図面のことが書いてあった・・・ところがそのうちに暗号が変わり、部下がふえた。イギリス諜報本部ともあろうものが、そうたやすく騙されるはずはないと思うのは当たり前でしょうが?」
グレアム・グリーンのシニカルな人間観察は際立っており、そしてまた、全編を通して描かれるハバナの都市風景や、路地裏の猥雑な風俗にはおおいに興味をそそられるだろう。
いたるところ、ラムやダイキリの香りが漂ってくる。だが、くれぐれも情報の取り扱いには要注意――。
「ハバナの男」
グレアム・グリーン(著)
発行:早川書房
四六版:247ページ(2段組)、グレアム・グリーン全集第15巻
価格:2200円(税別)
発行日:1979年11月30日
ISBN:4-15-200315-4