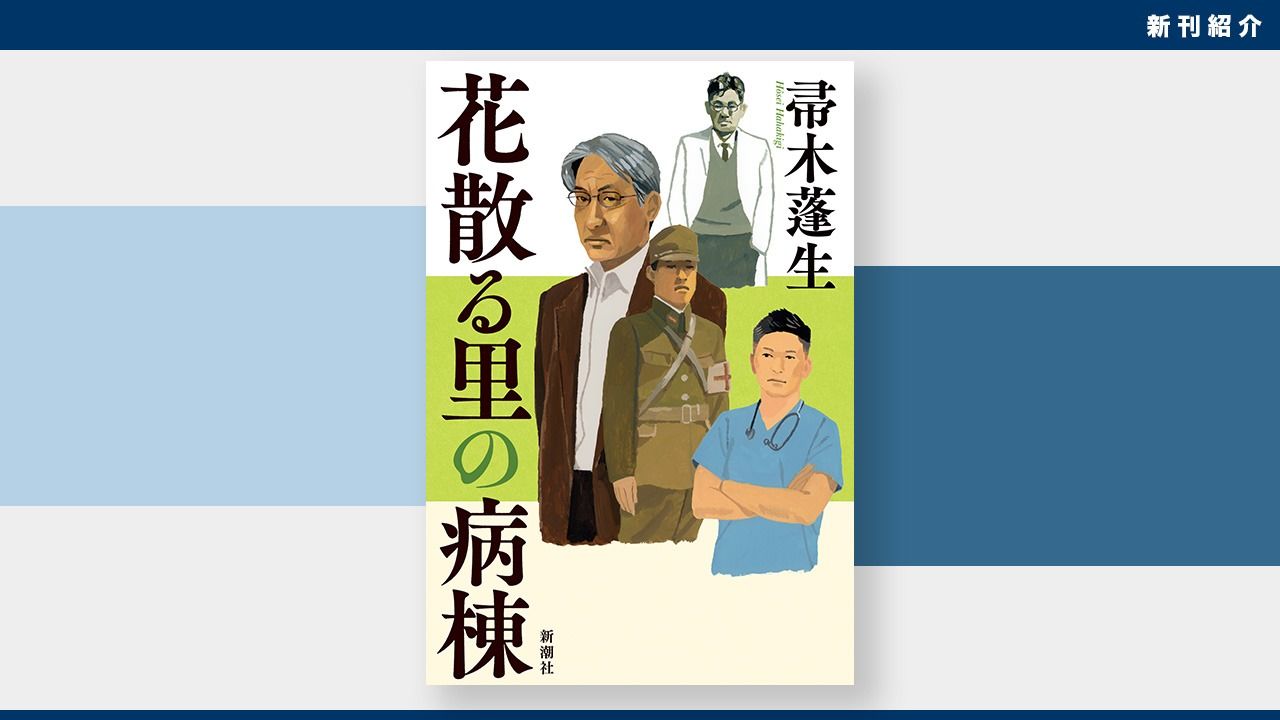
【新刊紹介】コロナ禍までの百年、医者4代の感動物語:帚木蓬生著『花散る里の病棟』
Books 健康・医療 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
10年かけた労作
著者の帚木蓬生(ははきぎ・ほうせい)は、福岡県の精神科医でもあり、映画にもなった『閉鎖病棟』で山本周五郎賞を受賞するなど、多くの文学賞を獲得した作家である。
本書はこの100年を医者、患者、その家族らの眼で描くため、10年をかけた労作となった。作品の特徴は、時代の流れに沿って書くのではなく、初めは2010年の話で、次は1936年というように、時代を行き来しながら10本の短編で進んでいくオムニバスになっている。各章の主人公も年代も毎回変わるが、4代にわたる医師たちが父、祖父らを少し意識しながら、町医者として、地元のため懸命に尽くしていく。
初代は大正期に腸の寄生虫退治がうまく、2代目は軍医としてフィリピンの野戦病院に赴き、敵機襲来と激しい飢えで生死をさまよう。3代目は高齢者医療に、そして留学して肥満治療を学んだ4代目は、同じ医師との結婚の矢先にコロナ禍に巻き込まれていく。
読者の涙を誘うのは、3代目が、戦場に行った父とほぼ同時代の大正15年(1926年)生まれの女性患者から聞いた話を綴った「胎(こ)を堕ろす 二〇〇七年」の章だろう。戦中期、朝鮮半島の赤十字病院で看護生徒だったこの女性は、博多に引き揚げ、家族と再会して間もなく、ある保養所に集合するよう連絡がくる。そこで、引き揚げ途中に心ならずも妊娠させられた女性たちの手術をしていった。
極度の栄養失調で手術も出来ないまま、「くやしい」と言って息を引き取った17歳の生徒もいたという。日本の医療現場100年を描くにあたり、著者は戦争の悲惨さを訴えることを忘れてはいない。
最終章の「パンデミック 二〇一九―二一年」も、医師である著者はコロナ病床をリアルに描き出し、政府・行政サイドの対応のまずさも物語の中に盛り込んでいる。ワクチン接種の遅れの問題で、父(3代目)は息子にこう言う。
「ワクチンが早ければ、その(死んだ患者の)半分は死なんでよかった人たち。無念じゃろね、鉄砲も持たずに戦場を歩かされたとに似とるよ。遺族も、悔やんでも悔やまれんじゃろ」
福岡弁と俳句
本作で、登場人物の会話がほとんど福岡弁で書かれているのも、地元に息づく町医者らしさを深めている。筆者は数年前、著者(帚木氏)を別の著書についてインタビュー取材した際、帚木さんの心地よいなまりを耳にしたが、その福岡弁が本作にそのまま生かされている。
もう一つ、本作の質を高めているのが、文章の流れを的確にとらえた、何十句も登場する俳句である。
患者らの 飢えたる小屋に 春の月 (フィリピンの戦場で)
コロナ明け 新芽を伸ばす 医家の幹
75歳になった著者の教養と、医師としての体験、作家としての構成力の巧みさが結実した作品になっている。
新潮社
発行日:2022年4月25日
361ページ
価格:1980円(税込み)
ISBN:978-4-10-331426-4
