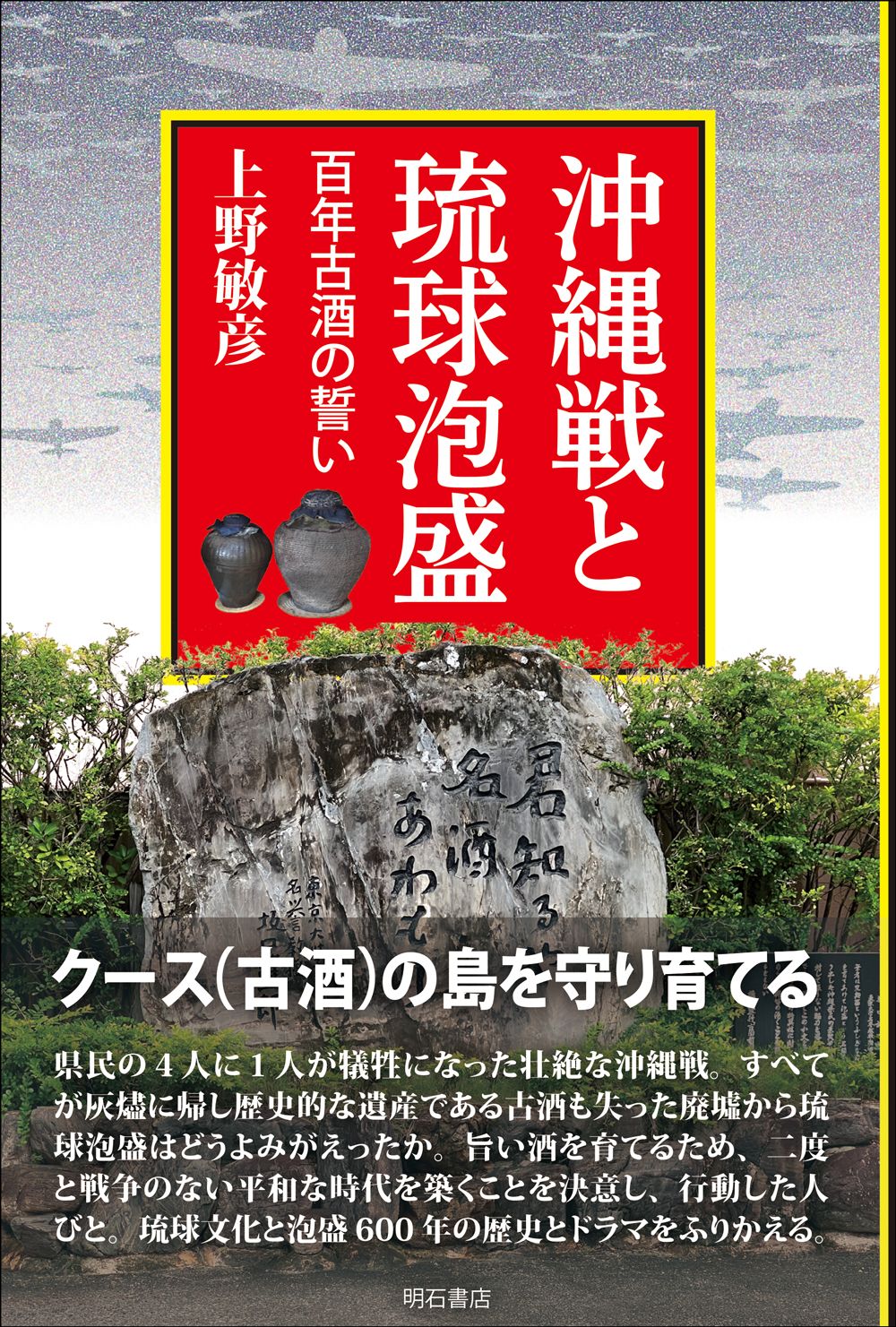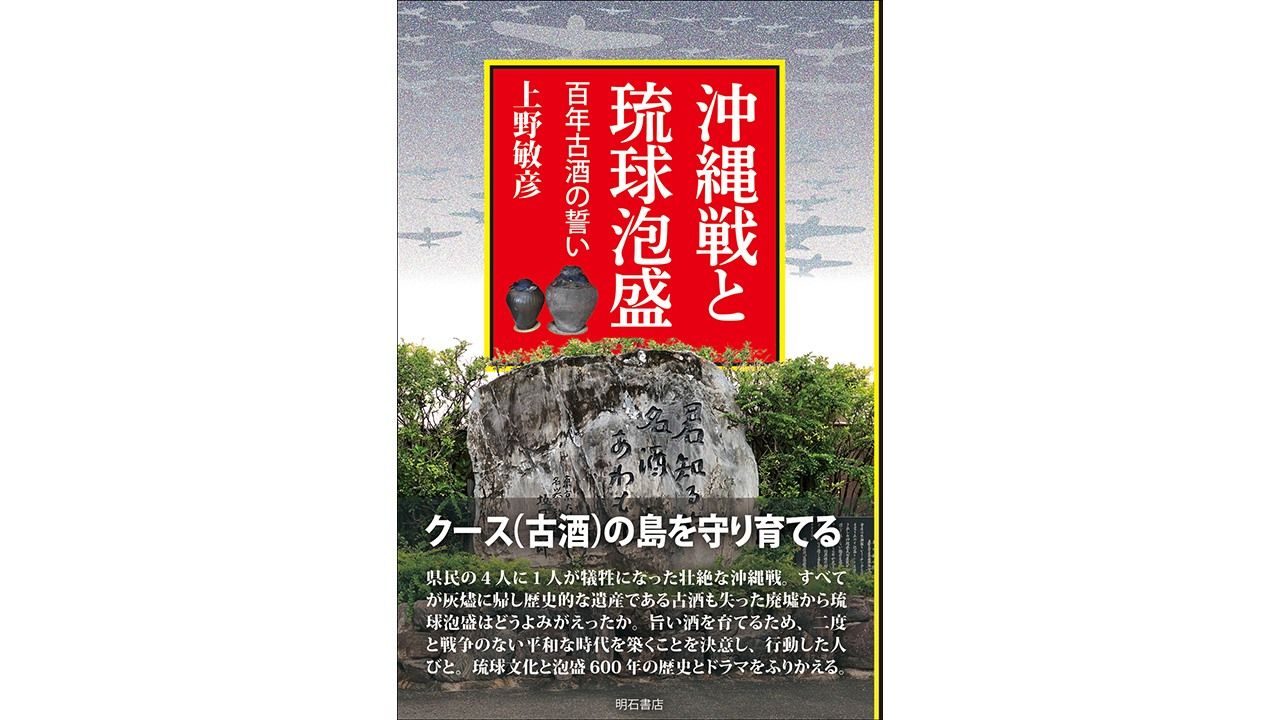
【書評】平和の酒をめぐる壮大な人間ドラマ:上野敏彦著『沖縄戦と琉球泡盛 百年古酒の誓い』
Books 歴史 社会 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
600年の歴史誇る最古の蒸留酒
米や麦など穀物を原料に酒を造るにはまず、その原料を糖化させるために「麹(こうじ)菌」を使うことが多い。約600年の歴史を持つ泡盛は伝統的にタイ産のインディカ米(長粒種米)と 「黒麹菌」(学名アスペルギルス・ルチュエンシス)で造る蒸留酒だ。本書ではこう説明している。
タイ米は硬質米のため蒸してもサラサラしていて黒麹を繁殖させやすく、発酵管理がしやすい利点もあるという。この黒麹菌から出るレモンのような酸味の強いクエン酸が、醪(もろみ)の雑菌繁殖を抑える作用をする。その結果、気温が高い沖縄では黒麹を使えば、一年を通しての酒造りが可能になる。
実は九州各地の焼酎の源流は沖縄だ。鹿児島や宮崎の芋焼酎、熊本の米焼酎、大分や長崎の麦焼酎などは、黒麹菌が変異した白麹菌や清酒を造る黄麹菌を使う。黒麹菌のみを使って酒造りを続けてきたのは沖縄だけであり、泡盛は「日本最古の蒸留酒」といわれる。薩摩の芋焼酎よりも歴史は古い。

沖縄本土復帰50周年の今年、沖縄県物産公社の「銀座わしたショップ本店」では県内全45酒造所復刻ラベルミニボトルをガラスケース内に展示している(2022年7月28日、東京・銀座1丁目で評者撮影)
大空襲や地上戦で存続の危機
泡盛は、長い年月をかけて熟成させれば、「クース」と呼ばれる古酒に育っていく。沖縄では甕(かめ)や瓶(びん)に入れて熟成させることを「寝かせる」と表現する。寝かせれば寝かせるほど、甘い香りや芳醇な味わいが増す。
沖縄では1944年10月の米軍機による大空襲や米軍上陸後の地上戦で「県民の4人に1人が犠牲になった」という凄惨な過去がある。沖縄が焦土と化すまでは、中国の康熙年間(1662-1722年)に造られた300年近い超古酒も存在していた。戦渦で百年を超える古酒は壊滅状態になったという。
琉球王朝時代の17~18世紀、泡盛は首里城の周辺の「首里三箇(しゅりさんか)」に限って製造が許された。三箇とは赤田、崎山、鳥堀の三つの村を指す。琉球王国崩壊後は沖縄全土に泡盛製造業者が生まれ、その数は19世紀末には447戸、そのうち約100戸が首里の酒屋だったという。
先の大戦で、城下町である首里三箇も激しい戦闘に見舞われ、廃墟となった。泡盛造りに必要不可欠な黒麹菌も絶滅したかと思われた。「沖縄の宝」だった古酒文化だけでなく、泡盛造りの存続さえ危ぶまれたのである。
首里の焼け跡から蘇った黒麹菌
戦後の泡盛再生には、劇的な出来事があった。首里三箇の蔵元のひとつ、咲元酒蔵の二代目、佐久本政良(さくもと・せいりょう)氏が終戦直後の1945年12月、酒蔵の焼け跡から奇跡的に黒麹菌を“発見”したのだ。
佐久本氏は戦時中、沖縄県中部の捕虜収容所に入れられていたが、終戦とともに首里に帰ってきた。当時48歳。酒蔵の焼け跡に埋もれていたニクブク(蒸し米に黒麹菌をまぶして敷く稲わらのむしろ)を見つけ、そこに生き残っていた黒麹菌を少しずつ培養し、他の蔵元にも無償で配布した。本書ではこう記述している。
蔵の地下に埋めて置いた古酒の甕はすべて割れて泡盛は外へ流れていたが、佐久本はこの黒麹菌を瑞泉酒造や識名酒造など首里のその他の蔵にも分けあたえ、戦後の泡盛復興への道を開いたのである。
佐久本氏は「酒造りの守り神」と呼ばれた。1987年に92歳で天寿を全うするまで、泡盛の生き字引でもあった。
「泡盛のご意見番」と「古酒の番人」
佐久本氏が戦後の泡盛再生の立役者だったとすれば、沖縄には「泡盛のご意見番」と「クースの番人」も存在した。
本書によると、ご意見番は、琉球泡盛復権のためのタブロイド紙「醸界飲料新聞」の編集発行人で、泡盛同好会を立ち上げた仲村征幸(なかむら・せいこう)氏。番人とは、泡盛専門の居酒屋「うりずん」の創業者で、古酒の魅力を県内外に発信した土屋實幸(つちや・さねゆき)氏である。

「泡盛のご意見番」仲村征幸氏(右)と「クースの番人」土屋實幸氏の2014年当時の写真=本書口絵
仲村氏は1930年11月、沖縄県北部の本部町具志堅に生まれた。子どものころから泡盛には関心があった。県立名護高校を卒業、いくつかの仕事を経て「沖縄朝日新聞」、「琉球新報」など戦後ジャーナリズムの第一線で活躍した。
米国統治下の戦後の沖縄は輸入ウイスキーがもてはやされ、泡盛会社の社長すら自分の蔵の酒を呑まないような状態だったという。洋酒ブームの中で、泡盛は飲み屋でもカウンターの下に隠されるなど、日陰の存在だった。仲村氏は「どん底状態の泡盛を何とか盛り立てたい」と、1969年に「醸界飲料新聞」(現「泡盛新聞」)を創刊した。
泡盛業界をめぐる話題や将来への提言、酒や居酒屋の紹介などをタブロイド判四ページに収めて、年に数回約五千部を発行した。取材や記事の執筆、広告営業、販売とすべてを仲村一人でこなし、離島にまで自ら新聞を運んで行った。
一方、土屋氏は1942年2月に那覇市で生まれた。県立那覇高校を経て、東京の東洋大学に入学、苦学してUターンした。沖縄が本土に復帰した1972年、それも終戦記念日の8月15日に「うりずん」を開業した。木造二階建てで、「泡盛古酒と琉球料理」の看板がかかる。
輸入ウイスキー全盛の時代に弱冠三十歳の好青年が抱いた大志は、離島も含め沖縄全土にある五十七蔵の泡盛すべてを自分の店に集め、島酒ファンを増やすことだった。
土屋、仲村両氏が主導したのが「百年古酒プロジェクト」だ。1997年12月、沖縄県糸満市で「泡盛百年古酒元年」の発会式が挙行された。
百年古酒プロジェクトは、会員三千人が千円の会費を出し合って三石甕(約五百四十リットル)五本、一升瓶で千五百本分の泡盛を百年の長く深い眠りにつかせた。
酒を呑めるようになるのは二〇九七年だから会員本人が賞味することはまず不可能だが、子どもや孫、知人に権利を譲渡していい仕組みになっている。
土屋氏は会員自身が呑めないかもしれない古酒を長年貯蔵する意味について次のように説明した。
「泡盛を百年熟成させるというのは、そのあいだ沖縄が平和でありつづけるということ。あの戦争がなければ自分たちだって数百年ものの古酒を呑めたのだから、古酒を造りつづけることは戦争をしないという強い意思表示の表れでもあるのです」
泡盛、とりわけ古酒が「平和の酒」、「和合の酒」といわれる所以だ。ちなみに古酒の定義は「全量が泡盛を3年以上貯蔵したもの」で、古酒を育てるには年代ものの古酒にそれより少し若い古酒を注ぎ足す「仕次(しつ)ぎ」という泡盛独特の手法がある。
「鉄血勤皇隊」OBの波乱の人生
太平洋戦争の最終局面で、日米が沖縄諸島を舞台に凄まじい闘いをした「沖縄戦」には多数の住民が巻き込まれた。旧日本軍による集団自決強制、住民虐殺、食糧強奪なども相次いだ。沖縄戦は「米軍の死者一万四千名余に対して日本軍の死者九万名余、非戦闘員の一般住民の犠牲者は十五万名余を数えた」という。沖縄戦をめぐる様々な人間模様を活写しているのも本書の特徴だ。
戦局も押し詰まった1944年3月、旧日本軍は本土決戦の防衛ラインとして沖縄を守るため、第三十二軍(牛島満司令官)を編成した。東京の大本営は「沖縄を本土防衛のための捨て石として必要な存在と位置づけた」からだ。
第三十二軍は米軍が上陸する4カ月前の同年12月から、那覇の小高い丘の上に立つ首里城の地下に司令部を突貫工事で作った。琉球王国時代からの“聖域”の地下の石灰石の岩盤を地下約30メートルまで掘削し、総延長1キロ余の地下壕(ごう)は巨大な軍事要塞となった。
24時間3交代の突貫工事には学生や一般住民も動員された。近くの旧制第一中学(現県立首里高校)や沖縄師範学校の学徒兵は「鉄血勤皇(てっけつきんのう)隊」と呼ばれた。その一員だった與座章健(よざ・しょうけん)氏の波乱の人生は本書の随所で触れられる。
一中4年生だった與座氏は新米二等兵。1945年4月のある日、地下豪司令部で待機中に上官から「崎山町の酒造所に行って泡盛を汲んで来い」と命令を受けた。
米軍の爆撃におびえながら勤皇隊の二、三人と空の石油缶を二つつるした天秤棒を担いで酒蔵へ。缶に泡盛をなみなみと満たして地下壕へ戻る途中、頭上でいきなりバーンという音とともに米軍の榴散弾がさく裂し、地面に破片の雨が降り注いだ。
この時は地下壕に逃げ帰り、一命を取りとめた。しかし、勤皇隊員たちは教導兵らの理不尽な命令にも従わざるを得ない奴隷のようだったという。「口答えなどしようものなら、往復ビンタを食らい、体が立たなくなるくらい激しい体罰を受けた」。爆薬を抱えて敵戦車に体当たりするようにと命令された隊員もいた。與座氏は多くの学友を沖縄戦で失った。
戦後、與座氏は米国が学費を出す本土への留学制度に応募し、日本大学経済学部で学んだ。沖縄に戻ってからは琉球政府で金融検査の仕事をした。1964年にはかつての敵国、米国のペンシルベニア大学に1年間留学し、英語と会計学を習得した。
日本に戻ってからは琉球政府金融検査庁次長として本土復帰後の通貨交換の際、1ドル=360円の交換率を保証する手順づくりの作業に携わった。その後、沖縄相互銀行(現沖縄海邦銀行)副頭取などを歴任、沖縄経済の復興に貢献してきた。
與座氏は沖縄戦が終結した慰霊の日である2015年の6月23日、母校での追悼式で、次のように挨拶した。
「あちこちで旨い泡盛が造られ、みなが喜んで呑む。太平な時代が訪れたものだと思う。もうあのような愚かな戦争を二度と起こしてはならない」
卒寿を迎えた與座氏は今も、鉄血勤皇隊OBとして地道な反戦活動を続けている。
本土復帰50周年の沖縄の現実
2022年は沖縄の本土復帰50周年である。その節目に上梓された本書の著者、上野敏彦氏は1955年神奈川県生まれ。共同通信の記者となった2年目の夏、初めて沖縄を訪問し、その魅力に引き込まれた。沖縄勤務という夢は叶わなかったが、休暇がとれるたびに沖縄に通い続けた。
佐久本氏はすでに他界していたが、土屋と仲村の両氏からは本人たちが亡くなる前に生々しい内幕話を聞くことができた。そして休暇をとっては沖縄入りをくり返すうち見えてきたのが、六百年の歴史をもつ琉球王国の酒造りにまつわる壮大なドラマだったのである。
本書には実に多くの人物が登場する。講談社を創立した野間清治氏は若いころ、沖縄第一中学の教諭だった。当時の弟子たちから贈られた泡盛の甕は東京の野間家の倉庫に眠っていた。2009年12月、講談社創業百年の社員懇親会で、この「百年古酒」が振る舞われた。
琉球王国最後の王の四男、尚順(しょう・じゅん)男爵は琉球泡盛の古酒をこよなく愛した。本人は下戸だったとされるが、「古酒の話」や「豆腐の礼賛」などの文献も執筆した。泡盛のつまみになる「豆腐よう」を「世界的唯一と迄は行かざるも主位に列なる珍味」と評した。

評者が味わった泡盛の古酒と豆腐よう(2022年7月30日、都内で撮影)
豆腐ようは沖縄の島豆腐を米麹、紅麹、泡盛で発酵・熟成させたもので、チーズのような風味がある。著者は「古酒との相性も良く、知る人ぞ知る名物」と解説している。評者も実際に味わってみたが、古酒との組み合わせは絶妙だった。
尚順は貴族院議員を務め、「琉球新報」を創刊したり、沖縄銀行を設立したりした。地元政財界に大きな影響力を持ち、文化人でもあった。72歳になっていた尚順は1945年6月、糸満市の避難壕で衰弱死した。
泡盛の生産量は2004年にピークを迎えたが、その後は伸び悩んでいる。「百年古酒」の再興に尽力した仲村、土屋両氏は2015年に相次いで鬼籍に入った。著者は「二人が帰らぬ人となり、琉球泡盛の世界も一つの転機を迎えたといっていいのかもしれない」と指摘する。
かつて「捨て石」とされた沖縄は現在、在日米軍基地が国内で最も多く、日米同盟の「要石」となっている。しかし、沖縄全土にはいまだ多くの遺骨や貴重な古酒が埋まっている。さらに地中に眠る不発弾の処理にはあと70年もかかる見通しだ。
「百年古酒」とは実は戦争の“対義語”だった――。戦後77年、本書はそんなことを教えてもくれる。
琉球・沖縄と泡盛をめぐる歴史
| 1429年 | 琉球王国が成立(尚巴志、琉球を統一) |
|---|---|
| 1609年 | 琉球王国、薩摩藩の支配下に入る |
| 1671年 | 将軍家への献上品目に初めて「泡盛」の名が記載 |
| 1719年 | 新井白石、『南島志』で泡盛の詳細な製造法を記述 |
| 1853年 | 米国のペリー提督一行が那覇来航、夕食会に古酒 |
| 1879年 | 琉球処分により沖縄県設置、琉球王国の歴史に幕 |
| 1944年 | 米軍機による大空襲で那覇市は壊滅的打撃 |
| 1945年 | 太平洋戦争終戦、首里の酒蔵の焼け跡から黒麹菌発見 |
| 1950年 | 那覇市牧志の桜坂に「民藝酒場おもろ」開店 |
| 1955年 | 那覇市牧志の竜宮通りに赤提灯「小桜」開店 |
| 1969年 | 仲村征幸氏が「醸界飲料新聞」(現「泡盛新聞」)創刊 |
| 1970年 | 坂口謹一郎教授、「君知るや名酒泡盛」を執筆 |
| 1972年 | 沖縄本土復帰、土屋實幸氏が泡盛専門の居酒屋「うりずん」開業 |
| 2000年 | 九州・沖縄サミット晩さん会で古酒「春雨」が乾杯酒に |
| 2015年 | 泡盛のご意見番・仲村氏とクースの番人・土屋氏が死去 |
| 2019年 | 首里城で大火災、正殿など焼失 |
| 2022年 | 沖縄本土復帰50周年 |
『沖縄戦と琉球泡盛 百年古酒の誓い』
上野 敏彦(著)
発行:明石書店
四六判:328ページ
価格:2750円(税込み)
発行日:2022年7月15日
ISBN:978-4-7503-5429-3