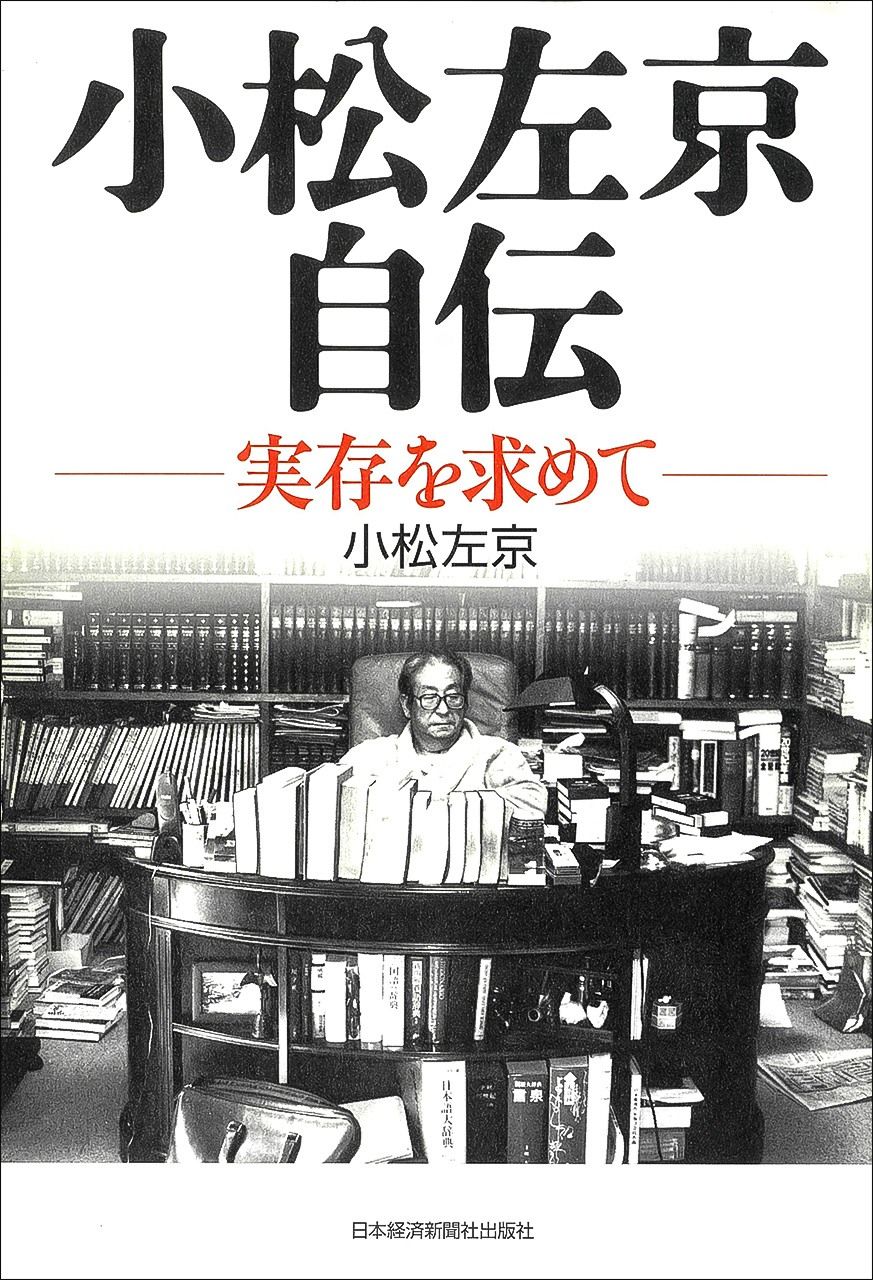小松左京の大ベストセラー『日本沈没』から50年:名作誕生の舞台裏
Books 気象・災害 防災 社会 科学- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
最初のタイトルは『日本沈没』ではなかった
「僕が小松さんの担当になったのは、小松さんが『日本沈没』を書き始めて4、5年経った頃でした。企画段階から関わったわけではないので、担当としては3代目、小松さんの『日本アパッチ族』がカッパ・ノベルスで刊行されてすでに数年が経っていました」と語るのは、当時、小松左京を担当していた光文社の編集者・浜井武氏(85)である。
小松左京は1961(昭和36)年に「小松左京」のペンネームで作家デビューし、次々とSF作品を世に送り出す。64年には初の長編小説『日本アパッチ族』(光文社)や『復活の日』(早川書房)を刊行し、小松は星新一、筒井康隆と並びSF小説の「三羽烏(がらす)」と呼ばれるほどの人気作家となっていく。
『日本沈没』は1973年3月、カッパ・ノベルスとして上下巻で刊行された。400字詰め原稿用紙にして1300枚の大作である。出版までの経緯はどうであったか。
「僕が担当したときに引き継いだ原稿はまだ200枚ほどで、1枚目の原稿用紙は黄ばんでいた。なるほど時間がかかっているのだなと思いました。小松さんは万年筆で書いていて、丸っこい字ですが読みやすかった。そこからが僕の仕事になったわけですが、これがなかなか書き終わらないんですよ」

「最初のタイトルは『日本滅亡』だったんです」と語る浜井武氏。手元にあるのは光文社カッパ・ノベルス版の『日本沈没』(ニッポンドットコム編集部)
意外なことに、最初に付けられたタイトルは『日本沈没』ではなかったという。
「そのときの題は『日本滅亡』だったんです。僕は、前任者から日本列島が沈没する話だと聞いていたので、てっきり『日本沈没』だと思いこんでいました。当時、小松さんは少し書くと郵便で原稿を送ってきた。だいたいが400字原稿で10枚かそこら。封筒には『日本滅亡原稿在中』と書いてあった。僕はそれをコピーして。コピーがないと小松さんが続きを書きにくいですから、本原稿はこちらでいただくけど、僕は封筒に『日本沈没原稿在中』と書いてコピーを送り返していたんです」
たちまち400万部を超える大ベストセラーになった
「最終的に出版する際に『日本沈没』というタイトルになりましたが、僕が勝手に考えたわけじゃなくて、小松さんもOKしてくれたからそうなったわけですが・・・」と、浜井氏は続けるが、『日本沈没』は書き始めてから完成までに9年の歳月を要した。
「やはり小説の内容が非常に難しいものなので、小松さんは地球物理学の竹内均さんをはじめ、専門家の方々に話を聞いて勉強されていたので時間がかかったと思う。もうひとつは、小松さんは他にもいろいろな仕事を抱えていて、特に大阪万博(1970年開催)の企画に関わっていたので執筆の時間が足りなかった。あと、70年安保と絡んで、光文社では労働史上有名な労使紛争というのがありまして、組合が2つに分裂し、社内はガタガタしていた。だから作家に原稿催促なんてできなかったんですよ」
ここで『日本沈没』のあらすじを紹介しておこう。小笠原諸島にある無人島が、一夜にして海に沈んだ。深海潜水艇の操縦士小野寺は、異端の地球物理学者・田所博士とともに海底を探索。田所博士は、日本海溝に不気味な異変が起こっていることを察知する。以後、日本各地で地震や火山噴火が頻発し、政府は田所博士らに海底調査を命じるが、ついには第二次関東大震災が首都圏を襲い、富士山大噴火に至る。いよいよ日本列島全体の沈没が避けられない事態となって、政府は密かに国民の海外移住をオーストラリアなど各国に打診するが――。
本作は当時の最先端の地球物理学を下敷きにしており、大陸移動説、プレートテクトニクス理論、マントル対流など、ストーリーの展開は、科学的専門知識に裏付けられており、それだけ迫真のリアリティがある。
「僕は、原稿を読んでいて、これは面白い作品だと思った。だけどカッパ・ノベルスは松本清張さんはじめミステリーを中心に売ってきたから、傍流のSFでどのくらい売れるのかわからなかった。しかも上下2冊ですから。会社の販売部なんかは、『清張さんの小説でも上下2冊は売りにくいのに』と、いい顔しないわけですよ。それで僕はひどいですよね、『先生、これ1冊になりませんか?』と言うわけです。小松さん怒ってね。『君はなんてこと言うんだ!俺が一生懸命書いたものを!』と言われました」
当時のカッパ・ノベルスは、初版の刷り部数3万部という決まりがあり、そこから増刷を重ねていく。『日本沈没』は上下で6万部からスタートした。ところが、「売れるだろうか」という心配を覆して、各出版取次会社に予告の案内を出したところから事前の注文がどんどん来たという。発売直後、新聞各紙に全5段で迫力のある広告を打ち、たちまち400万部を超える大ベストセラーになった。
「まず、『日本沈没』というタイトルが面白いでしょ。ブクブクと日本が沈んでいく。『日本滅亡』だとちょっとシリアス過ぎるんじゃないか。それがこの小説が受けた一つの理由ではないかと思うんですよ。当時、会社の販売部に、下町のおばさんから電話がかかってきて、『日本沈没はどこへ行ったら買えるのか』と問い合わせがあった。『本屋さんに行ってください』と答えたというくらいで、日頃、本を買わない人たちが買ってくれた。そうでないと大ベストセラーにはならない。毎週、5万、10万部と増刷していったくらいですから。上下巻あわせて398万部までは僕も覚えていました。小松さんは『もう刷るのはやめてくれ。あとは税金で取られちゃうだけだから』なんて言ってたんですよ(当時の所得税の最高税率は75%だった)」
『日本沈没』は未完の大作だった
ところで、『日本沈没』の下巻、物語が終わった末尾に「第一部完」とある。小松左京は続編として「第二部」を書くつもりだったのか。浜井氏は語る。
「これには小松さんとの間にやりとりがありました。僕は『日本沈没』はこれで完結していて十分面白いと思った。だけど小松さんは第一部だと言わせてくれ、と。カッパ・ノベルス版の『日本沈没』の『著者の言葉』にも『これは架空の物語の第一部と思ってほしい』と入っています。小松さんは、『日本漂流』というタイトルで日本民族が世界に散ってからの話まで書きたかったんですね。当時の僕は知らなかったけど、後に、その構想を書いた紙が出てきている。それなら僕はもっと続編を催促すべきだったなあ、と後から思うんですよね」
小松にとって、刊行された『日本沈没』は未完の大作だったのである。そして、第一部刊行後の夏、小松と浜井氏らはオーストラリア一周の旅に出る。「ベストセラーになったので、光文社から作家へのボーナスみたいなものでしたが、小松さんにとっては続きを書くための取材旅行でした」と浜井氏は言う。その後、小松は地球物理学者の竹内均氏らと火山国のアイスランドへの取材旅行も敢行していた。

小松左京(右)と編集者の浜井武氏(左)。取材のため、飛行機をチャーターしてオーストラリア各地を回った(浜井武氏提供)
ちなみに、2006年、『日本沈没』が再度映画化された際に、小松は作家の谷甲州との共著という形で『日本沈没第二部』を出している。浜井氏は、「小松さんはすでに高齢だったこともあり、僕はそもそもの『日本漂流』とは別物だったのではないかと思っています」と言う。
「日本人とは何か、日本とは何かを考え直してみたい」
小松左京にとって、『日本沈没』は何を意図した作品だったのか。浜井氏はこう考えている。
「当時、山本七平さんがイザヤ・ベンダサンの筆名で『日本人とユダヤ人』を書いてベストセラーになっていた。小松さんの『日本沈没』は、要するに、日本民族が国を失って、世界に散り散りになっていく。ちょうどユダヤ人と同じですよね。そうしたときに、はたしてユダヤ人のように生き残っていけるのかという問いかけがある。どうやって流浪の民となった日本人が世界で生き延びていくのか、小松さんはそれを描きたかった。『日本沈没』の次に『日本漂流』があって、その全体でもって『日本滅亡』だったんですね」
小松左京自身はどう考えていたか。作家は執筆動機についてこう書き残している。
「書き始めた動機は戦争だった(略)日本人は高度経済成長に酔い、浮かれていると思った。あの戦争で国土を失い、みんな死ぬ覚悟をしたはずなのに、その悲壮な気持ちを忘れて、何が世界に肩を並べる日本か、という気持ちが私の中に渦巻いていた。のんきに浮かれる日本人を、虚構の中とはいえ国を失う危機に直面させてみようと思って書き始めたのだった。日本人とは何か、日本とは何かを考え直してみたいとも強く思っていた」(小松左京著『小松左京自伝――実存を求めて』2008年日本経済新聞出版社刊より)
小松左京は、14歳のときに空襲で瓦礫(がれき)となった兵庫県西宮市で終戦を迎えている。そのときの体験が、のちの作家活動の原点であったのか。そして本作には、日本沈没にいたる大スペクタクルはむろんのこと、随所に読みどころがある。例えば、大災害に襲われたとき、人はどう行動するのか。作家は丹念に描写する。また、移住先を求める日本人をはたして受け入れてくれる国があるのか。その切羽詰まった場面は興味深いもので、50年後の今日でも日本を取り巻く状況はあまり変わっていないように思えてくる。浜井氏はこう語る。
「僕は、『日本沈没』を一つの文学として読みました。例えば、日本海溝の一番深いところに田所博士と小野寺が潜っていく。キシキシキシと、もの凄い気圧が掛かって、潜水艇の壁が破れたら死んでしまうところの描写。これはSF小説というけど、純文学の世界だなと思った。あるいは、地球の成り立ちの時間軸を何万倍にして回せば、将来、日本列島は本当に沈んでなくなるかもしれないでしょ。そういう意味では、コマを早めれば、もしかしたらこの作品はフィクションではなくノンフィクションであるかもしれないと思ったんですね」
奇しくも今年は関東大震災から100年となる。SFの枠を超えた本作は、今日の日本の在り様への警告の書でもある。
バナー写真:インタビューに答える小松左京=1978年10月16日、大阪・ホテルプラザで(共同)