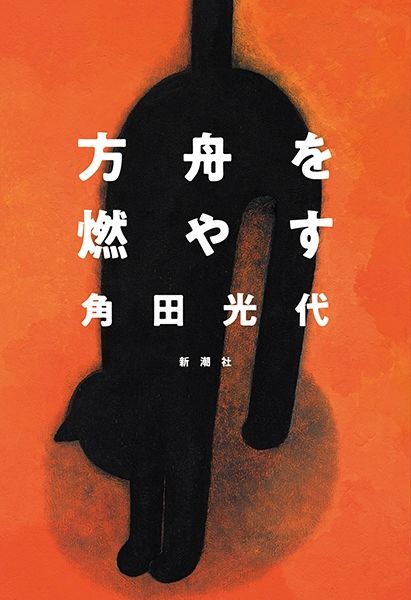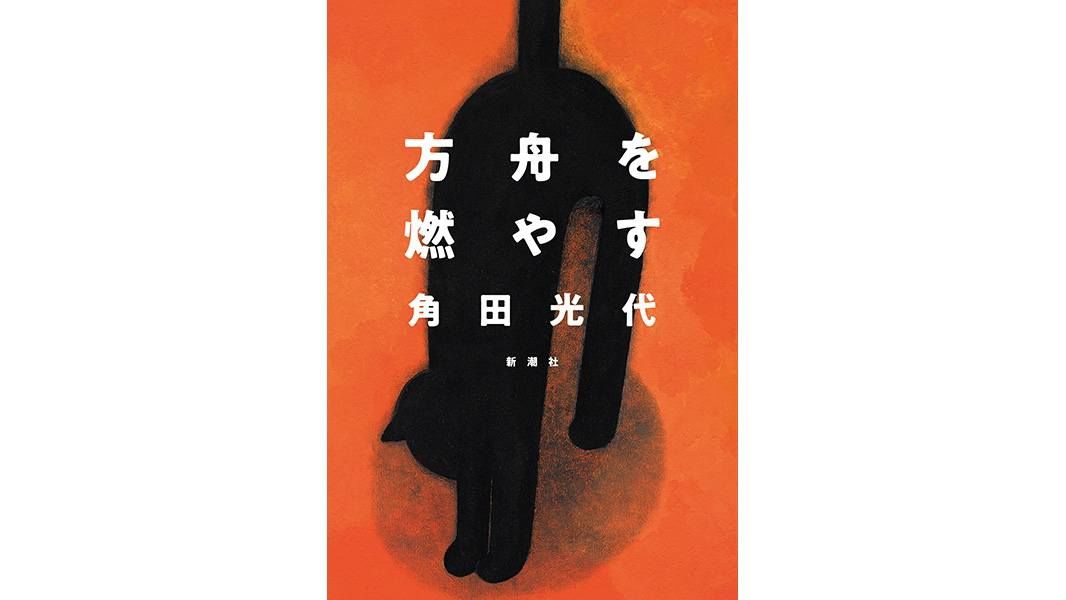
【書評】ぐらつく価値観、ゆらぐ自分:角田光代著『方舟を燃やす』
Books 社会- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
本書を貫くテーマは「噂」だ。
いや、「噂かどうか分からない言説」といったほうが正確かもしれない。
最初は軽く、まるで居酒屋のサイドメニューのようにさらりと触れられているだけのそのテーマは、徐々に重みを増し、気が付けば読み手の内部に浸み込んできている。まるでぞっとするくらいに。
きっとそう企みを持って筆を進めてきた著者に、終盤は恐ろしさすら感じる。そんな一冊だ。
いまなら笑い飛ばせる多くの噂
主人公は2人。1960年代はじめに鳥取県の山間に生まれた1人の少年と、同じ頃に東京で高校を卒業し、製菓会社に就職した1人の女性の人生が、まず第一部では、1967年、1976年、1980年……と、当時を思い起こさせるようなエピソードとともに、それぞれ別々に淡々と描写されていく。
たとえば、少年の兄が夢中になる無線機(ハム)は、一時、ブームになっていた。私も小さい頃、いとこの部屋で「ジー、ジー」と音を出す黒い機械を見かけた記憶がある。
同期に取り残されないよう結婚退社しなければと焦り、無事に成し遂げてほっとする女性の姿は、雇用機会均等法が施行される前の社会を知っている層からすれば、懐かしいに違いない。
ほかにも乳児のワクチン接種の事故による母親たちの疑心暗鬼、コックリさんで「たたられた!」と大騒ぎする高校生たち、誰もが口にしていたノストラダムスの大予言に、2000年問題など、「ああ、あったな」と、経験してもしていなくても、知っていることがたくさん出てくる。
第1部が、第2部に比べて相対的に軽く読めるのは、私たちはもう、そこから見たら「未来」にいる存在だから――つまり、空から恐怖の大王が降ってくることも、2000年問題で世界中のコンピューターが止まることもなく、無事に21世紀が訪れることを知っているからだ。
その時代の真っただ中に生き、こうした噂に触れて反応しながら日々の暮らしを送る主人公の2人の様子を、まるで安全圏から俯瞰(ふかん)しているような、そんな感覚になる。
気が付けば自分も噂のただなかに
第2部は、そこから一気に十数年が経過した2016年から始まる。すでに東日本大震災は起こっているが、新型コロナウイルスにはまだ誰も気が付いていない。そんなタイミングだ。
ここで初めて、それまでまったく異なる人生を歩んできていた主人公の2人の人生が交わる。区役所の職員になった少年は子ども食堂の活動に関わり、還暦を迎え、夫に先立たれた女性は、料理を作る側となってその子ども食堂に登場する。
とはいえ、何か劇的にドラマチックなことは起こるわけではない。
始まったばかりの子ども食堂の活動は徐々に軌道に乗り始め、離婚や死別、子どもの独立などでそれぞれ独りで暮らす2人の人生は、子ども食堂を起点に交わりながらも、それぞれに進んでいく。
そして新型コロナウイルスが中国で見つかり、マスクが店頭から消え、外出自粛令が出され、ワクチン接種が始まる。
第1部では“未来という安全圏”にいて、いわば結末がわかっている過去の噂を眺めながら本書を読んでいたはずが、第2部で2017年、2018年と、1年刻みで進むストーリーを追っていくうちに、まるで濁流にのみ込まれるかのように、こちら側も物語の中に巻き込まれてしまう。
緊急事態宣言下でこっそり営業していたお店に対するチクリや、ワクチンを巡る賛成派と反対派の対立、SNSで大量に発信される情報たち。どれもまだあまりにも最近のできごとで、何が真実で何が嘘で、何を笑い飛ばしていいのか自分もよく分かっていないことに気が付いた瞬間に、本書の見え方がパッと変わった。
「こんなおばあさん、かんたんにだませると思っているんでしょう」
高齢者にワクチンを無理やり接種させようとしているとか、台風からの避難だと偽って家から連れ出そうとしているのだとか、周囲に対して懐疑心を抱いた時に女性が口にするセリフだ。
だます、とはいったい何なのだろう。
自分はこれまで自分の頭で考え、判断してきたつもりだけど、もしかしてだまされていたのに気がついていないだけだとしたら--?
自分では持っていると思っていた自分なりの価値観というものが、ぐらり、とよろめき始める。
実在しない主人公たちが物語を織りなす小説というものをエンターテインメントとして読んでいたはずなのに、いつしか自分もその物語の中にいて、何が真実か分からない、あの時の行動は正しかったのかと不安に感じ、叫びたくなるような気持ちになっていた。
真実と嘘の境目にあるものとは
フェイクニュースという言葉は、もうずいぶん広まった。
SNSやAIという、過去にはなかったIT技術によって、フェイクニュース、つまり情報の捏造(ねつぞう)は広がり、真実と嘘の境目はどこまでも曖昧になっている。
でも、真実と嘘の境が分からないまま噂(だとされたもの)が広がり、多くの人間がそれを信じ、翻弄(ほんろう)されていく構造そのものは、実はずっと昔から変わっていないのではないか。
ノストラダムスの大予言と、コロナウイルスワクチンをめぐる言説と、何が違うのだろう。
ほら、あなただって賢そうにしているけど、何が正しいのか本当に分かっているの?分かってないでしょう?いま何かが起きたら、どうやって行動するの?
第2部の終盤、スピードをあげて進む物語は、そう読者に問いかけているようだ。
いま自分が信じている何かは、真実なのか、嘘なのか。自分は何をよりどころにして生きているのか。足元がぐらつくような問いを投げ掛けられた気分だ。