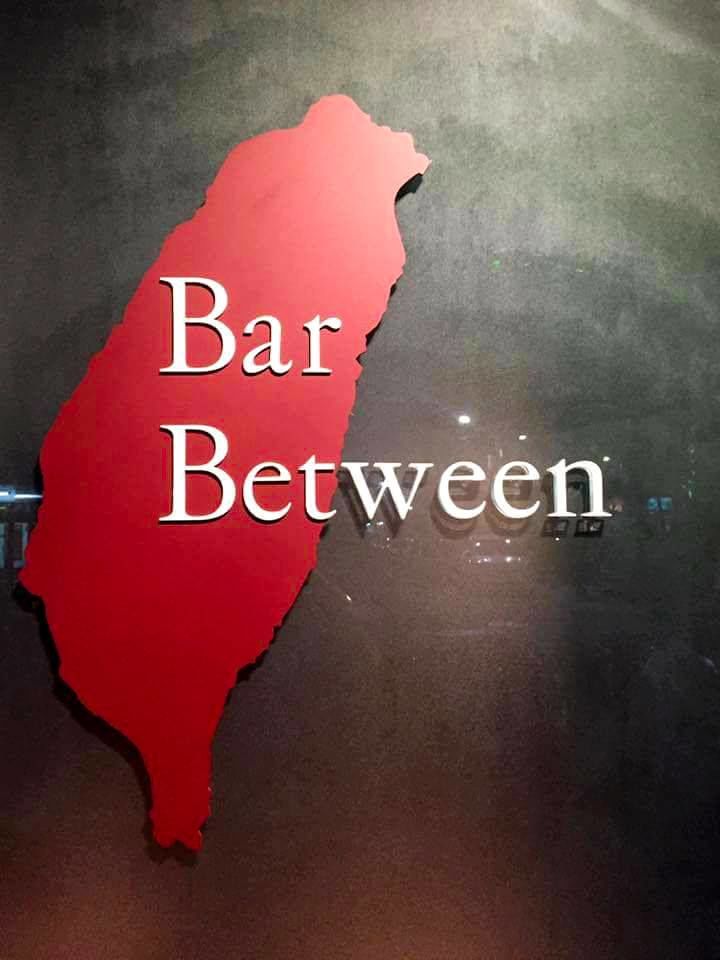台湾で根を下ろした日本人シリーズ:バーテンダー・川嶋義明さん
暮らし 国際交流 食- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
「川嶋君はきっと成功する」と言ってくれた最初の師匠
川嶋義明は、少年時代を過ごした台北・天母の風景が忘れられないという。家族と通った近所の小さな食堂の店主や、いつもお小遣いでお菓子を買うたびにおまけを付けてくれた駄菓子屋のおかみさんの姿だ。人情味あふれる笑顔がいつもそこにはあった。世界各地を渡り歩いた彼が、二十数年の時を経ていかにしてバーテンダーとしてこの街に舞い戻ったのか、そこには3人の恩師の存在が深く関わっていた。
1999年、川嶋が21歳の頃だった。帰宅途中だった彼は、地元の芦屋駅近くのビルの2階にあったバーに一人でふらりと立ち寄った。オリジナルカクテルもほとんどなく、ウイスキーも十数種類そろえているだけの何の変哲もない店だった。一見の客で、当時は金髪に眉ぞりという風貌の青年・川嶋に対し、店のマスターは表情一つ変えることなく温かく迎えてくれた。
「後で分かったことですが、マスターの中山隆さんは中学の先輩だったのです。とても聞き上手な方で、『川嶋君はきっと成功する』とも言ってくれました。何を根拠にそう思ったのか、今は知る由もありませんが、この言葉はその後ずっと自分の大事な『お守り』となりました。あの時、自分もこういう大人になりたいと思ったことが、バーテンダーを志したきっかけです。」
しかし、それから数年後に、中山は40歳で早世してしまう。それでも毎回カウンター越しの会話を通じて、直感を鍛えることや人と人とのコミュニケーションの大切さを若い川嶋に身をもって教えてくれた。川嶋の最初の人生の師だった。
相次ぐ挫折で自分自身を見失う
芦屋のバー通いと同じ頃、川嶋にもう一人の師が現れる。アルバイトとして働いていた大阪・梅田の喫茶店の店長、堀江孝俊である。堀江は川嶋が高校時代に入り浸っていた別のティーラウンジの店長だった人だ。もとより面識のあった二人だが、今度は同じ職場の上司と部下という関係での再会となった。
「堀江さんからは、仕事の優先順位の付け方や段取りの大切さを学びました。飲食業界の3S(Speed、Smart、Smile)をみっちりとたたき込まれ、ここで仕事の基礎を身に付けることができました」
堀江との再会から4年後の25歳の時、川嶋は運転免許証の更新を理由に、今度は出生地のサンディエゴに渡った。1カ月ほど過ぎた頃、あるラウンジバーで働くこととなった。川嶋が初めてバーテンダーとしてカウンターに立ったのはこの時だ。顧客は付いたものの、全てが我流の仕事だったと振り返る。異文化ギャップに苦しんだ米国での生活も、結局長くは続かなかった。
その2年後、再び芦屋に戻った川嶋は、ある居酒屋で仕込みをしていた職人と出会った。小田桂三と名乗ったその人物は、芦屋の老舗のバー「The Bar」のオーナー・バーテンダーだった。出勤前に知人の店を手伝っていたのだ。川嶋は3人目の師となる小田の下で働くこととなった。現在、川嶋が台北で営む「Bar Between」の看板メニューとなっている「神戸ハイボール」や「ウォッカリッキー」は、「The Bar」で学んだカクテルだ。しかし、ここで川嶋は挫折を経験する。
「我流で始めたことのツケだったんですね。アメリカではお客さんに会話を楽しんでいただければ良かったのですが、日本ではバーテンダーとしてのスキルを店からもお客さんからも求められました。『The Bar』のお客さんは年齢層も高く、この点はシビアでした。自分の才能のなさを思い知らされ、これまでの自分を責める毎日でした」
30歳で川嶋はバーテンダーとして生きていくことを諦め、Tシャツのデザインの仕事を新たに始めた。2番目の恩師の堀江にそのことを報告しに行くと、堀江の口からは意外にもこんな言葉が発せられた。
「川嶋は絶対に飲食に戻ってくるよ」
バーテンダーを志してから17年、台北で出店する
デザイナーを続けながらも、夜の帳(とばり)が下りると、川嶋の足は自然とバーへと向かった。あちこちのバーを巡っては、カウンター席に陣取り、バーテンダーの仕事を見つめ、自身のスタイルとの違いを分析しては楽しんでいる自分がいた。
ちょうどこの時期、川嶋は少年時代の一時期を過ごした台湾に足しげく通うようになっていた。台北日本人学校の同窓生たちとの交流もあり、もともと台湾には関心を持っていた。何より喜怒哀楽をはっきりと表現し、人間味あふれる台湾の人たちが好きだった。台湾関係の書籍も読みあさった。自分がかつて住んでいた場所を再認識するたびに、台湾をいとおしく感じ、いつか台湾に恩返しをしたいという思いが芽生えていった。将来自分の店を開くとすれば台湾しかない。川嶋はそう確信するようになっていた。
2人目の恩師・堀江の予言通り、34歳の年に芦屋の「The Bar」で再びバーテンダーの仕事に戻った川嶋は一念発起した。翌年学生ビザを取得すると台湾に渡り、中国文化大学で中国語を学び直した。そして、バーやレストランでアルバイトをしながら、台北市内で自分の店を開く準備を着々と進めた。途中1年ほど古巣の「The Bar」に戻り、それまで関心の薄かったフルーツ系カクテルも習得した。フルーツ王国の台湾でそれを生かさない手はない。
2016年11月、満を持して自らオーナー・バーテンダーを務める「Bar Between」を台北市内にオープンした。繁華街から一本離れた通りに出店することには、当初周りの知人たちからは反対された。しかし、川嶋は自分の直感を信じた。店の窓越しに小さな公園の緑が見える風景が決め手だった。店名はこの店を日本と台湾との間の懸け橋としたいとの思いから付けた。遅咲きのバーテンダーが異国の地でついに花を咲かせた。21歳の時にバーテンダーを志してから17年の歳月が流れていた。
その翌年、芦屋に帰省した際、これまでずっと果たせなかったことを行なった。最初の恩師である中山の墓参りだ。「君はきっと成功する」と言ってくれた師の言葉は、この十数年間いつも川嶋に寄り添ってくれた。ようやくお礼が言えた。人としての心構えを中山から、仕事の段取りを堀江から、バーテンダーとしての技術を小田からそれぞれ教わった。これらの恩師たちとの出会いによって、バーテンダー川嶋義明が完成したと言っても過言ではないだろう。
共感が生まれる時、懸け橋は築かれる
川嶋は高校2年生の時に芦屋で阪神・淡路大震災を経験している。幸い家族は無事だったが、一瞬にして全ての生活が一変する様を目の当たりにした。2011年に東日本大震災が起こった時、多くの台湾の人々が日本の復興を支援してくれたことは、素直にありがたいと思った。これを契機に、台湾に関心を持つ日本人が増えた。18年の夏休みに最も人気の高かった日本人の海外渡航先は、初めてハワイを抜いて台湾となった(日本旅行業協会調べ)。しかし、川嶋はこうした昨今の現象をやや冷めた目で見つめている。
「きっかけが台湾であることは良いことです。でも、自分は台湾を大切に思うからこそ、日本人にとっての台湾が一時的なブームで終わってほしくないとも思うのです」
では、地に足の着いた日本と台湾の関係を築くにはどうすれば良いのだろう。彼は自分の持ち場であるバーという空間を引き合いに出しつつ、こう語ってくれた。
「例えば、ドリンクはきっかけで、会話はおつまみなんです。最も大切なのは、カウンター越しにお客さんと店が対等な関係で向き合った時に生まれる『共感』なのです」
幅65センチのバーカウンターの距離から生まれる共感。バーという小空間で紡ぎ出される個と個の関係も、日台間の国際関係も、川嶋にとっては同じ世界観から出発している話なのではなかろうか。二者が対等な立場で対話をし、共感が生まれる時、その間に懸け橋は自然と築かれている。そして、自分の理想を語った川嶋のこの言葉は、実は21歳の彼に恩師の中山が示した教え、すなわち誰にも分け隔てなく温かく接し、相手の話にしっかりと耳を傾け、前向きな言葉で励ますこと、これらがコミュニケーションの基礎となるということにも気付かされるだろう。川嶋の中に中山は生きている。
「Bar Between」は開店から間もなく2年半を迎える。来客の9割は台湾の人だ。台湾を思う川嶋の気持ちに、地元の人たちもしっかりと応えてくれている。いつの間にか生前の中山の年齢も超えた。今日の川嶋の姿を一番喜んでくれているのは、草葉の陰の中山に違いない。
バナー写真=川嶋義明さん(松本崇撮影)