
コロナ禍の今だからこそ注目したい台湾の公園革命——みんなで育てる公共空間
暮らし- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
コロナに先駆けて公園の価値を再発見した台湾
新型コロナウイルスの登場によって、私たちの暮らしは一変した。先頃、「新しい生活様式」なるモデルが示され、今後しばらく元のような生活には戻れないのだと、改めて実感させられた。
「新しい生活様式」は、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言を、日常生活に即してまとめたものだ。そのひとつに「遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ」という項目がある。これを受け、誰もが利用できる屋外の公共空間として、公園が注目されそうだ。
実際、さまざまな活動の自粛を余儀なくされた期間中も、健康維持や気分転換のため、公園に出掛けた人は多いだろう。
新型コロナウイルスの流行より早く、公園の価値が「再発見」されているところがある。お隣、台湾だ。台湾では2017年に改修された台北の栄星公園を皮切りに、年齢や障害の有無などに関係なく、あらゆる人を包摂するという概念に基づく「インクルーシブ遊戯場」、ならびに、地域の文化や特性を生かした「特色公園」が続々と誕生している。特に前者は、幅広く市民の声を集め、遊戯場づくり(※1)に生かしている点に特徴がある。まさにみんなでつくる、みんなのための公園だ。
(※1) ^ 本稿では、遊技場の建設は概念形成にもつながるものだと考え、「つくり」と表記する。
市民の声でつくられたユニークな公園の数々
たとえば、台北市がインクルーシブ遊戯場のモデルケースと位置づける花博公園は、車椅子や義足の利用者、弱視者など、さまざまな障害を持つ人たちの意見を集めるところから始めた。それをもとに、車椅子のまま乗れるブランコ、段差のない砂場と手洗い場、点字の付いた案内板などが設けられた。
また、中央藝文公園の遊戯場をつくる際には、子どもたちを招いて、7回ものワークショップが開かれた。士林夜市に程近い前港公園は、近隣住民の声をデザインに生かすべく、オリジナルの遊具を地元メーカーにオーダーした。ひときわ目を引くシンボルツリーは、暗くなると発光する仕掛けまで付いている。
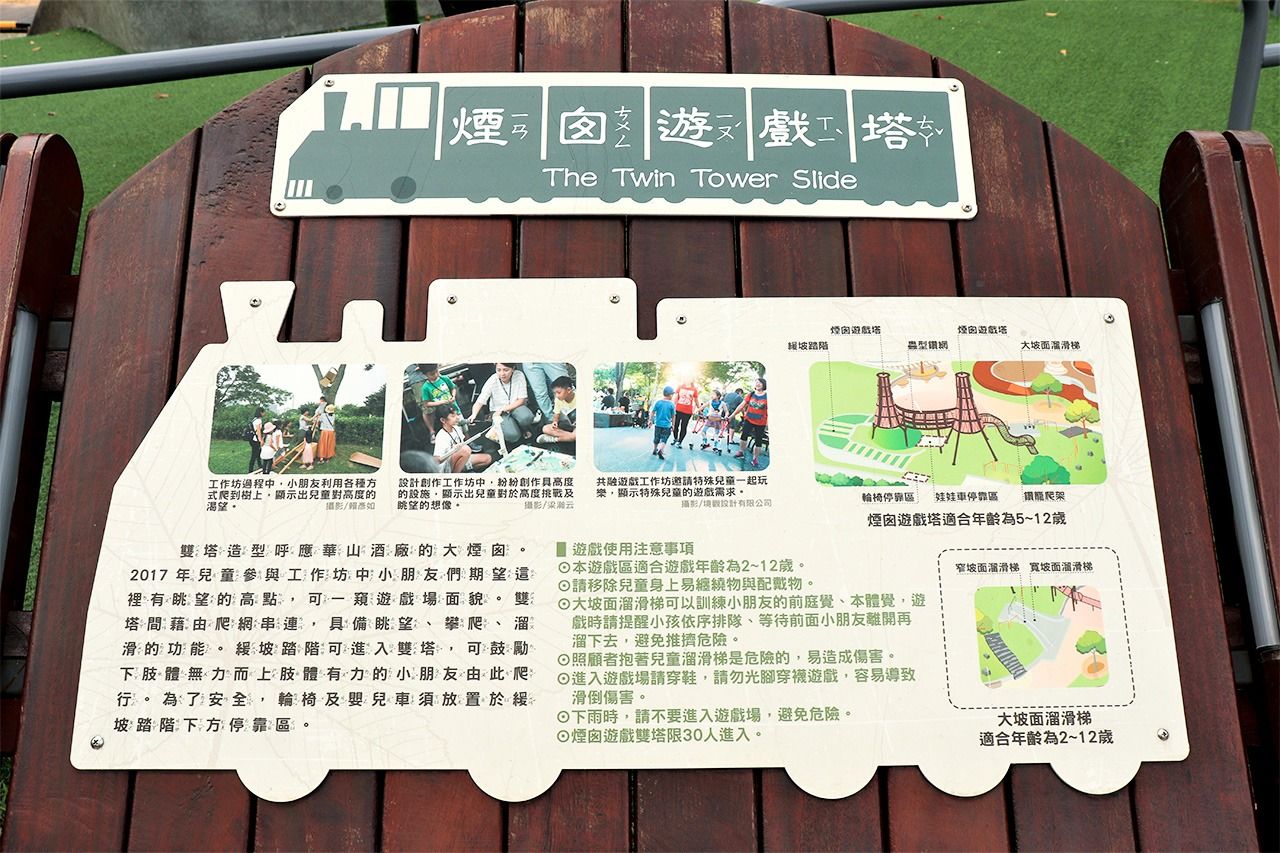
中央藝文公園ではワークショップの様子をパネルにして展示。スペシャルニーズの子どもたちも参加している(筆者撮影)
それぞれの場所の文化や歴史を踏まえ、地元のアーティストらにデザインを依頼した公園もある。
周辺に自動車部品を扱う町工場が集まる建成公園は、遊具のてっぺんに工具のモチーフが飾られ、人工芝に歯車の模様が描かれた。
朝陽公園があるのは、服飾材料を売る店が多く、「ボタン街」という異名を持つ場所。また老舗のお茶問屋が集まる迪化街も近いことから、目や背中はボタン、耳は茶葉というライオン型の遊具がつくられた。遊具がその街を知るきっかけになるのが面白い。

周辺に町工場の多い建成公園のすべり台は、てっぺんに工具のモチーフが付けられている(筆者撮影)
公園の利用者は子どもだけに限らない。
南港公園は遊戯場をリニューアルする際、公園で囲碁や将棋を楽しむ人たちのための東屋(あずまや)、運動に訪れる人たちのためのジョギングコースとサイクリングコースも一緒に整備した。
また、桃園メトロ空港線をテーマにした新北市の楽活公園には、本格的なトレーニングのできる健康器具が設置され、好評を博している。
我が町にも公園を。里長の秘策は
台北市は2021年中にインクルーシブ遊戯場を59、特色公園を39まで増やす計画だ。隣接する新北市も、この動きに追随。台北市を凌駕(りょうが)するスピードで、次々に公園を整備している。
台北市が既存の公園をリニューアルしているのに対し、新北市には新しくつくられた公園も多い。陶器の街として知られる鶯歌の、駅の南東側に位置する東鶯里には、公園がなかった。あるのは何十年も前に「公園予定地」に指定された土地だけ。それも2、30名の地権者に権利が分散していて、すべて買い戻すにはまとまった資金が必要だった。
そこで東鶯里の里長(※2)を務める陳陸賀さんは、「容積移転」という制度を利用することにした。
まず、各地権者に「公園をつくりたいから土地を売ってほしい」と数年をかけてお願いに回った。土地を買うのは、里でも市でもなく、ゼネコンだ。ゼネコンは土地を全て買うと、市に譲渡する。その代わり、提供した土地の広さに応じた容積率を、別の場所で建設するビルやマンションに移転し、より高層化できるのだ。
これで市は懐を痛めずに公園予定地の所有権を得、ゼネコンは別のところで利益を出せる。そして里は新しい公園を手に入れることができるというわけだ。この容積移転という仕組みは、歴史的建造物の保存にも活用されている。
実は日本にも、同じような「空中権の移転」制度がある。東京駅丸の内駅舎の復元工事を行った際、500億円にのぼる改修費用を、周辺のビルに空中権を売却することで賄(まかな)ったという話は、よく知られている。
こうして2019年3月、東鶯里に初めての公園が誕生。日本統治時代、この場所に火事を知らせるための鐘楼があったことにちなみ、「古鐘楼公園」と名づけられた。すべり台は在りし日の鐘楼に似せてつくられ、消防隊をモチーフにした遊具も設けられた。陳里長は「物語のある公園にしたかった」と語る。

古鐘楼公園のすべり台は日本統治時代の鐘楼がモチーフ。鐘楼の再建計画も練られている(筆者撮影)

火事と消防隊をイメージしたデザインが施された古鐘楼公園の遊具(筆者撮影)
(※2) ^ 里は市・区・鎮の下位に属す行政区分。里長は4年に一度の選挙で選ばれる
移行期ゆえの課題も浮上
台北市から始まった公園再生が台湾各地に波及するなか、徐々に課題も見えてきた。
台北市の公園路燈工程管理處・南港公園管理所で股長を務める許耀仁さんによれば、これまでにない新しい遊具に対して「危ない」と感じる保護者が少なくないという。
たとえば複数人で遊べる回転遊具は、大きな子の回すスピードについていけず、小さな子が振り落とされてしまうことがある。ターザンロープに至っては、そもそも正しい使い方が分からないという声もあった。こうした声には、ガイド動画を作成したり、休日に遊び方教室を開いたりして対応しているという。
新しい遊具は維持管理にも手がかかる。既製品からオーダーメードに変えたり、挑戦性の高い遊具を導入したり、使用頻度が上がったりしたことで、よりきめ細やかなメンテナンスが必要となった。

メンテナンスのため、使用が禁止された南港公園のターザンロープ。自力で体を支えられない人や、体の小さな子どもでも遊べるよう、ベルトがついている(筆者撮影)
公園が評判になり、多くの人が押し寄せるようになると、駐車場やトイレの不足問題も起こる。先の古鐘楼公園も、オープン当初、予想をはるかに上回る人出があり、周辺に車の行列ができたため、慌てて駐車場を整備したという。
そして、誰しもを包摂する「インクルーシブ」を標榜(ひょうぼう)しながら、青少年をうまく取り込めていないことが目下の課題だ。スケートボードやパルクール、ボルダリングなど、青少年が体を動かせる設備もつくれればと考えているそうだが、台北市では今のところ実現には至っていない。
許さんは、「今はまだ過渡期。外国から入ってきたインクルーシブの概念をローカライズしながら、周囲の人たちと一緒に公園を育てていく必要がある」と語る。
「物言う市民」と育てる公園
そもそも台湾では教育の場でしか語られることのなかった「インクルーシブ」という概念が、公園に持ち込まれた背景には、2015年、「子どもたちの遊ぶ権利」を訴えて声を上げた、市民たちの存在があった(※3)。
それ以前の行政府は、公園政策を重視していたわけでもなければ、公園づくりに市民が参画することに積極的でもなかった。それが今や、多くの地方自治体が、市民も参画できる公園づくりに熱をあげている。東鶯里の陳里長は言う。
「(以前は)公園なんて誰も取り上げたことはなかった。正直なところ、それが票になると分かって、みんなこぞって公園をつくるようになった」
「台湾の政府はいつも怒られてる。総統だって(笑)。僕たち里長も選挙というプレッシャーがあるから、きちんと仕事をする」
つまり「物言う市民」の存在と投票行動が、行政にしっかり影響を与えているというわけだ。
新北市議員・廖宜琨さんの事務所主任を務める劉徳彬さんによれば、「物言う市民」の存在は、2013年の「白シャツ軍運動」をきっかけに可視化されたのではないかという。
同年、台湾で兵役についていた若い兵士が、上官からのいじめが原因で死亡する事件が起きた。これを受けて、若者を中心に、事件の真相解明と軍の改革などを訴える運動が起こり、およそ25万人もの市民が、白いTシャツを身に着けて路上に出た。これは当時の台湾史上、最大規模のデモだった。
インターネットの普及も、呼びかけに力を貸した。電子掲示板やフェイスブックを介して、デモの趣旨に賛同する市民が集まり、大きなうねりとなった。結果、政府は一部の要求を呑まざるを得なくなった。
翌2014年には、サービス貿易協定に反対する学生らが、24日間にわたって立法院を占拠する「ひまわり学生運動」が起こる。立法院内部の様子はライブ配信され、SNS(会員制交流サイト)上でも連帯が呼びかけられた。立法院の外でも、学生を支持する人たちがデモを行うなど、「物言う市民」がますます存在感を増した。

ひまわり学生運動に呼応して開かれた抗議集会の様子(筆者撮影)
台湾には長らく「物を言えない」時代があった。その時代を実際には体験していない世代にも、劉さん曰く「結局のところ、何でも政治とつながっている」という認識が共有され、社会運動に結びついた。
2015年の「子どもたちの遊ぶ権利」を訴える抗議活動も、その流れと無縁ではない。抗議活動に関わったNPO法人「還我特色公園行動連盟」の李玉華さんは言う。
「子どもの遊ぶ権利も、ひとつの人権思想。市民参画とか人権とか、そういったものは、民主主義を追求する政治につながる。文化や市民の意識が高まることで、インクルーシブという概念も一緒に育っていくんです」
公園という公共空間を、市民と行政が協力しあって育てていこうとしている台湾。日本でも称賛されている台湾の新型コロナウイルス対策も、もとをたどれば、この市民と行政のつながりに支えられているのではないだろうか。
片や日本でも、新型コロナウイルスの影響で集会を開くのが難しい中、SNSの#(ハッシュタグ)を使った、ネット上での投稿デモが広がりを見せ、「物言う市民」が存在感を示したことは記憶に新しい。コロナ禍で、「何でも政治とつながっている」ことを実感した人が多かったのかもしれない。
ごく身近な場所である公園ひとつとっても、政治と無関係ではありえないことを、台湾の例は教えてくれる。願わくば日本の公園も、私たちみんなに開かれた、みんなのための場所だと、心から感じられるような空間であってほしい。
バナー写真:黄昏時に明かりを灯す前港公園のシンボルツリー(筆者撮影)
(※3) ^ 詳しくは『私たちの公園革命——台湾の公園に「インクルーシブ遊戯場」が生まれた日』を参照。

