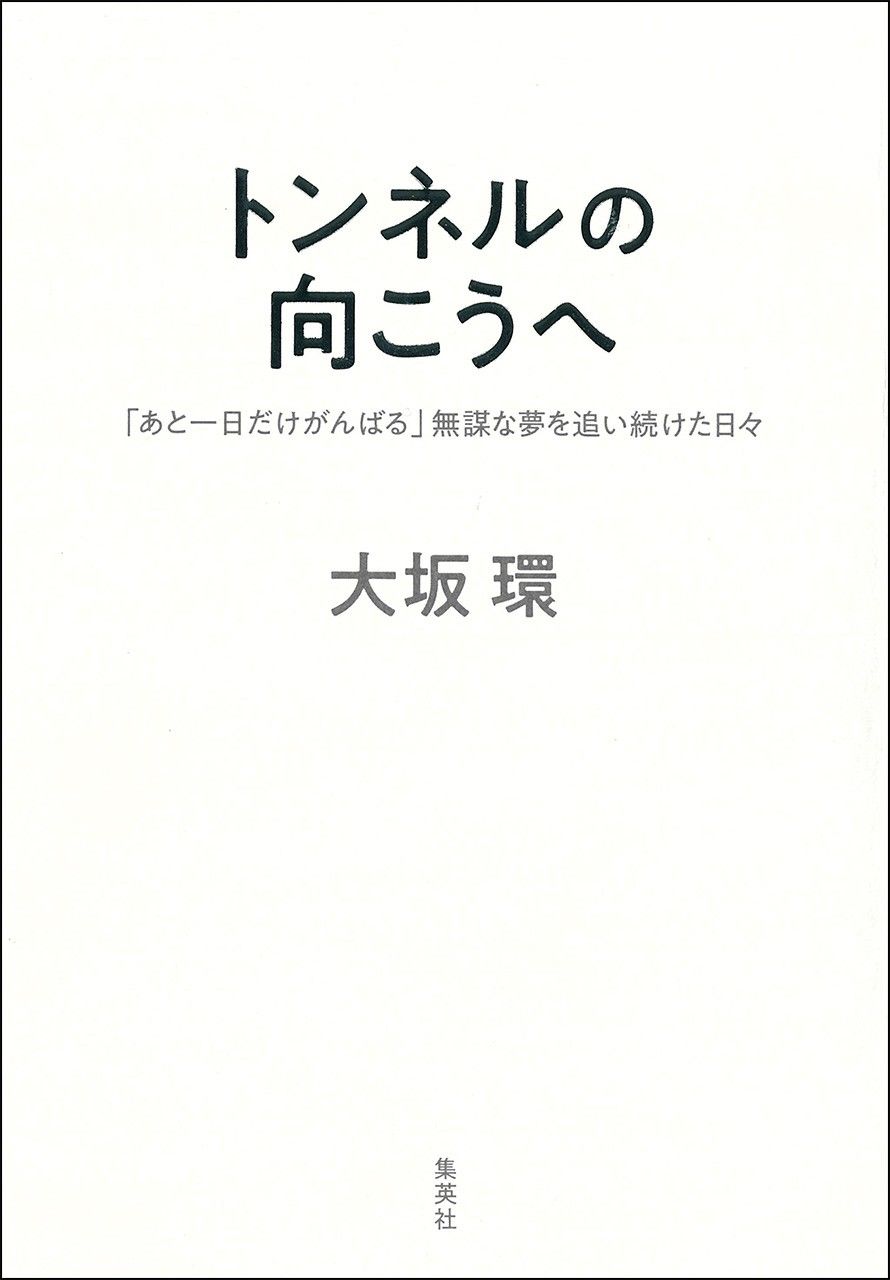大坂なおみの母・環さんインタビュー: 「なおみは人からコントロールされるのが嫌い。そんなところは私と似ている」
スポーツ People- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
母と娘の新たなチャレンジ
大坂なおみが最近また新たなチャレンジに乗り出した。大手スポーツマネジメント会社のIMGとの契約を更新せず、担当代理人だったスチュアート・ドゥグッド氏とともに独立してマネジメント会社を立ち上げたのだ。全仏オープンではアキレス腱のけがもあって1回戦負けに終わったが、コート外では相変わらずのトップニュース・メーカーである。
今回の決断について、「大手事務所の下では、やれることに限界があるけれど、自分の会社を作って自分が社長になればなんでも自由にできる。人からコントロールされるのが嫌で、自分のことは自分で管理したいんです。そういうところは私に似ているんですよ(笑)」と語るのは、なおみの母である大坂環さんだ。
自身を「反逆者」と称する環さんが、その半生をつづった『トンネルの向こうへ』(集英社)を刊行した。ハイチ系米国人のマックス・フランソワさんとの出会いよりも前にさかのぼるこの物語は、偉大なアスリートの母親というよりも、1人の日本人女性の勇敢な生き方を通して、世間の特に若い女性たちへ強いメッセージを届ける一冊だ。
現在も米国フロリダで暮らす環さんに、著書のこと、娘への思い、夫と取り組むプロジェクトなどについてインタビューした。
─ご著書を興味深く読ませていただきました。普通は伏せておきたいようなお話も赤裸々に書かれている印象でしたが、書き続けるエネルギーは何だったのでしょうか?
私にとっては、湧き出てくる自分の気持ちに従っただけのことです。今回これを書くために、昔の写真やビデオテープをあらためて見直しました。そうすると、当時の自分に戻ったように気持ちがどんどんあふれてくるんですね。書き出すと、止まらなくなってしまって。知り合いたちにも「露骨に書いたね」なんて言われました(笑)。でも、「これを書かないと自分の人生じゃない」とか「ここを省くとつじつまが合わなくなる」とか考えると、やっぱり全部書かないとダメだというふうにも思いました。

大阪に引っ越した翌年、夫のマックスさん(左)が店舗の一角を借りて始めたショップにて。生後4カ月の長女まりさん(中央)と。店ではニューヨークから仕入れた服を売っていた:大坂環氏提供
ウィリアムズ姉妹の活躍に触発
─ご主人のマックスさんはテニス未経験だったにもかかわらず、独学によって長女のまりさんと次女のなおみさんを幼少の頃から指導してきました。ウィリアムズ姉妹を幼少からコーチしてきた、同じくテニス未経験の父リチャードさんのやり方を参考にしたという話も有名です。でも、セリーナとビーナスの存在を知るよりも前、長女のまりさんが0歳の頃からもう“トレーニング”を始めていたという話には驚きました。
トレーニングといってももちろん遊び感覚ですよ。でもバランスを養ったり、体幹を鍛えたりすることを意識していました。私もスポーツが好きだけれど、主人はそれに輪をかけてスポーツが好きで、サッカー、バスケットボール、自転車やマラソンなど、どこにいても常に何らかのスポーツをしていたんですね。もっと本格的にやりたかったという思いがどこかにあったのかもしれない。自分の子供はスポーツ選手になってくれればいいなあという漠然とした願望がずっとあったのだと思います。それがはっきりとした目標に変わったきっかけがウィリアムズ姉妹の登場でした。
─17歳だったセリーナが全米オープンで初優勝した時、まりさんは3歳、なおみさんはまだ2歳になる前でした。翌年のウィンブルドンでは姉のビーナスが優勝。その活躍を見て、娘さんたちを一流のテニスプレーヤーに育てるという目標が定まったということですが、ウィリアムズ姉妹の、テニスの何にそれほどの魅力を感じたのでしょうか?
白人中心のテニス界であれほどの黒人のスターが出てきたことが、何よりもまず衝撃でした。男子ならアーサー・アッシュ、女子ではアリシア・ギブソンなど黒人のチャンピオンが過去にもいましたが、10代の姉妹というインパクトは強烈でしたよね。彼女たちがいくら稼いでいたかは、さほど気にしていませんでした。それよりも、テニスをしながら日常的に世界を飛び回り、いろいろな文化や人々に触れ、その年代の普通の女の子たちが到底経験できないような豊かな人生を送れる……なんてすばらしい職業なんだと純粋に思いましたね。

ニューヨークに引っ越した直後、市営公園内のテニスコートで練習するなおみ(右、3歳ころ)と父マックスさん:大坂環氏提供
─リチャードさんが娘たちをテニスプレーヤーにしようと決めたのは、あるテニス選手が自分の年収分に近いような優勝賞金を受け取るところを偶然テレビで見たからだと言われています。一方、お二人にとっての動機は、お金ではなかったということですか?
私たちは本当に貧しかったけれど、お金が一番の動機だったわけではありません。当時、主人は輸入衣料品の販売やバー経営などをし、私はそれを手伝いながら通販会社のコールセンターでパートもしていました。懸命に働いて睡眠時間は平均3時間、それでも一向に貧乏生活から抜け出せなかったので、もちろんお金はほしかった。でもそれ以上に夢がほしかったんだと思います。1歳違いのビーナスとセリーナという黒人姉妹の活躍には、夢と希望を与えられたような気がしました。特に長女のまりの持って生まれた運動神経は、その可能性を十分に信じられるほど抜群だったんです。その夢のおかげで、極貧生活の中でも喜びを感じられるようになりました。

ジュニア選手の地区大会で優勝し、トロフィーを掲げるなおみ(右)とまりさん(左):大坂環氏提供
社会的行動に積極的な背景
─なおみさんはテニスプレーヤーとして成功しただけでなく、世界に向けてさまざまな問題提起をし、その影響力の大きさを示してきました。2020年は『BLM(ブラック・ライブズ・マター)』運動に積極的に関わり、21年は記者会見ボイコットを通して、アスリートのメンタルヘルスへの配慮を訴えました。自分でも内向的だと言っていたなおみさんのイメージは、かなり変わってきたような気がします。母親としてはどう感じていますか?
皆さんの中では、全米で初めて優勝したときのなおみのイメージが大きいのではないでしょうか。実際、あのときのなおみは本当にああいう内気な感じだったんです。テニス以外にすることといったら、家でコンピュータゲームをするか、まりとおしゃべりするくらい。でも、だんだん人と接する機会が増えて、彼氏もできて、いろいろな世界のトップにいる人たちとの親交もできて、少しずつ心のドアが開いていったのだと思います。
最終的には全部自分で考えた行動でした。全米での(警察の人種差別的な暴力の被害に遭った黒人犠牲者たちの名前が書かれた)黒いマスクも本当になおみのアイデアです。周りからは反対や心配の声もあったけれど、自分の意志で実行した。その勇気があの子にはあるんです。反対されると逆に燃える性格でもあって、そこが残念ながら私と同じなんですね(笑)。私の父は保守的な人で、両親は礼儀作法や身なりにもすごく厳しく、私はそれに反発しました。他人がどう思うかを気にして生きたくないし、たとえ親であってもコントロールされたくない。私は娘たちを育てる中で「こうあるべき」と言ったことはないと思いますが、なおみの中には私と同じ考え方の“芽”がずっとあって、それが出てきた感じがしますね。

2020年の全米オープンで人種差別抗議の意を込めたマスクを着けて試合に臨んだ大坂なおみ(米国ニューヨーク)AFP=時事(2020年9月4日)
─なおみさんはすっかり自立し、まりさんはテニス界から引退しました。長かった旅もひと区切りというところだと思いますが、何か次の夢はありますか? ハイチには私財で設立した幼稚園や学校があると聞いています。
そのプロジェクトが忙しくて、主人はハイチにいるほうが多いくらいです。もともとは、大阪にいたときにボランティアグループを立ち上げてハイチに幼稚園を作ったことが発端でした。それがどんどん大きくなって、今では一つの小さなコミュニティのようなアカデミーになっています。テニスコートはもう何面もあるし、幼稚園も学校もあって、大きな寮も今が建設の最終段階です。生徒は200人以上いるから、学校や幼稚園の先生、警備員、清掃員、コーチなど合わせて何十人ものスタッフがいます。将来、ここからプロテニスプレーヤーを輩出するのが夢です。
実は今、そのアカデミーから大阪の高校に留学させている男の子が1人います。 将来的にはいろいろな国に生徒を送りたいと考えているのですが、留学にはものすごくお金がかかりますし、ハイチの子が異国で生きる困難もたくさんあります。私たちも悪戦苦闘しているのが実情ですが、子供たちの夢をかなえてあげたいという思いでがんばっています。
─大坂選手の存在はハイチはもちろん、日本の子供たちやその親御さんたちにとって大きな希望だと思います。国や家庭環境に関係なく、子供をプロテニスプレーヤーにしたいと思っている親たちに伝えるべきことはありますか?
ゴールへの道は一つではありません。私たちは貧しかったけれど、最初からお金やコネクションがあったなら別のやり方があったはずです。大事なのは方法ではなく、どんな方法でも100%、120%の力を注ぐことではないでしょうか。そうすれば、完璧に望んだところに行かなくても、夢に近づくことはできると思います。
ただ、全力でやるということと、子供に親の人生の責任も負わせることとは違う。子供が負けるとたたいたり、罵倒(ばとう)したり、テニスバッグをコートから遠くへ放り投げたりするような親の姿も見てきました。勝つことに親がこだわりすぎて、子供を萎縮させてはいけない。アスリートとしては、早いうちから成功して達成感を得ることよりも、ハングリーでハンブル(謙虚)であり続けることのほうが大事だと思います。

2019年9月、大阪で開催された東レパンパシフィックオープンで優勝した時の大坂一家。環さん、大坂なおみ、マックスさん(左から):大坂環氏提供
─ウィリアムズ家の物語を描いた映画『ドリームプラン』(原題『King Richard』)』でも、そういう自己中心な親が批判的に描かれていましたし、リチャードさんは娘たちに「謙虚であれ」と言い聞かせていました。映画はご覧になりましたか?
はい、観ました。私と主人は公開されてすぐに。なおみもその後に観たと言っていました。もう少し成長してからの話や他の大会での出来事も見たかったけれど、権利の問題もあり、上映時間の制約もありますよね。その中でも、リチャードの気持ちや言動は共感できるところがたくさんありました。とてもよくできた、おもしろい映画でした。
『トンネルの向こうへ』
大坂 環(著)
発行:集英社
四六判:176ページ
価格:1760円(税込み)
発行日:2022年4月30日
ISBN:978-4-08-781715-7
バナー写真:クルーザー上でくつろぐ大坂なおみ、環さん、まりさん(右から):大坂環氏提供