
法人税改革は課税ベース拡大とセットで
経済・ビジネス- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
日本の法人税は世界2番目の高率
6月24日閣議決定された「骨太方針2014」(以下「骨太」)は、「数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指す」とした。そしてその目的は「日本の立地競争力を強化するとともに、我が国企業の競争力を高めること」と記述した。
冷戦が終了した1990年代以降、旧東欧諸国に端を発した法人税引き下げ競争は全世界を巻き込んだ。OECD諸国の法人税率は20年間で平均して20%程度引き下がったのである。
わが国もこのような流れから独立してはおられず、1998年、99年、2012年に税率を引き下げたのだが、いまだ先進諸外国と比べて数%、アジア諸国と比べると10%高く、米国について世界2番目の高税率国である。
このように他国と比較して高い法人税率が、エネルギーコストなどと並んでわが国企業の立地コストに影響を与え、長く続いた円高の影響も加わって、グローバル企業を中心に海外移転・空洞化を招き、地方経済の雇用縮小の一因となっている。そこで、わが国の立地の競争力を回復し、一層の空洞化や雇用喪失を避けるという観点から、法人税率の引き下げが今回合意されたのである。
環境変化に対応、効果は成長戦略にかかる
その意味では、今回の引き下げは、わが国を取り巻く環境変化に対応したもので、前向きなものではない。わが国企業が設備投資をどこまで増加させるか、外国企業がどの程度わが国に来てくれるかなどの点については、今後のわが国の成長戦略にかかっているといえよう。
目指すべき税率については、わが国の競争相手がアジア諸国であることを考えると、何回かに分けて、最終的には10%程度の税率引き下げ(実効税率25%)を目標にすべきであると考える。
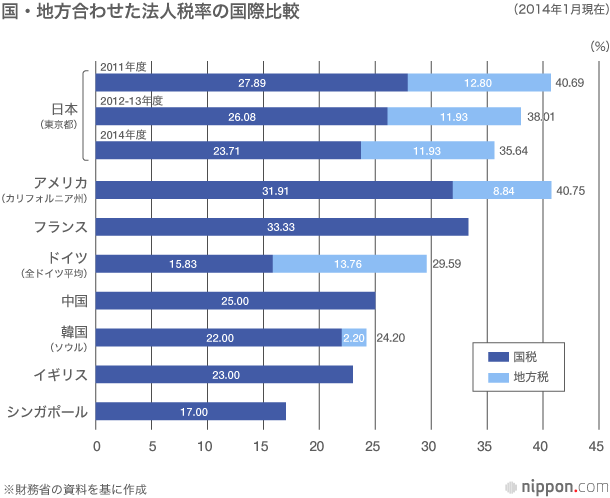
若者は賛成、60代は反対が多数
6月27-29日に行われた日本経済新聞社・テレビ東京の世論調査では、法人減税「賛成」と「反対」が40%で並んでいる。年代別では20~30歳代で賛成が56%、反対が26%。60歳代では賛成の37%を反対の45%が上回っており、世代間で見方に開きがある。(6月30日付の日経新聞朝刊)
このように、法人税減税に対する世の中の評価が極めて厳しい理由として考えられるのは、一方で高齢化に必要な財源を求めて消費税率の引き上げを行おうとしている時に、かならずしも効果が明確でない法人税減税を行う必要があるのだろうかという素朴な疑問であろう。
課税ベース拡大で、ネット減税は最小限に
この疑問に答えるためには、基本的に減税のための財源を、法人税を中心とした課税ベースの拡大で捻出することとしネットの減税幅は最小限にすること、併せて法人税に関して国民から不信感を持たれているような制度を改める法人税改革とすること、この2点を全面的に打ち出すことが必要である。
この点「骨太」は、「法人実効税率を、20年度のプライマリーバランス(PB)黒字達成目標を阻害しないよう、課税ベースの拡大等の恒久財源を確保しつつ、数年かけて、20%台まで引き下げる」と記述し、さらに「2020年度の国・地方を通じたPBの黒字化目標達成…に向けた進捗状況を確認しつつ行う」としており、安易なネット減税への歯止めをかけている。
租税特別措置の見直しが重要
課税ベース拡大策の各論としては、減価償却の見直しなどに加えてさまざまな政策税制(租税特別措置=租特)を見直すことが検討されている。この点についての政府税制調査会は、以下の考え方を示している。
租税特別措置は、これまで何度も改革が叫ばれながら手がつけられなかったが、今回は「ゼロベースの見直し」を行うべきだとし具体的には、①期限の定めのある政策税制は原則、期限到来時に廃止する、②期限の定めのない政策税制は期限を設定するとともに、対象の重点化などの見直しを行う、③利用実態が特定の企業に集中している政策税制や適用者数が極端に少ない政策税制は、廃止を含めた抜本的な見直しを行う――ということである。
デフレ経済の脱却のために期限付きで企業行動を誘導するための措置については、デフレ脱却が見えてきたら廃止することは当然である。租特は、いったん出来上がると期限を迎えても延長されるという悪弊が続いているが、期限が到来したら必ずやめるようにすることは重要だ。
加えて、ほとんど使われていない租特は一定の基準を作って廃止するという点については、民主党政権時に租税特別措置透明化法が制定され、ある程度の使用実績が世の中に出るようになったので、これを活用して行うことが有益であろう。
租特は、政・官・財のトライアングルの象徴である。安倍政権が、ドリルを使うべきは、このトライアングルの分野である。
減税だけでなく、視野広げた「法人税改革」を
最後に、今回の法人税議論は、減税を行うというだけではない。わが国経済の構造改革という観点も必要だ。そこで、法人税減税から法人税改革へと視野を広げ、国民の税に対する信頼を取り戻すような税制改革を合わせて行うことが必要だ。
この観点からは公益法人等の税制優遇にもメスを入れるべきだ。とりわけ社会福祉法人の税制は、前回の全面的な公益法人改革で手がつけられていない分野だ。公益法人等を取り巻く環境が変わり、非収益事業とされる場合であっても、一般の民間法人と競合する分野が生じていることを踏まえ、イコールフッティングの観点から優遇税制を見直すべきだ。
財政再建との両立を
わが国の法人税議論で、今後財源として、アベノミクスの経済政策による増収分を当てるべきだという考え方が出てくると予想される。このことについてどう考えるべきだろうか。
冷戦終了後の欧州では、旧東欧諸国がドイツやフランスなどの企業を自国に引き込むため法人税率を引き下げると、対抗するため先進諸国はやむを得ず自国の法人税率を引き下げる、という法人税引き下げ競争が行われてきたことは先述したとおりである。
しかし、EU諸国の法人税収を見ると、多くの国で法人税収のGDP比は上昇しており、税収の低下は生じていない。これが「法人税パラドックス」と呼ばれ、わが国でもアベノミクスの下で法人税減税をしても税収は減らないのではないかという議論を引き起こし、税の自然増収を減税財源に充てるべきだという主張の根拠と成っている。
「法人税パラドックス」が生じた原因を、EUの公式ペーパーから抜き出すと、第1に(法定)税率引き下げと同時に課税ベースの拡大が行われてきたこと、第2に税率引き下げや経済成長戦略により企業のアントレプレナーシップが発揮され、経済が活性化したことが要因とされている(そのほかに、個人から法人へのシフトもある)。
このことは、わが国の法人税改革が、課税ベースの拡大や成長戦略とセットで行われれば、「経済成長と財政再建の両立が達成できる」という極めて重要な事実を物語っている。つまり、法人税パラドックスが生じるためには、規制緩和などの強力な成長戦略が必要で、それが企業業績の向上を通じて家計に所得増、配当増、株式譲渡益増とつながっていき、成長の成果を国家財政(税収増)と国民(所得増)に還元されることを示している。
つまり、自然増収は、適切な経済政策の結果であって前提ではない。さらに今回の法人税減税が、経済活性化と財政再建の両立を目指す以上、「法人税パラドックス」で生じた増収は、財政再建に充てるということが正しい方法と思われる。
タイトル写真:大企業の本社が立ち並ぶ、東京・大手町のオフィス街を歩く会社員ら=2014年4月(時事)