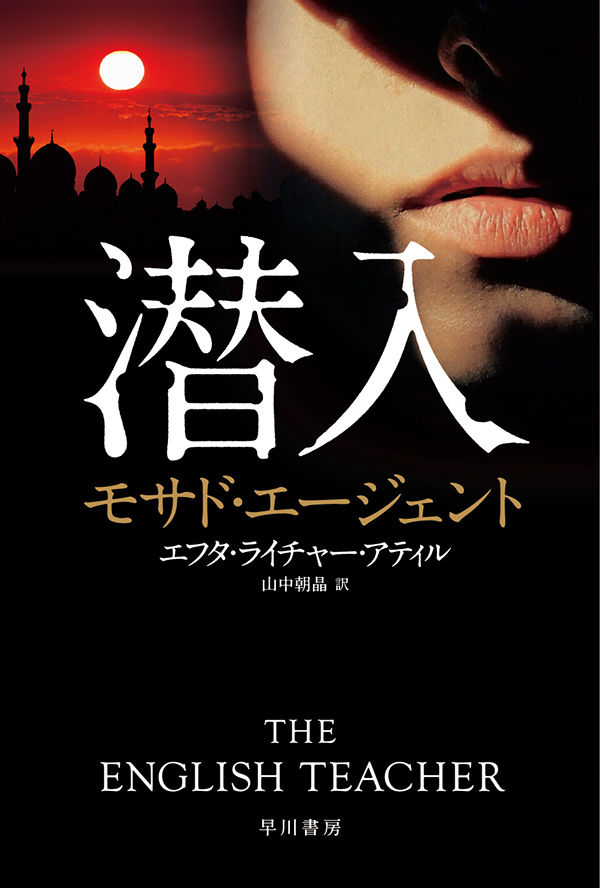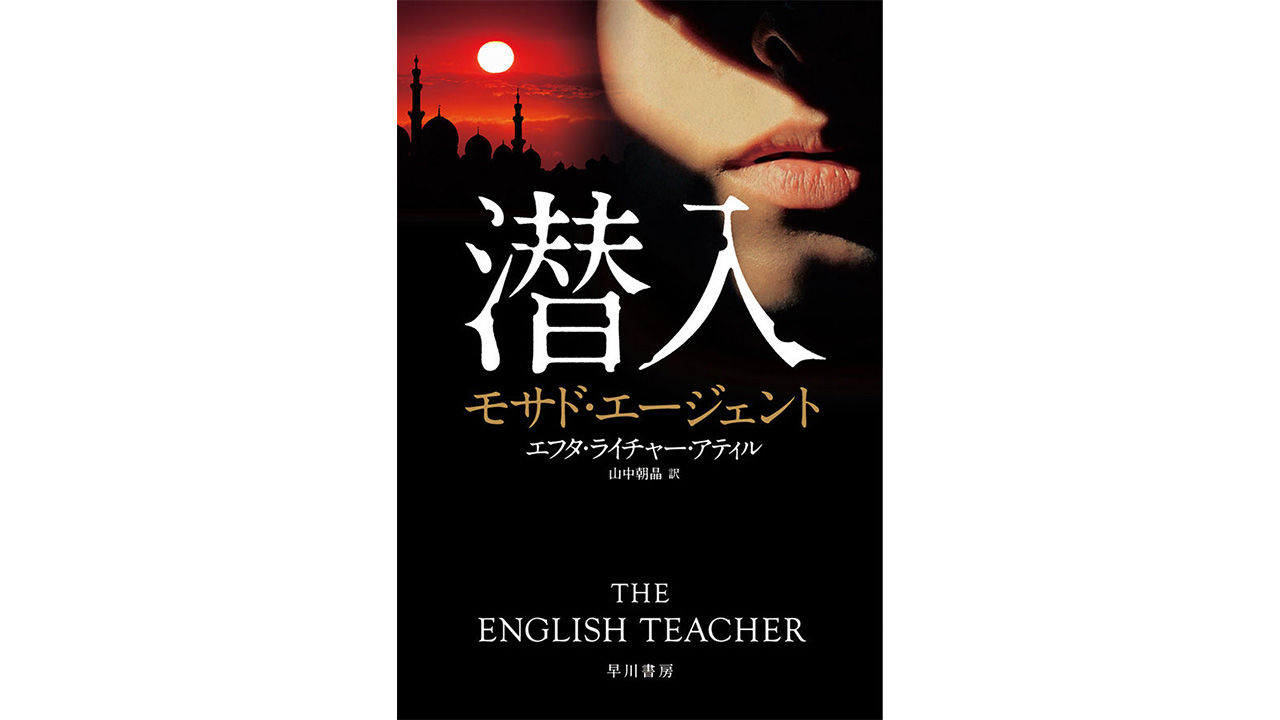
【書評】「モサドの女」がたどる苛烈な人生:エフタ・ライチャー・アティル著『潜入--モサド・エージェント』
Books- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
昨今のスパイ小説では、エンタメ的なストーリー展開に優れたものは多いが、スパイその人の心情や内面に鋭く踏み込んだ作品は少ないと思う。
かつてのグレアム・グリーンやジョン・ル・カレの作品にはそれがあり、時代背景にくわえ人物をきちんと描いているからこそ、物語に深みがあった。
しかし、今回紹介する作品には期待してよい。
登場するのは、世界最強と謳われるイスラエルの諜報機関モサドのスパイである。
物語にはいる前に、イスラエルを取り巻く状況を少しだけ。
トランプ米大統領がイスラエルの首都はエルサレムと明言し、今年5月14日、米国大使館をテルアビブからエルサレムに移転したことで、緊張は一気に高まった。
これにイスラム勢力は猛反発。パレスチナ自治区ガザでは、反対デモを鎮圧しようとするイスラエル軍による銃撃でパレスチナ人に多数の死傷者が出る事態となっており、このままでは周辺諸国を巻き込んだ紛争に発展する可能性も否定できない。
こうした緊迫した情勢のもと、水面下で各国情報機関の活動は激しさを増している。
ことにイスラエルは、国家の存亡に直結してくるだけに、アラブ諸国やイスラムのテロリストの動向に敏感にならざるをえない。近年でも「イスラエルを地図上から抹消する」と宣言した大統領がイランにいたくらいだ。
それだけにモサドのスパイは苛酷な任務を負う。敵国に潜伏しての情報収集や要人の暗殺、軍事施設などの破壊工作にいたるまで。こうした緊張を強いられる状況下に身をおいたスパイの実像とはいかなるものなのか――。
そうした興味にじゅうにぶんに応えてくれる小説が本作である。
「これは真実の物語だ」
著者のエフタ・ライチャー・アティルは元イスラエル国防軍情報部隊准将であるという。
1949年イスラエル南部のキブツの生まれ。国防軍の青年将校時代の1976年7月、ウガンダのエンテベ空港で敢行された人質救出作戦(エンテベ作戦)に従事するなど、数々の秘密作戦や諜報活動に携わり、1995年に退役。作家に転じたとされる。
そういう経歴であるならば、当然、本作はそうとうリアルな見聞が下敷きになっているはずだ。著者まえがきにこうある。
「本書は何か月ものあいだ、イスラエル民間・軍事検閲委員会に留め置かれた。そして、おびただしい個所の変更や削除を余儀なくされ、ようやく出版の許可が下りた。」
そしてこう言い切っている。
「それでもなお、これは真実の物語だ。」
と。検閲削除がどの程度のものだったかは判然としないが、けして作品のリアリティは損なわれていない。最後まで一気に読める。
さて、本作は女性のスパイが主人公となっており、まえがきによれば、どうやら実在のモデルがいるようである。
物語の出だしを紹介しよう。
かつてモサドの伝説的なスパイだったレイチェルは、ロンドンの実家で父親の葬儀を行った。
彼女は19歳のときに母親を亡くし、その後、厳格な父親とは折り合わず、イスラエルに移住。志願してモサドの一員となったが、今では現役を退いて15年が経っている。
父親の死後、身寄りが誰ひとりいなくなった彼女は、実家の不動産を処分してイスラエルへ帰国するはずだった。ところが、偶然、父親の蔵書に隠された手紙を見つけたことから、忽然と姿を消してしまう。
引退したとはいえ、何の届け出もなく行方をくらますことは、モサドの規則に違反することになる。
失踪のきっかけとなった手紙は、彼女のかつての上司で工作担当官だったエフードから父親に宛てて出されたものだった。
レイチェルは、ロンドンから何処へと出立する直前、エフードに手短な電話をかけている。
「『父が死んだわ』と言い、彼が答える前に言葉を継いだ。『父が死んだのは、これで二度目よ』カチリという音で、エフードは通話が切れたのを悟った。」
彼女が一方的に伝えた謎めいた言葉が、読者を物語に引きづりこんでいく。
「二度め」とはどういう意味なのか、と。
コードネームは「妖精」
こちらもとっくに引退しているエフードだが、重大な異変を察知してレイチェルの失踪をモサド本部に通報する。
彼女は「妖精」というコードネームをもつ凄腕のスパイだった。なにしろアラブの某敵国に数年間にわたって潜入、英語教師になりすまし、一般人として普通の生活を送るかたわら、軍事施設の情報収集から重要人物の暗殺にまで手をそめ、数々の功績をあげていた。むろん、モサドの仕業という痕跡をいっさい残さずに。
それだからこそ、イスラエルにとっては行方不明となったレイチェルが敵の手に落ち、過去のスパイ活動が白日の下にさらされるようなことになっては大打撃である。
モサドは彼女の身柄をいち早く確保しなければならない。本部は、「生死を問わず」という非情な命令をモサド要員に下す。
彼女はいったいどこに消えたのか?その意図するところは何なのか?
かくしてモサドの総力あげての探索が開始される。
ここから彼女の居場所を特定するまでの展開が、本作の読みどころである。
脇道にそれるが、本作の中で、レイチェルは2冊の小説を愛読している。そういう場面が出てくる。
まだ駆け出しの頃、機内持ち込み手荷物の中にジョン・ル・カレの『リトル・ドラマー・ガール』。これは中東に送りこまれる女性スパイが主人公だ。そして敵国に潜伏期間中に読んでいたのはグレアム・グリーンの『ヒューマンファクター』。これはイギリス情報部にもぐりこんだ二重スパイの物語。
いずれもスパイ小説の古典で名作だが、本作の著者もお薦めの作品なのだろうか。
ことに『リトル・ドラマー・ガール』を本作と合わせ読むと、読書を楽しみながらもかなりの中東通になれる。そもそも、なぜアラブとイスラエルの対立が生まれたのか。米英仏、大国の利害と都合によって翻弄され続ける中東情勢の悲劇が理解できるようになるだろう。
「尋常ではない孤独感」
もう少しだけ本作の内容にふみこんでみよう。
モサドの中でも、レイチェルの素顔を知るものは限られている。
彼女の行方はようとして知れず。もはや伝説のスパイであるだけに、現役世代のモサドの幹部には、彼女の行動パターンがさっぱりわからない。
そこで、かつての作戦部長でエフードの上司だった、今や老いたるジョーが駆り出される。
ジョーはエフードからレイチェルの過去を事情聴取する。リクルートしたいきさつから訓練の様子、任地への潜入、そこでの生活ぶりや人間関係、そして関与した情報収集活動に破壊工作。夜を徹して、微に入り細に入り話を聞く。何らかの手掛かりを得るために。
レイチェルをよく知るのはエフードをおいてほかになく、ジョーは彼女のスパイとしての人生をたどることで本人を発見できるとふんでいる。
そこから導き出された結論とは。行方不明の謎、そして現在の居所をつきとめる鍵は、彼女の過去の苦悩の中にあったのだ。
スパイの苦悩――、これこそが本作の主要なテーマである。
軍人だった著者はまえがきでこう書いている。
「軍事作戦を遂行するための戦闘や夜間の越境がいかなるものか、わたしはよく知っている。しかし、国境の向こう側で生活するのがどういうことなのかは、まったく知らない。そうした環境で、人は絶えざる不安や尋常ではない孤独感とどのように向き合うのか?そうした状況で、彼らの心はどうなるのか?」
こうした疑問は、レイチェルの人生をなぞることで見事に解き明かされていく。
不安要素を根絶やしに
秘密を抱えて生きていくには覚悟がいる。まして、発覚すればただちに死が待っているという状況下においては。偽装された日常生活を平然とおくりながら、親しくなった周囲の人たちにも秘密を気取られてはならない。並大抵の精神力ではもたないだろう。
本作には、レイチェルが関わったスパイ活動が、つぶさに記されている。
読者は、彼女の熾烈な任務とモサドの巧妙な手口に驚くことだろう。そこまでやるのか、と。そして潜入先での生活に馴染んでいくにつれ、揺れ動いていく彼女の感情に共感を覚えるにちがいない。そして彼女がとった行動にも――。
それにしても、ここで紹介されるモサドの非合法活動は徹底している。存亡の危機を回避するためには不安要素を根絶やしにするしかない。いや、モサドだけに限ったことではないのかもしれないが、「制圧」「無力化」という業界の言葉はあまりに非人間的であり、その行動原理に情容赦はないのである。
復讐はさらなる復讐を呼ぶ。
本作を読む限り、イスラエルとイスラム諸国の紛争には「際限がない」と暗澹たる気持ちになる。