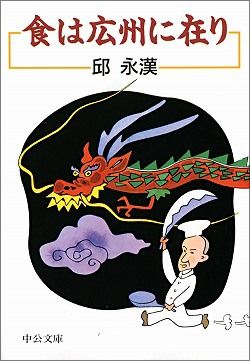台湾美食エッセイ60年:おいしい記憶は永遠に
食 文化 暮らし- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
台湾料理とは何か、ChatGPTによると、「台湾料理は、台湾独自の食文化を形成している多様な料理のことを指します」とのことだ。分かったような分からないような…。大岡響子は、「「台湾料理」は何料理?」で次のように述べている。
「台湾料理とは何か」を説明することの難しさは、台湾が経験してきた歴史の屈折と複雑な折り重なりからくるものだ。だからこそ、そのおいしさの背後に何があるのかについて、少し思いを巡らすことがあってもいい。
食は台南に在り?:邱永漢『食は広州に在り』
戦後日本の美食エッセイの草分け的一冊といえば、『食は広州に在り』(※1)だろう(※2)。著者の邱永漢(1924-2012)は、台南に生まれ、台北高校を経て東大に学び、卒業後は一時台湾に帰国するものの、台湾独立運動に関わったことから香港に亡命、日本へと移り住んだ。本書は、雑誌連載後、小説「香港」で外国人として初の直木賞を受賞した翌々年の1957年に出版された。
香港での体験を交えながら、タイトルの通り、広州料理や中華文明について、洒脱(しゃだつ)な筆致で書き下ろしている。例えば粽(ちまき)については、端午の節句に粽を食べる理由、起源とされる屈原の故事から現代の年中行事に至った解説に始まり、日中の比較文化的視点も加えた怜悧(れいり)な分析は勉強になる。本書では台湾料理は主役でないものの、台湾の粽の話になると一転して、解説のみならず、生活感あふれる切なくも温かい思い出がつづられ、胸に迫る。中でも自身の舌へのこだわりを、台南生まれの美食家の父譲りだとする文の複雑な温度感は特別だ。
2022年9月に刊行したNPO法人日本台湾教育支援研究者ネットワーク編『臺灣書旅―台湾を知るためのブックガイド』では、400冊の台湾関連書籍を、テーマありきではなく、本の内容に従って29種類に分類した。その結果、都市の中で唯一テーマとして成立したのが台南だった。台湾美食本に至っては、31冊あり、その豊富さ故に、グルメとレシピとの2つに分けて紹介した。もし邱永漢が今も生きていたとしたら、迷わず『食は台南に在り』を書いた違いない。
やっぱり食は台南に在り!:辛永清『安閑園の食卓 私の台南物語』
台南に行ったことがなくても、日本で台湾の美食都市といえば台南を思う人が多いのは、恐らく『安閑園の食卓』(※3)のイメージによるところが大きいのではないだろうか。本書は、台南の名家の令嬢で、日本で料理研究家として名を知られた辛永清(1933-2002)が、年中果物が実る果樹園を備えた庭園を有する広大なお屋敷「安閑園」で、大家族と過ごした少女時代の思い出を、品格あふれる流麗な文体で書きつづった美食エッセイだ。

『安閑園の食卓 私の台南物語』辛永清著、集英社文庫、2010
華やかな料理や大家族のにぎわいに彩られつつも、日本統治下の台南で、早くから日本語を学び、事業で成功し、総督府でも要職にあった父・辛西准が、最後まで家の名、家の宗教、自らの文化伝統を守り通した生きざまは受け継がれ、このエッセイに通底する凛としたたたずまいとして表れている。
圧巻なのが下ごしらえから丁寧に作られた究極の料理の数々である。珠玉の料理は、安閑園の食卓だからこそと博物館をのぞくような気持ちで読み進めていたところ、鶏を殺して料理ができないようでは嫁にも行けないとある。要求の高さにおののくとともに、博物館級の料理が普通に作れるものとして書かれていることにも驚愕(きょうがく)した。その証拠に、各章末には、思春期を迎える子どものための「姜味烤鶏」、父親の誕生日などお祝い事のある日に食べる「什錦全家福大麵」、豚の血の入ったスープ「猪血菜糸湯」などレシピも付してある。この味を、私にも調理可能なものとして公開してくださった寛容さに心躍り感謝しつつも、そのハードルの高さに諦め、いつか夢でいいから、ジャスミンの花を髪に挿して、安閑園の食卓に迷い込めないかと妄想してしまう。料理自慢の皆さんは、ぜひ読んでお試しいただきたい。
隣の台湾料理:焦桐『味の台湾』
『安閑園の食卓』が夢の美食だとしたら、『味の台湾』(※4)はいたって庶民的、現実的な隣の台湾美食だ。著者は有名な詩人の焦桐(1956-)で、本書以外に、レシピを詩として著した『完全強壮レシピ―焦桐詩集』にも邦訳がある(※5)。
日本語序で、著者は「何が台湾の味なのでしょう?」という問いへの答えに窮したエピソードを告白している。まず60品の料理名を並べた壮観な目次(原書は160品)をご覧いただきたい。本書はその問いへの回答となっており、台湾料理の特徴の一つを、「台湾の食といえば小吃(シアオチー)に重きを置く」ことだと断言し、滷肉飯(ルーローハン)、蚵仔煎(カキのオムレツ)、炒米粉(焼きビーフン)など手軽に食べられる料理を中心に、台湾に根付いた歴史的文化的背景を一品ごとにひもときながら、自身の体験を重ね合わせ展開していく。
例えば、日本でもよく知られた滷肉飯の「滷」は醤油で煮込むことを意味する。魯肉飯と書くこともあるが、魯は当て字だ。また、滷(魯)肉飯は北部の呼び方で、南部では肉燥飯である。こうした知識編に加え、今すぐに食べにいきたい衝動に駆られるのは、著者の推しのお店情報、付け合わせ料理の推薦を含むお店での楽しみ方まで惜しげなくアドバイスしてくれる実践編までもが完璧だからだ。
後半は、大学入試に合格できず兵役で送られた金門島で食べた蚵嗲(カキのかき揚げ)、半年後に彼女にふられ苦痛を忘れさせてくれた貢糖(ピーナッツのプラリネ)、学生時代に通った永和豆漿など著者の思い出とともに台湾の味が語られていく。
小吃とは言えない、本書の中で最も豪華な料理は、佛跳牆と呼ばれる高級スープだろう。著者は、お手製の佛跳牆を、毎年除夜にこしらえて妻の実家に届けていたという。また台湾では、坐月子(出産後の女性が約ひと月静養する伝統的産後ケア)の際に、麻油鶏(酒とごま油の鶏肉煮込)を毎日食べる習慣があるが、著者は、坐月子の時もその後も妻のために麻油鶏を作ったとのことだ。だが妻はがん闘病の末に他界してしまう。ある時、二人で通った豆花店の廃業に気付き、一緒に豆花を食べた妻ももういなことに落胆するのだった。
本書は台湾の庶民の味のナビゲーターであると同時に、甘く、酸っぱく、つらく、切ない人生の滋味をも味わい尽くす一冊だ。
守るべき台湾北部の家庭料理:洪愛珠『オールド台湾食卓記─祖母、母、私の行きつけの店』
レトロで印象的な表紙は、1983年生まれのグラフィックデザイナーである著者の洪愛珠によるものだ。200年前から台湾北部に定住してきた実家の家庭料理を、著者が自ら「オールド」と紹介するほど、家庭料理は絶滅危惧種だという。日本でも昨今多くの台湾グルメ本が刊行されているというのに、家庭料理にいたっては驚くほど未知のままだ。

『オールド台湾食卓記─祖母、母、私の行きつけの店』洪愛珠著/新井一二三訳、筑摩書房、2022
『オールド台湾食卓記』(※6)は、一人暮らしを始めた著者の小さなI字型キッチンの描写から回顧式に始まり、子ども時代に台北郊外の大きな邸宅にあった祖母の大きなキッチン、そして母親のヨーロピアンシステムキッチン―3世代の女性たちのキッチンが中心的な舞台となって展開していく。
3世代の女性たちの台湾家庭料理と家族の記憶を縦糸に、英国や東南アジア滞在中に客として、あるいは現地のキッチンでの著者の体験を横糸として、客観的なまなざしをもって比較文化的に台湾料理の特徴を織りなし、浮かび上がらせていく手法は圧巻だ。
こうした冷静な視点と、失われていく台湾家庭料理、亡くなった母との思い出を書き残さなければという使命感にあふれた情熱が掛け合わされた本書は、滷肉へのこだわり、切仔麺の神髄、盛大なる揚げ物のコツ、迪化街での買物の方法、台湾料理界では若輩のパイナップルケーキの来歴など、台湾料理の解像度を格段に上げてくれる。
本書は、台湾社会で爆発的な支持を集め、著者が書き留めた母親と台湾料理の個人的な記憶は、今や台湾社会に共有する「オールドファッション」な台湾料理の記録となった。
文化を語り味わう台湾美食エッセイ
邱永漢が、広州の美食の知識を披露しながら、自身のルーツである台南の料理と父の記憶も書き留めた『食は広州に在り』から30年後の1986年、辛永清は、日本で台南での豊かな食文化を少女時代の思い出とともに真正面から書いた『安閑園の食卓』を刊行した。台湾がまだ戒厳令下にあり著者も中国人と名乗らざるを得なかった時代である。約30年経った2012年、『安閑園の食卓』は台湾でも翻訳出版され、中国時報の十大良書にも選ばれた。2015年、焦桐は台湾の味とは何かと問いながら、庶民派の台湾料理の来歴を、妻との思い出とともに書きつづった。2021年、洪愛珠は、守るべきものとして台湾北部の家庭料理と母の記憶を書き留めた『オールド台湾食卓記』を刊行し、多くの賞を受賞した。
邱永漢『食は広州に在り』から60年を経て、2010年以降、日本では多くの台湾グルメ本が刊行されている。台湾でも、「台湾料理は、歴史の屈折と複雑な折り重なり」、変化し、融合し続けつつも、おいしさはもちろん、台湾文化を語り味わう大切な役割をも担い始めたようだ。
今回取り上げた4冊の台湾美食エッセイには、いずれも大切な人との思い出が書きつづられている。食べることは生きること。だからこそ、思い出のおいしい味、香りがある限り、思う人も思われる人もともに生き続けることができるに違いない。
バナー写真=PIXTA