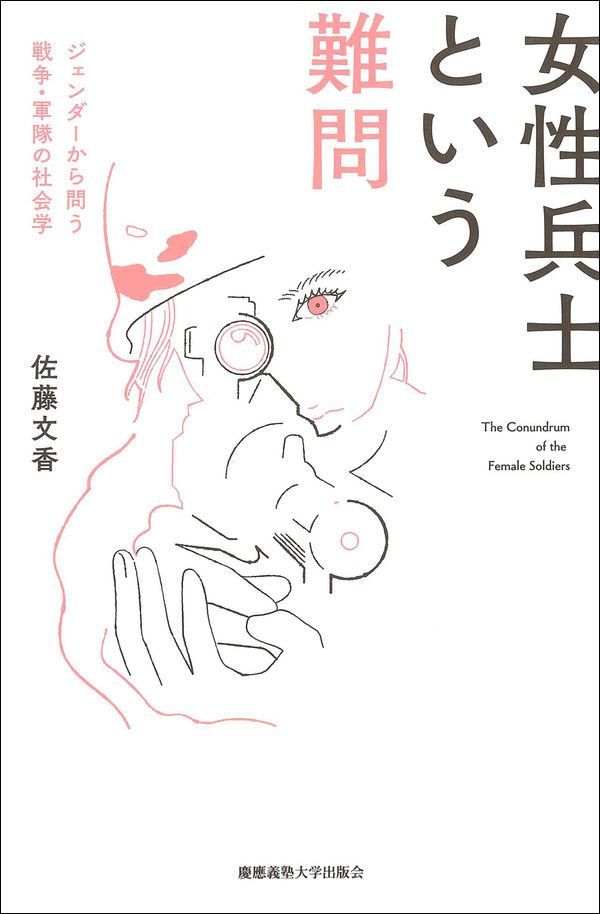自衛隊という職場―女性自衛官から考える軍隊とジェンダー
社会 政治・外交 仕事・労働 国際・海外- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
1973年に徴兵制を廃止した米国では、全米最大のフェミニスト組織NOW(National Organization for Women)などを中心に、女性も男性と同様に軍隊で活躍すべきだという主張がフェミニズムの一角を占める。90年代の湾岸戦争は女性参画の大きな契機となり、4万人もの女性兵士が派遣された。97年製作のハリウッド映画『G.I.ジェーン』は、米海軍の精鋭部隊シールズに女性として初めて志願したヒロインが、特別待遇を拒否して猛特訓に挑む「究極の男女平等の姿を描いた」サクセスストーリーとして評価され、大ヒットした。
映画公開当時大学院生だった佐藤氏は、こうした米国の潮流に違和感を覚えたと言う。「男性社会の論理や物差しに合わせていくことを目指すのが男女平等なのか。フェミニズムとはそういうことなのだろうかと、疑問を持ちました」
その違和感が軍隊・戦争とジェンダーの問題に関心を持つ一つのきっかけとなり、博士論文では、日本の“軍事組織”にあたる自衛隊の女性自衛官を研究対象とした。「女性たちがどのような動機を持って入隊し、どういう経験をしているのか。彼女たちを他者化して済ませるべきではないと思いました。私たちと切り離された遠い世界の人たちと思うことで、見逃してしまうさまざまな本質的な問題がある。ヒアリングを重ねるうちに、そんな思いが強まりました」
その結実が、2004年に刊行した『軍事組織とジェンダー 自衛隊の女性たち』だ。
自衛隊への強い警戒感の中で
「日本のフェミニストたちの間では、自衛隊を研究対象として取り上げることが警戒され、強い抵抗がありました」と佐藤氏は振り返る。「こういう研究が出てきたことを遺憾に思うなどの声がありました。その背景にあったのは、他国の軍隊と比較すること自体、曖昧な存在の自衛隊を軍隊として正当化することにつながるという懸念です。若い研究者が無自覚なまま、日本の軍事化に加担していると受け止められたのだと思います」
孤立感を抱えた佐藤氏を勇気づけたのは、米国のフェミニスト国際政治学者、シンシア・エンローの論考だった。軍隊における家父長制の作用、軍事化・脱軍事化のプロセスを検証するには、軍隊の中の女性たちが抱える問題をつぶさに観察することも研究者の重要な仕事だと指摘したのだ。
「米国では、軍隊への参画が女性など社会的弱者の地位向上につながるという発想がありました。日本では、自衛隊に関する国民の認知が曖昧で、入隊して軍事任務を果たすことが “一流の日本国民” になることと直結するとは考えられていません。だからこそ、女性を包摂する際の軍隊の “本音” がより分かりやすく現れる事例となり得るのです」
最初の著書から17年を経た『女性兵士という難問』では、軍隊を巡るグローバルな状況の変化を踏まえ、新たな視点を加えて自衛隊を検証した。
「冷戦終結後、軍隊の役割は戦闘遂行から平和維持・人道的活動中心にシフトしていきました。憲法9条の下で災害救助など非戦闘業務を担ってきた自衛隊を『特殊』と捉えるよりも、新しい軍隊の在り様の先駆けと位置付けられるのではないか。海外の日本研究者の論考にも触発されて、次第にそう考えるようになりました」
男性の人材不足補充とイメージアップに貢献
戦後、憲法9条により戦争を放棄した日本の新たな軍事組織は、1950年の警察予備隊として始まり、保安隊を経て、54年、自衛隊に改編された。女性の採用は看護職に限定されていたものの、当初から組み込まれていた。
50年代から60年代前半にかけて、女性隊員の存在は、自衛隊を旧軍とは違う組織だと差異化することに役立ったと佐藤氏は分析する。
「発足当初から、軍事色を弱めるために女性を活用するという発想がありました。“軍隊”として認知させず、市民社会に溶け込ませようと、自衛隊のイメージをソフトにする必要があったのです」
67年、陸上自衛隊が女性採用を一般職(人事、総務、補給、会計、通信など)に拡大した。背景にあったのは、男性の人材不足だ。高度経済成長期で若い男性の雇用情勢が良好だったため、隊員募集は難航を極め、新たな人材として女性に頼らざるを得ない状況があったのだ。
70年代以降、自衛官募集のポスターには女性隊員が頻出し始め、ソフトで親しみやすいイメージを演出してきた。
女性への門戸開放は、男性の人材不足に加えて、国際的な潮流に歩調を合わせる形で進む。1979年、国際連合が女性差別撤廃条約を採択し、日本は85年に批准。翌年、男女雇用機会均等法が施行され、女性自衛官の職域が広がる追い風となった。92年、防衛大学校に女性の入学が認められ、上級幹部への道が開けたことは大きな転機だった。
93年、女性に全職域を開放。この時も、80年代後半のバブル経済下の好況な労働市場の中で、男性隊員不足に直面したことが背景にある。ただし、「母性の保護」等を理由に潜水艦、戦闘機などの配置には制限がかかった。
職域を広げる一方で、女性自衛官を「マスコットガール」的に活用もしている。1990年代、「ワインレッド作戦」と称して、女性隊員を地元のミスコンテストに積極的に参加させた。「ミス」のタイトルを獲得した女性は、雑誌のグラビアなどに大きく取り上げられ、自衛隊の広告塔の役割を果たした。
安倍元首相の「汚名返上」戦略
2000年に国連で採択された「安全保障理事会決議1325号」は、平和と安全保障を巡るあらゆる活動に女性の参加とジェンダー視点の導入を要求した。自衛隊では02年、国連東ティモール支援団に女性自衛官が初めてPKO(国連平和維持活動)要員として含まれ、以後、女性隊員がPKO任務に参加することが常態となった。03年~09年のイラク派遣にも、通信、補給、看護を担う女性隊員たちがいた。地元民と交流する女性自衛官の姿は、「戦闘地帯」への派遣ではないかという批判や疑念をかわすことにも貢献しただろうと、佐藤氏は指摘する。
2015年以降は、安倍首相(当時)の「女性活躍推進法」によって、さらなる女性の包摂が進んだ。15年、航空自衛隊が戦闘機、17年、陸上自衛隊が歩兵と戦車の部隊、18年、海上自衛隊が潜水艦への配置を女性に開放すると発表。また、ワークライフバランス施策として、庁内託児所や育児休業代替要員制度なども整備されていった。

自衛隊観閲式で行進する陸上自衛隊の女性自衛官=2018年10月14日、陸自朝霞訓練場(時事)
「安倍首相は、国際社会の動きに敏感で、女性活躍推進政策の一環として、女性の平和維持活動参加にも熱心でした。慰安婦問題の対応や、ジェンダー平等に遅れを取っていることが背景にあったと思います。ジェンダーギャップ指数が発表されるたびに、先進国で最下位なのですから。国際的な汚名返上のための戦略でもあり、タカ派の歴史修正主義者という自身のイメージを挽回する効果があったでしょう」
2022年3月末時点で、自衛隊には2万人弱、全体の約8%の女性自衛官が働く。NATO加盟国の女性比率(2019年平均=12%) と比較するとまだ低いため、防衛省は30年までに12%以上にするという数値目標を挙げている。
「男性隊員の心のオアシスになりたい」
日本では、女性の入隊を後押しするようなフェミニズム運動は存在しなかった。では、彼女たちの入隊の動機はどこにあるのか。
「国家公務員なので同じ階級である限り男女同賃金だし、何より安定した職だという経済的動機が大きいです。それに加えて、民間企業より実力で評価されるのではないか、刺激的な経験ができるのでは、という期待もあります。1995年の阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災を契機に、自分も災害救助の仕事がしたいと入隊する人もかなりいました」
だが、全職域が女性に開放された先進的な職場でも、制度と実態が異なることはあるだろう。2004年1月、イラクに派遣されたある女性隊員は、テレビのインタビューでこう発言した。「疲れた男性隊員の心のオアシスになりたい」
意外にも思える言葉だが、自衛隊に適応してきた女性の発言としては、典型的なものだと佐藤氏は言う。「民間企業と同様に、男性社会で軋轢(あつれき)を生まないように快適に生き抜くための戦略が必要なのです。問題は、男性基準の組織の中で、女性が二極化しやすいことです。自衛隊にも、女性らしい気配りを前面に出す女性たちと、彼女たちは“二流”で、自分は男性並みにできる “例外”だと考えるエリート女性が存在します。こうした分断は、職場の改善に向けた協力を難しくします」
セクシュアルハラスメントも深刻な問題だが、「被害に遭った場合、人を守る、国を守る存在であるべき兵士が、自分が脆弱な被害者であると訴え出ることへのハードルが高い」と指摘する。「声を上げにくく、被害がもみ消されやすい。セクハラの矮小化は、他国の軍隊でも観察されています」
自衛隊はどこへ向かうのか
男性も含めた自衛官のヒアリングを重ねてきた佐藤氏は、彼らの「被害者意識」を度々感じてきたと言う。
「他国の軍隊と違ってグレーな状況に置かれ、国民の正当な認知も得られない。自分たちの日々の努力には関心が持たれず、不祥事ばかりが注目されてバッシングを受けると感じている隊員は多くいます」
この被害者意識を基盤にして、「内部のセクハラが問題になった際、女性隊員たちからも、こんなことは他でもよくあるのに、自衛隊だからたたかれるんですよね、といった発言が出てきます」
「左派やフェミニストに多く見られる自衛隊の他者化と批判は、自衛隊と市民社会の距離を広げることに寄与してきました。批判的な視点を持ちつつ、外部からつながりを保ち、自衛隊の組織や隊員の意識を変えていくことも考えるべきでしょう」
佐藤氏は、元自衛官の五ノ井(ごのい)里奈さんが、陸自在職中に性被害を受けたと実名で告発している件に注目する。「同様の被害に遭って退官した元女性自衛官たち、そして現職自衛官も賛同の声を上げ始めています。今までになかった動きで、ネット社会の#MeTooから生まれた大きな変化です」
一方、ウクライナ侵攻を契機に、9条を含む憲法改正への動きが加速する兆しもある。
「自衛隊を憲法の中に位置付けようという世論が大勢を占めたとき、長年押さえつけられていると感じてきた自衛官たちの意識がどう変わるのか、注意深く見守っていく必要があります。ジェンダーの視点を持つ批判的考察も、まだ十分ではありません。自衛隊員たちの実像を可視化するような研究がもっと後に続くことを願っています」
バナー:航空自衛隊で、女性初の戦闘機パイロットとなった松島美紗2等空尉(当時)=2018年8月、宮崎県の空自新田原基地(共同)