
面白がる心をいつまでも:『魔女の宅急便』著者・角野栄子さん
文化 Books- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
相模湾に臨み、小高い山に抱かれた古都・鎌倉に、角野さんは住んでいる。小さなおばけシリーズ『アッチ、コッチ、ソッチ』や『魔女の宅急便』をはじめとする200冊以上の絵本、童話、翻訳、エッセーを手掛けてきた。2018年には児童文学のノーベル賞とも呼ばれる国際アンデルセン賞の作家賞を受賞した。20年は処女作『ルイジンニョ少年―ブラジルをたずねて』の出版から50周年を迎える。鎌倉で4年間続けている月に一度の読み聞かせの会は、世代を超えた多くのファンであふれている。22年頃には、東京に江戸川区角野栄子児童文学館(仮称)がオープンする予定だ。魔法のように物語を紡ぎ続ける角野さんにアイデアの源泉を尋ねようと、森に囲まれたカフェで話を聞いた。
娘の絵から生まれたキキ
『魔女の宅急便』は、人間のお父さんと魔女のお母さんの一人娘キキが、13歳になって親元を離れ、魔女修行の旅に出る物語シリーズ。
執筆のきっかけは、角野さんの娘リオさんが12歳の時に描いたほうきにまたがる魔女の絵だった。ほうきにはラジオがぶら下がっていて、そこから音符が吹き出していた。その絵を見て「こんな魔女の話を書いてみたら面白いな」と創作意欲が湧いた。18歳の時、米国の雑誌『ライフ』で鳥の目から見たニューヨークの空撮写真を目にして、ずっと忘れられずにいた角野さん。「空飛ぶ魔女の物語を書けば、私も飛べる!」と思った。

娘リオさんが12歳の時に描いた魔女のイラスト。『魔女の宅急便』のモチーフとなった。(写真提供=角野栄子オフィス)
角野さんは、5歳の時に母親を病で亡くしている。寂しさから、いつも不安でよく泣く子どもだった。母がどこに行ったのか、見えない世界に関心を持ち、「どこかに行ったら何かいいことあるかな」と考えていた。本が読めるようになると、本の世界が「どこか」になった。
そんな小さい時からの自分の思いを物語に重ねていくうちに、自然にキキが「ここでないどこか」へ行って、一人暮らしをする設定になった。13歳のキキは思春期の入り口。年齢的に描くのが難しいけれど面白い年頃かもしれない、と思って書き始めた。キキはほうきに乗って、花嫁のベールから病気のカバまで運び、やきもちを焼いたり、悲しんだり、失敗を経験しながら、人を愛する喜びを知り、長年の恋を実らせて結婚。そして双子を産む。
角野さんには最初から決めていたことが二つあった。「まず魔法は一つだけにしようと思った。キキの魔法はほうきで飛ぶことだけ。そして、どうして男の子は魔女になれないの?という疑問についても書きたかった。だから、キキが結婚して双子(男の子と女の子)を産むように6巻まで書いたのです」
1985年に1巻目を出版。4年後には、長編アニメ映画『魔女の宅急便』(監督:宮崎駿、スタジオジブリ)が公開された。それ以降、2009年までに6巻、スピンオフ2巻を合わせると全8巻を出版した。

中国、タイ、ベトナム、フランス、英 、スウェーデン、ロシア、イタリアなど、13カ国語に訳された『魔女の宅急便』。2020年には、スペイン語、ルーマニア語も刊行予定。(協力=福音館書店 )
「誰にでも一つは魔法がある」
物語を書いていて「つくづく、誰にでも一つは魔法があると思った」とほほ笑む。面白がる気持ち、好奇心が大切だという。「何か面白がる、目をキョトキョトさせて。何かを見つけて楽しみながらコツコツと続けると、世界が広がってくるでしょ。すると厚みができてくるの」
「面白がる気持ちは、その人一人のものだから、一人でやらなくちゃだめね」と角野流の人生を楽しむこつを明かす。「例えばその時の気持ちを自分だけのノートに書いてみる。誰にも見せない秘密のノート。絵でも何でもその時気付いたことを書けばいい。悪口でもいいの。悪口もうまく書けたら上等よ!」
『わるくちしまいます』という角野さんの絵本がある。いじめられて帰ってきた女の子が、母親にバッタバッタと悪口を言う。すると母親は「この中にもっと言いなさい」と帽子の箱を持ってくる。ところがたくさん言い過ぎてふたが閉まらなくなる、という話だ。恐る恐る読み聞かせの会で披露すると、子どもたちはお腹を抱えて笑い、それまでで最もウケた。「子どもはちゃんと見ているし、ちゃんと分かっている。表現しなくても、表現豊かなのよ」

「なるべく明るい色の服でお願いします」とのリクエストにすてきなイチゴ色の服を選んでくれた。
想像から創造へ
角野さんは「心が動くとだんだんその人の魔法が育っていく」と言う。「花が好き、種が好きとか、だんだん好きなことが見つかってくるじゃない?それを大事にしていると、関係する新しいものを見つけた時にワクワクして、うれしいじゃない。それを続けていくと、その好奇心がその人にとっての魔法になるの」と言う。ワクワクや好奇心という名の魔法が育ち、その人の生きる力になるのだ。「好きだからできるの。嫌いだったらコツコツやれないでしょ?」
周囲のことを全然考えないのもおかしいけれど、隣の人と同じようにするのではなく、自分の目で見て考え、自分で判断し、工夫する。そうした想像する力がその人をつくっていくと強調する。「人間を木に例えると『想像力』は肥やし。『想像力』を持つとワクワクするじゃない。それで心が動くでしょ。すると『創造』に変わっていく。想像から創造へ。イマジネーションからクリエーションに」。異なる文化や言語を話す人に思いを伝える時も「想像力」が勝負だと力説する。

「人まねでない自分の面白いことを探すのに遅すぎることはないのよ」
自分でつくっているのに自分がつくっていない?
キキの物語には不思議なせりふが時々登場する。例えばお母さん魔女のコキリが「つくるって不思議よ。自分でつくっていても自分がつくっていないのよ」とキキに言うシーンがある。
「人間は自分でつくって、自分だけで完成したみたいに思うけれども、違うのよね」と角野さん。例えば水を運ぶとき、最初は木の葉や両手ですくっていたけれど、病気の子どもに飲ませるとなると少ししか運べない。そこでこぼさず、運べるものを探して、器やガラスを作り出した。電気製品もIT(情報技術)も目に見えない世界から想像力を得たからこそ出来上がるという。「まきでご飯を炊いていた時代を知っているから、どれだけ多くの人の願いや気持ちが込められて電気釜ができたのかを考えるの」。物語の登場人物が発する短いせりふには、角野さんのメッセージが凝縮されている。

「病気の子どもに飲ませる水を両手で運ぼうとすると、どうしてもこぼれちゃうじゃない」
物語の原点は父の膝の上で聞いたお話
角野さんは1935年、東京の下町、深川で生まれた。戦争中は山形県への学童疎開も経験した。母を亡くした寂しさを父の話や本の世界が慰めてくれた。角野さんは父の膝の上で物語や落語のせりふを聞いた。「子どもの時に聞いたレ・ミゼラブルのジャン・バルジャンが忘れられなかったらしく、父はよく話してくれました。『タタタターと走った』とか、『メソメソ泣いた』とか、音(おん)で表現するオノマトペを使って。オリジナルとは違うけれども、とても面白かった」

神奈川県鎌倉市の鎌倉山にあるカフェ「ハウス・オブ・フレーバーズ」で。
角野さんの物語には独特のオノマトペがたくさん登場する。日本語にオノマトペが多いのは、言葉に自然や生活の音を入れて風景を形作っていくからではないかと角野さんは考える。少し前までの日本の家は、柱でできていた。屋根があって、玄関や窓が大きくて、壁は襖(ふすま)や障子などの引き戸。「朝起きて、全部開けると外の自然界と家の中が一体になります。自然が家の中に入って来るので、鳥の鳴き声、風や雨の音に対して敏感になったのだと思うの」
「ここでないどこか」を求めてブラジルへ
小学5年生で終戦を迎え、それまで敵性語だった英語に中学校で出会う。文法で「be+動詞+ingは現在進行形」と習い、「そういう生き方っていいな。一刻一刻を楽しくコツコツと『現在進行形』でいこう」と心に決めた。
大学では、英文学を専攻。卒業して出版社に就職し、23歳で結婚。翌年、デザイナーの夫と自費移民としてブラジルに渡った。2カ月の船旅で見えるのはひたすら海と空を隔てる水平線。「贈り物のふたを開けるときみたいにワクワクしていた」
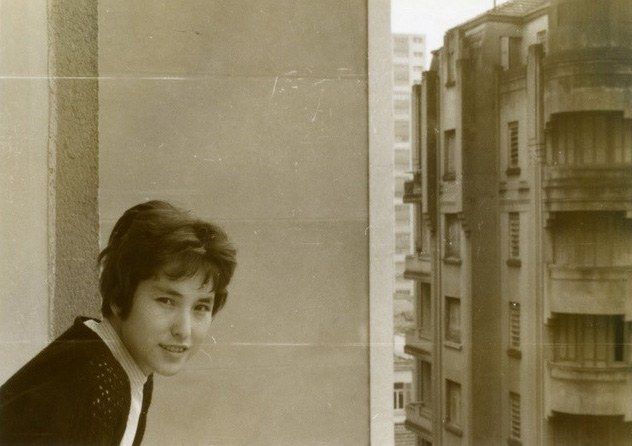
1959年にブラジルへ。サンパウロ市のグァイアナーゼス通りのアパート609号室。(写真提供=角野栄子オフィス)
ところがブラジルに着いた途端、角野さんの当てが外れた。英語が全く通じないのだ。それでも同じアパートの12歳の少年に、リズムに合わせてサンバを踊るようにポルトガル語を習い、仕事を見つけて2年近く暮らした。欧州を回って帰国の途についたのは1961年だった。
やっと見つけた「好きなこと」
帰国後、34歳の時に大学の恩師で英米文学研究者の龍口直太朗さんからブラジルでの経験を児童書に書いてみないかと勧められた。何度も書き直して翌年出版したのが処女作『ルイジンニョ少年ーブラジルを訪ねて』だ。それが角野さんの作家人生の出発点となった。「飽きっぽい私が毎日書いても飽きない!」と角野さんは書くことが大好きな自分に気付いた。今も、どんなに調子が悪い時でも、必ず机に向かう。
情報にあふれ何でも手に入る現代は、見えないものを想像する機会が少なくなっている。子どもたちが好きなことを探すこつを聞いてみた。「面白がる気持ちを小さい時からつくってあげること。『あれ!面白いことに気が付くのね』という一言がとても大切。親も少し工夫しないとね。忙しくても仕事でこういう面白いことをしているんだよ、って話してあげるといいわね」
「大人や親はみんな、子どもに本を読んでもらいたいと思っているでしょ。だけれども、親が本を読んでいない。『うちの子どもは本が大好きです』と言うけど、それは親が子どもたちに読み聞かせている「聞き書」であって「読書」じゃないの。自分で読まなくちゃ読書にならないのよ」と苦言を呈す。聞き書から読書への橋渡しとなる幼児期はとても大事だ。誰でも何かを面白がる気持ちは持っている。だからこそ、角野さんは人間の本質を突くような面白い幼年童話との出会いが大切だという。
水平線は見えない扉

浜の階段に並ぶ色とりどりのビーチサンダルに目を奪われ、「ちょっと待って。インスタの写真を撮るから」と好奇心旺盛な角野さん。
夕方になると、鎌倉の海辺で水平線と夕陽を眺める。角野さんにとって水平線は何かが始まるところだ。「誰でも一つは持っている魔法」を育てるのは「面白がる力と想像力」。自分の判断や感じ方を信じていいのよ、と読者の背中を押してくれる。ワクワクすることから生まれた想像力は、創造する力となり、その人の心の支えになる。角野さんの「面白い」を探す旅はまだまだ続く。
バナー写真:角野栄子さん、ハウス・オブ・フレーバーズの入り口で
写真撮影=川本 聖哉(角野栄子オフィス提供写真を除く)
取材協力=ハウス オブ フレーバーズ
角野 栄子
1935年1月1日東京に生まれる。1957年早稲田大学教育学部英語英米文学科卒業。1959年から2年間ブラジルに渡る。1970年頃より絵本・童話の創作を始める。『ズボン船長さんの話』で旺文社児童文学賞、『魔女の宅急便』で野間児童文芸賞、小学館文学賞などを受賞。2018年に国際アンデルセン賞の作家賞を受賞した。『アッチ ・コッチ・ソッチのちいさなおばけシリーズ』『ナーダと言う名の少女』『ラストラン』戦争体験をもとに書いたフィクション『トンネル 1945』など200を超える作品がある。



